幾何学的秩序に従って論証された
エ チ カ
五部に分たれ、その内容は左記の通り
1神について
2精神の本性および起源について
3感情の起源および本性について
4人間の隷属あるいは感情の力について
5知性の能力あるいは人間の自由について
BENEDICTI DE SPINOZA
E T H I C A
ORDINE GEOMETRICO DEMONSTRATA
ET
IN QUINQUE PARTES DISTINCTA
IN QUIBUS AGITUR
I. DE DEO.
II. DE NATURA ET ORIGINE MENTIS.
III. DE ORIGINE ET NATURA AFFECTUUM.
IV. DE SERVITUTE HUMANA SEU DE AFFECTUUM VIRIBUS.
V. DE POTENTIA INTELLECTUS SEU DE LIBERTATE HUMANA.
第 一 部
定義、
一、二、三、四、五、六、七、八
公理、一、二、三、四、五、六、七
定理、
一、二、三、四、五、六、七、八、九、一〇、
一一、一二、一三、一四、一五、一六、一七、一八、一九、二〇、
二一、二二、二三、二四、二五、二六、二七、二八、二九、三〇、
三一、三二、三三、三四、三五、三六、付録、第一部TOP、第二部TOP、TOP☆
神について
定 義
一 自己原因とは、その本質が存在を含むもの、あるいはその本性が存在するとしか考えられえないもの、と解する。
二 同じ本性の他のものによって限定されうるものは自己の類において有限であると言われる。例えばある物体は、我々が常により大なる他の物体を考えるがゆえに、有限であると言われる。同様にある思想は他の思想によって限定される。これに反して物体が思想によって限定されたり思想が物体によって限定されたりすることはない。
三 実体とは、それ自身のうちに在りかつそれ自身によって考えられるもの、言いかえればその概念を形成するものに他のものの概念を必要としないもの、と解する。
四 属性とは、知性が実体についてその本質を構成していると知覚するもの、と解する。
五 様態とは、実体の変状、すなわち他のもののうちに在りかつ他のものによって考えられるもの、と解する。
六 神とは、絶対に無限なる実有、言いかえればおのおのが永遠・無限の本質を表現する無限に多くの属性から成っている実体、と解する。
説明 私は「自己の類において無限な」とは言わないで、「絶対に無限な」と言う。なぜなら、単に自己の類においてのみ無限なものについては、我々は無限に多くの属性を否定することができる〈(言いかえれば我々はそのものの本性に属さない無限に多くの属性を考えることができる)〉が、これに反して、絶対に無限なものの本質には、本質を表現し・なんの否定も含まないあらゆるものが属するからである。 38
七 自己の本性の必然性のみによって存在し・自己自身のみによって行動に決定されるものは自由であると言われる。これに反してある一定の様式において存在し・作用するように他から決定されるものは必然的である、あるいはむしろ強制されると言われる。
八 永遠性とは、存在が永遠なるものの定義のみから必然的に出てくると考えられる限り、存在そのもののことと解する。
説明 なぜなら、このような存在は、ものの本質と同様に永遠の真理と考えられ、そしてそのゆえに持続や時間によっては説明されないからである、たとえその持続を始めも終わりもないものと考えようとも。
公 理
一 すべて在るものはそれ自身のうちに在るか、それとも他のもののうちに在るかである。
二 他のものによって考えられないものはそれ自身によって考えられなければならぬ。
三 与えられた一定の原因から必然的にある結果が生ずる。これに反してなんら一定の原因が与えられなければ結果の生ずることは不可能である。
四 結果の認識は原因の認識に依存しかつこれを含む。
五 たがいに共通点を持たないものはまたたがいに他から認識されることができない。すなわち一方の概念は他方の概念を含まない。
六 真の観念はその対象(観念されたもの)と一致しなければならぬ。
七 存在しないと考えられうるものの本質は存在を含まない。
定理一 実体は本性上その変状に先立つ。
証明 定義三および五から明白である。
定理二 異なった属性を有する二つの実体は相互に共通点を有しない。
証明 これもまた定義三から明白である。なぜなら、おのおのの実体はそれ自身のうちに存しなければならずかつそれ自身によって考えられなければならぬから、すなわち、一の実体の概念は他の実体の概念を含まないから、である。
定理三 相互に共通点を有しない物は、その一が他の原因たることができない。
証明 もしそれらの物が相互に共通点を有しないなら、それはまた(公理五により)相互に他から認識されることができない、したがって(公理四により)その一が他の原因たることができない。Q・E・D・
定理四 異なる二つあるいは多数の物は実体の属性の相違によってか、そうでなければその変状の相違によってたがいに区別される。
証明 存在するすべてのものはそれ自身のうちに在るか、他のもののうちに在るかである(公理一により)。すなわち(定義三および五により)知性の外には、実体およびその変状のほか何ものも存在しない。ゆえに知性の外には、実体、あるいは同じことだが(定義四により)その属性、およびその変状のほかは、多くの物を相互に区別しうる何ものも存在しない。Q・E・D・
定理五 自然のうちには同一本性あるいは同一属性を有する二つあるいは多数の実体は存在しえない。
証明 もし異なった多数の実体が存在するとしたら、それらは属性の相違によってかそうでなければ相違変状によって区別されなければならぬであろう(前定理により)。もし単に属性の相違によって区別されるなら、そのことからすでに、同一属性を有する実体は一つしか存在しないことが容認される。これに反して、もし変状の相違によって区別されるなら、実体は本性上その変状に先立つのだから(定理二により)、変状を考えに入れず実体をそれ自体で考察すれば、言いかえれば(定義三および公理六により)実体を正しく考察すれば、それは他と異なるものと考えられることはできない。すなわち(前定理により)同一属性を有する実体は多数存在しえず、ただ一つのみ存在しうる。Q・E・D・
定理六 一の実体は他の実体から産出されることができない。
証明 自然のうちには同一属性を有する二つの実体は存在しえない(前定理により)、言いかえれば(定理二により)相互に共通点を有する二つの実体は存在しえない。したがって(定理三により)一の実体は他の実体の原因であることができない。あるいは一の実体は他の実体から産出されることができない。Q・E・D・
系 この帰結として、実体は他の物から産出されることができないことになる。なぜなら、公理一および定義三と五から明白なように、自然のうちには、実体とその変状とのほか何ものも存在しない。ところが実体は実体から産出されることができない(前定理により)。ゆえに実体は絶対に他の物から産出されることができない。Q・E・D・
別の証明 このことはまた反対の場合が不条理であるということからいっそう容易に証明される。すなわち、もし実体が他の物から産出されうるとしたら、実体の認識はその原因の認識に依存しなければならなくなり(公理四により)、したがって(定義三により)それは実体ではなくなるからである。
定理七 実体の本性には存在することが属する。
証明 実体は他の物から産出されることができない(前定理の系により)。ゆえにそれは自己原因である。すなわち(定義一により)その本質は必然的に存在を含む。あるいはその本性には存在することが属する。Q・E・D・
定理八 すべての実体は必然的に無限である。
証明 同一属性を有する実体は一つしか存在せず(定理五により)、そしてその本性には存在することが属する(定理七により)。ゆえに実体は本性上有限なものとして存在するか無限なものとして存在するかである。しかし有限なものとして存在することはできない。なぜなら、有限なものとして存在すればそれは同じ本性を有する他の実体によって限定されなければならず(定義二
により)、そしてこの実体もまた必然的に存在しなければならぬのであり(定理七により)、したがって同一本性を有する二つの実体が存在することになるが、これは不条理だからである(定理五により)。ゆえに実体は無限なものとして存在する。Q・E・D・
備考一 有限であるということは実はある本性の存在の部分的否定であり、無限であるということはその絶対的肯定であるから、この点から見れば、単に定理七だけからして、すべての実体は無限でなければならないことが出てくる。〈なぜなら、もし実体を有限であると仮定すれば、我々は実体の本性の存在を部分的に否定することになるが、これは前述の定理により不条理だからである。〉
備考二 事物について混乱した判断をくだし・事物をその第一原因から認識する習慣のないすべての人々にとって、定理七の証明を理解することは疑いもなく困難であろう。なぜなら彼らは実体の様態的変状と実体自身とを区別せず、また事物がいかにして生ずるかを知らないからである。この結果として彼らは、自然の事物に始めがあるのを見て実体にも始めがあると思うようになっているのである。
いったいに、事物の真の原因を知らない者はすべてのものを混同し、またなんら知性の反撥を受けることなしに平気で樹木が人間のように話すことを想像し、また人間が石や種子からできていたり、任意の形相が他の任意の形相に変化したりすることを表象するものである。同様にまた、神の本性を人間本性と混同する者は、人間的感情を容易に神に賦与する。特に感情がいかにして精神の中に生ずるかを知らない間はそうである。
これに反して、もし人々が実体の本性に注意するならば、定理七の真理について決して疑わないであろう。そればかりでなくこの定理はすべての人々にとって公理でありそして共通概念の中に数えられるであろう。なぜなら、そうした人々は実体をそれ自身のうちに在りかつそれ自身によって考えられるもの、すなわちその認識が他の物の認識を要しないもの、と解するであろうから。それから様態的変状を、他の物のうちに在るもの、そして自らが含まれている物の概念によってその概念が形成されるもの、と解するであろう。だから我々は存在していない様態的変状についても真の観念をもつことができる。たとえそうした様態的変状が知性の外には現実に存在しなくともその本質は他の物の中に含まれていて、この物によって考えられることができるようになっているからである。これに反して実体はそれ自身によって考えられるのであるから、その真理は知性の外にはただ実体自身のうちにのみ存する。ゆえにもしある人が、自分は実体に関して明瞭かつ判然たる観念すなわち真の観念を持っているがそれにもかかわらずそうした実体が存在するかどうかを疑うと言うならば、これは実に、「自分は真の観念を持っているがそれにもかかわらずそれが誤った観念ではあるまいかと疑う」と言うのと同然である(これは十分注意する者にとっては明白であろう)。あるいはもしある人が、「実体は創造される」と主張するなら、これは同時に「誤った観念が真の観念になった」と主張するものである。実にこれ以上不条理なことは考えられない。したがって実体の存在はその本質と同様に永遠の真理であることを我々は必然的に容認しなくてはならないのである。
またこのことから、同じ本性を有する実体は一つしかないことを他の仕方で結論することができる。これをここに示すことは徒労ではないと思う。しかしこれを秩序だててするためには次のことを注意しなくてはならぬ。
一、おのおのの物の真の定義は定義された物の本性のほかは何ものも含まずまた表現しない。このことから次のことが出てくる。
二、定義は定義された物の本性のほかは何ものも表現しないのであるからには、いかなる定義もある一定数の個体(*)を含まずまた表現しない。例えば三角形の定義は三角形の単純な本質のみを表現し、決してある一定数の三角形を表現しない。
(* 個体とは一つの類に属する個物のことと解される。)
三、存在するおのおのの物には、それが存在するある一定の原因が必然的に存することに注意しなければならぬ。
四、最後に注意すべき点は、ある物が存在するその原因は、存在する物の本性ないし定義自身のうちに含まれているか(これは存在することがその物の本性に属する場合である)、そうでなければその物の外部に存していなければならぬということである。
以上の前提から、もし自然の中にある一定数の個体が存在するとしたら、なぜそれだけの個体が、そしてなぜそれより多くもなく少なくもない個体が存在するかの原因が、必然的に存しなければならぬことになる。例えば、もし自然の中に二〇人の人間が存在するとしたら(いっそう分かりやすくするため私はこれらの人間が同時に存在しかつこれまで自然の中に他の人間が存在しなかったと仮定する)、なぜ二〇人の人間が存在するかの理由を挙げるためには一般に人間本性の原因を示すだけでは十分でないのであって、その上さらに、なぜ二〇人より多くもなく少なくもない人間が存在するかの原因を示すことが必要であろう。各人にはなぜ存在するかの原因が必然的に存しなければならぬのであるから(注意三により)。ところがこの原因は(注意二および三)、人間の真の定義が二〇人という数を含まないゆえに、人間本性そのもののうちに含まれていることはできない。したがって(注意四により)なぜこれら二〇人の人間が存在するか、したがってまたなぜ彼らの一人ひとりが存在するかの原因は、必然的に各個人の外部に存しなければならぬ。この理由からして我々は一般的にこう結論しなければならぬ、すべて本性を同じくする多数の個体が存在しうるような物は、その存在のために、必然的に外部の原因を持たなければならぬのであると。
さて実体の本性には(すでにこの備考で示したところにより)存在することが属するのであるから、その定義は必然的な存在を含まなければならず、したがって単にその定義だけからそれ自身の存在が結論されなければならぬ。ところがその定義からは(すでに注意二および三で示したように)多数の実体の存在が導き出されえない。ゆえにそのことから、同一本性を有する実体はただ一つしか存在しないことが必然的に出てくる。そしてこれが我々の証明しようとしたことであった。
定理九 およそ物がより多くの実在性あるいは有をもつに従ってそれだけ多くの属性がその物に帰せられる。
証明 定義四から明白である。
定理一〇 実体の各属性はそれ自身によって考えられなければならぬ。
証明 なぜなら、属性とは知性が実体についてその本質を構成していると知覚するものである(定義四により)。したがってそれは(定義三により)それ自身によって考えられなければならぬ。Q・E・D・
備考 これから分かるのは、たとえ二つの属性が実在的(レアリテル)に区別されて考えられても、言いかえれば一が他の助けを借りずに考えられても、我々はそのゆえにその両属性が二つの実有あるいは二つの異なる実体を構成するとは結論しえないことである。事実その属性のおのおのがそれ自身によって考えられるというのは実体の本性なのである。なぜなら、実体の有するすべての属性は常に同時に実体の中に存し、かつ一が他から産出されえず、おのおのは実体の実在性あるいは有を表現するからである。ゆえに一実体に多数の属性を帰することは少しも不条理でない。それどころか、おのおのの実有がある属性のもとで考えられなければならぬこと、そしてそれはより多くの実在性あるいは有をもつに従って必然性(すなわち永遠性)と無限性とを表現するそれだけ多くの属性をもつこと、そうしたことほど自然において明瞭なことはないのである。したがってまた、絶対に無限な実有を、おのおのが永遠・無限な一定の本質を表現する無限に多くの属性から成っている実有(我々が定義六で述べたように)と定義しなければならぬことほど明瞭なこともないのである。
だが今もしある人が、ではいかなる標識によって我々は諸実体の相違を識別しうるかと問うならば、その人は次の諸定理を読むがよい。その諸定理によって、自然のうちにはただ一つの実体しか存在しないこと、またその実体は絶対に無限なものであること、したがってそうした標識を求めることは無用であることが判明するであろう。
定理一一 神、あるいはおのおのが永遠・無限の本質を表現する無限に多くの属性から成っている実体、は必然的に存在する。
証明 これを否定する者は、もしできるなら、神が存在しないと考えよ。そうすれば(公理七により)その本質は存在を含まない。ところがこれは(定理七により)不条理である。ゆえに神は必然的に存在する。Q・E・D・
別の証明 すべて物についてはなぜそれが存在するか、あるいはなぜそれが存在しないかの原因ないし理由が指示されなくてはならぬ。例えば、三角形が存在するなら、なぜそれが存在するかの理由ないし原因がなければならぬし、存在しないなら同様にそれの存在することを妨げたりその存在を排除したりする理由ないし原因がなければならぬ。だがこの理由ないし原因は物の本性のうちに含まれているかそれとも物の外部にあるかそのどちらかでなければならぬ。例えば、なぜ四角の円が存在しないかの理由は四角の円なるものの本性自身がこれを物語る。つまりそうしたものの本性が矛盾を含むからである。これに反して、なぜ実体が存在するかということは、やはり実体の本性のみから出てくる。すなわちその本性が存在を含むからである(定理七を見よ)。しかしなぜ円あるいは三角形が存在するかまたはなぜ存在しないかの理由は、円や三角形の本性からは出てこず、一般に物体的自然の秩序から出てくる。すなわち三角形が現に必然的に存在するか、それとも現に存在することが不可能であるかは、そうした秩序から出てこなければならぬのである。以上のことはそれ自体で明白である。この帰結として、存在することを妨げる何の理由も原因もない物は必然的に存在することになる。だからもし神の存在することを妨げたり神の存在を排除したりする何の理由も原因も有りえないとすれば、我々は神が必然的に存在することを絶対的に結論しなければならぬ。だがもしそうした理由ないし原因があるとすれば、それは神の本性それ自身のうちに在るか、それともその外部にすなわち異なった本性を有する他の実体のうちに在るかでなければならない。なぜなら、もしそれが同じ本性を有する実体であるとしたら、すでにそのことによって、神の存在することが容認されるからである。ところが(神の本性とは異なる)他の本性を有する実体は神とは何の共通点も有せず(定理二により)、したがってそれは神の存在を定立することも排除することもできない。このようなわけで、神の存在を排除する理由ないし原因が神の本性の外部には在りえないのだから、それは必然的に〜〜もし神が存在しないとするなら〜〜神の本性それ自身のうちになければならぬ。そうなればその本性は(我々の第二の例により)矛盾を含むことになるであろう。しかし、そうしたことを絶対に無限で最高完全である実有について主張することは不条理である。ゆえに神のうちにも神の外にも神の存在を排除する何の原因ないし理由もない。したがって神は必然的に存在する。Q・E・D・
別の証明 存在しえないことは無能力であり、これに反して存在しうることは能力である(それ自体で明らかなように)。だからもし今必然的に存在しているものが有限な実有だけであるとすれば、有限な実有は絶対的に無限な実有よりも有能であることになろう。しかしこれは(それ自体で明らかなように)不条理である。ゆえに何物も存在しないか、それとも絶対に無限な実有もまた必然的に存在するか、そのどちらかである。ところが我々は、我々のうちにかそうでなければ必然的に存在する他の物のうちに存在している(公理一および定理七を見よ)。ゆえに絶対的に無限な実有、言いかえれば(定義六により)神は必然的に存在する。Q・E・D・
備考 この最後の証明において私は神の存在をアポステリオリに示そうとした。これは証明が容易に理解されるようにであって、同じ根底から神の存在がアプリオリに帰結しえないためではない。なぜなら、存在しうることが能力である以上は、ある物の本性により多くの実在性が帰するに従ってその物はそれだけ多くの存在する力を自分自身に有することになり、したがって絶対に無限な実有すなわち神は存在する絶対に無限な能力を自分自身に有することになり、こうして神は絶対的に存在することになるからである。
しかし多くの人々はおそらくこの証明の自明性を容易に理解しえないであろう。それというのも彼らは外的諸原因から生ずる物のみを観想することに慣れているからである。そしてそれらの物のうち早く生ずる物すなわち容易に存在する物はまた容易に滅びるのを見、これに反してより多くの属性を有すると考えられる物はより生じ難い、すなわち存在するのがそう容易でないと判断しているのである。しかし彼らをこうした偏見から解放するためには「早く生ずるものは早く滅ぶ」という格言がどんな意味で真理であるか、また全自然を顧慮すれば、一切は等しく容易であるかそれともそうではないかということをここに示す必要はない。ただここでは外的諸原因から生ずる物について語っているのではなく、どんな外的原因からも産出されえない実体(定理六により)についてのみ語っているのであることを注意するだけで十分である。なぜなら、外的諸原因から生ずる物は、多くの部分から成っていようと少ない部分から成っていようと、それが完全性あるいは実在性に関して有する一切を外的原因の力に負っており、したがってその存在は外的原因の完全性からのみ生じ、それ自身の完全性からは生じない。これに反して実体は、完全性に関して有するすべてのものを外的原因にはまったく負っていない。ゆえにその存在もまたその本性のみから帰結されなければならぬ。したがってその存在はその本質にほかならない。このようにして、完全性は物の存在を排除しないばかりでなく、かえってこれを定立し、これに反して不完全性は物の存在を排除する。したがって我々は、どのような物の存在についても、絶対的に無限なあるいは完全な実有、すなわち神の存在についてほど確実ではありえない。なぜなら神の本質は、一切の不完全性を除外し、絶対的完全性を含むがゆえに、まさにそのことによってその存在を疑う一切の原因を排除し、その存在について最高の確実性を与えるからである。これは多少でも注意する人にとってはきわめて明白であろうと私は信ずる。
定理一二 ある実体をその属性のゆえに分割可能であるとするような考え方は、実体のいかなる属性についてもあてはまらない。
証明 なぜなら、そのように考えられた実体の分割された部分は、実体の本性を保持するか保持しないかであろう。第一の場合(すなわちそれが実体の本性を保持する場合)は、おのおのの部分は無限であり(定理八により)、また(定理六により)自己原因でなければならぬ。そして(定理五により)異なった属性から成らなければならぬ。したがって一の実体から多数の実体が構成されうることになる。これは(定理六により)不条理である。これに加えて部分は(定理二により)その全体と何の共通点ももたぬことになり、また全体は(定義四および定理一〇により)その部分なしに在りかつ考えられうることになる。これが不条理なことは何びとも疑いがないであろう。これに反して第二の場合すなわち部分が実体の本性を保持しない場合は、実体全体は同じような部分に分割されて実体の本性を喪失し、存在することをやめるであろう。これも(定理七により)不条理である。
定理一三 絶対に無限な実体は分割されない。
証明 なぜなら、もし分割されるとすれば、分割された部分に絶対に無限な実体の本性を保持するか保持しないかであろう。第一の場合なら、同じ本性を有する多数の実体が存在することになるであろう。これは(定理五により)不条理である。第二の場合には、絶対に無限な実体は(上に述べたように)存在することをやめうることになり、これもまた(定理一一により)不条理である。
系 これらの帰結として、いかなる実体も、したがってまたいかなる物体的実体も、それが実体である限り、分割されないことになる。
備考 実体が分割されないことは、次のことからだけでももっと単純に理解される、〜〜実体の本性は無限としか考えられえない、ところが実体の部分とは有限なる実体のこととしか解することができない、これは(定理八により)明白な矛盾を含んでいる。
定理一四 神のほかにはいかなる実体も存しえずまた考えられえない。
証明 神は実体の本質を表現するあらゆる属性が帰せられる絶対に無限な実有であり(定義六により)、そして必然的に存在する(定理一一により)。ゆえにもし神のほかに何らかの実体が存するとすれば、その実体は神のある属性によって説明されなければならぬであろう。そうなれば、同じ属性を有する二つの実体が存在することになり、これは(定理五により)不条理である。したがって神のほかにはいかなる実体も存しえない。したがってまたいかなる実体も考えられえない。なぜなら、もし考えられうるとすれば、必然的にそれは存在するものとして考えられなくてはならぬが、これは(この証明の始めの部分により)不条理である。ゆえに神のほかにはいかなる実体も存しえずまた考えられえない。Q・E・D・
系一 これからくるきわめて明白な帰結として、第一に、神は唯一であること、言いかえれば(定義六により)自然のうちには一つの実体しかなく、そしてそれは絶対に無限なものであることになる。これは我々がすでに定理一〇の備考で暗示したことである。
系二 第二に、延長した物および思惟する物は神の属性であるか、そうでなければ(公理一により)神の属性の変状であるということになる。
定理一五 すべて在るものは神のうちに在る、そして神なしには何物も在りえずまた考えられえない。
証明 神のほかにはいかなる実体も存せずまた考えられえない(定理一四により)。言いかえれば(定義三により)神のほかにはそれ自身のうちに在りかつそれ自身によって考えられる物は何もない。一方、様態は(定義五により)実体なしには在りえずまた考えられえない。つまり様態は神の本性のうちにのみ在りうるし、かつこれによってのみ考えられうる。ところが実体と様態のほかには何物も存しない(公理一により)。ゆえに何物も神なしには在りえずまた考えられえない。Q・E・D・
備考 神が人間のように物体〔身体〕と精神とから成り・感情に支配される、と想像する人々がある。しかし彼らが神の真の認識からどんなに遠ざかっているかはすでに証明されたことどもから十分明白である。私はこうした人々のことを問題にせずにおこう。神の本性についていやしくも考察したほどの人なら誰でもみな神が物体的であることを否定するからである。このことを彼らは、次のことから、〜〜物体とは長さ・幅・深さを有しある一定の形状に限定された量をいうのであるが、神すなわち絶対に無限な実体についてそうしたことを言うほど不条理なことはありえないということから、最もよく証明している。
しかし一方彼らは、このことを証明するのに用いた他の諸理由によって、彼らが物体的実体そのものあるいは延長的実体そのものをも神の本性からまったく遠ざけていることを明らかにし、そして物体的実体は神から創造されたものであると主張する。しかしそれがどんな神の能力によって創造されえたのかを彼らは全然知っていない。これは彼らが自分自らの言うところを理解していない明白な証拠である。私はいかなる実体も他のものから産出ないし創造されえないことを、少なくも自分の判断では、十分明瞭に証明した(定理六の系および定理八の備考二を見よ)。我々はまた定理一四で、神のほかにはいかなる実体も存しえずまた考えられえないことを示し、このことから〈(この部の同定理の系二の中で)〉延長的実体が神の無限に多くの属性の一であることを結論した。
しかしこれをもっと詳しく説明するため、私はここに反対者たちの論拠を反駁するであろう。彼らの論拠はすべて次の点に帰着する。
第一に彼らは、物体的実体が実体として部分から成っていると思っている。そのゆえに彼らはそれが無限でありうることを、したがってまた神に属しうることを否定する。彼らはこれを多数の例で説明する。その一、二を私は引用してみよう。彼らはこう言う。〜〜もし物体的実体が無限であるなら、それが二つの部分に分割されると考えてみよ、そうすればその各部分は有限であるか無限であるかであろう、もし前の場合なら無限のものが二つの有限なる部分から成ることになるが、これは不条理である。もし後の場合〈すなわち各部分が無限である〉ならある無限のものより二倍の大きさの無限のものが存することになるがこれも不条理である。次に、もし無限の量をフィート単位で測るならそれは無限に多くのフィートから成るに相違ない。またインチ単位で測るなら同様に〔それは無限に多くのインチから成るに違いない〕、したがって一の無限なる数より三倍大きいことになり〈これも前のことに劣らず不条理である〉、最後に、もしある無限の量の中の一点から発するAB、ACのような二線が初めはある一定の距離をもって遠ざかりつつ無限に延長されると考えるならばBとCの間の距離はたえず増大して、ついには限定された距離から限定されえぬものになるであろう。〜〜こうしたもろもろの不条理は、彼らの考えによれば、無限の量を仮定することから生ずるのであるから、彼らはこのことから、物体的実体は有限でなければならぬこと、したがってまたそれは神の本質には属さないことを結論するのである。
 第二の論拠を、彼らは同様に、神の最高完全性からとっている。彼らは言う。神は最高完全な実有であるから働き受けることができぬ、ところが物体的実体は分割可能であるから働きを受けることができる、ゆえに物体的実体は神の本質に属さないと。
第二の論拠を、彼らは同様に、神の最高完全性からとっている。彼らは言う。神は最高完全な実有であるから働き受けることができぬ、ところが物体的実体は分割可能であるから働きを受けることができる、ゆえに物体的実体は神の本質に属さないと。
このようなものが著作家たちの間に見られる論拠である。彼らはこれによって、物体的実体は神の本性に価せずまた神の本性に属さないこと示そうと試みている。しかし正当に注意する者は、私がこれにたいしてすでに答弁していること見いだすであろう。なぜなら、これらの論拠は物体的実体が部分から成るという仮定の上にのみ立っているのであるが、そうした仮定が不条理なことは私のすでに(定理一二および定理一三の系)示したところであるから。さらにまた事態を正常に熟考しようとする者は、次のことを、〜〜すなわち、延長的実体が有限であるという彼らの結論の基礎となっているこれらすべての不条理(それについて今私は論争しないがもしそれがみな不条理なものとして)は決して無限なる量を仮定することから生ずるのではなく、むしろ無限なる量が測定可能でありかつ有限な部分から成ると仮定することから生ずるということを、認めるであろう。ゆえにこの仮定から生ずるもろもろの不条理から彼らの結論しうることは、〜〜無限なる量は測定可能ではなくかつ有限な部分から成りえない〜〜ということだけである。そしてこれは我々が上に(定理一二その他)すでに証明したことと同じである。だから、彼らが我我を狙った投槍は、実は彼ら自身に向かって投げられているのである。
ゆえにもし彼らがそれにもかかわらず、彼らのこの不条理な仮定から、延長的実体は有限でなければならぬと結論しようと欲するなら、それはある人が、円は四角形の諸特質を有すると想像して、それから、円は円周に向かって引かれたすべての直線の等しいような中点を有しない、と結論するのとまったく異なるところがない。なぜなら、無限で唯一で不可分であるとしか考えることのできない物体的実体(定理八、五および一二を見よ)について、彼らは、それが有限であることを結論するために、それは有限な部分から成り、多様であり、可分的であると考えているのだからである。同様にまた他の人々は、線が点から成ると想像した上で、線が無限に分割されえないことを示す多くの論拠を発見することを心得ている。そして実に、物体的実体が物体あるいは部分から成るという仮定は、物体が面から成り面が線から成り最後に線は点から成るという仮定に劣らず不条理なのである。
このことは明晰な推理が誤りないものであることを知るすべての人々、ことに空虚の存在を否定する人々が容認しなければならぬことである。なぜなら、もし物体的実体はその諸部分が実在的に区別されうるようなふうに分割されうるものとしたら、その一部分が消滅して他の部分は依然として前のように相互に結合しているということも不可能ではなくなるであろう。また空虚ができないようなふうにすべての部分が接合しなければならぬという理由もなくなるであろう。まったくのところ、相互に実在的に区別される物にあっては、一が他なしに在りうるしまたその状態にとどまりうるのである。しかし自然の中には空虚なるものが存せず(これについては他の個所で述べる)、すべての部分は空虚ができないようなふうにたがいに協力し合わなければならぬのであるから、このことからしてもまた、部分は実在的には区別されえぬこと、すなわち物体的実体はそれが実体である限り分割されえぬことが帰結されるのである。
しかし今もし誰かが、なぜ我々は生まれつき量を分割する傾向を有するのかと尋ねるなら、私はその人にこう答える。我々は量を二様の仕方で考える。一は抽象的にあるいは皮相的にであり、これは量を〈普通に〉表象する場合である。他は量を実体として考える場合であり、これは単に知性のみによって〈表象の助けを借りずに〉行なわれる。ゆえにもし我々が表象においてあるままの量に心を留める(これはしばしばそしてより容易に我々のするところだが)なら、量は有限で可分的で部分から成るものとして現われるであろう。これに反してもし知性においてあるままの量に心を留め、そしてこれを実体である限りにおいて考える(これはきわめて困難なことだが)なら、それは、我々がすでに十分示したように、無限で唯一で不可分なものとして現われるであろう。このことは表象と知性とを区別することを知っているすべての人に十分明白であろう。ことに物質はいたるところで同一であってその部分は物質がいろいろなふうに変状すると考えられる限りにおいてのみ区別されるのであり、したがってその部分は様態的にのみ区別されて実在的には区別されないということにも注意するならば、いっそう明らかであろう。例えば水は水である限りにおいて分割されまたその部分は相互に分離されると我々は考える。しかしそれが物体的実体たる限りにおいてはそうでない。その限りにおいては水は分離されも分割されもしない。さらに水は水としては生じかつ滅する。しかし実体としては生ずることも滅することもない。 (水)
これをもって私は第二の論拠にも答弁したと信ずる。なぜなら、それもまた、物質は実体として可分的でありかつ部分から成っているということに基づいているからである。そして仮にこの答弁でまだ十分でないとしても、なぜ物質が神の本性に価しないかは私の解しえないところである。なぜなら(定理一四により)神のほかには神の本性が働きを受けるいかなる実体も有りえないからである。あえて言うが、すべてのものは神のうちに在る。そして生起する一切のことは神の無限なる本性の諸法則によってのみ生起しかつ神の本質の必然性から生ずる(私がまもなく示すように)。ゆえに神が他のものから働きを受けるとか延長的実体が神の本性に価しないとかいうことは、いかなる理由をもってしても言うことができない、〜〜たとえ延長的実体を可分的であると仮定してもただそれが永遠かつ無限であることを容認しさえするならば。しかし今のところこのことについてはこれで十分である。
定理一六 神の本性の必然性から無限に多くのものが無限に多くの仕方で(言いかえれば無限の知性によって把握されうるすべてのものが)生じなければならぬ。
証明 この定理は次のことに注意しさえすれば誰にも明白でなければならぬ。それはおよそ物の定義が与えられると、そこから知性は多数の特質を〜〜実際にその定義(言いかえれば物の本質そのもの)から必然的に生ずるもろもろの特質を〜〜結論すること、そして物の定義がより多くの実在性を表現するにつれて、言いかえれば定義された物の本質がより多くの実在性を含むにつれて、それだけ多くの特質を結論すること、これである。ところで神の本性は、おのおのが自己の類において無限の本質を表現する絶対無限数の属性を有するから(定義六により)、このゆえに、神の本性の必然性から無限に多くのものが無限に多くの仕方で(言いかえれば無限の知性によって把握されうるすべてのものが)必然的に生じなければならぬ。Q・E・D・
系一 この帰結として、神は無限の知性によって把握されうるすべての物の起成原因であることになる。
系二 第二に、神はそれ自身による原因であって偶然による原因ではないことになる。
系三 第三に、神は絶対に第一の原因であることになる。
定理一七 神は単に自己の本性の諸法則のみによって働き、何ものにも強制されて働くことがない。
証明 単に神の本性の必然性のみから、あるいは(同じことだが)単に神の本性の諸法則のみから、無限に多くのものが絶対的に生ずることを私は今しがた定理一六で示した。また定理一五では、いかなるものも神なしには在りえずまた考えられえず、一切は神のうちに在ることを証明した。ゆえに神の外には神を働くように決定しあるいは強制するいかなるものも存しえない。したがって神は単に自己の本性の諸法則のみによって働き、何ものにも強制されて働くことがない。Q・E・D・
系一 この帰結として第一に、神の本性の完全性以外には神を外部あるいは内部から駆って働かせるいかなる原因も存在しない、〈むしろ神は自己の完全性の力のみによって起成原因である、〉ということになる。
系二 第二に、ひとり神のみが自由原因であることになる。なぜなら、ひとり神のみが、単に自己の本性の必然性のみによって存在し(定理一一および定理一四の系一により)、かつ単に自己の本性の必然性のみによって働く(前定理による)。したがって(定義七により)ひとり神のみが自由原因である。Q・E・D・
備考 他の人々はこう思っている〜〜神は、神の本性から生ずると我々の言ったことがら、言いかえれば神の力の中に在ることがら、そうしたことがらを生じないようにしたり、あるいはそれを神自身産出しないようにしたりすることができる(彼らはそう信ずる)がゆえに自由原因なのである〜〜と。しかしこれは、〜〜神は、三角形の本性からその三つの角の和が二直角に等しいことが起こらないようにしたり、あるいは与えられた原因から何の結果も生じないようにしたりすることができる〜〜と言うのと同然であって、不条理である。
なお私は以下において、この定理の助けを借りずに、神の本性には知性も意志も属さないことを示すであろう。
たしかに私は、神の本性に最高の知性と自由な意志とが属することを証明しうると信じている多くの人々がいることを知っている。なぜなら彼らは、我々のうちにおいて最高完全性を意味するもの以外には、神に帰しうるより完全な何ものをも知らないと言っているからである。しかし、神を現実に最高の認識者と考えながらも、彼らは、神が現実に認識することをすべて存在するようにさせることができるとは信じない。なぜならもしそうなれば、彼らは、神の能力を破壊すると思うからである。彼らは言う、神がその知性のうちに存することをすべて創造したとすれば、もうそれ以上何ものをも創造することができないであろうと。そしてこれは彼らの信念によれば神の全能と矛盾するのである。ゆえに彼らは、神が一切のことにたいして無関心であってただある絶対的な意志によって創造しようと決意したもの以外には何ものも創造しないという意見に傾いたのである。
これに反して私は、神の最高能力あるいは神の無限の本性から無限に多くのものが無限に多くの仕方で、すなわちあらゆるものが、必然的に流出したこと、あるいは常に同一の必然性をもって生起すること、そしてこれは三角形の本性からその三つの角の和が二直角に等しいことが永遠から永遠にわたって生起するのと同じ次第であること、そうしたことを十分明瞭に示したと信ずる(定理一六を見よ)。ゆえに神の全能は現実に、永遠から存しかつ、永遠にわたって同一現実性にとどまるであろう。そしてこの仕方で神の全能は、少なくとも私の判断によれば、はるかに完全に確立される。そればかりでなく反対者たちは神の全能を否定するように見える(あからさまに言ってよいならば)。というのは彼らは、神が無限に多くの創造可能なものを認識しながら、しかもそれを決して創造しえないことを認めないわけにはいかないからである。なぜなら、もしそうではなくて、神がその認識するものをすべて創造したとしたら、神は、彼らの見解によれば、自己の全能を使い果して不完全なものになるからである。ゆえに彼らは、神を完全な者として立てるためには、同時に、神は自己の能力の及びうることをことごとくはなしえないと主張しなければならぬ結果になるのであるが、およそいかなる仮定にしても、これ以上不条理なあるいはこれ以上神の全能に矛盾するものを私は知らないのである。
さらに我々が一般に神に帰している知性および意志についてここでなお少しく語りたい。もしこの知性および意志が神の永遠なる本質に属するとしたら、この両属性はたしかに、人々が通常解しているのとは異なって解されるべきである。すなわち神の本質を構成するような知性および意志なら、我々の知性および意志とは天地の相違がなければならぬのであって、それはただ名前において一致しうるのみで他のいかなる点においても一致しえないことは、あたかも星座の犬と吠える動物の犬との相互の間におけるごとくであろう。このことを私は次のように証明するであろう。もし知性が神の本性に属するとしたら、その知性は本性上、我々の知性のごとく、その対象があってあとからこれを認識したり(大抵の人々が主張するように)、あるいはその対象と同時にあったりすることができないであろう。神は原因として万物に先立つからである(定理一六の系一による)。むしろ反対に、真理ならびに物の形相的本質(エッセンティア・フォルマリス)は、それが神の知性の中に想念的(オブエクティヴェ)に〔すなわち観念として〕その通りに存在するがゆえにこそそのようにあるのである。だから神の知性は、神の本質を構成すると考えられる限り、実際に物の原因〜〜物の本質ならびに存在の原因〜〜なのである。このことは神の知性・意志および能力が同一であると主張した人々も認めていたように思われる。このようにして神の知性は物の唯一の原因、すなわち(今言ったように)物の本質ならびに存在の唯一の原因であるから、それ自身は、本質に関しても存在に関しても、物とは必然的に異ならなければならぬ。なぜなら、ある原因から生ぜられたものは、まさに原因から受けたものにおいてその原因と異なるのであり、(このゆえにこそそれはそうした原因の結果と呼ばれるのである)から。例えば人間は他の人間の存在の原因ではあるがその本質の原因ではない。この本質は永遠の真理だからである。そしてこのゆえに、人間は本質に関してはまったく一致しうるが、存在においては異ならなければならぬ。したがって一人の人間の存在が滅びたとてそのゆえに他の人間の存在が滅びるということはないであろう。しかしもし一人の人間の本質が破壊されて虚偽のものになるということがありうるとしたら、他の人間の本質もまた破壊されるであろう。このようなわけで、ある結果の本質ならびに存在の原因である物は、そうした結果とは本質に関しても存在に関しても異ならなければならぬ。ところが今、神の知性は我々の知性の本質ならびに存在の原因なのである。ゆえに神の知性は、神の本質を構成すると考えられる限り、我々の知性とは本質に関しても存在に関しても異なり、我々が主張したごとく、それは人間の知性とは名前において一致しうるだけで他のいかなる点においてもー致しないのである。
意志に関しても同じぐあいに議論を進めていけることは誰にも容易に分かるであろう。 64
定理一八 神はあらゆるものの内在的原因であって超越的原因ではない。
証明 在るものはすべて神のうちに在りかつ神によって考えられなければならぬ(定理一五より)。したがって(この部の定理一六の系一により)神はその中に在るものの原因である。これが第一の点である。次に神のほかにはいかなる実体も存在しえない(定理一四により)。言いかえれば(定義三により)神の外にあって自立するようないかなるものも存在しえない。これが第二の点であった。ゆえに神はあらゆるものの内在的原因であって超越的原因ではない。Q・E・D・
定理一九 神あるいは神のすべての属性は永遠である。
証明 なぜなら、神は実体であり(定義六により)、そしてそれは(定理一一により)必然的に存在する。言いかえれば(定理七により)その本性には存在することが属する。あるいは(同じことだが)その定義から存在することそのことが生起する。ゆえに神は(定義八により)永遠である。次に、神の属性とは神的実体の本質を表現するもの(定義四により)、言いかえれば実体に属するもの、と解されるべきである。したがって実体に属するすべてのものは属性の中に含まれていなければならぬ。ところが実体の本性には(すでに定理七で証明したように)永遠性が属する。ゆえにおのおのの属性は永遠性を含んでいなければならぬ。したがってすべての属性は永遠である。Q・E・D・
備考 この定理は私が神の存在を証明した仕方(定理一一)からもきわめて明瞭に分かる。つまりその証明から、神の存在はその本質と同様に永遠の真理であることが確立されるのである。さらに私は神の永遠性を他の仕方でも証明した(『デカルトの哲学原理』定理一九)。しかしこれをここでくりかえすことは必要ないであろう。
定理二〇 神の存在とその本質とは同一である。
証明 神ならびに神のすべての属性は永遠である(前定理により)。言いかえれば(定義八により)おのおのの属性は存在を表現する。ゆえに神の永遠なる本質を表わすその属性(定義四により)が同時に神の永遠なる存在を表わしている。言いかえれば神の本質を構成するもの自体が同時に神の存在を構成している。したがって神の存在とその本質とは同一である。Q・E・D・
系一 この帰結として第一に、神の存在はその本質と同様に永遠の真理であることになる。
系二 第二に、神あるいは神のすべての属性は不変であることになる。なぜなら、もしそれが存在に関して変化するなら、本質に関しても変化しなければならないであろう(前定理により)。言いかえれば(それ自体で明らかなように)異なるものが偽なるものになることになるであろう。これは不条理である。
定理二一 神のある属性の絶対的本性から生ずるすべてのものは常にかつ無限に存在しなければならぬ、言いかえればそれはこの属性によって永遠かつ無限である。
証明 この定理を否定しようとする者は、もしできるなら、神のある属性の絶対的本性からして、その属性の中に有限でかつ定まった存在ないし持続を有するあるものが生ずる、〜〜例えば思惟の中に神の観念が生ずる、と考えてみよ。さて思惟は神の属性と仮定されているのだから、その本性上必然的に無限である(定理一一により)。しかし思惟は神の観念を有する限り有限であると仮定されている。ところが(定義二により)思惟が有限と考えられるのはそれが思惟自身によって限定される場合のみである。だが思惟は神の観念を構成する限りにおいての思惟そのものによっては限定されない、なぜならその限りにおいて思惟は有限であると仮定されているのだから。ゆえにそれは神の観念を構成しない限りにおいての思惟によって限定されるのである、そしてそうした思惟もまた必然的に存在しなければならぬ(定理一一により)。これで見れば神の観念を構成しない思惟が存在することになる。したがって神の観念は絶対的なものである限りにおいての思惟の本性から必然的に生ずるのではないということになる(なぜなら神の観念を構成する思惟と構成しない思惟とが考えられるのであるから)。このことは仮定に反する。ゆえにもし神の観念が思惟の中に、またはあるものが神のある属性の中に(この証明は普遍的なものであるから何をとろうとも同様である)その属性の絶対的本性の必然性から生ずるとしたら、それは必然的に無限でなければならぬ。これが第一の点であった。
次に、ある属性の本性の必然性からこのようにして生起するものは定まった存在ないし持続を有することができない。なぜというに、これを否定しようと思う者は、ある属性の本性の必然性から生ずる物が神のある属性の中に在る、例えば神の観念が思惟の中に在ると仮定し、なおまたこの観念がかつて存在しなかったあるいは将来存在しなくなるであろうと仮定せよ。ところで思惟は神の属性と仮定されているがゆえに必然的にかつ不変的に存在しなければならぬ(定理一一および定理二〇の系二により)。ゆえに神の観念の持続する限界の外では(というのは神の観念はかつて存在しなかった、あるいは将来存在しなくなるであろうと仮定されているのだから)思惟は神の観念なしに存在しなければならないであろう。ところがこのことは仮定に反する。なぜなら、思惟が与えられればそれから必然的に神の観念が生ずると仮定されているのだから。このゆえに、思惟の中における神の観念、または、神のある属性の絶対的本性から必然的に生起するある物は、定まった持続を有することができ、むしろその属性によって永遠である。これが(証明すべき)第二の点であった。
神の絶対的本性から神のある属性の中に必然的に生起するすべてのものについても同じことがあてはまることに注意されたい。
定理二二 神のある属性が、神のその属性によって必然的にかつ無限に存在するようなそうした一種の様態的変状に様態化した限り、この属性から生起するすべてのものは同様に必然的にかつ無限に存在しなければならぬ。
証明 この定理の証明は前定理の証明と同様の仕方で進められる。
定理二三 必然的にかつ無限に存在するすべての様態は、必然的に、神のある属性の絶対的本性から生起するか、それとも必然的にかつ無限に存在する一種の様態的変状に様態化したある属性から生起するかでなければならぬ。
証明 なぜなら、様態は他のもののうちに在りかつ他のものによって考えられなければならぬ(定義五により)。言いかえれば(定理一五により)神のうちにのみ在りかつ神によってのみ考えられうる。ゆえにもし様態が必然的に存在しかつ無限であると考えられるなら、この二つのことは、必然的に、無限性と存在の必然性〜〜すなわち(定義八により同じことだが)永遠性〜〜とを表現すると考えられる限りにおいての、言いかえれば(定義六および定理一九により)絶対的に考察される限りにおいての、神のある属性によって結論ないし知覚されなければならぬ。ゆえに必然的にかつ無限に存在する様態は、神のある属性の絶対的本性から生起しなければならぬ。そしてこのことは直接的に起こるか(これについては定理二一)、それともその絶対的本性から生起するような、言いかえれば、(前定理により)必然的にかつ無限に存在するような、ある種の様態的変状を媒介として起こるかでなければならぬ。Q・E・D・
定理二四 神から産出された物の本質は存在を含まない。
証明 定義一から明白である。なぜならその本性(それ自体で考察された)が存在を含むような物は自己原因であって、単に自己の本性の必然性のみによって存在するからである。
系 この帰結として、神は物が存在し始める原因であるばかりでなく、物が存在することに固執する原因でもあること、あるいは(スコラ学派の用語を用いれば)神は物の「有ることの原因」でもあること、になる。なぜなら、物が存在していても存在していなくても、我々はその本質に注目するごとに、それが存在も持続も含まないことを発見する。したがってそれらの物の本質は、その存在なりその持続なりの原因であることができず、ただ存在することがその本性に属する唯一者たる神(定理一四の系一により)のみがこれをなしうるのである。
定理二五 神は物の存在の起成原因であるばかりでなく、また物の本質の起成原因でもある。
証明 これを否定するなら、神は物の本質の原因でないことになる。したがって(公理四により)物の本質は神なしに考えられうることになる。しかしこれは(定理一五により)不条理である。ゆえに神はまた物の本質の原因でもある。Q・E・D・
備考 この定理は定理一六からいっそう明瞭に帰結される。というのは、神の本性が与えられると、それから物の本質ならびに存在が必然的に結論されなければならぬということが定理一六から帰結されるからである。一言で言えば、神が自己原因と言われるその意味において、神はまたすべてのものの原因であると言われなければならぬ。このことはなお次の系からいっそう明白になるであろう。
系 個物は神の属性の変状(アフエクテイオ)、あるいは神の属性を一定の仕方で表現する様態(モードス)、にほかならぬ。この証明は定理一五および定義五から明らかである。
定理二六 ある作用をするように決定された物は神から必然的にそう決定されたのである。そして神から決定されない物は自己自身を作用するように決定することができない。
証明 物がある作用をするように決定されていると言われるのは必然的に積極的なあるもののためである(それ自体で明らかなように)。したがって神は自己の本性の必然性からそうしたものの本質ならびに存在の起成原因である(定理二五および一六により)。これが第一の点であった。これからまたこの定理の第二の部分がきわめて明瞭に帰結される。なぜなら、神から決定されない物が自己自身を決定しうるとしたら、この定理の第一の部分が誤りとなるであろう。しかしそれが不条理であることは我々の示した通りである。
定理二七 神からある作用をするように決定された物は自己自身を決定されないようにすることができない。
証明 この定理は公理三から明白である。
定理二八 あらゆる個物、すなわち有限で定まった存在を有するおのおのの物は、同様に有限で定まった存在を有する他の原因から存在または作用に決定されるのでなくては存在することも作用に決定されることもできない。そしてこの原因たるものもまた、同様に有限で定まった存在を有する他の原因から存在または作用に決定されるのでなくては存在することも作用に決定されることもできない。このようにして無限に進む。
証明 存在または作用に決定されているすべてのものは神からそのように決定されたのである(定理二六および定理二四の系により)。ところが有限で定まった存在を有する物は神のある属性の絶対的本性から産出されることができない。神のある属性の絶対的本性から生起するすべてのものは無限かつ永遠だからである(定理二一により)。ゆえにそれは神のある属性がある様態に変状したと見られる限りにおいて神ないし神の属性から生起しなければならぬ。なぜなら実体と様態のほかには何ものも存在せず(公理一ならびに定義三と五により)、そして様態は(定理二五の系により)神の属性の変状にほかならないからである。しかしそれはまた神のある属性が永遠かつ無限なる様態的変状(モディフィカティオ)に変状(アフェクトゥス)した限りにおいては神ないし神の属性から生起することができない(定理二二により)。ゆえにそれは神のある属性が定まった存在を有する有限な様態的変状に様態化した限りにおいて神ないし神の属性から生起し、あるいは存在ないし作用に決定されなくてはならない。これが第一の点であった。次にこの原因あるいはこの様態もまた(我々がこの定理の第一の部分を証明したと同じ理由により)、同様に有限で定まった存在を有する他の原因から決定されなければならぬ、そしてこの後者もまた(同じ理由により)他の原因から決定され、このようにして常に(同じ理由により)無限に進む。Q・E・D・
備考 ある種の物は神から直接的に産出されなければならぬ。神の絶対的本性から必然的に生起するものがすなわちそれである。また他の種の物はこの前者の媒介によって生起しなければならぬ。しかしこれとても神なしには存在することも考えられることもできない。この帰結として第一に、神は神自身が直接的に産出した物の絶対的な最近原因であることになる。私は(絶対的な最近原因と言う、そして)いわゆる自己の類における最近原因とは言わない。なぜなら、神の結果は原因としての神なしには存在することも考えられることもできないからである(定理一五および定理二四の系により)。第二に、神を個物の遠隔原因と名づけるのは、神が直接的に産出したもの・あるいはむしろ神の絶対的本性から生起するものと普通の個物とを区別するためになら別だが、本来的意味においては適当でないということになる。なぜなら、遠隔原因とは結果と何の関連もないものと我々は解するが、およそ存在する一切の物は神のうちに在り、かつ神なしには存在することも考えられることもできないように神に依存しているからである。
定理二九 自然のうちには一として偶然なものがなく、すべては一定の仕方で存在し・作用するように神の本性の必然性から決定されている。
証明 在るものはすべて神のうちに在る(定理一五により)。しかし神を偶然なものと呼ぶことはできない。なぜなら神は偶然的に存在するのではなく必然的に存在するからである(定理一一により)。次に神の本性の様態は、やはり神の本性から偶然的にではなく必然的に生起している(定理一六により)。そしてこれは神の本性が絶対的に働くように決定されたと見られる限りにおいても(定理二ーにより)、あるいは神の本性が一定の仕方で働くように決定されたと見られる限りにおいても(定理二七により)、同様である。さらに神はそれらの様態が単に存在する限りにおいてばかりでなく(定理二四の系により)、その上またそれらが(定理二六により)ある作用をなすように決定されたと見られる限りにおいても、それらの原因なのである。もしそれらの様態が神から決定されなかったとすれば、それが自己自身を決定するということは不可能であって、偶然そうなるなどということはない(同定理により)。また反対に、神から決定されたとしたら、それが自己自身を決定されていないようにすることは不可能であって、やはり偶然そうなるなどいうことはない(定理二七により)。ゆえに一切は、単に存在するようにだけではなく、さらにまた一定の仕方で存在し・作用するように神の本性の必然性から決定されているのであり、そして一として偶然なものはないのである。Q・E・D・
備考 先へ進む前にここで、能産的自然(ナトゥラ・ナトゥランス)および所産的自然(ナトゥラ・ナトゥラタ)をどう解すべきかを説明しよう〜〜というよりはむしろ注意しよう。というのは、前に述べたことどもからすでに次のことが判明すると信ずるからである。すなわち我々は能産的自然を、それ自身のうちに在りかつそれ自身によって考えられるもの、あるいは永遠・無限の本質を表現する実体の属性、言いかえれば(定理一四の系一および定理一七の系二により)自由なる原因として見られる限りにおいての神、と解さなければならぬ。これにたいして所産的自然を私は、神の本性あるいは神の各属性の必然性から生起する一切のもの、言いかえれば神のうちに在りかつ神なしには在ることも考えられることもできない物と見られる限りにおいての神の属性のすべての様態、と解する。
定理三〇 現実に有限な知性も、現実に無限な知性も、神の属性と神の変状を把握しなければならぬ。そして他の何ものをも把握することがない。
証明 真の観念はその対象と一致しなければならぬ(公理六により)。言いかえれば(それ自体で明らかなように)、知性のうちに想念的(オブエクティヴェ)に〔すなわち観念として〕含まれているものは必然的に自然のうちに存在しなければならぬ。ところが自然のうちには(定理一四の系一により)一つの実体しか、すなわち神しか、存在しない。また神のうちに在りかつ神なしには在ることも考えられることもできないもの(定理一五により)以外のいかなる変状も存在しない(同定理により)。ゆえに現実に有限な知性も、現実に無限な知性も、神の属性と神の変状を把握しなければならぬ。そして他の何ものをも把握することがない。Q・E・D・
定理三一 現実的知性は、有限なものであろうと無限なものであろうと、意志・欲望・愛などと同様に、能産的自然にではなく所産的自然に数えられなければならぬ。
証明 なぜなら、我々は知性を(それ自体で明らかなように)絶対的思惟とは解せず、単に思惟のある様態、〜〜欲望・愛などのごとき思惟の他の諸様態とは異なるある様態、と解する。したがってそれは(定義五により)絶対的思惟によって考えられなければならぬ。すなわち(定理一五および定義六により)思惟の永遠・無限な本質を表現する神のある属性によって考えられなければならず、しかもその属性なしには在ることも考えられることもできないようなふうに考えられなければならぬ。このゆえにそれは(定理二九の備考により)思惟のその他の諸様態と同様に、能産的自然にではなく所産的自然に数えられなければならぬ。Q・E・D・
備考 ここで私が現実的知性について語る理由は、何らかの可能的知性が存在することを認めているからではない。私はただ、一切の混乱を避けるため、我々のきわめて明瞭に知覚するもの、すなわち知性作用それ自身についてのみ語ることを欲したからである。知性作用は我々が何ものにもまして明瞭に知覚するものである。というのは我々が認識するすべてのものはみな知性作用についての我々の認識をより完全なものにするのに役立っているからである。
定理三二 意志は自由なる原因とは呼ばれえずして、ただ必然的な原因とのみ呼ばれうる。
証明 意志は知性と同様に思惟のある様態にすぎない。したがって(定理二八により)個々の意志作用は他の原因から決定されるのでなくては存在することも作用に決定されることもできない。そしてこの原因もまた他の原因から決定され、このようにして無限に進む。もし意志を無限であると仮定しても、それはやはり神から存在および作用に決定されなくてはならぬ。そしてこれは神が絶対に無限な実体である限りにおいてではなくて、神が思惟の無限・永遠なる本質を表現する一属性を有する限りにおいてである(定理二三により)。ゆえに意志はどのように考えられても、つまり有限であると考えられても無限であると考えられても、それを存在および作用に決定する原因を要する。したがってそれは(定義七により)自由なる原因とは呼ばれえずして、ただ必然的なあるいは強制された原因とのみ呼ばれうる。Q・E・D・
系一 この帰結として第一に、神は意志の自由によって作用するものではないということになる。
系二 第二に、意志および知性が神の本性に対する関係は、運動および静止、または一般的に言えば、一定の仕方で存在し作用するように神から決定されなければならぬすべての自然物(定理二九により)が神に対する関係と同様であるということになる。なぜなら、意志は、他のすべての物のように、それを一定の仕方で存在し作用するように決定する原因を要するからである。そしてたとえ与えられた意志あるいは知性から無限に多くのものが生起するとしても、神はそのために意志の自由によって働くと言われえないことは、運動および静止から生起するもののために(というのはこれからもまた無限に多くのものが生起する)神は運動および静止の自由によって働くと言われえないのと同様である。ゆえに意志は、他の自然物と同様に、神の本性には属さないで、むしろこれに対しては、運動および静止、また神の本性の必然性から生起しかつそれによって一定の仕方で存在し作用するように決定されることを我々が示した他のすべてのものと、まったく同様な関係に立っているのである。
定理三三 物は現に産出されているのと異なったいかなる他の仕方、いかなる他の秩序でも神から産出されることができなかった。
証明 なぜなら、すべての物は与えられた神の本性から必然的に生起し(定理一六により)、かつ神の本性の必然性によって一定の仕方で存在し・作用するように決定されている(定理二九により)。だからもし物が異なった本性をもちあるいは異なった仕方で作用するように決定されて、その結果自然の秩序が今と異なったものになるということがありうるとしたら、神の本性もまた現に在るのとは異なったものになりうるであろう。そこで(定理一一により)この異なった神の本性もまた同様に存在しなければならぬであろう。したがって二つまたは多数の神が存在しうることになるであろう。これは(定理一四の系一により)不条理である。それゆえに物は他のいかなる仕方、他のいかなる秩序においても云々。Q・E・D・
備考一 私はこれで、物自身の中にはその物を偶然であると言わしめるような何ものも絶対に存在しないことを十二分に明白に示したから、ここに私は、偶然ということをどう解すべきかを手短かに説明しよう。しかしその前に、必然および不可能ということをどう解すべきかを語ろう。ある物が必然と呼ばれるのは、その物の本質に関してか、それとも原因に関してかである。何となれば、ある物の存在は、その物の本質ないし定義からか、それとも与えられた起成原因から必然的に生起するからである。次に、ある物が不可能と呼ばれるのも、やはり同様の理由からである。すなわちその物の本質ないし定義が矛盾を含むか、それともそうした物を産出するように決定された何の外的原因も存在しないからである。これに反して、ある物が偶然と呼ばれるのは、我々の認識の欠陥に関連してのみであって、それ以外のいかなる理由によるものでもない。すなわち、その本質が矛盾を含むことを我々が知らないような物、あるいはその物が何の矛盾も含まないことを我々がよく知っていてもその原因の秩序が我々に分からないためにその物の本質について何ごとも確実に主張しえないような物、そうした物は我々に必然であるとも不可能であるとも思われないので、したがってそうした物を我々は偶然とか可能とか呼ぶのである。
備考二 前述のことからして、物は与えられた最も完全な本性から必然的に生起したのだから最高の完全性において神から産出されたのだということが明瞭に帰結される。このことは神に何の不完全性をも負わせるものではない。なぜならまさに神の完全性がこのことを我々に主張するように迫るのだから。のみならずもし逆ならば、神が最高完全でないということが明瞭に帰結されるであろう。なぜならもし物が他の仕方で産出されたとしたら我々が最高完全な実有の考察に基づいて神に帰せざるをえなかった本性とは異なる他の本性を神に帰することになるからである(先ほど示したように)。だが多くの人々がこの見解を不条理なものとして排斥しこれを熟考する気にならないことを私は疑わない。それというのも彼らは我々が述べたもの(定義七)とはまるで異なる他の自由を、〜〜すなわち絶対的意志を、神に帰するのに慣れているからにほかならない。しかし彼らが事態を瞑想し・我々の諸証明の系列をよく熟慮しようとするならば、ついに彼らは、いま神に帰しているような種類の自由を単に愚かしいものとしてだけではなく、さらにまた知識の大きな障害としてまったく放棄するだろうこと、これまた私の疑わないところである。
ここに定理一七の備考で述べたことを再び繰りかえすことは必要ないであろう。しかし仮に意志が神の本質に属することを認めたとしても、やはり神の完全性からして、物はいかなる他の仕方、他の秩序においても神から創られることができなかったという帰結になることを私は彼らのために改めて示したい。これは我々が次のことを考察するなら容易に明らかになるであろう。それはまず彼ら自身の容認していること、すなわちすべての物がその現に在るところのものであるのは神の決意および意志のみに依存する(そうでなければ神は万物の原因ではなくなるから)ということである。次に神のすべての決意は永遠このかた神自身によって定められた(そうでなければ神に不完全性と不恒常性とを負わせることになるから)ということである。ところで永遠の中にはいつということがなくまた以前ということも以後ということもないのであるから、このことから、すなわち神の完全性だけからして、神は決して他の決意をなしえないしまたなしえなかったこと、あるいは神はその決意の以前には存在しなかったしまたその決意なしには存在しえないことが帰結されるのである。
ところが彼らは言うであろう、たとえ神が異なった自然を創造したと仮定しても、あるいは神が永遠このかた自然ならびにその秩序に関して異なった決意をしたと仮定しても、そのために神には何の不完全性も生じないであろうと。だがこういうならば彼らは同時に神が〔今なお〕その決意を変更しうることを容認するものである。なぜなら、もし神が自然およびその秩序に関して決意したのとは異なった決意をしたなら、すなわち自然に関して他のことを意志したり概念したりするなら、必然的に神は現に有するのとは異なった知性・現に有するのとは異なった意志をもったであろう。そしてもし神の本質と完全性とを少しも変更することなしに神に他の知性・他の意志を帰しうるとすれば、神が被造物に関するその決意を今なお変更してしかも依然として等しく完全にとどまることができない理由はないからである。被造物およびその秩序に関する神の知性と意志がどんなふうに考えられようとも、それは神の本質および完全性に何の影響も及ぼさないと言うのであるからには。
さらにまた私の知るすべての哲学者は、神の中には可能的知性は存在せずただ現実的知性のみが存在することを容認する。ところで神の知性と意志は神の本質と区別されないことと、これもまたすべての哲学者の容認するところであるから、このことからまた、もし神が他の現実的知性および他の意志を持つとしたら、神の本質もまた必然的に異なるものであるべきこと、したがって(私が始めから主張したように)もし物が現に在るのと異なったふうに神から産出されたとしたら、神の知性および意志、言いかえれば(人々の容認するように)神の本質は異なったものでなければならぬこと、になる。これは不条理である。
このように、物はいかなる他の仕方・いかなる他の秩序においても神から産出されえなかったのであり、そしてこの定理の真理は神の最高完全性からの帰結なのであるから、神が自己の知性の中にあるすべてのものを認識したのと同一の完全性をもってそれを創造することを欲しなかったと我々を信じさせるようないかなる根拠ある理由もまったく存在しえないのである。
しかし彼らは言うであろう、物それ自身の中には完全性も不完全性もなく、物の中にあってそのため物が完全とか不完全とか善とか悪とか呼ばれるところのものは神の意志にのみ依存する、したがって神は、もし欲したなら、現に完全であるものをきわめて不完全なものであるようにすることができたろうし、また反対に(現に物の中にあって不完全性を意味するものをきわめて完全なものであるようにすることが)できたであろうと。しかしこれは、その意志することを必然的に認識する神が、自らの意志によって、物をその認識するのとは異なった仕方で認識するようにすることができると公然と主張するのに異ならない。これは(今しがた示したように)はなはだしい不条理である。ゆえに私は彼らの論証を彼ら自身に投げ返して次のように言うことができる。一切は神の力に依存する、だから物が異なったようにありうるためには神の意志もまた必然的に異なっていなければならぬ、ところが神の意志は異なったようにあることができない(我々が今しがた神の完全性に基づいてきわめて明瞭に示したように)、ゆえに物は異なってあることができないと。
一切を神の勝手な意志に従属させ、すべては神の裁量に依存すると主張するこの意見は、神がすべてを善の考慮のもとになすと主張する人々の意見ほどは真理から遠ざかっていないと私も認める。なぜなら後者は、神に依存しないある物、神が行動に際して理想と目し・あるいは一定の目的としてそれに向かって努力するようなある物、そうしたある物を神の外に立てているように見えるからである。これはまったく神を運命に従属させるのにほかならぬのであって、我々が示したように万物の本質ならびに存在の第一にして唯一の自由原因たる神についてこれ以上不条理な主張はありえない。ゆえに私はこうした不条理を反駁するのに時間を費やすことはないのである。
定理三四 神の能力は神の本質そのものである。
証明 なぜなら、神の本性の単なる必然性からして、神は自己(
定理一一により)ならびに(定理一六およびその系により)すべての物の原因であるということが出てくる。ゆえに神自身ならびにすべてのものがそれによって存在しかつ働きをなす神の能力は神の本質そのものである。Q・E・D・ (一定理16系1)
定理三五 神の力の中に在ると我々の考えるすべての物は必然的に存する。
証明 なぜなら、神の力の中に在るすべてのものは(前定理により)神の本質から必然的に生起するようなふうに神の本質の中に含まれていなければならぬ。したがってそれは必然的に存する。Q・E・D・
定理三六 その本性からある結果が生じないようなものは一として存在しない。
証明 存在するすべての物は神の本性あるいは本質を一定の仕方で表現する(定理二五の系により)。言いかえれば(定理三四により)存在するすべての物は神の能力を〜〜万物の原因である神の能力を一定の仕方で表現する。したがって(定理一六により)存在するすべての物からある結果が生起しなければならぬ。Q・E・D・
付 録
以上をもって私は神の本性を示し、その諸特質を説明した。すなわち神が必然的に存在すること、唯一であること、単に自己の本性の必然性のみによって在りかつ働くこと、万物の自由原因であること、ならびにいかなる意味で自由原因であるかということ、すべての物は神の中に在りかつ神なしには在ることも考えられることもできないまでに神に依存していること、また最後に、すべての物は神から予定されており、しかもそれは意志の自由とか絶対的裁量とかによってではなく神の絶対的本性あるいは神の無限の能力によること、そうした諸特質を説明した。さらに私は、機会あるごとに、私の証明の理解を妨げるような諸偏見を取り除くことに努力してきた。しかしまだ少なからぬ偏見が残っていて、人々が私の説明した仕方で物の連結を把握することを同様に、いな、きわめてはなはだしく、妨げえたしまた現に妨げえているのであるから、それらをここで理性の検討にゆだねることはむだではないと思うのである。
ところで、ここに私が指摘しようとするすべての偏見は次の一偏見に由来している。その一偏見というのは〜〜一般に人々はすべての自然物が自分たちと同じく目的のために働いていると想定していること、のみならず人々は神自身がすべてをある一定の目的に従って導いていると確信していること、これである(なぜなら彼らはこう言う、神はすべての物を人間のために造り、神を尊敬させるために人間を造った、と)。だから私はまずこの偏見を考察しよう。それには第一に、なぜ多くの人々がこの偏見に甘んじ、またなぜすべての人が生来この偏見をいだく傾向があるかの理由を探究する。次にそれが誤っていることを示し、最後にいかにしてこの偏見から善と悪、功績と過罪、賞讃と非難、秩序と混乱、美と醜その他こうした種類の他のことどもに関する諸偏見が生じたかを示そう。 83
しかしこのことを人間精神の本性から導き出すことはこの場所では適当でない。ここでは何びとも承認しなければならぬこと、すなわちすべての人間は生まれつき物の原因を知らないこと、およびすべての人間は自己の利益を求めようとする衝動を有しかつこれを意識しているということ、そうしたことを議論の根底とするので十分であろう。なぜなら、このことから次のことが出てくるからである。それは第一に、人間は自分を自由であると思うということである。実際、彼らは自分の意欲および衝動を意識しているが彼らを衝動ないし意欲に駆る原因は知らないのでそれについては夢にも考えないからである。第二に、人間は万事を目的のために、すなわち彼らの欲求する利益のために行なうということである。この結果として、彼らはできあがったものごとについて常に目的原因のみを知ろうとつとめ、これを聞けばそれで満足する。彼らにはそれ以上疑念をいだく何の理由もないからである。これに反してもしそれを他人から聞くことができない場合は、自分自身をふりかえって見て、自分が平素類似のことをするように決定されるのはどんな目的からであるかを反省してみるよりほかない。このようにして彼らは必然的に、自分の性状から他人の性状を判断することになる。さらに彼らは、自分の利益を獲得するのに少なからず役立つ多数の手段を、例えば見るための目、咀嚼するための歯、栄養のための植物や動物、照らすための太陽、魚を養うための海のごときものを自分の内外に発見するから、(そして他のほとんどすべてのものに関してもこれと同じ次第であって、彼らはそうしたものの自然的原因が何であるかについて疑念をいだく何の理由も持たないのであるから、)このことから彼らは、すべての自然物を自分の利益のための手段と見るようになった。そして、それらの手段は彼らの発見したものではあるが彼らの供給したものではないことを知っているから、これが誘因になって彼らは、そうした手段を彼らの使用のために供給した他のある者が存在することを信ずるようになった。すなわち、一度物を手段と見てからは、彼らはそれがひとりでにできたと信ずるわけにはいかなくて、彼らが平素自分自身に手段を供給する場合から推し量り、人間的な自由を賦与された一人あるいは二、三の自然の支配者が存在していて、これが彼らのためにすべてを熟慮し、彼らの使用のためにすべてを造ったと結論せざるをえなかった。彼らはまたこうした支配者の性情については少しも聞き知ることがなかったので、これを自分の性情に基づいて判断せざるをえなかった。そしてこのことから彼らは、神々は人間に感謝の義務を負わせ、人間から最高の尊敬を受けるためにすべてのものを人間の使用に向けるのだと信じた。この結果として各人は、神が自分を他の人々以上に寵愛し・全自然を自分の盲目的欲望と飽くことなき食欲の用に向けてくれるように、敬神のいろいろの様式を自分の性情に基づいて案出した。こうしてこの偏見は迷信に堕し、人々の心に深い根をおろした。そしてこれが原因となって各人は、すべてのものについて目的原因を認識し・説明することに最大の努力を払うようになった。
しかし自然が何らむだなこと(言いかえれば人間の役に立たぬこと)をしないことを示そうと試みながら、彼らは自然と神々とが人間と同様に狂っていることを示したにすぎないように思われる。見るがいい、事態はついにいかなる結末になったかを! 自然におけるかくも多くの有用物の間にまじって少なからぬ有害物を、例えば暴風雨・地震・病気などなどを彼らは発見しなければならなかった。そこでこうした事柄は神々〈(彼らが自分たちと同種のものと判断しているような)〉が人間の加えた侮辱のゆえに、あるいは敬神に際して人間の犯した過失のゆえに怒ったから起こったのだと信じた。そして日常の経験は、これに反して、有用物ならびに有害物が敬虔者にも不敬虔者にも差別なく起こることを無数の例をもって示すのであるけれども、彼らはそのゆえに昔ながらの偏見から脱することをしなかった。なぜなら、彼らにとっては、これをもろもろの不可知な事柄、何のためそれが生ずるか了解できぬ事柄の中に数え入れ、このようにして彼らの現に在る生まれながらの無知状態を維持するほうが、前述の組織全体を破壊して新しい組織を案出するよりも容易だったからである。このため彼らは、神々の判断が人間の把握力をはるかに凌駕すると確信した。そしてもし数学が一目的には関係せずに単に図形の本質と諸特質とにのみ関係する数学がー真理の他の規範を人間に示さなかったとしたら、この理由一つだけでも真理は永遠に人類に秘められたであろう。なお、数学のほかにも、人々〈(といっても全人類から言えばごく少数の人であるが)〉にこの共通の偏見に気づかせて物の真の認識に進むことができるようにさせた他の諸原因が挙げられうる(しかしこれをここに数えたてることは無用である)。
これをもって私は第一に約束したことを十分説明した。だから今、自然は何の目的も立てずまたすべての目的原因は人間の想像物以外の何ものでもないことを示すのに多言を要しない。なぜなら、私がこの偏見の源泉として示した根底および原因から、ならびに定理一六と定理三二の二つの系とから、さらにまた私が自然における一切はある永遠なる必然性と最高の完全性とから生ずることを示す際に用いた諸理由から、このことはすでに十分明白になったと私は信ずるからである。
しかしまだ付け加えたいことがある。それは、目的に関するこの説は自然をまったく転倒するということである。なぜならこの説は、実は原因であるものを結果と見、また反対に(結果であるものを原因と)見る。次にこの説は本性上さきなるものをあとにする。また最後にこの説は最高かつ最完全なものを最不完全なものにする。というのは、(前の二つは自明であるからこれを略すとして、)定理二一、二二および二三から明らかなように、神から直接的に産出される結果は最完全であり、そして物は産出されるためにより多くの中間原因を要するに従ってそれだけ不完全である、ところがもし神から直接的に産出される物は神が自己の目的を達するために造ったのだとすれば、最後のもの〜〜それのために始めのものが造られたところの〜〜はすべてのもののうちで最も価値あるものになるからである。
次にこの説は神の完全性を没却する。なぜなら、もし神が目的のために働くとすれば、神は必然的に何か欠けるものがあってそれを欲求していることになるからである。もっとも神学者ならびに形而上学者たちは需要の目的と同化の目的を区別してはいるが、それでもやはり彼らは神が一切を被造物のためにではなくて自己自らのためになしたことを承認する。なぜなら彼らは、創造以前においては、神のほかには神がそのため働くような何ものも示すことができないからである。したがって神がある物のために手段を用意しようとしたと言うなら、神はそのある物を欠いていてそれを欲求した、ということを必然的に彼らは承認せざるをえなくなる。これは自明の理である。
なおここに見逃してならないのは、物の目的性を説明するにあたって自己の才能を示そうと欲したこの説の信奉者たちが、この自説を確証するために、一つの新しい証明法を提起したことである。それは帰謬法ではなくて帰無知法(人の無知に基づく証明法)とでも言うべきやりかたである。このことはこの説にとって他の何の証明方法もなかったことを物語るものである。例えばもしある屋根から石がある人間の頭上に落ちてその人間を殺したとするなら、彼らは石が人間を殺すために落ちたのだとして次のように証明するであろう。もし石が神の意志によってそうした目的のために落ちたのでなかったら、どうしてそのように多くの事情が偶然輻輳(ふくそう)しえた(というのはしばしば多くの事情が同時に輻輳するから)のであるかと。これに対して、それは風が吹いたから、そして人間がそこを通ったから起こったのだと答えでもすれば、彼らはなぜ風がその時吹いたか、なぜ人間がちょうどその時刻にそこを通ったかと迫るであろう。これに対してまた、前日まだ天候が穏かだったのに海が荒れ出したからその時になって風が起こったのだ、そしてその人間は友人から招待されていたのだ、と答えるならば、彼らはさらに〜〜問いには際限がないから〜〜迫るであろう、しかしなぜ海が荒れ出したのか、なぜその人間がその時刻に招待されていたのかと。このように次から次へと原因の原因を尋ねて、相手がついに神の意志すなわち無知の避難所へ逃れるまではそれをやめないであろう。同様にまた彼らは、人間の身体の構造を見て驚く。そしてそうした巧みな技術の原因を知らないので、それは機械的技術によってではなく神的な、あるいは超自然的な技術によって作られ、一つの部分が他の部分を損なわないようなふうに仕組まれていると結論する。このゆえに諸奇蹟の真因を探究する者、また自然物を愚者として驚歎する代りに学者として理解しようと努める者は、一般から異端者、不敬虔者と見なされ、民衆が自然ならびに神々の代弁者として崇める人々からはこのような者として罵倒されることになる。なぜなら、神の代弁者と崇められる人々は、無知〈あるいはむしろ愚鈍〉がなくなれば、驚き、すなわち自己の権威を証明し・維持するための唯一の手がかりもまたなくなることを知っているからである。〈しかしここに述べたような証明法にどんな効力があるかの判断はこの証明法の提起者自身にまかせる。〉私はこれらのことどもを措(お)いて、ここで取り扱おうと定めた第三の事柄に移る。 89
人々は生起する一切が自分のために生起すると思いこんでからは、すべての物について、彼らに最も有用な点を重要事と判断し、彼らを最も快く刺激するものをすべて最も価値あるものと評価しなければならなかった。ここからして彼らは、物の本性を説明するために善、悪、秩序、混乱、暖、寒、美、醜のような概念を形成しなければならなかった。また彼らは自分を自由であると思うがゆえに、これから賞讃と非難、罪過と功績のような概念が生じた。後者についてはあとで人間本性を論じた上で述べることにして、ここでは前者について簡単に説明しよう。すなわち健康と敬神とに役立つ一切のことを人々は善と呼び、これに反することを悪と呼んだ。また物の本性を認識せずに物を単に表象のみする人々は、物について何ら〔正しい〕肯定をすることなく、表象力を知性と思っているから、そのゆえに彼らは、物ならびに自己の本性に無知であるままに、秩序が物自体の中に存すると固く信じている。すなわち物が我々の感覚によって容易に表象され、したがってまた容易に思い出せるようなふうにできていれば、我々はそれを〈善き秩序にある、あるいは〉善く秩序づけられていると呼び、その反対の場合は、悪しく秩序づけられている、あるいは混乱していると呼ぶのである。そして、我々が容易に表象しうる物は我々にとって他の物より快いから、そのゆえに人々は混乱よりも秩序を選び取るのである。あたかも秩序が我々の表象力との関係を離れて自然の中に実在するある物であるかのように。また彼らは神が一切を秩序的に創造したと言う。このようにして彼らは知らず知らず神に表象力を帰している。もし神に表象力を帰しているのでないとすれば、あるいは彼らは、神が人間の表象力を考えてすべての物を我々が最も容易に表象しうるようなふうに按配したと思っているのかもしれぬ。だがその際彼らは、我々の表象力をはるかに凌駕する無限に多くのものが存在し、また我々の表象力が微弱であるゆえにそれを混乱させるきわめて多くのものが存在するということには何の顧慮も払わないらしい。しかしこのことについてはもう十分である。 90
次にその他の諸概念も、同様に、表象力を種々なふうに刺激する表象の様式にほかならない。けれどもそれは無知者たちからは事物の主要属性と見られている。なぜなら、すでに述べたように、彼らはすべてのものが自分たちのために造られていると信じ、そしてある物から刺激されるぐあいに応じてその物の本性を善あるいは悪、健全または頽廃および腐敗と言うからである。例えば目に映る対象から神経が受ける刺激が健康に役立つなら、これを引き起こす対象は美と言われ、反対の刺激を生ずるものは醜と言われる。次に鼻によって感覚を刺激するものを芳香あるいは臭気と呼び、舌によるものを甘あるいは苦、美味あるいは不味などと呼ぶ。また触覚によるものを硬あるいは軟、粗あるいは滑などと言う。また最後に、耳を刺激するものを騒音、音響、または諧音を発すると言う。これらのうちで諧音は、神もまたこれを喜ぶと信じたほど人々の心を奪った。そればかりでなく天体の運行が諧音をたてることを確信した哲学者たちもなくはない。これらすべては、各人が事物を脳髄の状態に従って判断し、あるいはむしろ表象力の受けた刺激を事物自体と見たことを十分に示すものである。このゆえに(ついでながら注意するが)人々の間に、我々の見聞きするようなあんなに多くの論争が生じ、これからついに懐疑論が発生したことも怪しむに足りない。なぜなら、人々の身体は多くの点において一致するがもっと多くの点において異なり、そのゆえにある人に善く見えるものが他の人に悪しく見え、ある人に秩序正しく思えるものが他の人には混乱して思え、ある人には快いものが他の人には不快だからである。そしてその他のことについてもこれと同様であるが、それはここに述べない。ここはそうしたことを詳しく論ずる個所でないし、それにまたそれはすべての人が十分に経験しているところだからである。というのは「頭数だけの意見」「誰でも自分の意見で一杯になっている」「脳髄は味覚に劣らず相違している」などいう諺はすべての人の口にするところである。これらの諺は、人間が物を脳髄の状態に従って判断し、また物を知性的に認識するよりはむしろ感覚的に表現することを十分物語っている。なぜなら、もし彼らが物を知性的に認識するとしたら、数学において見るように、それらの物は、彼らすべてを惹きつけないまでも、少なくとも彼らすべてを同じ確信に導いたであろうからである。 (頭数、テレンティウス)
このようにして、民衆が自然を説明するに用い慣れたすべての概念は単に表象の様式であって、何ら物の本性を表示せずただ表象力の状態を示すのみであるということを我々は知る。そしてこれらの概念は、あたかも表象力の外部に存在する実有を意味するかのような名称を有するから、私はこれを理性の有とではなく表象の有と呼ぶ。こうして我々はこれと類似の概念に基づいて、我々に向けられるすべての論拠を容易に撃退することができる。すなわち、多くの人々は次のように論ずるのが常である。もし万物が神の最完全な本性の必然性から起こったとするなら自然におけるあれほど多くの不完全性は一体どこから生じたのか。例えば悪臭を発するにいたるまでの物の腐敗、嘔吐を催させるような物の醜怪、混乱、害悪、罪過などなどはどうかと。しかし、今も言ったように、これを反駁することは容易である。なぜなら、物の完全性は単に物の本性ならびに能力によってのみ評価されるべきであり、したがって物は人間の感覚を喜ばせ、あるいは悩ますからといって、また人間の本性に適合しあるいはそれと反撥するからといって、そのゆえに完全性の度を増減しはしないからである。さらになぜ神はすべての人間を理性の導きのみによって導かれるようなふうに創造しなかったかと問う人々にたいしては、次のことをもって答えとするほかはない。すなわち神には完全性の最高程度から最低程度にいたるまでのすべてのものを創造する資料が欠けていなかったからである、あるいは(もっと本源的な言いかたをすれば)、神の本性の諸法則は、定理一六で示したように、ある無限の知性によって概念されうるすべてのものを産出するに足るだけ包括的なものであったからである、と。
これが私のここで述べようと思った諸偏見である。もしこうした偏見の粉末がいくらかまだ残っているとしても、誰でも少しく考察すれば、その誤りを正しうるであろう〈ゆえに私はこうした事柄にこれ以上留まっている理由はない、云々〉。
第一部 終り
注:以下、『デカルトの哲学原理』第一部(岩波文庫p.79)より、抜粋
「 定理十九
神は永遠である。
証 明
神は最高完全な実有である(定義八により)。これからして(定理五により)、神は必然的に存在することになる。今もし我々が神を限定された存在とするなら、神の存在の限界は、我々によっては認識されないにしても少くとも神自身によっては必ず認識されねばならぬ。神は全知だからである(定理九により)。従って神はその限界の外では、自己を、換言すれば(定義八により)最高完全の実有を、存在しないものとして認識するであろう。これは不条理である(定理五により)。 故に神は限定された存在を持つものでなく、無限な存在を持つものである。この無限な存在を我々は永遠と呼ぶのである(本書附録第二部一章参照)。このようにして神は永遠である。Q・E・D・」
以下、『デカルトの哲学原理』第二部(岩波文庫p.94)より、抜粋
「 定理三
真空が存在するということは自己矛盾である。
証 明
真空とは物体的実体のない延長のことと解される(定義五により)。換言すれば(この部の定理二により)物体のない物体のことである。しかしこれは不条理である。
真空に関するもっと詳細な説明のために、また真空に関する先入見の是正のためには、「哲学原理」第二部十七及び十八節を読んでいただきたい。そこでは相互の間に何も介在しないような物体は必ず相接触すること、また無にはどんな特質も属しないことが特に注意されている。」
以下、ユークリッド『原論』第七巻命題一九及びその証明
「命題19 4つの数が比例するならば、第1の数と第4の数から作られた数は第2の数と第3の数から作られた数と等しい。
第1の数と第4の数から作られた数は第2の数と第3の数から作られた数と等しいならば、4つの数は比例する。
A、B、C、Dを比例している4つの数とする。つまりAはBに対し同じようにCはDに対するとし、そしてAにDをかけてEをつくとし、BにCをかけてFをつくるとする。
EがFと等しいことをいう。
GをつくるためにAにCをかける。AにCをかけてGをつくり、そしてDをかけてEをつくるから、それゆえに数Aに2つの数CとDをかけてGとEをつくる。それゆえにCはDに対し同じようにGはEに対する。しかしCはDに対し同じようにAはBに対し、それゆえにAはBに対し同じようにGはEに対する。proposition7.17、(proposition5.11)
再度、AにCをかけてGをつくり、しかし、さらに、BにCをかけてFをつくるから、それゆえに2つに数AとBにある数CをかけてGとFをつくる。それゆえにAはBに対し同じようにGはFに対する。proposition7.18
しかしさらにAはBに対し同じようにGはEに対するから、それゆえにGはEに対し同じようにGはFに対する。それゆえにGは数EとFのそれぞれに同じ比をもつ。それゆえにEはFと等しい。(proposition5.11)、(proposition5.9)
−
再度、EはFと等しいとする。
AはBに対し同じようにCはDに対することを言う。
同じ結果で、EはFと等しいから、それゆえにGはEに対し同じようにGはFに対する。(第5巻命題7)
しかしGはEに対し同じようにCはDに対し、そしてGはFに対し同じようにAはBに対し、それゆえにAはBに対し同じようにCはDに対する。proposition7.17、proposition7.18、(proposition5.11)
それゆえに、4つの数が比例するならば、第1の数と第4の数から作られた数は第2の数と第3の数から作られた数と等しい。第1の数と第4の数から作られた数が第2の数と第3の数から作られた数と等しいならば、4つの数は比例している。
証明終了」
以下、デカルト『感情論』第一部二七節(『情念論』岩波文庫より)
「二七 精神の情念〔受動〕の定義。
精神の情念が他の思考すべてと異なる点を考察したので、情念を一般的に次のように定義できると思われる。すなわち、精神の知覚、感覚、情動であり、それらは、特に精神に関係づけられ、そして精気の何らかの運動によって引き起こされ、維持され、強められる。」
以下、デカルト『感情論』第一部五〇節(『情念論』岩波文庫pp.49-50より)
「五〇 いかに弱い精神でも、良く導かれれば、情念に対して絶対的な力を獲得できること。
そして、ここで次の点をわかっていると有益だ。すでに述べたように、腺の各運動は、わたしたちの生の最初から、自然によって各々一つひとつの思考に結びつけられたと思われるが、しかし、習性によって、腺の運動を別の思考に結びつけることができるのだ。たとえば言葉について経験が示しているように、言葉は腺にある運動を引き起こすが、この運動は自然の設定に従って、言葉が声で出されたときは音を、書かれたときは文字の形を精神にー表象するだけである。だが、その音を聞きその字を見て言葉の意味を思考することで身につける習性によって、文字の形や音節の発音よりも、意味を思考させる習わしとなる。また次の点をわかっておくのも有益だ。腺の運動であれ精気や脳の運動であれ、精神に一定の対象を表象する運動は、自然的に、精神のうちに一定の情念を引き起こす運動と結びつけられているが、それにもかかわらず、習性によって、その運動から分離して、まったく違った別の運動と結びつけることができる。しかも、この習性はただ一度の行為によって獲得することができ、長期の馴れを要しない。たとえば、おいしそうに食べている食物のなかに思いがけず何かひどくいやなものにぶつかったときだ。その出来事の驚きが脳の状態を大きく変えてしまい、以前は喜んで食べていたのに、以後は嫌悪感をもってしか、その食物を見ることができなくなる。そして同じことは動物においても認められる。動物は理性を持たないし、おそらく何の思考も持たない。しかし、わたしたちのうちに情念を引き起こす精気や腺の運動すべてを、やはり具えているのである。これらの運動は動物では、わたしたちの場合のように情念を維持し強める役をすることはないが、通例わたしたちの情念にともなう神経や筋肉の運動を維持し強める役を果たしている。たとえば犬は生来、ヤマウズラを見るとそれを追って走りたがり、銃声を聞くと逃げたがる。にもかかわらず通常、猟犬を訓練してヤマウズラを見るととどまるようにし、次にヤマウズラを撃つとその音をきいて鳥のほうへ駆けるようにするのである。さて以上のことは、各人にみずからの情念を統御することを学ぶ勇気を与えるために、知っておくのが有益である。理性を欠いた動物を、わずかの工夫で脳の運動を変えることができるのだから、人間ではそれをさらに良くできるのは明らかだ。そして、最も弱い精神の持ち主でも、精神を訓練し導くのに十分な工夫の積み重ねを用いるなら、あらゆる情念に対してまさに絶対的な支配を獲得できるのは明らかである。」
第 二 部
☆、定義、
一、二、三、四、五、六、七
公理、一、二、三、四、五
定理、
一、二、三、四、五、六、七、八、九、一〇、一一、一二、
一三、備考(公理一、二)、補助定理一、二、三(公理一、二、定義、三)、補助定理四、五、六、七、
(要請、一、二、三、四、五、六)、
一四、一五、一六、一七、一八、一九、二〇、
二一、二二、二三、二四、二五、二六、二七、二八、二九、三〇、三一、三二、三三、三四、三五、三六、三七、三八、三九、四〇、
四一、四二、四三、四四、四五、四六、四七、四八、四九、第一部TOP、第二部TOP、TOP☆
精神の本性および起源について
今や私は神、すなわち永遠・無限な実有、の本質から必然的に生起しなければならぬことどもの説明に移る。しかしそのすべてについてではない。なぜなら、第一部定理二六で証明したように、神の本質からは無限に多くのものが無限に多くの仕方で生起しなければならぬからである。ここではただ、人間精神とその最高の幸福との認識へ我々をいわば手を執って導きうるものだけにとどめる。
定 義
一 物体とは、神が延長した物と見られる限りにおいて神の本質をある一定の仕方で表現することと解する。第一部定理二五の系を見よ。
二 それが与えられればある物が必然的に定立され、それが除去されればそのある物が必然的に滅びるようなもの、あるいはそれがなければある物が、また逆にそのある物がなければそれが、在ることも考えられることもできないようなもの、そうしたものをその物の本質に属すると私は言う。
三 観念とは、精神が思惟する物であるがゆえに形成する精神の概念のことと解する。
説明 私は知覚というよりもむしろ概念という。その理由は知覚という言葉は精神が対象から働きを受けることを示すように見えるが、概念はこれに反して精神の能動を表現するように見えるからである。
四 妥当な観念〔十全な観念〕とは、対象との関係を離れてそれ自体で考察される限り、真の観念のすべての特質、あるいは内的特徴を有する観念のことであると解する。
説明 私は内的特徴と言う。これは外的特徴すなわち観念とその対象との一致を除外するためである。
五 持続とは存在の無限定な継続である。
説明 私は無限定な継続と言う。なぜなら、存在の継続は決して存在する物の本性自身によっては限定されることができないし、また同様にその起成原因によっても限定されることができないからである。起成原因は物の存在を必然的に定立するがこれを除去することはないのだから。
六 実在性と完全性とは同一のものであると解する。
七 個物とは有限で定まった存在を有する物のことと解する。もし多数の個体(あるいは個物)がすべて同時に一結果の原因であるようなふうに一つの活動において協同するならば、私はその限りにおいてそのすべてを一つの個物と見なす。 (協同)
公 理
一 人間の本質は必然的存在を含まない。言いかえれば、このあるいはかの人間が存在することも存在しないことも同様に自然の秩序から起こりうる。
二 人間は思惟する〈、あるいは他面から言えば、我々は我々が思惟することを知る〉。
三 愛・欲望のような思惟の様態、その他すべて感情の名で呼ばれるものは、同じ個体の中に、愛され・望まれなどする物の観念が存しなくては存在しない。これに反して観念は、他の思惟の様態が存しなくとも存在することができる。
四 我々はある物体〔身体〕が多様の仕方で刺激されるのを感ずる。
五 もろもろの物体およびもろもろの思惟の様態のほかには、いかなる個物も〈あるいは所産的自然に属するいかなる物も〉我々は感覚ないし知覚しない。定理一三の後の要請を見よ。
定理一 思惟は神の属性である。あるいは神は思惟する物である。
説明 個々の思想、すなわちこのあるいはかの思想は、神の本性をある一定の仕方で表現する様態である(第一部定理二五の系により)。ゆえに神には(第一部定義五により)一属性、〜〜それの概念がすべての個々の思想の中に含まれており、またそれによってすべての個々の思想が考えられもするそうした属性があることになる。したがって思惟は神の無限に多くの属性の一つであって、神の永遠・無限な本質を表現している(第一部定義六を見よ)。あるいは神は思惟する物である。Q・E・D・
備考 この定理はまた、我々が思惟する無限の実有を考えうることからも明白である。なぜなら、思惟する実有がより多くのものを思惟しうるに従って、それはそれだけ多くの実在性あるいは完全性を含むと我々は考える。ゆえに無限に多くのものを無限に多くの仕方で思惟しうる実有は、必然的に、思惟する力において無限である。このように我々は、単に思惟だけを眼中に置くことによって無限の実有を考えうるのだから、思惟は、我々が主張したように、必然的に(第一部定義四および六により)神の無限に多くの属性の一つである。 96
定理二 延長は神の属性である。あるいは神は延長した物である。
証明 この定理の証明は前定理の証明と同様の仕方でなされる。
定理三 神のうちには必然的に神の本質の、ならびに神の本質から必然的に生起するあらゆるものの、観念が存する。
証明 なぜなら、神は(この部の定理一により)無限に多くのものを無限に多くの仕方で思惟しうる。あるいは(第一部定理一六によりこれと同じことだが)神は神の本質、ならびに神の本質から必然的に生起するあらゆるもの、について観念を形成しうる。ところが神の力の中に在るすべてのものは必然的に在る(第一部定理三五により)。ゆえにそうした観念は必然的に在りかつ(第一部定理一五により)神のうちにのみ在る。Q・E・D・
備考 民衆は、神の能力ということを、神の自由意志、ならびにありとあらゆるものにたいする神の権能、と解する。このゆえにあらゆるものは一般に偶然なものと見なされている。なぜなら彼らは神があらゆるものを破壊して無に帰する力を有すると言っているからである。さらに彼らはしばしば神の能力を王侯の能力に比較する。しかし我々はこのことを第一部定理三二の系一
および二で反駁したし、また第一部定理一六では、神は自己自身を認識するのと同一の必然性をもって活動することを示した。言いかえれば神が自己自身を認識することが神の本性の必然性から起こるように(これはすべての人が一致して容認するところである)、神が無限に多くのことを無限に多くの仕方でなすこともまたそれと同一の必然性をもって起こるのである。次に我々は第一部定理三四において、神の能力は神の活動的本質にほかならないことを示した。したがって神が活動しないと考えることは神が存在しないと考えるのと同様に不可能である。
なおもし私がこれらのことどもをいっそう深く追求してよいならば、私はここで、民衆が神に帰しているあの能力は、人間的能力である(つまり民衆は神を人間としてあるいは人間に類似のものとして考えているのである)というばかりでなく、さらにまたそれは無能力をも含むものであることを示しうるであろう。しかし私は同じことについてそうたびたび語ることは好まない。
私はただ読者に、第一部において定理一六から終結に至るまでこれについて述べられてあることを改めて熟慮されるよう幾重にもお願いするのみである。なぜなら、何びとといえども、神の能力を王侯の人間的能力あるいは権能と混同しないように極力用心しなくては、私の述べようとするところを正しく理解することができないであろうからである。
定理四 無限に多くのものが無限に多くの仕方で生じてくる神の観念はただ唯一でしかありえない。
証明 無限の知性は神の属性とその変状のほか何物も把握しない(第一部定理三〇により)。ところが神は唯一である(第一部定理一四の系一により)。ゆえに無限に多くのものが無限に多くの仕方で生じてくる神の観念はただ唯一でしかありえない。Q・E・D・
定理五 観念の形相的有(エッセ・フォルマーレ)は、神が思惟する物と見られる限りにおいてのみ神を原因と認め、神が他の属性によって説明される限りにおいてはそうでない。言いかえれば、神の属性の観念ならびに個物の観念は観念された物自身あるいは知覚された物自身を起成原因と認めずに、神が思惟する物である限りにおいて神自身を起成原因と認める。
証明 これはすでにこの部の定理三から明白である。なぜなら、我々はそこで、神がその本質の観念およびその本質から必然的に生起するすべてのものの観念を形成しうることを、単に神が思惟する物であるということに基づいて〜〜神が自己の観念の対象であるなどということに基づいてではなく〜〜結論した。ゆえに観念の形相的有は、神が思惟する物である限りにおいて神を原因と認める。
しかしこのことは別に次のような仕方でも証明される。観念の形相的有は(それ自体で明白なように)思惟の様態である。言いかえれば(第一部定理二五の系により)思惟する物である限りにおいての神の本性をある一定の仕方で表現する様態である。そこでそれは(第一部定理一〇により)神の他のいかなる属性の概念も含まず、したがってまた(第一部公理四により)思惟以外のいかなる他の属性の結果でもない。ゆえに観念の形相的有は、神が思惟する物と見られる限りにおいてのみ神を原因と認め云々。Q・E・D・
定理六 おのおのの属性の様態は、それが様態となっている属性のもとで神が考察される限りにおいてのみ神を原因とし、神がある他の属性のもとで考察される限りにおいてはそうでない。
証明 なぜなら、おのおのの属性は他の属性の助けを借りずにそれ自身によって考えられる(第一部定理一〇により)。ゆえに各属性の様態はその属性の概念を含み他の属性の概念を含まない。したがって様態は(第一部公理四により)自らが様態となっている属性のもとで神が考察される限りにおいてのみ神を原因とし、神がある他の属性のもとで考察される限りにおいてはそうでない。Q・E・D・
系 この帰結として〜〜思惟の様態でない事物の形相的有(エッセ・フォルマーレ)は、神の本性がそれらの事物を前もって認識したがために神の本性から起こるのではない、むしろ観念の対象たる事物は、観念が思惟の属性から生ずる(我々が示したように)のと同一の仕方・同一の必然性をもって、それ自身の属性から起こりあるいは導き出される〜〜ということになる。
定理七 観念の秩序および連結は物の秩序および連結と同一である。
証明 第一部公理四から明白である。なぜなら、結果として生ぜられたおのおのの物の観念は、そうした結果を生じた原因の認識に依存するからである。
系 この帰結として、神の思惟する能力は神の行動する現実的能力に等しいことになる。言いかえれば、神の無限な本性から形相的(フォルマリテル)に起こるすべてのことは、神の観念から同一秩序・同一連結をもって神のうちに想念的(オブエクティヴェ)に〔すなわち観念として〕起こるのである。
備考 先へ進む前に、ここで、我々が以前に示したことを記憶に呼びもどさなくてはならぬ。それはすなわち、無限な知性によって実体の本質を構成していると知覚されうるすべてのものは単に唯一の実体に属しているということ、したがってまた思惟する実体と延長した実体とは同一の実体であって、それが時にはこの属性のもとにまた時にはかの属性のもとに解されるのであるということ、これである。同様に、延長の様態とその様態の観念とは同一物であって、ただそれが二つの仕方で表現されているまでである。(このことは二、三のヘブライ人たちもおぼろげにではあるが気づいていたらしい、なぜなら彼らは神と神の知性と神によって認識された物とが同一であることを主張しているのだから)。例えば自然の中に存在する円と、同様に神の中にあるこの存在する円の観念とは同一物であり、それが異なった属性によって説明されるのである。ゆえに我々が自然を延長の属性のもとで考えようと、あるいは思惟の属性のもとで考えようと、あるいは他の何らかの属性のもとで考えようと、我々は同一の秩序を、すなわち諸原因の同一の連結を、言いかえれば同一物の相互的継起を、見いだすであろう。 (マイモニデス)
私が〈先に〉、神はただ思惟する物である限りにおいてのみ、例えば円の観念の原因でありまた延長した物である限りにおいてのみ円の原因である、と言ったのも、その理由とするところは次のようなものにほかならない。すなわち、円の観念の形相的有(エッセ・フォルマーレ)はその最近原因としての思惟の他の様態によってのみ知覚され、思惟のこの様態はさらに他のそれによって知覚され、このようにして無限に進み、こうして物が思惟の様態として見られる間は全自然の秩序あるいは原因の連結は思惟の属性によってのみ説明されなければならぬし、物が延長の様態として見られる限りは全自然の秩序もまた延長の属性のみによって説明されなければならぬ、という理由からにほかならない。そして同じことが他のすべての属性についてもあてはまると私は考えるのである。ゆえに、神が無限に多くの属性から成っている限りにおいては、神は真に、それ自体においてあるがままの事物の原因である。私はこのことを現在のところこれ以上明瞭に説明することができない。
定理八 存在しない個物ないし様態の観念は、個物ないし様態の形相的本質(エッセンティア・フォルマリス)が神の属性の中に含まれていると同じように神の無限な観念の中に包容されていなければならぬ。
証明 この定理は前の定理から明白であるが、さらに前の備考からいっそう明瞭に理解される。
系 この帰結として次のことが出てくる。個物がただ神の属性の中に包容されている限りにおいてのみ存在する間は、個物の想念的有(エッセ・オブエクティヴム)すなわち個物の観念は神の無限な観念が存在する限りにおいてのみ存在する。しかし個物が神の属性の中に包容されている限りにおいて存在するばかりでなく、さらにまた時間的に持続すると言われる限りにおいても存在すると言われるようになると、個物の観念もまた持続すると言われる存在を含むようになる。
備考 もし誰かがこの事柄をもっと詳細に説明するために例を求めても、私がここに語っている事柄は特殊な事柄だから、これを十分に説明するいかなる例も私は挙げることができないであろう。しかし私はできる限りこの事柄を(一つの例をもって)解説することに努めよう。
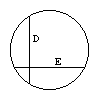 円は、その中でたがいに交わるすべての直線の線分から成る矩形が相互に等しいような本性を有する。ゆえに円の中には、相互に等しい無限に多くの矩形が含まれていることになる。しかしこういう炬形は、どれも、円の存在する限りにおいてでなくては存在すると言われえない。同様にまたこれらの矩形の観念は、どれも、円の観念の中に包容されている限りにおいてでなくては存在すると言われえない。今、かの無限に多くの矩形の中でただ二つだけ、すなわちEおよびDの線分から成る矩形だけが〔現実に〕存在すると仮定しよう。そうすればたしかに、それらの矩形の観念もまた、単に円の観念の中に包容されている限りにおいて存在するだけでなく、さらにまたそれらの矩形の存在を含む限りにおいても存在する。そしてこれによってそれらの矩形の観念は、他の矩形の観念と区別されるのである。
円は、その中でたがいに交わるすべての直線の線分から成る矩形が相互に等しいような本性を有する。ゆえに円の中には、相互に等しい無限に多くの矩形が含まれていることになる。しかしこういう炬形は、どれも、円の存在する限りにおいてでなくては存在すると言われえない。同様にまたこれらの矩形の観念は、どれも、円の観念の中に包容されている限りにおいてでなくては存在すると言われえない。今、かの無限に多くの矩形の中でただ二つだけ、すなわちEおよびDの線分から成る矩形だけが〔現実に〕存在すると仮定しよう。そうすればたしかに、それらの矩形の観念もまた、単に円の観念の中に包容されている限りにおいて存在するだけでなく、さらにまたそれらの矩形の存在を含む限りにおいても存在する。そしてこれによってそれらの矩形の観念は、他の矩形の観念と区別されるのである。
定理九 現実に存在する個物の観念は、神が無限である限りにおいてではなく神が現実に存在する他の個物の観念に変状(アフェクトゥス)した〔発現した〕と見られる限りにおいて神を原因とし、この観念もまた神が他の第三の観念に変状した限りにおいて神を原因とする、このようにして無限に進む。
証明 現実に存在する個物の観念は、思惟のある特定の様態であって、他の諸様態とは区別されるものである(この部の定理八の系および備考により)。したがってそれは(この部の定理六により)神が思惟する物である限りにおいてのみ神を原因とするが、しかし(第一部定理二八によ
り)神が絶対的に思惟する物である限りにおいてではなく、神が他の〈有限な〉思惟の様態に変状したと見られる限りにおいてである。そしてこの思惟の様態もまた神が他〈の有限な思惟の様態〉に変状した限りにおいて神を原因とする、このようにして無限に進む。ところで、観念の秩序および連結は(この部の定理七により)原因の秩序および連結と同一である。ゆえに各個の観念は他の観念を、あるいは他の観念に変状したと見られる限りにおける神を、原因とし、この観念もまた他の観念に変状した限りにおける神を原因とする、このようにして無限に進む。Q・E・D・
系 おのおのの観念の個々の対象の中に起こるすべてのことは、神がまさにその対象の観念をもつ限りにおいてのみ、神のうちにその認識がある。
証明 おのおのの観念の対象の中に起こるすべてのことは、神の中にその観念が存する(この部の定理三により)、しかしそれは神が無限なる限りにおいてではなく神が他の個物の観念に変状したと見られる限りにおいてである(前定理により)。だが(この部の定理七により)観念の秩序および連結は物の秩序および連結と同一である。ゆえに個々の対象の中に起こる事柄についての認識は、神がまさにその対象の観念をもつ限りにおいてのみ神の中に在るであろう。Q・E・D・
定理一〇 人間の本質には実体の有は属さない、あるいは実体は人間の形相(フォルマ)を構成しない。
証明 なぜなら、実体の有は必然的存在を含んでいる(第一部定理七により)。ゆえにもし人間の本質に実体の有が属するとすれば、その場合、実体が存するとともに人間も必然的に存することになるであろう (この部の定義二により)。したがって人間は必然的に存在することになるであろう。これは(この部の公理一により)不条理である。ゆえに云々。Q・E・D・
備考 この定理はまた第一部の定理五からも証明される。すなわち第一部の定理五によれば、同じ本性を有する二つの実体は存しえない。ところが多くの人間が存在しうる。ゆえに人間の形相を構成するものは実体の有ではない。
さらにこの定理は実体のその他の諸特質からも、すなわち実体はその本性上無限・不変・不可分などなどであることからも、明白である。これは何びとにも容易に解しうるところであろう。
系 この帰結として、人間の本質は神の属性のある様態的変状(モディフィカティオ)から構成されていることになる。
証明 なぜなら、実体の有は(前定理により)人間の本質に属さない。ゆえに人間は(第一部定理一五により)、神の中に在りかつ神なしには在ることも考えられることもできないあるものである。言いかえれば(第一部定理二五の系により)神の本性をある一定の仕方で表現する変状あるいは様態(モードス)である。
備考 神なしには何ものも在りえずまた考えられえないということはたしかにすべての人の容認するところに違いない。なぜなら、神は万物にとってその本質ならびに存在の唯一の原因であること、言いかえれば神は、単にいわゆる「生成に関して」だけではなく「有に関して」も物の原因であることをすべての人が認めているのであるから。しかしそれでいて大抵の人々は、ある物の本質にはそれがなければそのある物が在ることも考えられることもできないようなものが属すると言っており、これで見れば彼らは、神の本性が被造物の本質に属すると信じているか、それとも被造物が神なしにも在りあるいは考えられうると信じているか、それともまた〜〜そしてこれがもっともありそうなことであるが〜〜これについて何ら首尾一貫した意見を持ちえないでいるか、そのどれかであることになる。こんなことになる原因は、私の見るところでは、彼らが哲学的思索の順序を守らなかったことに在るのである。なぜなら、神の本性は認識上から言っても本性上から言っても最初のものであるから何ものよりも先に観想されなければならなかったのに、彼らはこれを認識の秩序の上で最後のものと信じ、そして感覚の対象と呼ばれる物をすべてのものに先立っていると信じたからである。この結果として彼らは、自然物を観想するに際しては神の本性については少しも思惟せず、またあとで、神の本性の観想に心を向けた時には、彼らが初め自然物の認識を築くに際して根底としたもろもろの勝手な想像については少しも思惟しえなくなったのである。そうした想像は神の本性の認識に何ら役立ちえなかったのであるから。だから彼らがいたるところで自己矛盾に陥ったのも何ら怪しむに足りない。
しかし私はこのことには深く触れないでおこう。というのは、私のここでの意図は、〈彼らを攻撃することにあるのではなく、〉ただなぜ私が「ある物の本質には、それがなければそのある物が存することも考えられることもできないものが属する」と言わなかったかの理由を、〜〜すなわち私がそう言わなかったのは個物は神なしに在ることも考えられることもできないがそれにもかかわらず神は個物の本質には属さないからだということを、示そうとすることにのみあったからである。それで私は先に、ある物の本質は、それが与えられればそのある物が定立され、またそれが除去されればそのある物が滅びるようなもの、あるいはそれがなければある物が、また逆にそのある物がなければそれが在ることも考えられることもできないようなもの、そうしたものから必然的に構成されていると言ったのであった。 106
定理一一 人間精神の現実的有を構成する最初のものは、現実に存在するある個物の観念にほかならない。
証明 人間の本質は(前定理の系により)神の属性のある様態から、すなわち(この部の公理二により)思惟の諸様態から構成されている。そしてこれらすべての様態にあっては(この部の公理三により)観念が本性上さきであって、観念が与えられればその他の諸様態(すなわち本性上観念のあとになるもの)が同じ個体の中に存しなければならぬ(この部の公理三により)。したがって観念は人間精神の有を構成する最初のものである。
しかしそれは存在しない物の観念ではない。なぜなら、その場合は(この部の定理八の系により)観念自身が存在すると言われえないからである。ゆえにそれは現実に存在する物の観念でなければならぬであろう。
しかしまたそれは無限な物の観念ではない。なぜなら、無限な物は(第一部定理二一および二二により)常に必然的に存在しなければならぬ。しかし人間についてそれを言うのは(この部の公理一により)不条理である。
ゆえに人間精神の現実的有を構成する最初のものは現実に存在する個物の観念である。Q・E・D・
系 この帰結として、人間精神は神の無限な知性の一部である、ということになる。したがって我々が「人間精神がこのことあるいはかのことを知覚する」と言う時、それは、「神が無限である限りにおいてでなく、神が人間精神の本性によって説明される限りにおいて、あるいは神が人間精神の本質を構成する限りにおいて、神がこのあるいはかの観念をもつ」と言うのにほかならない。また我々が「神が人間精神の本性を構成する限りにおいてのみでなく、神が人間精神と同時に他の物の観念をも有する限りにおいて、神がこのあるいはかの観念をもつ」と言う時に、それは「人間精神が物を部分的にあるいは非妥当的に知覚する」と言う意味である。
備考 ここで読者は疑いもなく蹟(つまず)くであろう。そして躊躇を促す多くのことが心に浮かぶであろう。この理由から私は、読者がゆっくり私とともに歩を進めて、すべてを通読するまではこのことについて判断を下さないようにお願いする。
定理一二 人間精神を構成する観念の対象の中に起こるすべてのことは、人間精神によって知覚されなければならぬ。あるいはその物について精神の中に必然的に観念があるであろう。言いかえれば、もし人間精神を構成する観念の対象が身体であるならその身体の中には精神によって知覚されないような〈あるいはそれについてある観念が精神の中にないような〉いかなることも起こりえないであろう。
証明 なぜなら、おのおのの観念の対象の中に起こるすべてのことは、神がその対象の観念に変状したと見られる限りにおいて必然的に神の中にその認識がある(この部の定理九の系により)、言いかえれば(この部の定理一一により)神がある物の精神を構成する限りにおいて、必然的に神の中にその認識がある。ゆえに人間精神を構成する親念の対象の中に起こるすべてのことは、神が人間精神の本性を構成している限りにおいて必然的に神の中にその認識が存する、言いかえれば(この部の定理一一の系により)そのものについての認識は必然的に精神の中に在るであろう、すなわち精神はそれを知覚する。Q・E・D・
備考 この定理はこの部の定理七の備考からも明白であり、しかもいっそう明瞭に理解される。その個所を見よ。
定理一三 人間精神を構成する観念の対象は身体である、あるいは現実に存在するある延長の様態である、そしてそれ以外の何ものでもない。
証明 なぜなら、もし身体が人間精神の対象でないとしたら身体の変状(アフェクティオ)〔刺激状態〕の観念は(この部の定理九の系により)神が我々の精神を構成する限りにおいて神のうちになく、神が他の物の精神を構成する限りにおいて神のうちにあるであろう、言いかえれば(この部の定理二の系により)、身体の変状(アフェクティオ)の観念は我々の精神の中にはないであろう。ところが(この部の公理により)我々は身体の変状(アフェクティオ)の観念を有する。ゆえに人間精神を構成する観念の対象は身体であり、しかも(この部の定理二により)現実に存在する身体である。次にもし身体のほかにも精神の対象が他にあるとすれば、およそ何らかの結果の生じないようなものは一つとして存在しないのであるから(第一部定理三六により)、その対象から生ずる何らかの結果についての観念が必然的に我々の精神の中に存しなければならぬ(この部の定理一二により)を。ところが(この部の公理五により)何らそうした観念が存しない。ゆえに我々の精神の対象は存在する身体であって他の何ものでもない。Q・E・D・
系 この帰結として、人間は精神と身体とから成りそして人間身体は我々がそれを感ずるとおりに存在する、ということになる。
備考 これによって我々は、人間精神が身体と合一していることを知るのみならず、精神と身体の合一をいかに解すべきかをも知る。しかし何びともあらかじめ我々の身体の本性を妥当に認識するのでなくてはこの合一を妥当にあるいは判然と理解することができないであろう。なぜなら、我々がこれまで示したことどもはごく一般的な事柄であって、人間にあてはまると同様その他の個体にもあてはまる。そしてすべての個体は程度の差こそあれ精神を有しているのである。なぜならあらゆる物について必然的に神の中に観念があって、その観念は、人間身体の観念と同様に神を原因とするのであり、したがって我々が人間身体の観念について述べたことはあらゆる物の観念についても必然的に言われうるからである。しかし私は同時に次のことも否定しえない。すなわちもろもろの観念はその対象自身と同様に相互に異なっているということ、そしてある観念の対象が他の観念の対象よりもより優秀でより多くの実在性を含むにつれてその観念も他の観念よりもより優秀でより多くの実在性を含むということである。このゆえにいかなる点で人間精神が他の精神と異なるか、またいかなる点で人間精神が他の精神より優秀であるかを決定するためには、すでに述べたように、その対象の本性を、言いかえれば人間身体の本性を認識することが必要である。しかしこうしたことをここで十分詳しく説くことはできないし、またそれは我々が証明しようと欲する事柄にとって必要でもない。私はただ一般論として次のことを言っておく。すなわちある身体が同時に多くの働きをなし・あるいは多くの働きを受けることに対して他の身体よりもより有能であるに従って、その精神もまた多くのものを同時に知覚することに対して他の精神よりそれだけ有能である。またある身体の活動がその身体のみに依存することがより多く・他の物体に共同して働いてもらうことがより少ないのに従って、その精神もまた判然たる認識に対してそれだけ有能である。そしてこのことから我々は、二つの精神が他の精神に対して有する優秀性を認識しうるし、さらにまたなぜ我々が我々の身体についてきわめて混乱した認識しかもたないかの理由ならびに私が以下においてそれから導こうとする他の多くのことどもを知りうる。このゆえに私はこれらのことをある程度詳しく説明し証明することを徒労ではないと考えた。しかしそれには諸物体の本性についていくつかの注意を前提とすることが必要である。 (身体、ネグリ)
公理一 すべての物体は運動しているか静止しているかである。
公理二 おのおのの物体はある時は緩(ゆる)やかに、ある時は速(すみ)やかに運動する。
補助定理一 物体は運動および静止、迅速および遅緩に関して相互に区別され、実体に関しては区別されない。
証明 この補助定理の始めの部分はそれ自体で明白であると考える。次に物体が実体に関しては区別されないということは、第一部の定理五ならびに定理八から明らかである。しかし第一部の定理一五の備考の中で述べたことから、なおいっそう明瞭である。
補助定理二 すべての物体はいくつかの点において一致する。
証明 なぜなら、すべての物体は同一属性の概念を含むという点で一致する(この部の定義一により)。次にそれらは、ある時は緩やかに、ある時は速やかに運動しうるという点で〜〜一般的に言えばある時は運動しある時は静止しうるという点で一致する。
補助定理三 運動あるいは静止している物体は、他の物体から運動あるいは静止するように決定されなければならなかった、この後者も同様に他の物体から運動あるいは静止するように決定されている、そしてこれもまたさらに他の物体から決定され、このようにして無限に進む。
証明 物体は、運動および静止に関して相互に区別される(補助定理一により)個物である(この部の定義一により)。したがって(第一部定理二八により)おのおのの物体は必然的に他の個物から、すなわち同様に運動もしくは静止している(公理一により)他の物体から(この部の定理六により)運動あるいは静止に決定されなければならなかった。ところがこの後者もまた(同じ理由により)他の物体から運動あるいは静止に決定されなかったならば運動あるいは静止することができなかった。そしてこのものもまたさらに(同じ理由により)他の物体から決定され、このようにして無限に進む。Q・E・D・
系 この帰結として、運動している物体は他の物体から静止するように決定されるまでは運動し、また同様に、静止している物体は他の物体から運動に決定されるまでは静止している、ということになる。これはすでにそれ自体で明白である。なぜなら、ある物体例えばAが静止すると仮定し、そして運動する他の諸物体を眼中に置かないならば、私は物体Aについてそれが静止しているということ以外には何ごとをも言いえないであろう。もしそのあとで、物体Aが運動するということが起こるなら、それはたしかに、Aが静止していたということからは起こりえなかったのである。なぜならそのことからは物体Aが静止していたということ以外の何ごとも生じえなかったからである。これに反してもしAが運動していると仮定するなら、我々がAだけを眼中に置く間は、我々はそれについて、それが運動しているということ以外の何ごとをも主張しえないであろう。もしそのあとで、Aが静止するということが起こるとしたら、それはまたたしかに、Aが有していた運動からは起こりえなかったのである。なぜなら、その運動からは、Aが運動していたということ以外のいかなることも生じえなかったからである。ゆえにそれは、Aの中になかった物から、すなわち(運動している物体Aを)静止するように決定した外的原因から生じたのである。
公理一 ある物体が他の物体から動かされる一切の様式は、動かされる物体の本性からと同時に動かす物体の本性から生ずる。したがって、同一の物体が、動かす物体の本性の異なるにつれてさまざまな様式で動かされ、また反対に、異なった物体が、同一の物体からさまざまな様式で動かされることになる。
公理二 運動している物体が静止している他の物体に衝突してこれを動かすことができない場合には、それは酔ね返って自己の運動を継続する。そして弾ね返る運動の線がその衝突した静止物体の面となす角度は、打ち当る運動の線が同じ面となす角度に等しいであろう。
 以上は最も単純な物体について、すなわち単に運動および静止、迅速および遅緩によって相互に区別される物体についてである。これから我々は複合した物体に移ろう。
以上は最も単純な物体について、すなわち単に運動および静止、迅速および遅緩によって相互に区別される物体についてである。これから我々は複合した物体に移ろう。
定義 同じあるいは異なった大いさのいくつかの物体が、他の諸物体から圧力を受けて、相互に接合するようにされている時、あるいは(これはそれらいくつかの物体が同じあるいは異なった速度で運動する場合である)自己の運動をある一定の割合で相互に伝達するようにされている時、我々はそれらの物体がたがいに合一していると言い、またすべてが一緒になって一物体あるいは一個体を組織していると言う。そしてこの物体あるいは個体は、構成諸物体のこうした合一によって他の諸物体と区別される。 (振動数、ホイヘンス?)
公理三 個体の、あるいは複合した物体の、各部分がより大なるあるいはより小なる表面をもって相互に接合するにつれて、それらの部分は自己の位置を変えるように強制されることがそれだけ困難にあるいはそれだけ容易になる。したがってまたその個体自身も他の形状をとるようにされることがそれだけ困難にあるいはそれだけ容易になる。そこで私は、その部分が大なる表面をもって相互に接合する物体を硬、その部分が小なる表面をもって接合する物体を軟、最後にまたその部分が相互に運動する物体を流動的と呼ぶであろう。 114
補助定理四 もし多くの物体から組織されている物体あるいは個体から、いくつかの物体が分離して、同時に、同一本性を有する同数量の他の物体がそれに代るならば、その個体は何ら形相を変ずることなく以前のままの本性を保持するであろう。
証明 なぜなら、物体は(補助定理一により)実体に関しては区別されない。一方、個体の形相を構成するものは(前定義により)(単に)構成物体の合一に存する。ところがこの合一は(仮定により)、構成物体の絶えざる変化にもかかわらず保持されることになっている。ゆえにこの個体は実体ならびに様態に関して以前のままの本性を保持するであろう。Q・E・D・
補助定理五 もし個体を組織する各部分が、すべてその相互間の運動および静止の割合を以前のままに保つような関係において、より大きくあるいはより小さくなるならば、その個体もまた何ら形相を変ずることなく以前のままの本性を保持するであろう。
証明 この補助定理の証明は前の補助定理のそれと同一である。
補助定理六 もし個体を組織するいくつかの物体がある方向に対して有する運動を他の方向に転ずるように強いられ、しかもその運動を継続しかつその運動を以前と同じ割合において相互間に伝えることができるようにされるならば、その個体はやはり何ら形相を変ずることなくその本性を保持するであろう。
証明 それ自体で明らかである。なぜなら、仮定によれば、この個体は我々が先に個体の定義の中で個体の形相を構成すると言ったすべてのものを保持しているからである。(補助定理四の前にある定義を見よ。)
補助定理七 そのほか、このように複合した個体は、全体として運動ないし静止していようとも、あるいはこのないしかの方向に運動していようとも、もしただその各部分が自己の運動を保持してそれを以前と同じように他の部分に伝えてさえいれば、その本性を保持する。
証明 これ(もまた)その定義から明白である。補助定理四の前にある定義を見よ。
備考 このようにして我々は、これから、複合した個体が多様の仕方で動かされかつそれにもかかわらずその本性を保ちうることの理由を解しうる。
これまで我々は単に運動および静止、迅速および遅緩によって相互に区別される諸物体からのみ組織されている個体、言いかえれば最も単純な諸物体からのみ組織されている個体を考えた。しかし今もし本性を異にする多くの個体から組織されている他の個体を考えるなら、その個体は他のいっそう多くの仕方で動かされかつそれにもかかわらずその本性を保ちうることを我々は見いだすであろう。なぜなら、その個体の各部分が種々の物体から組織されているのだから、その各部分は(前の補助定理により)個体の本性を少しも変えることなしに、ある時は緩やかにある時は速やかに運動し、したがってまたその運動を他の部分へ速やかにあるいは緩やかに伝えることができるだろうからである。
もしさらに我々がこうした第二の種類の個体から組織された第三の種類の個体を考えるなら、我々はそうした個体がその形相を少しも変えることなしに他の多くの仕方で動かされうることを見いだすであろう。そしてもし我々がこのようにして無限に先へ進むなら、我々は、全自然が一つの個体であってその部分すなわちすべての物体が全体としての個体には何の変化もきたすことなしに無限に多くの仕方で変化することを容易に理解するであろう。
もし私の意図が(物質についてあるいは)物体について専門に(かつ特別に)論ずることにあったとしたら、私はこれらのことをもっと詳しく説明し証明しなければならなかったであろう。しかし、すでに述べたように、私の意図するところは別のものであり、私がこうした事柄をここに問題としたのは、私が本来証明しようと企てたことをそれから容易に引き出しうるためにほかならなかったのである。
要請
一 人間身体は、本性を異にするきわめて多くの個体〜〜そのおのおのがまたきわめて複雑な組織の〜〜から組織されている。
二 人間身体を組織する個体のうち、あるものは流動的であり、あるものは軟かく、最後にあるものは硬い。
三 人間身体を組織する個体、したがってまた人間身体自身は、外部の物体からきわめて多様の仕方で刺激される。
四 人間身体は自らを維持するためにきわめて多くの他の物体を要し、これらの物体からいわば絶えず更生される。
五 人間身体の流動的な部分が他の軟かい部分にしばしば突き当るように外部の物体から決定されるならば、その流動的な部分は軟かい部分の表面を変化させ、そして突き当たる運動の源である外部の物体の痕跡のごときものをその軟かい部分に刻印する。
六 人間身体は外部の物体をきわめて多くの仕方で動かし、かつこれにきわめて多くの仕方で影響することができる。
定理一四 人間精神はきわめて多くのものを知覚するのに適する。そしてこの適性は、その身体がより多くの仕方で影響されうるに従ってそれだけ大である。
証明 なぜなら人間身体は(要請三および六により)きわめて多くの仕方で外部の物体から刺激(アフィキトゥル)されるし、またきわめて多くの仕方で外部の物体を刺激するような状態にされる。ところが人間身体の中に起こるすべてのことを人間精神は知覚しなければならぬ(この部の定理一二により)。ゆえに人間精神はきわめて多くのものを知覚するのに適し、そしてこの適性は(人間身体の適性がより大なるに従ってそれだけ大である。)Q・E・D・
定理一五 人間精神の形相的有(エッセ・フォルマーレ)を構成する観念は単純ではなくて、きわめて多くの観念から組織されている。
証明 人間精神の形相的有を構成する観念は身体の観念であり(この部の定理一三により)、そしてこの身体は(要請一により)きわめて複雑な組織のきわめて多くの個体から組織されている。ところが身体を組織するおのおのの個体について必然的に神の中に観念が存する(この部の定理八の系により)。ゆえに(この部の定理七により)人間身体の観念は、身体を組織する部分についてのきわめて多くのこうした観念から組織されている。Q・E・D・
定理一六 人間身体が外部の物体から刺激(アフィキトゥル)されるおのおのの様式の観念は、人間身体の本性と同時に、外部の物体の本性を含まなければならぬ。
証明 なぜなら、ある物体が刺激される一切の様式は、刺激される物体の本性からと同時に刺激する物体の本性から生ずる(補助定理三の系のあとにある公理一により)。ゆえにこれらの様式の観念は(第一部公理四により)必然的に両方の物体の本性を含む。したがって人間身体が外部の物体から刺激される一切の様式の観念は、人間身体の本性ならびに外部の物体の本性を含む。
Q・E・D・
系一 この帰結として第一に、人間精神は自分自身の身体の本性とともにきわめて多くの物体の本性を知覚するということになる。
系二 第二に、我々が外部の物体について有する観念は外部の物体の本性よりも我々の身体の状態をより多く示すということになる。これは私が第一部の付録の中で多くの例を挙げて説明したところである。
定理一七 もし人間身体がある外部の物体の本性を含むような仕方で刺激されるならば、人間精神は、身体がこの外部の物体の存在あるいは現在を排除する刺激を受けるまでは、その物体を現実に存在するものとして、あるいは自己に現在するものとして、観想するであろう。
証明 明白である。なぜなら人間身体がそのような仕方で刺激されて(アフェクトゥス)いる間は、人間精神は(この部の定理一二により)身体のこの刺激(アフェクティオ)を観想するであろう。言いかえれば、精神は(前定理により)現実に存在する刺激状態について、外部の物体の本性を含む観念を、言いかえれば外部の物体の本性の存在あるいは現在を排除せずにかえってこれを定立する観念を有するであろう。したがって精神は(前定理の系一により)、身体が外部の物体の存在あるいは現在を排除する刺激を受けるまでは、外部の物体を現実に存在するものとして、あるいは現在するものとして観想するであろう。Q・E・D・
系 人間身体をかつて刺激した外部の物体がもはや存在しなくても、あるいはそれが現在しなくても、精神はそれをあたかも現在するかのように観想しうるであろう。
証明 人間身体の流動的な部分が軟かい部分にしばしば衝き当るように外部の物体から決定されると、軟かい部分の表面は(要請五により)変化する。この結果として、流動的な部分は、軟かい部分の表面から、以前とは異なる仕方で弾ね返ることになる。そしてあとになって流動的な部分がこの変化した表面に自発的な運動をもって突き当たると、流動的な部分は前に外部の物体から軟かい部分の表面を衝くように促された時と同じ仕方で弾ね返ることになる(補助定理三の系
のあとにある公理二を見よ)。したがってまたそれはこのように弾ね返る運動を継続する間は〔以前外部の物体に促されてした時と〕同じ仕方で人間身体を刺激することになる。この刺激を精神は(この部の定理一二により)ふたたび認識するであろう。言いかえれば精神は(この部の定理一七により)ふたたび外部の物体を現在するものとして観想するであろう。そしてこのことは、人間身体の流動的な部分がその自発的な運動をもって軟かい部分の表面を衝くたびごとに起こるであろう。ゆえに人間身体をかつて刺激した外部の物体がもはや存在しなくても、精神は、身体のこうした活動がくり返されるたびごとに、外部の物体を現在するものとして観想するであろう。Q・E・D・
備考 このようにして我々は、しばしば起こるように、もはや存在しないものをあたかも現在するかのごとく観想するということがいかにして起こりうるかを知る。そしてこのことは他の原因からも起こることが可能である。しかしここでは真の原因によってそれを説明したと同様の効果のある一つの原因を示しただけで私にとっては十分である。それにまた私は真の原因からそれほど遠ざかっているとは信じない。なぜなら、私が採用したあのすべての要請は経験によって裏付けられないことをほとんど含んでいないのであり、そして人間身体が我々の感ずるとおりに存在していることを示した今では、経験について疑うことは我々にとって許されないからである(この部の定理一三のあとにある系を見よ)。
その上我々は(前の系ならびにこの部の定理一六の系二から)例えばペテロ自身の精神の本質を構成するペテロの観念と、他の人間例えばパウロの中に在るペテロ自身の観念との間にどんな差異があるかを明瞭に理解しうる。すなわち前者はペテロ自身の身体の本質を直接に説明し、ペテロの存在する間だけしか存在を含んでいない。これに反して後者はペテロの本性よりもパウロの身体の状態をより多く示しており〈この部の定理一六の系二を見よ〉、したがって。パウロの身体のこの状態が持続する間は、パウロの精神は、ペテロがもはや存在しなくてもペテロを自己にとって現在するものとして観想するであろう。
なお普通に用いられている言葉を保存するために、人間身体の変状(アフェクティオ)〔刺激状態〕〜〜我々はこの変状の観念によって外部の物体を我々に現在するものとして思い浮かべるのである〜〜は物の形状を再現しないけれども我々はこれを物の表象像(イマゴ)と呼ぶであろう。そして精神がこのような仕方で物体を観想する時に我々は精神が物を表象(イマギナリ)すると言うであろう。
それから私はここに誤謬とは何であるかを示す手始めとして、次のことを注意したい。それは、精神の表象はそれ自体において見れば何の誤謬も含んでいないということ、言いかえれば精神は物を表象するからといってただちに誤りを犯しているのではなく、ただ精神が自己に現在するものとして表象する事物についてその存在を排除する観念を欠いていると見られる限りにおいてのみ誤りを犯しているのであるということである。なぜなら、もし精神が存在しない物を自己に現在するものとして表象するのに際し、それと同時にその物が現実に存在しないことを知っていたとしたら、精神はたしかに、表象するこの能力を、自己の本性の欠点とは認めず、かえって長所と認めたことであろう。特にもしこの表象能力が精神の本性にのみ依存しているとしたら、言いかえれば(第一部定義七により)もし精神のこの表象能力が自由であったとしたら、なおさらそうであろう。
定理一八 もし人間身体がかつて二つあるいは多数の物体から同時に刺激されたとしたら、精神はあとでその中の一つを表象する場合ただちに他のものをも想起するであろう。
証明 精神がある物体を表象するのは(前の系により)人間身体のいくつかの部分がかつて外部の物体自身から刺激されたのと同様の刺激・同様の影響を人間身体が外部の物体の残した痕跡から受けることに基づくのである。ところが(仮定によれば)身体はかつて、精神が同時に二つの物体を表象するようなそうした状態に置かれていた。ゆえに精神は、今もまた、同時に二つのものを表象するであろう。そしてその一つを表象する場合、ただちに他のものを想起するであろう。Q・E・D・
備考 このことから我々は、記憶(メモリア)の何たるかを明瞭に理解する。すなわちそれは、人間身体の外部に在る物の本性を含む観念のある連結にほかならない。そしてこの連結は精神の中に、人間身体の変状(アフェクティオ)〔刺激状態〕の秩序および連結に相応して生ずる。
私は第一に、それは単に人間身体の外部に在る物の本性を含む観念の連結であって、それらの物の本性を説明する観念の連結ではないと言う。なぜなら、それは実は人間身体の変状〔刺激状態〕の観念にほかならぬのであり、そしてこの観念は人間身体の本性と外部の物体の本性とを含んでいるからである(この部の定理一六により)。私は第二に、この連結は人間身体の変状〔刺激状態〕の秩序および連結に相応して生ずると言う。そのわけはこれを知性の秩序に相応して生ずる観念の連結と区別するためである。この知性の観念の連結においては精神はその第一原因によって知覚する、そしてこの知性の観念の連結はすべての人間にあって同一なのである。
さらにこれから我々は、なにゆえに精神が一つの物の思いからただちにそれとは少しも類似性のない他の物の思いへ移るかを明瞭に理解する。例えばローマ人はポームム〔くだもの〕という言葉の思いからただちにある果実の思いへ移るであろう。この果実はあの発音された音声とは何の類似性もなくまた何の共通点もない。ただ同じ人間の身体がこの両者からしばしば刺激されただけにすぎない。言いかえれば、人間がその果実自体を目にしながら同時に幾度もポームムという言葉を聞いたというにすぎない。このようにして各人は、自分の習慣が事物の表象像を身体の中で秩序づけているのに応じて一つの思いから他の思いへ移るであろう。例えば軍人は、砂の中に残された馬の足跡を見て、ただちに馬の思いから騎士の思いへ、また騎士の思いから戦争その他の思いへ移るであろう。ところが農夫は、馬の思いから鋤や畑その他の思いへ移るであろう。このようにして各人は、自分が事物の表象像をこのあるいはかの仕方で結合し、連結するように習慣づけられているのに応じて一つの思いからこのあるいはかの思いへ移るであろう。
定理一九 人間精神は身体が受ける刺激(アフェクティオ)〔変状〕の観念によってのみ人間身体自身を認識し、またそれの存在することを知る。
証明 なぜなら、人間精神は人間身体の観念あるいは認識にほかならない(この部の定理一三により)。そしてこの観念あるいは認識は、神が他の個物の観念に変状(アフェクトゥス)したと見られる限りにおいて神の中に在る(この部の定理九により)。言いかえれば、人間身体はいわば絶えず更生されるためにきわめて多くの物体を要するから(要請四により)、そして観念の秩序および連結は原因の秩序および連結と同一であるから(この部の定理七により)、この観念〔人間身体の観念〕は、神がきわめて多くの個物の観念に変状(アフェクトゥス)したと見られる限りにおいて神のうちに在るであろう。こうして神は、人間精神の本性を構成する限りにおいてではなく、きわめて多くの他の観念に変状した限りにおいて、人間身体の観念を有し、あるいは人間身体を認識する。言いかえれば(この部の定理一一の系により)人間精神は人間身体を認識しないのである。〜〜これに反して、身体の変状〔刺激状態〕の観念は、神が人間精神の本性を構成する限りにおいて神の中に在る。すなわち人間精神はそうした変状〔刺激状態〕を知覚する(この部の定理一二により)。したがって人間精神は(この部の定理一六により)人間身体自身を知覚し、しかもそれを(この部の定理一七により)現実に存在するものとして知覚する。ゆえにこの限りにおいてのみ人間精神は人間身体自身を知覚する。Q・E・D・
定理二〇 人間精神についても神の中に観念あるいは認識がある。そしてこの観念あるいは認識は、人間身体の観念あるいは認識と同様の仕方で神の中に生じ、また同様の仕方で神に帰せられる。
証明 思惟は神の属性である(この部の定理一により)。ゆえに思惟ならびに思惟のすべての変状について(この部の定理三により)、したがってまた人間精神についても(この部の定理一一により)、必然的に神の中に観念がなければならぬ。次に精神のこの観念あるいは認識は、神が無限である限りにおいて神の中にあるのではなく、神が他の個物の観念に変状した限りにおいて神の中にある(この部の定理九により)。ところが観念の秩序および連結は原因の秩序および連結と同一である(この部の定理七により)。ゆえに精神のこの観念あるいは認識は、身体の観念あるいは認識と同様の仕方で神の中に生じ、また神に帰せられる。Q・E・D・
定理二ー 精神のこの観念は、精神自身が身体と合一しているのと同様の仕方で精神と合一している。
証明 精神が身体と合一していることを我々は身体が精神の対象であることから明らかにした(この部の定理一二および一三を見よ)。したがってこれと同じ理由により、精神の観念も、精神自身が身体と合一しているのと同様の仕方でその対象と、言いかえれば精神自身と、合一していなければならぬ。Q・E・D・ 126
備考 この定理はこの部の定理七の備考の中で述べたことからはるかに明瞭に理解される。なぜなら、我々はそこで、身体の観念と身体とは、言いかえれば(この部の定理一三により)精神と身体とは同一個体であって、それがある時は思惟の属性のもとである時は延長の属性のもとで考えられるのであることを明らかにした。同様に、精神の観念と精神自身ともまた同一物であって、それが今度は同一の属性すなわち思惟の属性のもとで考えられるのである。つまり、精神の観念と精神自身とは同一の必然性をもって同一の思惟能力から神の中に生ずるのである。なぜなら、精神の観念すなわち観念の観念というものは実は観念〜〜その対象との関係を離れて思惟の様態として見られる限りにおいて〜〜の形相〔本質〕にほかならないからである。これは、ある人があることを知ればその人はそれによって同時に自分がそれを知ることを知り、また同時に自分は自分がそれを知ることを知ることを知り、このようにして無限に進む、ということから明らかである。しかしこれについてはあとにゆずる。
定理二二 人間精神は、身体の変状〔刺激状態〕のみならずこの変状の観念をも知覚する。
証明 変状の観念の観念は、変状の観念そのものと同様の仕方において神の中に生じ、また同様の仕方において神に帰せられる。これはこの部の定理二〇と同様の方法で証明される。ところが身体の変状の観念は人間精神の中にある(この部の定理一二により)。言いかえればそれは神が人間精神の本質を構成する限りにおいて神の中にある(この部の定理一一の系により)。ゆえにこれらの観念の観念は、神が人間精神の認識あるいは観念を有する限りにおいて神の中にあるであろう。言いかえればそれは(この部の定理二一により)人間精神自身の中にあるであろう。それゆえ人間精神は、身体の変状のみならず、その観念をも知覚する。Q・E・D・
定理二三 精神は身体の変状〔刺激状態〕の観念を知覚する限りにおいてのみ自分自身を認識する。
証明 精神の観念あるいは認識は(この部の定理二〇により)身体の観念あるいは認識と同様の仕方で神の中に生じ、かつ同一の仕方で神に帰せられる。ところが(この部の定理一九により)人間精神は人間身体自身を認識しないから、言いかえれば(この部の定理一一の系により)人間身体の認識は神が人間精神の本性を構成する限りにおいては神に帰せられないから、したがって精神の認識もまた、神が人間精神の本質を構成する限りにおいては神に帰せられない。それゆえ(同じくこの部の定理一一の系により)人間精神はその限りにおいては自分自身を認識しない。次に身体が受ける刺激〔変状〕の観念は人間身体自身の本性を含む(この部の定理一六により)、言いかえればそれは(この部の定理一三により)精神の本性と一致する。それゆえにこれらの観念の認識は必然的に精神の認識を含む。ところが(前定理により)これらの観念の認識は人間精神自身の中に在る。ゆえに人間精神はその限りにおいてのみ自分自身を認識するのである。Q・E・D・
定理二四 人間精神は人間身体を組織する部分の妥当な認識を含んでいない。
証明 人間身体を組織する部分は、それが自己の運動をある一定の割合で相互間に伝達する限りにおいてのみ身体自身の本質に属し(補助定理三の系のあとにある定義を見よ)、それが個体として人間身体と関係なしに考察されうる限りにおいては身体の本質に属さない。事実、人間身体の部分はきわめて複雑な組織の個体であり(要請一により)、それらの部分は、身体の本性および形相を少しも変えることなしに、身体から分離することもできるし(補助定理四により)また自己の運動を他の諸物体へ異なる仕方で伝達することもできる(補助定理三のあとにある公理一を見よ)のである。こうして(この部の定理三により)おのおののこうした部分の観念あるいは認識は神の中に在るであろうが、しかしそれは神が他の個物自然の秩序から言ってそうした部分に先立っているような(この部の定理七により)の観念に変状したと見られる限りにおいてである(この部の定理九により)。さらに人間身体を組織する個体自身のそのまたおのおのの部分についても同じことが言われうる。したがって人間身体を組織するおのおのの部分の認識は、神が単に人間身体の観念、言いかえれば(この部の定理一三により)人間精神の本性を構成する観念を有する限りにおいてではなく、神がきわめて多くの事物の観念に変状した限りにおいて、神の中に在る。したがって(この部の定理一一の系により)人間精神は人間身体を組織する部分の妥当な認識を含んでいない。Q・E・D・
定理二五 人間身体のおのおのの変状〔刺激状態〕の観念は外部の物体の妥当な認識を含んでいない。
証明 外部の物体が人間身体をある一定の仕方で刺激する限りその限りにおいて人間身体の変状(アフェクティオ)〔刺激状態〕の観念はその外部の物体の本性を含んでいることを我々は示した(この部の定理一六を見よ)。しかし外部の物体がもともと人間身体と関係のない個体である限りにおいては、それの観念あるいは認識は、神が他の事物〜〜本性上外部の物体自身に先立っているような(この部の定理七により)〜〜の観念に変状(アフェクトゥス)したと見られる限りにおいてのみ神の中に在る(この部の定理九により)。ゆえに外部の物体の妥当な認識は、神が人間身体の変状の観念を有する限りにおいては神の中にない。すなわち人間身体の変状の観念は外部の物体の妥当な認識を含んでいない。Q・E・D・
定理二六 人間精神は自己の身体の変状(アフェクトゥス)〔刺激状態〕の観念によってのみ外部の物体を現実に存在するものとして知覚する。
証明 もし人間身体がある外部の物体からいかなる仕方でも刺激(アフェクトゥス)ぎれないなら、人間身体の観念もまた(この部の定理七により)、言いかえれば(この部の定理一三により)人間精神もまた、いかなる仕方でもそうした物体の存在の観念に刺激されない。すなわち人間精神はそうした外部の物体の存在をいかなる仕方でも知覚しない。これに反して人間身体がある外部の物体からある仕方で刺激される限り、人間精神は(この部の定理一六およびその系一により)外部の物体を知覚する。Q・E・D・
系 人間精神は、外部の物体を表象する限り、それの妥当な認識を有しない。
証明 人間精神がその身体の変状の観念によって外部の物体を観想する時、我々は精神が物を表象すると言う(この部の定理一七の備考を見よ)。しかも精神は他の仕方では(前定理により)外部の物体を現実に存在するものとして表象しえない。したがって(この部の定理二五により)精神は外部の物体を表象する限りそれの妥当な認識を有しない。Q・E・D・
定理二七 人間身体のおのおのの変状〔刺激状態〕の観念は人間身体そのものの妥当な認識を含んでいない。
証明 人間身体のおのおのの変状の観念は、すべて、人間身体自身がある一定の仕方で刺激されると見られる限りにおいて人間身体の本性を含んでいる(この部の定理一六を見よ)。しかし人間身体がなお多くの他の仕方で刺激されうる個体である限りにおいてはそれの観念は云々。この部の定理二五の証明を見よ。
定理二八 人間身体の変状の観念は、単に人間精神に関連している限り、明瞭判然たるものではなく、混乱したものである。
証明 なぜなら、人間身体の変状の観念は外部の物体ならびに人間身体自身の本性を含んでいる(この部の定理一六により)。しかもそれは人間身体の本性のみならずその部分の本性も含んでいなければならない。なぜなら変状とは人間身体の部分、したがってまた身体全体が刺激される様式だからである(要請三により)。ところが(この部の定理二四および二五により)外部の物体の妥当な認識ならびに人間身体を組織する部分の妥当な認識は神が人間精神に変状したと見られる限りにおいては神の中になく、神が他の多くの観念に変状したと見られる限りにおいて神の中に在る、〈言いかえれば(この部の定理一三により)この認識は神が人間精神の本性を構成する限りにおいては神の中にない〉。ゆえにこの変状の観念は、単に人間精神に関連している限りは、いわば前提のない結論のようなものである。言いかえればそれは(それ自体で明白なように)混乱した観念である。Q・E・D・
備考 人間精神の本性を構成する観念は単にそれ自体のみにおいて考察すれば明瞭判然たるものでないということは同様の仕方で証明される。人間精神の観念および人間身体の変状の観念の観念も、それが単に精神にのみ関連している限りそうである。〈すなわち混乱したものである。〉これは各人の容易に知りうるところである。
定理二九 人間身体のおのおのの変状の観念の観念は人間精神の妥当な認識を含んでいない。
証明 なぜなら、人間身体の変状の観念は(この部の定理二七により)身体自身の妥当な認識を含んでいない。あるいはその本性を妥当に表現しない。言いかえればそれは(この部の定理一三により)精神の本性と妥当に一致しない。したがって(第一部公理六により)その観念の観念もまた人間精神の本性を妥当に表現しない。あるいはその妥当な認識を含んでいない。Q・E・D・
系 この帰結として、人間精神は物を自然の共通の秩序に従って知覚する場合は、常に自分自身についても自分の身体についても外部の物体についても妥当な認識を有せず単に混乱し・毀損(きそん)した認識のみを有する、ということになる。なぜなら、精神は、身体の変状の観念を知覚する限りにおいてのみ自分自身を認識する(この部の定理二三により)、また精神は身体の変状の観念自身によってのみ自分の身体を知覚し(この部の定理一九により)、さらに同じくこの変状の観念自身によってのみ外部の物体を知覚する(この部の定理二六により)。したがって精神は、そうした観念を有する限りは、自分自身についても(この部の定理二九により)、自分の身体についても(この部の定理二七により)、外部の物体についても(この部の定理二五により)、妥当な認識を有せず、単に(この部の定理二八ならびにその備考により)毀損し・混乱した認識を有するのみである。Q・E・D・
備考 私ははっきり言う〜〜精神は物を自然の共通の秩序に従って知覚する場合には、言いかえれば外部から決定されて、すなわち物との偶然的接触に基づいて、このものあるいはかのものを観想する場合には、常に自分自身についても自分の身体についても外部の物体についても妥当な認識を有せず、単に混乱し(毀損し)た認識を有するのみである。これに反して内部から決定されて、すなわち多くの物を同時に観想することによって、物の一致点・相違点・反対点を認識する場合にはそうでない。なぜなら精神がこのあるいはかの仕方で内部から決定される場合には、精神は常に物を明瞭判然と観想するからである。このことについてはのちに示すであろう。
定理三〇 我々は我々の身体の持続についてはきわめて非妥当な認識しかもつことができない。
証明 我々の身体の持続は身体の本質に依存しないし (この部の公理一により)、また神の絶対的本性にも依存しない(第一部定理二一により →第一部定理二八)。むしろ身体は(他の)原因から存在し・作用するように決定され、この原因がまた他の原因からある一定の仕方で存在し・作用するように決定され、さらにこの後者も他から決定され、このようにして無限に進む。したがって我々の身体の持続は自然の共通の秩序および諸物の排列状態に依存する。しかし諸物がいかなる仕方で排列されているかについての妥当な認識は、神がすべての物の観念を有する限りにおいて神の中に在り、神が単に人間身体の観念を有する限りにおいては神の中にはない(この部の定理九の系により)。ゆえに我々の身体の持続の認識は、神が単に我々の精神の本性を構成すると見られる限りにおいては神の中においてきわめて非妥当なものである。言いかえれば(この部の定理一一の系により)この認識は我々の精神の中においてはきわめて非妥当なものである。Q・E・D・
定理三一 我々は我々の外部に在る個物の持続についてはきわめて非妥当な認識しかもつことができない。
証明 なぜなら、おのおのの個物は人間身体と同様に他の個物からある一定の仕方で存在し・作用するように決定されなければならぬ、そしてこの後者もまた他の物から決定され、このようにして無限に進む(第一部定理二八により)。ところが我々は前定理において、我々が我々の身体の持続についてきわめて非妥当な認識しか有しないことを個物のこの共通の特質から証明した。ゆえに個物の持続についても同じことが結論されるであろう。すなわち我々は個物の持続についてはきわめて非妥当な認識しかもつことができない。Q・E・D・
系 この帰結として、すべての個物は偶然的でかつ可滅的であるということになる。というのは、我々は個物の持続について何ら妥当な認識をもつことができないのであり(前定理により)、そして我々が物の偶然性とか可滅性とか言っているのは結局そうしたことを指しているのだからである(第一部定理三三の備考一を見よ)。実際この意味以外ではおよそ偶然的な物は一つとして存在しないのであるから(第一部定理二九により)。 (個物、可滅性)
定理三二 すべての観念は神に関係する限り真である。
証明 なぜなら、神の中に在るすべての観念は、その(対象すなわち)観念されたものとまったく一致する(この部の定理七の系により)。したがって(第一部公理六により)すべて真である。
Q・E・D・
定理三三 観念の中にはそれを虚偽と言わしめるような積極的なものは何も存しない。
証明 これを否定しようとする者は、もしできるなら、誤謬または虚偽の形相を構成するある積極的な思惟の様態が存在すると考えてみよ。この思惟の様態は神の中に在ることができない(前定理により)。しかしそれは神の外にも在りまたは考えられることができない(第一部定理一五により)。それゆえ、観念の中には、それを虚偽と言わしめるような積極的なものは何も存しえない。Q・E・D・
定理三四 我々の中において絶対的なあるいは妥当で完全な観念はすべて真である。
証明 我々の中に妥当で完全な観念が存すると我々が言う時、それは(この部の定理一一の系
により)、我々の精神の本質を構成する限りにおいての神の中に妥当で完全な観念が存すると言っているのにほかならぬのであり、したがってまた(この部の定理三二により)そうした観念が真であると言っているのにほかならないのである。Q・E・D・
定理三五 虚偽〔誤謬〕とは非妥当なあるいは毀損し・混乱した観念が含む認識の欠乏に存する。
証明 観念の中には虚偽の形相を構成する積極的なものは何も存しない(この部の定理三三により)。しかし虚偽は(認識の)絶対的な欠乏には存しえない(なぜなら、誤るとか錯誤するとか言われるものは精神であって身体などではないのだから)。だからといってそれは絶対的無知にも存しない。なぜなら、あることを知らないということと誤るということは別ものだからである。
それゆえ虚偽〔誤謬〕とは事物の非妥当な認識、あるいは非妥当で混乱した観念が含む認識の欠乏に存する。Q・E・D・
備考 この部の定理一七の備考の中で私はいかなるわけで誤謬が認識の欠乏に存するかを説明した。しかしそのことをいっそう詳細に説明するために例を挙げよう。
例えば人間が自らを自由であると思っているのは、(すなわち彼らか自分は自由意志をもってあることをなしあるいはなさざることができると思っているのは、)誤っている。そしてそうした誤った意見は、彼らがただ彼らの行動は意識するが彼らをそれへ決定する諸原因はこれを知らないということにのみ存するのである。だから彼らの自由の観念なるものは彼らが自らの行動の原因を知らないということにあるのである。なぜなら、彼らが、人間の行動は意志を原因とすると言ったところで、それは単なる言葉であって、その言葉について彼らは何の理解も有しないのである。すなわち意志とは何であるか、また意志がいかにして身体を動かすかを彼らは誰も知らないのである。またそれを知っていると称して魂の在りかや住まいを案出する人々は嘲笑か嫌悪をひき起こすのが常である。
同様に、我々は太陽を見る時太陽が約二百フィート我々から離れていると表象する。この誤謬はそうした表象自体の中には存せず、我々が太陽をそのように表象するにあたって太陽の真の距離ならびに我々の表象の原因を知らないことに存する。なぜなら、もしあとで我々が太陽は地球の直径の六百倍以上も我々から離れていることを認識しても、我々はそれにもかかわらずやはり太陽を近くにあるものとして表象するであろう。なぜなら、我々が太陽をこれほど近いものとして表象するのは、我々が太陽の真の距離を知らないからではなく、我々の身体の変状〔刺激状態〕は身体自身が太陽から刺激される限りにおいてのみ太陽の本質を含んでいるからである。
定理三六 非妥当で混乱した観念は、妥当なあるいは明瞭判然たる観念と同一の必然性をもって生ずる。
証明 すべての観念は神の中に在る(第一部定理一五により)、そしてそれは神に関する限りにおいて真であり(この部の定理三二により)、また(この部の定理七の系により)妥当である。したがっていかなる観念も、それがある人間の単独の精神に関する限りにおいてでなくては、非妥当でもなければ混乱してもいない(これについてはこの部の定理二四および二八を見よ)。それゆえに観念は、妥当なものでも非妥当なものでも、すべて同一の必然性をもって生ずるのである(この部の定理六の系により)。Q・E・D・
定理三七 すべての物に共通であり(これについては先の補助定理二を見よ)、そして等しく部分の中にも全体の中にもあるものは、決して個物の本質を構成しない。
証明 これを否定しようとする者は、もしできるなら、そうしたものがある個物の本質を、例えばBの本質を構成すると考えてみよ。この場合(この部の定義二により)そうしたものはBなしには存在することも考えられることもできないであろう。ところがこれは仮定に反する。ゆえにそうしたものはBの本質に属さないしまた他の個物の本質も構成しない。Q・E・D・
定理三八 すべての物に共通であり、そして等しく部分の中にも全体の中にも在るものは、妥当にしか考えられることができない。
証明 Aがすべての物体に共通でありそして等しく各物体の部分の中にも全体の中にも在るものであるとしよう。私はAが妥当にしか考えられることができないと主張するのである。なぜなら、Aの観念は(この部の定理七の系により)神が人間身体の観念を有する限りにおいても、また神が人間身体の変状〔刺激状態〕の観念〜〜人間身体の本性ならびに外部の物体の本性を部分的に含むような(この部の定理一六、二五および二七により)〜〜を有する限りにおいても、必然的に神の中で妥当であるであろう。言いかえれば(この部の定理一二および一三により)Aの観念は神が人間精神を構成する限りにおいて、あるいは神が人間精神の中に在る観念を有する限りにおいて、必然的に神の中で妥当であるであろう。ゆえに精神は(この部の定理一一の系により)Aを必然的に妥当に知覚する。しかもそれは精神が自分自身を知覚する限りにおいても、自分の身体あるいは外部の物体を知覚する限りにおいてもそうである。そしてAは他の仕方では考えられることができないのである。Q・E・D・
系 この帰結として、すべての人間に共通のいくつかの観念あるいは概念が存することになる。なぜなら(補助定理二により)すべての物体はいくつかの点において一致し、そしてこれらの点は(前定理により)すべての人から妥当にあるいは明瞭判然と知覚されなければならぬからである。
定理三九 人間身体および人間身体が刺激されるのを常とするいくつかの外部の物体に共通でかつ特有であるもの、そして等しくこれら各物体の部分の中にも全体の中にも在るもの、そうしたものの観念もまた精神の中において妥当であるであろう。
証明 Aが人間身体およびいくつかの外部の物体に共通でかつ特有であるもの、等しく人間身体の中にもこれらの外部の物体の中にも在るもの、そして最後に等しくこれら外部の各物体の部分の中にも全体の中にも在るもの、としよう。そうすればA自身については、神が人間身体の観念を有する限りにおいても、また神が前述の外部の諸物体の観念を有する限りにおいても、神の中に妥当な観念が在るであろう(この部の定理七の系により)。いま人間身体が、外部の物体から、外部の物体と共通に有するところのものによって、すなわちAによって刺激されると仮定しよう。そうすればこの刺激〔変状〕の観念はAという特質を含むであろう(この部の定理一六により)。またそれゆえに(再びこの部の定理七の系により)この刺激〔変状〕の観念は、Aという特質を含む限りにおいて、神の中で妥当であるであろう〜〜神が人間身体の観念に変状した限りにおいて、言いかえれば(この部の定理一三により)神が人間精神の本性を構成する限りにおいて。したがってまた(この部の定理一一の系により)この観念は人間精神の中でも妥当である。Q・E・D・
系 この帰結として、身体が他の物体と共通のものをより多く有するに従ってその精神は多くのものを妥当に知覚する能力をそれだけ多く有することになる。
定理四〇 精神のうちの妥当な観念から精神のうちに生起するすべての観念は、同様に妥当である。
証明 明白である。なぜなら、「人間の精神のうちの妥当な観念から精神のうちにある観念が生ずる、」と我々が言う場合、それは(この部の定理一一の系により)、「神が無限である限りにおいてではなく、また神がきわめて多くの個物の観念に変状した限りにおいてでもなく、神が単に 人間精神の本質を構成する限りにおいて、神の知性自身の中に神を原因とするある観念が在る、」と言っているのにほかならない〈、そしてこのゆえにそれは妥当なものでなければならぬ〉。
備考一 これをもって私は共通概念と呼ばれていて我々の推論の基礎となっている概念の原因を説明した。しかしある種の公理あるいは概念には他の原因があるのであり、これを我々のこうした方法で説明することは有益であるであろう。なぜならそれによって、いかなる概念が他の概念より有用であるか、またこれに反していかなる概念がほとんど無用であるかが判明するだろうし、さらにまたいかなる概念が〔すべての人々に〕共通であり、そしていかなる概念が偏見に煩(わずら)わされない人々にのみ明瞭判然であるか、最後にまたいかなる概念が悪しき基礎の上に立っているかが判明するであろうから。なおまた第二次概念と呼ばれる概念が、したがってまたその概念を基礎としている公理が、どこにその起因を有しているかも明らかになるだろうし、また私が今までこれについて考察してきた他の多くのこともはっきりするであろうから。しかし私はこのことを他の論文に譲ったし、それにまたこの事項についてあまり長くなって嫌気を起こさせてはと思ったので、ここではそれを省くことにした。 (他の論文=『知性改善論』)
けれども知る必要のあることは決して洩らさないために、私は「有」「物」「ある物」のようないわゆる超絶的名辞が起こった原因をついでに簡単に示すであろう。これらの名辞は、人間身体は限定されたものであるから自らのうちに一定数の表象像(表象像が何であるかはこの部の定理一七の備考の中で説明した)しか同時に判然と形成することができないということから生ずる。もしこの数が超過されれば表象像は混乱し始めるであろう。そしてもし身体が自らのうちに同時に明瞭に形成しうる表象像のこの数が非常に超過されればすべての表象像は相互にまったく混乱するであろう。こんな次第であるから、この部の定理一七の系ならびに定理一八からして、人間精神は、その身体の中で同時に形成されうる表象像の数だけの物体しか同時に判然と表象しえないということが明らかである。これに反して表象像が身体の中でまったく混乱するような場合には、精神もまたすべての物体を混乱してまったく差別なしに表象するであろう、そしてそれをいわば一つの属性すなわち「有」「物」などの属性のもとに包括するであろう。なおこのことは表象像が常に等しく清澄でないということからも導き出されるし、またこれと類似の他の諸原因からも導き出される。しかしそれをここに説明することは必要でない。我々の目指す目的のためにはただ一つの原因を考察するだけで十分である。なぜなら、どの原因を持ってきてみても、それは結局、超絶的名辞はきわめて混乱した観念を表示するということを示すことに落ちつくからである。
次に「人間」「馬」「犬」などのような一般的概念と呼ばれる概念が生じたのも同様の原因からである。すなわちそれは人間身体の中で同時に形成される表象像、例えば「人間」の表象像の数が表象力を徹底的には超過しないがある程度には超過する場合、つまり精神がその個々の人間の些細な相違(例えばおのおのの人間の色、大いさなど)ならびにそれらの人間の定数をもはや表象することができずただそれらの人間全体の一致点〜〜身体がそれらの人間から刺激される限りにおいて生ずる一致点〜〜のみを判然と表象しうる(なぜならその点において身体は最も多くそれら個々の人間から刺激されたのだから)ような場合である。そしてこの場合、精神はこの一致点を人間なる名前で表現し、これを無数に多くの個人に賦与するのである。今も言ったように精神はそれらの個々の人間の定数を表象しえないのであるから。しかし注意しなければならぬのは、これらの概念はすべての人から同じ仕方で形成されはしないこと、身体がよりしばしば刺激されたもの、したがってまた精神がよりしばしば表象しまたは想起するものに応じてそれは各人において異なっていることである。例えばよりしばしば人間の姿を驚歎して観想した者は人間という名前を直立した姿の動物と解するであろう。これに反して人間を別なふうに観想するのに慣れた者は人間に関して他の共通の表象像を形成するであろう。すなわち人間を笑う動物、羽のない二足動物、理性的動物などとするであろう。このようにしてその他のことについても各人は自分の身体の状態に応じて物の一般的表象像を形成するであろう。だから自然の事物を事物の単なる表象像によって説明しようとした哲学者たちの間にあれほど多くの論争が起こったのも不思議はないのである。
備考二 上に述べたすべてのことからして、我々が多くのものを知覚して一般的ないし普遍的概念を形成することが明白に分かる。すなわち次の手段で〜〜
一 感覚を通して毀損的・混乱的にかつ知性による秩序づけなしに我々に現示されるもろもろの個物から(この部の定理二九の系を見よ)。このゆえに私は通常こうした知覚を漠然たる経験による認識と呼び慣れている。
二 もろもろの記号から。例えば我々がある語を聞くか読むかするとともに物を想起し、それについて物自身が我々に与える観念と類似の観念を形成することから(この部の定理一八の備考を見よ)。
事物を観想するこの二様式を私はこれから第一種の認識、意見(オピニオ)もしくは表象(イマギナティオ)と呼ぶであろう。
三 最後に、我々が事物の特質について共通概念あるいは妥当な観念を有することから(この部の定理三八の系、定理三九およびその系ならびに定理四〇を見よ)。そしてこれを私は理性(ラティオ)あるいは第二種の認識と呼ぶであろう。
これら二種の認識のほかに、私があとで示すだろうように、第三種のものがある。我々はこれを直観知(スキエンティア・イントゥイティヴァ)と呼ぶであろう。そしてこの種の認識は神のいくつかの属性の形相的本質(エッセンティア・フォルマリス)の妥当な観念から事物の本質の妥当な認識へ進むものである。
これらすべてを私は一つの例で説明しよう。例えばここに三つの数が与えられていて第二数が第一数に対するのと等しい関係を第三数に対して有する第四数を得ようとする。商人は躊躇なく第二数に第三数を乗じ、その結果を第一数で除する。これは彼が先生から何の証明もなしに聞いたことをまだ忘れずにいたためであるか、あるいは彼がごく簡単な数でそれをしばしば経験したためか、あるいはまたユークリッド第七巻の定理一九の証明すなわち比例数の共通の特質に基づいたかである。しかしごく簡単な数ではこうしたことは必要でない。例えば一、二、三の数が与えられた場合第四の比例数が六であることは誰にも分かるであろう。そしてこの場合は、第一数が第二数に対して有する関係そのものを直観の一瞥(べつ)をもって見てとってそれから第四数自身を帰結するのであるから、はるかに明瞭である。
定理四一 第一種の認識は虚偽〔誤謬〕の唯一の原因である。これに反して第二種および第三種の認識は必然的に真である。
証明 我々は前の備考において、第一種の認識には非妥当で混乱したすべての観念が属すると言った。したがって(この部の定理三五により)この認識は虚偽の唯一の原因である。次に我々は、第二種および第三種の認識には妥当な諸観念が属すると言った。したがって(この部の定理三四により)これらの認識は必然的に真である。Q・E・D・
定理四二 我々に真なるものと偽なるものとを区別することを教えるのは、第一種の認識でなくて第二種および第三種の認識である。
証明 この定理はそれ自体で明白である。なぜなら、真なるものと偽なるものとを区別することを知っている者は、真なるものと偽なるものとについて妥当な観念を有しなければならぬからである。言いかえれば(この部の定理四〇の系二(×→○備考二)により)真なるものと偽なるものとを第二種または第三種の認識によって認識しなければならぬからである。
定理四三 真の観念を有する者は、同時に、自分が真の観念を有することを知り、かつそのことの真理を疑うことができない。
証明 我々の中の真の観念は、神が人間精神の本性によって説明される限りにおいて神の中で妥当な観念である(この部の定理一一の系により)。そこで今、神が人間精神の本性によって説明される限りにおいて神の中に妥当な観念Aが存在すると仮定しよう。この観念についてはまた、この観念と同様の仕方で神に帰せられるある観念が神の中に必然的に存在しなければならぬ(この部の定理二〇による。その証明は普遍的である〈そしてすべての観念にあてはめられうる〉から)。ところが、仮定によれば、観念Aは神が人間精神の本性によって説明される限りにおいて神に帰せられている。ゆえに観念Aの観念もまた同様の仕方で神に帰せられなければならぬ。言いかえれば(再びこの部の定理一一の系により)観念Aについての妥当なこの観念は、妥当な観念Aを有する同じ精神の中に在るであろう。したがって、妥当な観念を有する者、あるいは(この部の定理三四により)物を真に認識する者は、同時に、自分の認識について妥当な観念あるいは真の認識を有しなければならぬ。言いかえれば(それ自体で明らかなように)彼は同時にそれについて確実でなければならぬ。Q・E・D・
備考 この部の定理二一の備考の中で私は、観念の観念とは何であるかを説明した。しかし前定理はそれ自体で十分明白であることをここに注意しなくてはならぬ。なぜなら、真の観念を有する者は誰でも、真の観念が最高の確実性を含んでいることを知っているからである。というのは、真の観念を有するとは物を完全にあるいは最も善く認識するという意味にほかならないから。実際これについては何びとも疑うことができない。観念が画板の上の画のように無言のものであって思惟様態すなわち認識作用そのものではないと信じない限りは。あえて問うが、前もって物を認識していないなら自分がその物を認識していることを誰が知りえようか。すなわち前もって物について確実でないなら自分がその物について確実であることを誰が知りえようか。次に真理の規範として役立つのに真の観念よりいっそう明白でいっそう確実なものがありえようか。実に、光が光自身と闇とを顕(あら)わすように、真理は真理自身と虚偽との規範である。
これで私は次の諸問に答えたと信ずる。
それはすなわち、もし真の観念が〈思惟の様態である限りにおいてではなく〉単にその対象と一致すると言われる限りにおいてのみ偽の観念と区別されるのなら、真の観念は実在性あるいは完全性において偽の観念以上のものを何ら有しないのかどうか(なぜなら両者は単に外的特徴によってのみ区別される〈内的特徴によっては区別されない〉のだから)、〜〜したがってまた真の観念を有する〈人間あるいは人間精神〉も単に偽の観念のみを有する人間より実在性あるいは完全性において優れていないのかどうか、という問いである。
次に、人間が偽の観念を有するのは何に由来するのか、という問いである。
最後にまた、人は自らがその〈客体あるいは〉対象と一致する観念を有することを何によって確知しうるか、という問いである。
これらの問いに私は、今も言ったように、すでに答えたと信ずる。
なぜなら、真の観念と偽の観念との相違に関して言えば、前者は後者に対して有が非有に対するような関係にあることがこの部の定理三五によって明らかになっている。
次に、虚偽の原因については、私は定理一九から定理三五およびその備考に至るまでの間に十分明瞭に示した。これによってまた、真の観念を有する人間と偽の観念しか有しない人間との相違も明白になっている。 (虚偽の原因)
最後の点、すなわち人間は自らが〈その客体または〉その対象と一致する観念を有することを何によって知りうるかということについて言えば、それは、今しがた十二分に示したように、単に、彼が〈その客体あるいは〉その対象と一致する観念を有するということ、あるいは真理が真理自身の規範であるということ、そのことだけから出てくる。これに加えて、我々の精神は物を真実に知覚する限りにおいて神の無限な知性の一部分である(この部の定理一一の系により)。したがって精神の有する明瞭判然たる観念が神の有する観念と同様に真であることは必然である。
定理四四 事物を偶然としてでなく必然として観想することは理性の本性に属する。
証明 事物を真実に知覚すること(この部の定理四一により)、すなわち(第一部公理六により)事物をそれ自身あるとおりに知覚すること、は理性の本性に属する。言いかえれば(第一部定理二九により)事物を偶然としてでなく必然として知覚することは理性の本性に属する。Q・E・D・
系一 この帰結として、我々が物を過去ならびに未来に関して偶然として観想するのはもっばら表象力にのみ依存するということになる。
備考 だがこのことがどのようなふうにして起こるかを私は簡単に説明しよう。
我々はさきに(この部の定理一七およびその系)、精神は物の現在する存在を排除する原因が現われぬ限り、たとえ物が存在していなくとも、常にその物を自己に現在するものとして表象することを明らかにした。次に(この部の定理一八)もし人間身体がかつて外部の二物体から同時に刺激されたなら、精神はあとになってそのどちらか一つを表象する場合ただちに他の一つを想起するであろうということ、言いかえれば両者の現在する存在を排除する原因が現われぬ限り両者を現在するものとして観想するであろうということを我々は示した。なおまた我々が時間をも表象することは何びとも疑わぬところである。すなわち我々は、ある物体が他の物体と比べてより緩やかにあるいはより速やかにあるいは等しい速度で運動すると考えることによって時間を表象するのである。
ところでここに一人の小児があって、昨日はじめて朝にペテロを、昼にパウロを、夕にシモンを見、そして今日また朝にべテロを見たと仮定しよう。この部の定理一八から明らかなように、彼は暁の光を見るや、ただちに太陽が前日と同じ天域を運行することを表象するであろう。言いかえれば彼は一日全体の経過を表象するであろう。そして朝の時間とともにペテロを、昼の時間とともにパウロを、夕の時間とともにシモンを表象するであろう。それで今彼はパウロとシモンの存在を未来の時間に関連させて表象するであろう、これに反して彼が夕方シモンを見るとしたら、彼はパウロとペテロを過去の時間とともに表象してこの二人を過去の時間に関連させるであろう。そしてこうした表象結合は彼がこれらの人間をこの同じ順序において見る度合が重なるにつれてますます確乎たるものになるであろう。
だが彼がある夕シモンの代りにヤコブを見るということが一度起こるとしたら、翌朝彼は夕の時間を思う際にあるいはシモンをあるいはヤコブを表象するが両者を同時に表象することはないであろう。なぜなら、仮定によれば、彼は夕の時間常に両者の一人だけを見て両者を同時に見ることはなかったからである。ここにおいて彼の表象は動揺し、来るべき夕の時間を思う際にあるいはこの人をあるいはかの人を表象するであろう。言いかえれば彼は両者のいずれの出現をも確実とは考えず両者いずれかの出現を偶然なものとして表象するであろう。そしてこうした表象の動揺は、我々が同様の仕方で過去あるいは現在に関して観想する物について表象がなされる場合に常に現われるであろう。こうして我々は物を現在に関してもあるいは過去ないし未来に関しても偶然なものとして表象するであろう。
系二 物をある永遠の相のもとに知覚することは理性の本性に属する。
証明 なぜなら物を偶然としてでなく必然として観想することは理性の本性に属する(前定理により)。ところで理性は物のこの必然性を(この部の定理四一により)真実に、言いかえれば(第一部公理六により)それ自身においてあるとおりに、知覚する。ところが(第一部定理一六により)物のこの必然性は神の永遠なる本性の必然性そのものである。ゆえに物をこの永遠の相のもとに観想することは理性の本性に属する。その上、理性の基礎は概念であって(この部の定理三八により)、そうした概念はすべての物に共通なものを説明しそして(この部の定理三七により)決して個物の本質を説明しない。このゆえにそれらの概念は何ら時間との関係なしにある永遠の相のもとに考えられなければならぬ。Q・E・D・
定理四五 現実に存在するおのおのの物体ないし個物の観念はすべて神の永遠・無限なる本質を必然的に含んでいる。
証明 現実に存在する個物の観念はその個物の本質ならびに存在を必然的に含んでいる(この部の定理八の系により)。ところが個物は(第一部定理一五により)神なしには考えられることができない。そして(この部の定理六により)個物はそれ自身が様態となっている属性のもとで神が考察される限りにおいて神を原因とするから、個物の観念もまた(第一部公理四により)自己の属する属性の概念を、言いかえれば(第一部定義六により)神の永遠・無限なる本質を、必然的に含んでいなければならぬ。Q・E・D・ 150
備考 私がここで存在というのは持続のことではない。すなわち、抽象的に考えられる限りの存在、いわば一種の量として考えられる限りの存在のことではない。なぜなら私は、存在の本性そのものについて〜〜神の本性の永遠なる必然性から無限に多くのものが無限に多くの仕方で生ずる(第一部定理一六を見よ)がゆえに個物に付与される存在の本性そのものについて語っているのだから。つまり私は、神の中に存する限りにおける個物の存在そのものについて語っているのである。というのは、おのおのの個物は他の個物から一定の仕方で存在するように決定されているとはいえ、各個物が存在に固執する力はやはり神の本性の永遠なる必然性から生ずるからである。これについては第一部定理二四の系を見よ。
定理四六 おのおのの観念が含んでいる神の永遠・無限なる本質の認識は妥当で完全である。
証明 前定理の証明は普遍的なものであり、我々が物を部分として考察しようと全体として考察しようと、その物の観念は、神の永遠・無限なる本質を含んでいるのであって、その観念が全体に関するものであろうと部分に関するものであろうと変りはない(前定理により)。ゆえに神の永遠・無限なる本質の認識を与えるようなものはすべての物に共通なのであって、部分の中にも全体の中にも等しく存するのであり、したがって(この部の定理三八により)この認識は妥当であるであろう。Q・E・D・
定理四七 人間精神は神の永遠・無限なる本質の妥当な認識を有する。
証明 人間精神はもろもろの観念を〜〜それによって精神が自分自身(この部の定理二三により)、および自分の身体(この部の定理一九により)、ならびに外部の物体(この部の定理一六の系(1)および定理一七により)を現実に存在するものとして知覚するもろもろの観念を有する(この部の定理二二により)したがって人間精神は(この部の定理四五および四六により)神の永遠・無限なる本質の妥当な認識を有する。Q・E・D・
備考 これによって神の無限なる本質ならびにその永遠性はすべての人に認識されることが分かる。ところで、ありとあらゆるものは神の中に在りかつ神によって考えられるのであるから、この結果として、我々はこの神の認識からきわめて多くの妥当な認識を導き出し、このようにしてかの第三種の認識を形成しうる、ということになる。第三種の認識について我々はこの部の定理四〇の備考二の中で述べたが、その価値と効用についてはさらに第五部で述べるであろう。
しかし人間が神については共通概念によってほど明瞭な認識を有しないのはなぜかといえば、それは人間が神を物体のように表象することができないということ、また人間が神という名前を自分らの通常見慣れている諸物の表象像に結合してきたということによる。これは人間が絶えず外部の物体から刺激されている関係上ほとんど避けがたい事柄である。
実際大抵の誤謬は、単に次の点にのみ、すなわち我々が物を正しい名前で呼ばないという点にのみ存する。例えばある人が、円の中心から円周に向かって引かれた諸線は等しくないと言うなら、たしかにその人は、少なくともその瞬間には、円を数学家たちと異なって解しているのである。同様に、人々が計算において誤る場合も、彼らは精神の中においては紙上におけるのと異なった数を有しているのである。だからもし彼らの精神を見ることができるとしたら、彼らは誤っているとは言えない。それにもかかわらず彼らが誤っているように見えるのは、彼らが精神の中においても紙上におけるのと同じ数を有すると我々が思うからである。もしそう思わなかったとしたら、我々は彼らが誤っているとは信じないであろう。現に私はこのあいだある人が「うちの座敷が隣りの鶏へ飛び込んだ」と叫ぶのを聞いたが、〈(彼の言葉は不条理であったけれども)、〉彼の精神が私には十分よくのみこめたので、彼が誤っているとは信じなかった。世の大抵の論争も、人々が自分の精神を正しく表現しないか、それとも相手の精神を誤って解釈しているかから起こる。というのは、彼らは最も激しく対立している場合でも、実はまったく同じことを考えているか、そうでなければまるで異なる主題について考えているかであり、したがってたがいに相手のせいにしている誤謬あるいは不条理が本当は存在していないことが多いのである。
定理四八 精神の中には絶対的な意志、すなわち自由な意志は存しない。むしろ精神はこのことまたはかのことを意志するように原因によって決定され、この原因も同様に他の原因によって決定され、さらにこの後者もまた他の原因によって決定され、このようにして無限に進む。
証明 精神は思惟のある一定の様態であり(この部の定理一一により)、したがって(第一部定理一七の系二により)自己の活動の自由原因でありえない、あるいは意志したり意志しなかったりする絶対的な能力を有しえない。むしろ精神はこのことあるいはかのことを意志するように原因によって決定されなければならぬ。そしてこの原因も同様に他の原因によって決定され、さらにこの後者もまた他の原因によって決定され云々(第一部定理二八により)。Q・E・D・
備考 精神の中に認識し・欲求し・愛しなどする絶対的な能力が存しないこともこれと同一の仕方で証明される。この帰結として、これらならびにこれと類似の能力は純然たる想像物であるか、そうでなければ形而上学的有、すなわち我々が個々のものから形成するのを常とする一般的概念にほかならないということになる。したがって、知性がこのあるいはかの観念に対し・意志がこのあるいはかの意志作用に対する関係は、石なるもの一般がこのあるいはかの石に対し・人間なるもの一般がペテロあるいはパウロに対する関係と同様である。なお、何ゆえに人間が自分を自由であると思うかの理由は第一部の付録の中で説明した。
だが先へ進む前に、ここで注意しなければならないのは、私が意志を欲望とは解せずに、肯定し・否定する能力と解することである。つまり私は意志を、真なるものを肯定し・偽なるものを否定する精神の能力と解し、精神をして事物を追求あるいは忌避させる欲望とは解しないのである。しかし我々が、これらの能力は一般的概念であってそれは個々のものから形成され実は個々のものと区別されないものであるということを証明したので、今度は、その個々の意志作用が事物の観念そのもの以外のある物であるかどうかを探求しなければならぬ。つまり精神の中には観念が観念である限りにおいて含む肯定ないし否定以外になお他の肯定ないし否定が存するかどうかを探求しなければならぬ。観念が観念である限りにおいて肯定ないし否定を含むことについては次の定理ならびにこの部の定義三を参照して欲しい、そして思惟を絵画に堕さしめないようにしてもらいたい。なぜなら私は、観念を、眼底に形成される〜〜脳の中央に形成される、と言いたければ言ってもよい〜〜表象像とは解せずに、思惟の概念〈あるいは単に思惟の中に存する限りにおける事物の想念的有(エッセ・オブエクティヴム)〉と解するからである。
定理四九 精神の中には観念が観念である限りにおいて含む以外のいかなる意志作用も、すなわちいかなる肯定ないし否定も存しない。
証明 精神の中には(前定理により)意志したり意志しなかったりする絶対的能力がなく、単に個々の意志作用、すなわちこのあるいはかの肯定、ないしこのあるいはかの否定、があるのみである。そこで今ここにある一個の意志作用を、〜〜例えば三角形の三つの角の和が二直角に等しいことを精神に肯定させる思惟様態を、考えよう。この肯定は三角形の概念あるいは観念を含んでいる。言いかえればそれは三角形の観念なしには考えられることができない。なぜならAはBの概念を含まなければならぬというのとAはBなしに考えられることができないというのとは同じことだからである。次にこの肯定は(この部の公理三により)三角形の観念なしには在ることもできない。ゆえにこの肯定は三角形の観念なしには在ることも考えられることもできないのである。さらにまた三角形のこの観念はこの同じ肯定を、すなわちその三つの角の和は二直角に等しいということを、含まなければならぬ。ゆえにまた逆に三角形のこの観念は、この肯定なしには在ることも考えられることもできないのである。したがって(この部の定義二により)この肯定は三角形の観念の本質に属し、結局三角形の観念そのものにほかならない。そして我々がこの意志作用について述べたことは(我々はそれを任意に選び採ったのであるから)すべての意志作用についても言われうる。すなわちすべての意志作用は観念そのものにほかならない。Q・E・D・
系 意志と知性とは同一である。
証明 意志は個々の意志作用そのものにほかならぬし、知性は個々の観念そのものにほかならぬ(この部の定理四八およびその備考により)。ところが個々の意志作用と個々の観念とは(前定理により)同一である。ゆえに意志と知性とは同一である。Q・E・D・
備考 これでもって我々は通常誤謬の原因とされているものを取り除いた。ところでさきに我々の示したところによれば、虚偽〔誤謬〕とは単に毀損(きそん)し混乱した観念の含む欠乏にのみ存するのである。ゆえに偽なる観念は偽である限りにおいて確実性を含まない。だからある人間が偽なる観念に安んじて少しもそれについて疑わぬと我々が言う場合、それは彼がそれについて確実であるというのではなくて、単にそれについて疑わぬというだけのことである。あるいは彼の表象を動揺させる原因(言いかえれば彼にそれを疑わせる原因)が少しも存在しないから彼はその偽なる観念に安んじているというだけのことである。これについてはこの部の定理四四の備考を見よ。したがってある人間が偽なる観念にどこまでも固執する(そして誰も彼にそれを疑わせることができない)と仮定しても、我々は彼がそれについて確実であるとは決して言わぬであろう。なぜなら我々は確実性をある積極的なものと解し(この部の定理四三およびその備考を見よ)、疑惑の欠乏とは解しないからである。これに反して我々は確実性の欠乏を虚偽と解する。
しかし前定理をいっそう詳しく説明するため
に二、三の注意すべきことが残っている。なおまた、我々のこの説に対してなされうるもろもろの反対論に答えることが残っている。最後に、すべての疑惑を除去するため、この説の二、三の効用を指摘することを徒労ではないと私は考えた。二、三の、と私は言う。なぜなら、主要な効用は、第五部で述べることからいっそうよく理解されるであろうからである。
そこで第一の点から始めるとして、私は読者に、観念あるいは精神の概念と、我々が表象する事物の表象像とを、正確に区別すべきことを注意する。それから観念と、我々が事物を表現する言葉とを、区別することが必要である。なぜなら、この三者すなわち表象像、言葉、観念を多くの人々がまったく混同しているか、そうでなければ十分正確に区別していないか、あるいはまた十分慎重に区別していないかのために、意志に関するこの説は、思索のためにも、(学問のためにも、)賢明な生活法樹立のためにも、ぜひ知らなくてはならぬことであるにもかかわらず、まるで彼らに知られていなかったのである。実に彼らは、観念を、物体との接触によって我々の中に形成される表象像であると思っているがゆえに、(我々の脳髄に何の痕跡も印しえない事物、すなわち)我々がそれについて何ら類似の表象像を形成しえない事物、の観念は、実は観念でなく、我々が自由意志によって勝手に造り出す想像物にすぎないと信じ込んでいる。だから彼らは観念をあたかも画板の上の無言の絵のごとくに見ているのである。そしてこの偏見に捉われて彼らは、観念は観念である限りにおいて肯定ないし否定を含んでいるということに気づかないのである。次に言葉を、観念あるいは観念が含む肯定と混同する人々は、自分が感覚するのと反対のことを単なる言葉だけで肯定ないし否定するたびに自分は自分の感覚するのと反対のことを意志することができると信ずるのである。
しかし延長の概念を全然含まない思惟の本性に注意する人は、これらの偏見から容易に脱することができるであろう。そして彼はこのようにして、観念が(観念は思惟の様態であるがゆえに)物の表象像や言葉に存しないことを明瞭に理解するであろう。なぜなら、言葉および表象像の本質は思惟の概念を全然含まない単なる身体的運動に基づくものだからである。
これらのことについては以上二、三の注意で十分であろう。だから私は前に予告したもろもろの反対論に移る。
反対論の第一は、人々が、意志は知性より広きにわたること、したがって知性と異なっていることを確定事項と思っていることにある。ところで彼らが意志を知性よりも広きにわたると思っている理由は次のごときものである。彼らはこう主張する。経験によれば、我々が今知覚していない無限に多くの事物に同意するためには我々が現に有するよりもより大なる同意能力あるいはより大なる肯定ないし否定の能力を要しないがより大なる認識能力を要する。ゆえに知性は有限であり意志は無限であってその点において意志と知性とは区別される、と。
第二に我々に対して次のような反対がなされうる。我々が我々の判断を控えて・我々の知覚する事物に同意しないようにすることができることは、経験の最も明瞭に教えるところであるように見える、このことは、何びとも物を知覚する限りにおいては誤ると言われないで、ただ彼がそれに同意しあるいは反対する限りにおいてのみ誤ると言われることからも確かめられる、例えば、翼ある馬を想像する人はだからといってまだ翼ある馬が存在することを容認するわけではない、言いかえれば彼はだからといってまだ誤っているわけではない、ただ彼が同時に、翼ある馬が存在することを容認する場合にはじめて誤るのである、ゆえに意志すなわち同意能力が自由であって認識能力と異なるということは経験の最も明瞭に教えるところであるように見える、と。
第三に次のような反対がなされうる。一の肯定が他の肯定よりもよりその実在性を含むとは思われない、言いかえれば我々は真なるものを真として肯定するにも偽なるものを真として肯定するより以上の能力を要するとは思われない、ところが(観念にあってはこれと事情が異なる、なぜなら〉我々は一の観念が他の観念よりもより多くの実在性ないし完全性を有することを認識する、すなわち一の対象が他の対象よりすやれていればいるほどその対象の観念もまた他の対象の観念よりそれだけ多く完全である、このことからもまた意志と知性との相違が明らかになるように見える、と。
第四に次のような反対がなされうる。もし人間が自由意志によって行動するのでないとしたら、彼がブリダンの驢馬のように平衡状態にある場合にはどんなことになるであろうか、彼は餓えと渇きのために死ぬであろうか、もしこのことを容認するなら、私は驢馬、もしくは人間の彫像を考えて現実の人間を考えていないように見えるであろう、これに反してもしこのことを否定するなら彼は自分自身を決定するであろう、したがって彼は自分の欲する所へ行き自分の欲することをなす能力を有することになる、と。
このほかおそらくなお他の反対がなされうるであろう。しかし私は各人の夢想しうるすべての場合を持ち出す義務がないから、ただ以上挙げた反対論にのみ答えることにしよう。しかもできるだけ簡単に。
第一の反対論に対して私はこう答える。もし彼らが知性を明瞭判然たる観念とのみ解するなら意志が知性より広きにわたることは私も容認する。しかし私は意志が知覚一般あるいは思惟能力一般より広きにわたることはこれを否定する。また何ゆえに意志する能力が感覚する能力に比して無限であると言われるべきかは私のまったく了解しえぬところである。なぜなら、我々が無限に多くのものを(と言っても一つずつ順次にである。無限に多くのものを同時に肯定することはできないから)同一の意志能力で肯定しうるように、我々はまた無限に多くの物体を(もちろん一つずつ順次に〈、そして同時にではなく、それは不可能だから〉)同一の感覚能力で感覚ないし知覚しうるからである。もし彼らが「我々の知覚しえない無限に多くのものが存在する」と主張するなら、私はそうしたものはいかなる思惟をもってしても、したがってまたいかなる意志能力をもってしても把握しえないと答えるであろう。しかし彼らは言う、「もし神が我々にそれらのものをも知覚させようと欲したとしたら、神は我々に、現に与えたよりもより大なる知覚能力を与えなければならなかったであろうが、より大なる意志能力は与える必要がなかったであろう」と。これはあたかも「もし神が我々に無限に多くの他のものを認識させようと欲したとしたら、その無限に多くのものを把握するには、神が現に与えたよりもより大なる知性を我々に与えることが必要であったろうが、実在に関するより一般的な〔より広汎な〕観念を与える必要はなかったであろう」と言うに等しい。なぜなら、我々の示したように、意志とはある一般的な有、あるいはすべての個々の意志作用(言いかえればすべての個々の意志作用に共通のもの)を説明するためのある観念、であるからである。だからもし彼らがすべての意志作用に共通的ないし一般的なこの観念を〈我々の精神の〉能力であると信じているのなら、この能力が知性の限界を越えて無限にわたることを彼らが主張するとしても、何の不思議もないのである。なぜなら、一般的なものは、一の個体にも、多数の個体にも、また無限に多くの個体にも、等しくあてはまるのであるから。 160
第二の反対論に対して私は、判断を控える自由な力が我々にあることを否定することをもって答えとする。なぜなら、「ある人が判断を控える」と我々が言う時、それは「彼が物を妥当に知覚しないことに自ら気づいている」と言うのにほかならないからである。ゆえに判断の差控えは実は知覚であって自由意志ではない。このことを明瞭に理解するため、我々は、ここに翼ある馬を表象してそのほか何ものも知覚しない一人の小児を考えよう。この表象は馬の存在を含んでいるし(この部の定理一七の系により)、また小児は馬の存在を排除する何ものも知覚しないのであるから、彼は必然的にその馬を現在するものとして観想するであろう。そして彼はその馬の存在について確実でないにしてもその存在について疑うことができないであろう。こうしたことを我我は日常夢の中で経験する。しかし夢見ている間自分の夢見ているものについて判断を控えたり自分が夢みているものを夢見ていないようにしたりする自由な力が自分にあると思う人はないであろうと私は信ずる。もっとも夢の中でも我々が判断を控えることは起こる。それはすなわち我我が夢見ていることを夢見る場合である。なおまた私は、何びとも知覚する限りにおいては誤っていないということを容認する、言いかえれば精神の表象はそれ自体で見れば何の誤謬も含まないということを容認する(この部の定理一七の備考を見よ)。しかし私は、人間が知覚する限りにおいて何ものも肯定していないということはこれを否定する。なぜなら、翼ある馬を知覚するとは馬について翼を肯定するというのと何の異なるところがあろうか。すなわちもし精神が翼ある馬のほか何ものも知覚しないとしたら精神はその馬を現在するものとして観想するであろう。そしてその馬の存在を疑う何の原因も、またそれについて不同意を表明する何の能力も有しないであろう。ただし翼ある馬の表象がその馬の存在を排除する観念と結合しているか、あるいは精神が自らの有する翼ある馬の観念は妥当でないことを知覚する場合はこの限りでない。その場合には精神はその馬の存在を必然的に否定するか、そうでなければその馬について必然的に疑うであろう。
これでもって私は第三の反対論にも答えたと信ずる。すなわち意志とはすべての観念に適用されるある一般的なもの、単にすべての観念における共通物〜〜肯定〜〜のみを表示するある一般的なもの、である。ゆえに、意志がこのように抽象的に考えられる限りにおいては、意志の妥当な本質は、すべての観念の中になければならず、かつこの点においてのみ意志の本質はすべての観念において同一である。(それはちょうど人間の定義がまったく同様に各個の人間に適用されなければならぬのと同じである。このようにして我々は意志が常にすべての観念において同一であることを認めうるのである。)しかし意志が観念の本質を構成すると見られる限りにおいてはそうでない。なぜならその限りにおいては個々の肯定は観念自身と同様相互に異なっているからである。例えば円の観念が含む肯定と三角形の観念が含む肯定とはあたかも円の観念と三角形の観念とが異なるのと同様に異なっているのである。さらにまた我々が真なるものを真として肯定するのに偽なるものを真として肯定するのと同等の思惟能力を要するということを私は絶対に否定する。なぜならこの二つの肯定は(その言葉をでなく)その精神を(のみ)見るならば、相互に、有が非有に対するのと同様の関係にあるからである。というのは観念の中には虚偽の形相を構成する積極的なものは何も存しないのだから(この部の定理三五とその備考およびこの部の定理四七の備考を見よ)。
ゆえに、一般的なものと個々のものとを混同したり理性の有ないし抽象的有と実在的有とを混同したりする時に我々はいかに誤謬に陥りやすいかをここで特に注意しておかなければならぬ。
最後に第四の反対論に関しては、そのような平衡状態に置かれた人間(すなわち餓えと渇き、ならびに自分から等距離にあるそうした食物と飲料のほか何ものも知覚しない人間)が餓えと渇きのため死ぬであろうことを私はまったく容認する。もし反対者たちが、そうした人間は人間よりもむしろ驢馬と見るべきではないかと私に問うなら、自ら溢死する人間を何と見るべきか、また小児、愚者、狂人などを何と見るべきかを知らぬようにそれを知らぬと私は答える。
終りに、この説の知識が実生活のためにいかに有用であるかを指摘することが残っている。このことは次のことどもから容易に看取しうるであろう、すなわち〜〜
一 この説は、我々が神の命令のみによって行動し・神の本性を分有する者であること、そして我々の行動がより完全でありかつ我々がより多く神を認識するにつれていっそうそうなのであることを教えてくれる。ゆえにこの説は、心情をまったく安らかにしてくれることのほか、さらに、我々の最高の幸福ないし至福がどこに存するかを我々に教えてくれるという効果をもつ。すなわち我々の最高の幸福ないし至福は神に対する認識にのみ存するのであり、我々はこの認識によって、愛と道義心の命ずることのみをなすように導かれる。これからして〜〜徳そのもの、神への奉仕そのものがとりもなおさず幸福であり・最高の自由であることを知らずに、徳と善行を最も困難な奉仕とし、これに対して神から最高の報酬をもって表彰されようと期待する人々は、徳の真の評価からどんなに遠ざかっているかを、我々は明瞭に理解するのである。 163
二 この説は、運命に関する事柄あるいは我々の力の中にない事柄に対して、言いかえれば、我々の本性から生じない事柄に対して、どんな態度を我々がとらなければならぬかを教えてくれる。すなわち我々は運命の両面を平然と待ちもうけ、かつこれに耐えなければならぬのである。三角形の本質からその三つの角の和が二直角に等しいことが生ずるのと同一の必然性をもって、一切のことは神の永遠なる決定から生ずるからである。
三 この説は共同生活のために寄与する。なぜならこの説は、何びとをも憎まず、蔑(さげす)まず、嘲らず、何びとをも怒らず、嫉(ねた)まぬことを教えてくれるし、その上また、各人が自分の有するもので満足すべきこと、そして隣人に対しては女性的同情、偏頗心ないし迷信からでなく、理性の導きのみによって、すなわち私が第四部で示すだろうように時と事情が要求するところに従って、援助すべきことを教えてくれるからである。
四 最後にこの説は国家社会のためにも少なからず貢献する。なぜならこの説は、人民をいかなる仕方で統治し指導すべきかを、すなわち人民を奴隷的に服従させるようにでなく自由な動機から最善を行なわせるように統治し指導すべきことを教えてくれるからである。(国家) 164
以上をもって私はこの備考で取り扱おうと企てたことを果した。これで私はこの第二部を終えることにする。私の信ずるところによれば、私は、この第二部で、人間精神の本性とその諸特質とを十分詳細にかつ事情の困難が許す限り明瞭に説明し、そしてもろもろの事柄を、〜〜それから多くのすやれたこと・きわめて有用なこと・ぜひ知らなければならぬことが導き出されうる(そのことは一部分は次の部から明らかになるであろう)ようなもろもろの事柄を、述べたのであった。
第二部 終り
序言、
定義、一、二、三、要請、一、二
定理、
一、二、三、四、五、六、七、八、九、一〇、一一、一二、一三、一四、一五、一六、一七、一八、備考1、2、一九、二〇、
二一、二二、二三、二四、二五、二六、二七、二八、二九、三〇、三一、三二、三三、三四、三五、三六、三七、三八、三九、備考、四〇、
四一、四二、四三、四四、四五、四六、四七、四八、四九、五〇、五一、五二、五三、五四、五五、五六、五七、五八、五九
付録:感情の諸定義、
一、二、三、四、五、六、七、八、九、一〇、一一、一二、一三、一四、一五、一六、一七、一八、一九、二〇、
二一、二二、二三、二四、二五、二六、二七、二八、二九、三〇、三一、三二、三三、三四、三五、三六、三七、三八、三九、四〇、
四一、四二、四三、四四、四五、四六、四七、四八、感情の総括的定義、第三部TOP、TOP☆
感情の起源および本性について
序 言
感情ならびに人間の生活法について記述した大抵の人々は、共通した自然の法則に従う自然物について論じているのではなくて、自然の外にある物について論じているように見える。実に彼らは自然の中の人間を国家の中の国家のごとく考えているように思われる。なぜなら彼らは、人間が自然の秩序に従うよりもむしろこれを乱し、また人間が自己の行動に対して絶対の能力を有して自分自身以外の何ものからも決定されない、と信じているからである。それから彼らは、人間の無能力および無常の原因を、共通の自然力には帰さないで、人間本性の欠陥〜〜どんな欠陥のことか私は知らない〜〜に帰している。だから彼らは、こうした人間本性を泣き・笑い・侮蔑し・あるいは〜〜これが最もしばしば起こることであるが〜〜呪詛(じゅそ)する。そして人間精神の無能力をより雄弁にあるいはより尖鋭に非難することを心得ている人は神のように思われている。 165
とはいえまた、正しい生活法について多くのすぐれたことを書いて、思慮に充ちた勧告を人間に与えた卓越せる人々もないではなかった(我々は彼らの労作と勤勉とに負うところが多いことを告白する)。しかし感情の本性と力について、また他面精神が感情の制御に関して何をなしうるかについては、私の知る限り、まだ何びとも規定するところがなかった。もちろん私は有名なデカルトのなしたことを知っている。デカルトはやはり精神がその活動に対して絶対の能力を有すると信じていたものの、それでも人間の感情をその第一原因から説明しようとし、同時に、精神が感情に対して絶対の支配権を有しうる道程を示そうとつとめたのであった。しかし彼は、少なくとも私の判断によれば、彼の偉大な才能の鋭利さを示したにとどまっている。このことについては適当な場所で論証するであろう。なぜなら今私は前に戻って、人間の感情および行動を理解するよりもむしろ呪詛し・嘲笑しようとする人々へ立ち向かおうと思うのであるから。これらの人々にとっては、私が人間の欠陥や愚行を幾何学的方法で取り扱おうと企てること、また理性に反した空虚な、不条理な、厭(いと)うべきものとして彼らの罵る事柄を厳密な推論で証明しようと欲することは、疑いもなく奇異に思えるであろう。しかし私の理由はこうである。自然の中には自然の過誤のせいにされうるようないかなる事も起こらない。なぜなら自然は常に同じであり、自然の力と活動能力はいたるところ同一であるからである。言いかえれば、万物が生起して一の形相から他の形相へ変化するもととなる自然の法則および規則はいたるところ常に同一であるからである。したがってすべての事物〜〜それがどんなものであっても〜〜の本性を認識する様式もやはり同一でなければならぬ。すなわちそれは自然の普遍的な法則および規則による認識でなければならぬ。このようなわけで憎しみ、怒り、ねたみなどの感情も、それ自体で考察すれば、その他の個物と同様に自然の必然性と力とから生ずるのである。したがってそれらの感情は、それが認識されるべき一定の原因を持ち、また他の事物〜〜単にそれを観想することそのことだけで我々に喜びを与えてくれるようなそうした他の事物〜〜の諸特質と等しく我々の認識に値する一定の特質を有しているのである。
そこで私は感情の本性と力、ならびに感情に対する精神の能力を、私がこれまでの部で神および精神について論じたのと同一の方法で論じ、人間の行動と衝動とを線・面および立体を研究する場合と同様にして考察するであろう。
定 義
一 ある原因の結果がその原因だけで明瞭判然と知覚されうる場合、私はこの原因を妥当な〔十全な〕原因と称する。これに反して、ある原因の結果がその原因だけでは理解されえない場合、私はその原因を非妥当な〔非十全な〕原因あるいは部分的原因と呼ぶ。
二 我々自らがその妥当な原因となっているようなある事が我々の内あるいは我々の外に起こる時、言いかえれば(前定義により)我々の本性のみによって明瞭判然と理解されうるようなある事が我々の本性から我々の内あるいは我々の外に起こる時、私は我々が働きをなす〔能動〕と言う。これに反して、我々が単にその部分的原因であるにすぎないようなある事が我々の内に起こりあるいは我々の本性から起こる時、私は我々が働きを受ける〔受動〕と言う。
三 感情とは我々の身体の活動能力を増大しあるいは減少し、促進しあるいは阻害する身体の変状〔刺激状態〕、また同時にそうした変状の観念であると解する。
そこでもし我々がそうした変状のどれかの妥当な原因でありうるなら、その時私は感情を能動と解し、そうでない場合は受動と解する。
要 請
一 人間身体はその活動能力を増大しあるいは減少するような多くの仕方で刺激(アフィキ)されることができるし、またその活動能力を増大も減少もしないような仕方で刺激(アフィキ)されることもできる。
この要請あるいは公理は第二部定理一三のあとにある要請一ならびに補助定理五と七に基づく。
二 人間身体は多くの変化を受けてしかもなお対象の印象あるいは痕跡を(これについては第二部要請五を見よ)、したがってまた事物の表象像を保持することができる。表象像の定義については第二部定理一七の備考を見よ。
定理一 我々の精神はある点において働きをなし、またある点において働きを受ける。すなわち精神は妥当な観念を有する限りにおいて必然的に働きをなし、また非妥当な観念を有する限りにおいて必然的に働きを受ける。
証明 おのおのの人間精神の中にある観念は一部は妥当なものであり一部は毀損し・混乱したものである(第二部定理四〇の備考(1or2)により)。ところがある物の精神の中で妥当であるような観念は、神がこの精神の本質を構成する限りにおいて神の中で妥当であり(第二部定理一一の系により)、一方、精神の中で非妥当である観念も同様に神の中で(同じ系により)妥当であるが、この場合は神が単にこの精神の本質だけではなく、同時に他の諸物の精神も自らの中に含む限りにおいてである。さらにまた与えられたおのおのの観念から必然的にある結果が生じなければならぬのであり(第一部定理三六により)、そしてこのような結果について神はその妥当な原因である(この部の定義一を見よ)。しかもそれは神が無限である限りにおいてではなく、この与えられた観念に変状したと見られる限りにおいてである(第二部定理九を見よ)。しかし神がある物の精神の中で妥当であるような観念に変状している限りにおいてある結果の原因となっているとすれば、同時にこの精神がまたこのような結果の妥当な原因である(第二部定理一一の系により)。ゆえに我々の精神は(この部の定義二により)妥当な観念を有する限りにおいて必然的に働きをなす。これが第一の点であった。次に単に一人の人間の精神だけではなくその人間の精神とともに他の諸物の精神も自らの中に有する限りにおいての神の中で、妥当である観念から必然的に生ずるすべてのもの、そうしたものについては(再び第二部定理一一の系により)この人間の精神はその妥当な原因ではなくて、単に部分的原因にすぎない。したがって(この部の定義二により)精神は非妥当な観念を有する限りにおいて必然的に働きを受ける。これが第二の点であった。ゆえに我々の精神は云々。Q・E・D・
系 この帰結として、精神は非妥当な観念をより多く有するに従ってそれだけ多く働きを受け、反対に、妥当な観念をより多く有するに従ってそれだけ多く働きをなすことになる。
定理二 身体が精神を思惟するように決定することはできないし、また精神が身体を運動ないし静止に、あるいは他のあること(もしそうしたものがあるならば)をするように決定することもできない。 170
証明 思惟のすべての様態は、神が思惟する物である限りにおいて神を原因とし、神が他の属性によって説明される限りにおいてはそうでない(第二部定理六により)。ゆえに精神を思惟に決定するものは思惟の様態であって延長の様態ではない、言いかえれば(第二部定義一により)身体ではない。これが第一の点であった。次に、身体の運動ないし静止は必ず他の物体から生じ、この物体がまた他の物体から運動ないし静止に決定されなければならぬ。一般的に言えば、身体の中に生ずるすべてのことは、思惟のある様態に変状したと見られる限りにおける神からではなく、延長のある様態に変状したと見られる限りにおける神から生じなければならぬ(再び第二部定理六により)。言いかえれば、それは思惟の様態である精神(第二部定理一一により)から生ずることができない。これが第二の点であった。ゆえに身体が精神を云々。Q・E・D・
備考 このことは第二部定理七の備考で述べたことからいっそう明瞭に理解される。それによれば、精神と身体とは同一物であってそれが時には思惟の属性のもとで、時には延長の属性のもとで考えられるまでなのである。この結果として、物の秩序ないし連結は、自然がこの属性のもとで考えられようとかの属性のもとで考えられようとただ一つだけであり、したがって我々の身体の能動ならびに受動の秩序は、本性上、精神の能動ならびに受動の秩序と同時であるということになる。このことはまた我々が第二部定理一二を証明した仕方からも明らかになる。
事情はかくのごとくであってこれについてはもはや何ら疑う理由が残っていないにもかかわらず、もしこのことを私が経験によって確証しない限りは、人々にこれを冷静に熟慮するようにさせることはまずできない相談であろう。それほどまでに根強く彼らはこう思い込んでいる〜〜身体は精神の命令だけであるいは運動しあるいは静止し、そして彼らの行動の多くは単に精神の意志と思考の技能にのみ依存している、と。これというのも、身体が何をなしうるかをこれまでまだ誰も規定しなかったからである。言いかえれば、身体が、単に物体的と見られる限りにおける自然の法則のみによって何をなしうるか、また精神から決定されなくては何をなしえないかを、これまで誰も経験によって確定しなかったからである。
実際、今日まで、誰も身体の機能のすべてを説明しうるほど正確には身体の組織を知らなかった。人間の知恵をはるかに凌駕する多くのことが動物において認められることや、夢遊病者が覚醒時にはとてもしないような多くのことを睡眠中になしていること(これは、身体が単に自己の本性の法則のみによって、自分の精神を驚かすような多くのことをなしうることを十分に示している)について説明できないのは言うまでもない。次にどのような仕方、どのような媒介で精神が身体を動かすか、またどのような程度の運動を身体に与えうるか、またどのような速度で身体を動かしうるかを誰も知らない。こうした点から見れば、人々が身体のこのあるいはかの活動は身体の支配者である精神から来ていると言う時、彼らは実は自らの言っていることを理解していないのである。そして彼らがその活動の真の原因を知らず、しかもそれを何ら怪しんでいないということを体裁のよい言葉で告白しているのに異ならないのである。
しかし彼らは言うであろう。どのような媒介で精神が身体を動かすかを知っていようと知っていまいと、人間精神が思考に適しない場合は身体が不活発であることを自分らは経験する、と。また言うであろう。話すことや沈黙すること、その他多くのことが単に精神の力の中にのみあることを自分らは経験する、だからそうしたことは精神の決意に依存すると信ずる、と。 172
だが第一の点に関して私は彼らにこう尋ねる。経験はまた逆に、身体が不清澄な場合には同時に精神が思惟に適しないことも教えはしないか、と。なぜなら、身体が眠って静止している間は精神も同時に身体とともに無意識状態にとどまり、覚醒時のように思考する能力を有しないからである。さらにまた精神が同一対象について常に等しく思惟するのに適当しているわけでなく、むしろ身体がこのあるいはかの対象の表象像を自らの中に生み出すのに適当した度合に応じて精神もこのあるいはかの対象を考察するのに適当するということは誰しもみな経験しているところと信ずる。
しかし彼らは言うであろう。建築・絵画・その他人間の技能のみから生ずるこの種の事柄の原因を、単に物体的と見られる限りにおける自然の法則のみから導き出すことはできない、また人間身体は精神から決定され導かれるのでなくては寺院のごときものを構築することはできまい、と。しかし、私のすでに指摘したように、彼らは、身体が何をなしうるかまた身体の本性の単なる考察だけから何が導き出されうるかを全然知らないのであるし、また彼らは、精神の導きなしに起こりうるとは彼らの決して信じなかっただろうような多くのこと、例えば夢遊病者が睡眠中にしてあとで覚醒してから自分で驚くようなことが、単なる自然の法則のみによって生ずることを経験しているのである。なお私はここで、人間身体の構造そのものが人間の技能によって作り出されるすべてのものを技巧上はるかに凌駕していることを付言する。私がさきに述べたこと、すなわち自然がいかなる属性のもとで考察されようとも自然から無限に多くのものが生ずるということは、今は言わないとしても。
さらに第二の点に関しては、もし沈黙することも話すことも等しく人間の力の中にあるとしたら、たしかに人事はもっとうまくいっていたことであろう。しかし、経験は、人間にとって舌ほど抑えがたいものはなく、また自分の衝動を制御するほど困難なことはないことを十分以上に教えている。この結果として大抵の人々は、我々はただ軽度に欲求する事だけを自由になすと信じている。そうしたものへの衝動は我々の頭にしばしば浮かぶ他の事柄の想起によって容易に抑制されうるからである。これに反して、激しい感情をもって欲求する事柄に対してはそうはいかないと信じられている。このような感情は他の事柄の想起によっても鎮められえないからである。実際もし彼らが、人間はあとで後悔するような多くのことをなすものであり、また相反する感情に捉われる時は往々にしてより善きものを見ながらより悪しきものに従うものであるということを経験しなかったとしたら、彼らは人間が何もかも自由に行なうと信ずるのに躊躇しなかったであろう。 (善きもの〜、オヴィディウス) 173
このようにして、幼児は自由に乳を欲求すると信じ、怒った小児は自由に復讐を欲すると信じ、臆病者は自由に逃亡すると信ずる。次に酩酊者は、あとで酔いが醒めた時黙っていればよかったと思うようなことをその時は精神の自由な決意に従って話すと信ずる。同様に、狂人・おしゃべり女・小児その他この種の多くの者は、実は自分のもつ話したいという本能を抑ええないで話すのに、精神の自由決意から話すと信じている。これで見れば、経験そのものも理性に劣らず明瞭に、人間は自分の行動を意識しているが自分をそれへ決定する原因は知らぬゆえに自分を自由だと信じているということを教えてくれる。それからまた精神の決意とは衝動そのものにほかならず、したがって精神の決意は身体の状態の異なるのに従って異なるということを教えてくれる。
各人は自分の感情に基づいて一切を律し、さらに相反する感情に捉われる者は自分が何を欲したらいいかを知らず、また何の感情にも捉われない者はわずかのはずみによってもこっちに動かされあっちに動かされするからである。
以上すべてからきわめて明瞭に次のことが分かる。それは精神の決意ないし衝動と身体の決定とは本性上同時に在り、あるいはむしろ一にして同一物なのであって、この同一物が思惟の属性のもとで見られ・思惟の属性によって説明される時、我々はこれを決意(デクレトウム)と呼び、延長の属性のもとで見られ・運動と静止の法則から導き出される時、我々はこれを決定(デテルミナテイオ)と呼ぶということである。
このことはなお、これから述べることからいっそう明瞭になるであろう。というのは、ここで私の特に注意したい別のことがある。それは、我々は想起しないことは決して精神の決意によってなしえないということである。例えば我々は想起しない言葉を話すことはできない。なおあることを想起したり・忘れたりすることは精神の自由にはならない。そこで人々は想起することについて任意に黙っていたり・話をしたりすることだけは精神の力の中に在ると信じている。しかし我々が話をする夢を見る場合、我々はやはり精神の自由な決意によっで話をすると信じており、しかも実は話をしていない、あるいは話をするとしてもそれは身体の自発的運動から生じているのである。次に我々はいろいろなことを人に隠すという夢を見る。しかも覚醒時に我々が知っていることを人に黙っているのと同じ精神の決意でそうしていると夢の中で思っている。最後に我我は、覚醒時にはとてもしないようないろいろなことを精神の自由な決意によってやってのけるという夢を見る。そこで私はぜひ知りたい、精神の中には二種の決意、すなわち空想的な決意と自由な決意とがあるのかどうかを。もしそんな無意味な結論に到達したくなければ、この自由であると信じられている精神の決意は、表象そのものあるいは想起そのものと区別されないのであって、それは観念が観念である限りにおいて必然的に含む肯定(第二部定理四九を見よ)にほかならないということを人々は必然的に承認しなくてはならぬ。
こんなわけで、精神のこうした決意は、現実に存在するもろもろの事物の観念が生ずるのと同一の必然性をもって精神の中に生ずる。だから精神の自由な決意で話をしたり・黙っていたりその他いろいろなことをなすと信ずる者は、目をあけながら夢を見ているのである。
定理三 精神の能動は妥当な観念のみから生じ、これに反して受動は非妥当な観念のみに依存する。
証明 精神の本質を構成する最初のものは、現実に存在する身体の観念にほかならない(第二部定理一一および一三により)。そしてこの観念は(第二部定理一五により)多くの観念から組織されていて、そのあるものは(第二部定理三八の系により)妥当であり、またあるものは非妥当である(第二部定理二九の系により)。ゆえにすべて精神の本性から生ずるもの、精神をその最近原因とし精神によって理解されなければならぬものは、必然的に妥当な観念あるいは非妥当な観念から生じなければならぬ。ところが精神は非妥当な観念を有する限りにおいて必然的に働きを受ける(この部の定理一により)。ゆえに精神の能動は妥当な観念のみから生じ、また精神は非妥当な観念を有するゆえにのみ働きを受ける。Q・E・D・
備考 そこで受動は、精神が否定を含むあるものを有する限りにおいてのみ、あるいは精神が他のものなしにそれ自身だけでは明瞭判然と知覚されないような自然の一部分として見られる限りにおいてのみ、精神に帰せられるということが分かる。なおこの仕方で私は、受動が精神に帰せられると同様他の個物にも帰せられること、また受動はこれ以外の他の仕方では説明されえないことを示しうるであろう。しかし私の意図するところは単に人間精神について論ずることにある〔のだから今はそれに立ち入らない〕。
定理四 いかなる物も、外部の原因によってでなくては滅ぼされることができない。
証明 この定理はそれ自体で明白である。なぜなら、おのおのの物の定義はその物の本質を肯定するが否定しない。あるいはその物の本質を定立するが除去しない。だから我々が単に物自身だけを眼中に置いて外部の諸原因を眼中に置かない間は、その物の中にそれを滅ぼしうるようないかなるものも我々は見いだしえないであろう。Q・E・D・
定理五 物は一が他を滅ぼしうる限りにおいて相反する本性を有する。言いかえればそうした物は同じ主体の中に在ることができない。
証明 なぜなら、もしそうした物が相互に一致しあるいは同じ主体の中に同時に在りうるとしたら、同じ主体の中にその主体自身を滅ぼしうる物が在りうることになるであろう。これは(前定理により)不条理である。ゆえに物は云々。Q・E・D・
定理六 おのおのの物は自己の及ぶかぎり自己の有に固執するように努める。
証明 なぜなら、個物は神の属性をある一定の仕方で表現する様態である(第一部定理二五の系により)、言いかえればそれは(第一部定理三四により 二四→×)神が存在し・活動する神の能力をある一定の仕方で表現する物である。その上いかなる物も自分が滅ぼされうるようなあるものを、あるいは自分の存在を除去するようなあるものを、自らの中に有していない(この部の定理四により)。むしろおのおのの物は自分の存在を除去しうるすべてのものに対抗する(前定理により)。
したがっておのおのの物はできるだけ、また自己の及ぶかぎり、自己の有に固執するように努力する。Q・E・D・
定理七 おのおのの物が自己の有に固執しようと努める努力はその物の現実的本質にほかならない。
証明 おのおのの物の与えられた本質から必然的にいろいろなことが生ずる(第一部定理三六により)。また物はその定まった本性から必然的に生ずること以外のいかなることをもなしえない(第一部定理二九により)。ゆえにおのおのの物が単独であるいは他の物とともにある事をなしあるいはなそうと努める能力ないし努力、言いかえれば(この部の定理六により)おのおのの物が自己の有に固執しようと努める能力ないし努力は、その物の与えられた本質すなわち現実的本質にほかならない。Q・E・D・
定理八 おのおのの物が自己の有に固執しようと努める努力は、限定された時間ではなく無限定な時間を含んでいる。
証明 なぜなら、もしこの努力が物の持続を決定する限定された時間を含むとしたら、その物が存在する能力そのものだけからして、その物がその限定された時間のあとには存在しえずして滅びなければならぬということが帰結されるであろう。ところがこれは(この部の定理四により)不条理である。ゆえに物を存在せしめる努力は何ら限定された時間を含まない。むしろ反対に、おのおのの物は外部の原因によって滅ぼされなければそれが現に存在している同じ能力をもって常に存在しつづけるのであるから(同じくこの部の定理四により)、したがってこの努力は無限定な時間を含んでいる。Q・E・D・
定理九 精神は明瞭判然たる観念を有する限りにおいても、混乱した観念を有する限りにおいても、ある無限定な持続の間、自己の有に固執しようと努め、かつこの自己の努力を意識している。
証明 精神の本質は妥当な観念ならびに非妥当な観念から構成されている(この部の定理三で証明したように)。したがって精神は(この部の定理七により)妥当な観念を有する限りにおいても非妥当な観念を有する限りにおいても自己の有に固執しようと努める。しかも(この部の定理八により)ある無限定な持続の間自己の有に固執しようと努める。ところで精神は(第二部定理二三により)身体の変状〔刺激状態〕の観念によって自己を意識するのであるから、したがって精神は(この部の定理七により)自己の努力を意識している。Q・E・D・
備考 この努力が精神だけに関係する時には意志と呼ばれ、それが同時に精神と身体とに関係する時には衝動と呼ばれる。したがって衝動とは人間の本質そのもの、〜〜自己の維持に役立つすべてのことがそれから必然的に出て来て結局人間にそれを行なわせるようにさせる人間の本質そのもの、にほかならない。次に衝動と欲望との相違はといえば、欲望は自らの衝動を意識している限りにおいてもっぱら人間について言われるというだけのことである。このゆえに欲望とは意識を伴った衝動であると定義することができる。このようにして、以上すべてから次のことが明らかになる。それは、我々はあるものを善と判断するがゆえにそのものへ努力し・意志し・衝動を感じ・欲望するのではなくて、反対に、あるものへ努力し・意志し・衝動を感じ・欲望するがゆえにそのものを善と判断する、ということである。
定理一〇 我々の身体の存在を排除する観念は我々の精神の中に存することができない。むしろそうした観念は我々の精神と相反するものである。 180
証明 すべて我々の身体を滅ぼしうるものは身体の中に存することができない(この部の定理五により)。したがってそうした物の観念は神が我々の身体の観念を有する限りにおいて神の中に在ることができない(第二部定理九の系により)。言いかえれば(第二部定理一一および一三により)そうした物の観念は我々の精神の中に在ることができない。むしろ反対に、精神の本質を構成する最初のものは現実に存在する身体の観念であるから(第二部定理一一および一三により)、我々の精神の最初にして最主要なものは、我々の身体の存在を肯定する努力である(この部の定理七により)。したがって我々の身体の存在を否定する観念は我々の精神と相反する、云々。Q・E・D・
定理一一 すべて我々の身体の活動能力を増大しあるいは減少し、促進しあるいは阻害するものの観念は、我々の精神の思惟能力を増大しあるいは減少し、促進しあるいは阻害する。
証明 この定理は第二部定理七から、あるいはまた第二部定理一四から明白である。
備考 そこで我々は、精神がもろもろの大なる変化を受けて時にはより大なる完全性へ、また時にはより小なる完全性へ移行しうることが分かる。この受動が我々に喜びおよび悲しみの感情を説明してくれる。こうして私は以下において喜びを精神がより大なる完全性へ移行する受動と解し、これに反して悲しみを精神がより小なる完全性へ移行する受動と解する。さらに私は精神と身体とに同時に関係する喜びの感情を快感あるいは快活と呼び、これに反して同様な関係における悲しみの感情を苦痛あるいは憂鬱と呼ぶ。しかし注意しなければならないのは、快感および苦痛ということが人間について言われるのは、その人間のある部分が他の部分より多く刺激されている場合であり、これに反して快活および憂鬱ということが言われるのは、その人間のすべての部分が一様に刺激されている場合であるということである。
次に欲望の何たるかはこの部の定理九の備考において説明した。
この三者〔喜び・悲しみ・欲望〕のほかには私は何ら他の基本的感情を認めない。なぜならその他の諸感情は、以下において示すだろうように、この三者から生ずるものだからである。
だがさきへ進む前に、いかにして観念が観念と相反するかをいっそう明瞭に理解するために、私はこの部の定理一〇をここでもっと詳しく説明したい。
第二部定理一七の備考において我々は、精神の本質を構成する観念は身体自身が存在する間だけ身体の存在を含むということを示した。次に、第二部定理八の系ならびにその備考において示したことから、我々の精神の現在的存在は精神が身体の現実的存在を含むことにのみ依存するということが分かる。最後に、精神が物を表象し・想起する能力も同様に精神が身体の現実的存在を含むことに依存するということを我々は示した(第二部定理一七および一八ならびにその備考を見よ)。以上の帰結として、精神の現在的存在およびその表象能力は、精神が身体の現在的存在を肯定することをやめるや否や消滅するということになる。しかし精神が身体のこの存在を肯定することをやめる原因は精神自身ではありえない(この部の定理四により)。だからといってこの原因は身体が存在することをやめることにも存しない。なぜなら(第二部定理六により)精神が身体の存在を肯定する原因は身体が存在することを始めたことには存しないのである以上、同じ理由からして、精神が身体の存在を肯定することをやめる原因もまた身体が存在することをやめることには存しないからである。このことはむしろ(第二部定理八により)我々の身体の現在的存在、したがってまた我々の精神の現在的存在、を排除するある他の観念から生ずるのである。だからそうした観念は我々の精神の本質を構成する観念と相反する。
定理一二 精神は身体の活動能力を増大しあるいは促進するものをできるだけ表象しようと努める。
証明 人間身体がある外部の物体の本性を含むような仕方で刺激されている間は、人間精神はその物体を現在するものとして観想するであろう(第二部定理一七により)。したがってまた(第二部定理七により)人間精神がある外部の物体を現在するものとして観想する間は、言いかえれば(第二部定理一七の備考により)それを表象する間は、人間身体はその外部の物体の本性を含むような仕方で刺激される。だから精神が我々の身体の活動能力を増大しあるいは促進するものを表象する間は、身体はその活動能力を増大しあるいは促進するような仕方で刺激される(この部の要請一を見よ)。したがってまた(この部の定理一一により)その間は、精神の思惟能力は増大しあるいは促進される。そのゆえに(この部の定理六または九により)精神はできるだけそうしたものを表象しようと努める。Q・E・D・
定理一三 精神は身体の活動能力を減少しあるいは阻害するものを表象する場合、そうした物の存在を排除する事物をできるだけ想起しようと努める。
証明 精神がそうしたものを表象する間は精神ならびに身体の能力は減少しあるいは阻害される(前定理において証明したように)。それにもかかわらず精神はそうしたものの現在的存在を排除する他の物を表象するようになるまではそうしたものを表象するであろう(第二部定理一七により)。言いかえれば(今しがた示したように)精神ならびに身体の能力は精神がそうしたものの存在を排除する他のものを表象するようになるまでは減少しあるいは阻害される。したがって精神は(この部の定理九により)できるだけこのものを表象しあるいは想起しようと努めるであろう。
Q・E・D・
系 この帰結として、精神は自己の能力ならびに身体の能力を減少しあるいは阻害するものを表象することを厭うということになる。
備考 これらのことによって我々は愛および憎しみの何たるかを明瞭に理解する。すなわち愛とは外部の原因の観念を伴った喜びにほかならないし、また憎しみとは外部の原因の観念を伴った悲しみにほかならない。なおまた、愛する者は必然的に、その愛する対象を現実に所有しかつ維持しようと努め、これに反して憎む者はその憎む対象を遠ざけかつ滅ぼそうと努めることを我我は知る。しかしこれらすべてについては、以下においていっそう詳しく述べるであろう。
定理一四 もし精神がかつて同時に二つの感情に刺激されたとしたら、精神はあとでその中の一つに刺激される場合、他の一つにも刺激されるであろう。
証明 もし人間身体がかつて同時に二つの物体から刺激されたとしたら、精神はあとでその中の一つを表象する場合、ただちに他の一つをも想起するであろう(第二部定理一八により)。ところが精神の表象は、外部の物体の本性よりも我々の身体の感情をより多く示している(第二部定理一六の系二により)。ゆえにもし身体、したがってまた精神は(この部の定義三を見よ)かつて二つの感情に刺激されたとしたら、あとでその中の一つに刺激される場合他の一つにも刺激されるであろう。Q・E・D・
定理一五 おのおのの物は偶然によって喜び・悲しみあるいは欲望の原因となりうる。
証明 精神が同時に二つの感情に、すなわち一つは精神の活動能力を増大も減少もしないもの、他の一つはそれを増大あるいは減少するものに刺激されると仮定しよう(この部の要請一見よ)。
前定理から次のことが明白である。すなわち精神があとでそれ自体では精神の思惟能力を増大も減少もしない(仮定により)第一の感情の真の原因によってその第一の感情に刺激される場合、精神はただちに、自己の思惟能力を増大しあるいは減少する第二の感情に、言いかえれば(この部の定理一一の備考により)喜びあるいは悲しみに、刺激されるであろう。したがってかの〔第一の感情の原因となった〕物はそれ自体によってではなく偶然によって喜びあるいは悲しみの原因となるであろう。またこの同じ経路でそうした物が偶然によって欲望の原因となりうることを容易に示すことができる。Q・E・D・
系 我々は、ある物を喜びあるいは悲しみの感情をもって観想したということだけからして、その物自身がそうした感情の起成原因でないのにその物を愛しあるいは憎むことができる。
証明 なぜなら、このことだけからして(この部の定理一四により)、精神はあとでこの物を表象する時喜びあるいは悲しみの感情に刺激されるということになる、言いかえれば(この部の定理一一の備考により)精神ならびに身体の能力が増大あるいは減少させられるなどなどのことになる。したがってまた(この部の定理一二により)精神がその物を表象することを好みあるいは(この部の定理一三の系により)厭うことになる、言いかえれば(この部の定理一三の備考により)精神はその物を愛し、あるいは憎むことになる。Q・E・D・
備考 これによって我々は、その原因を知らずにただいわゆる同感〔先入的好感〕および反感だけからある物を愛したり憎んだりするということがどうして起こりうるかを理解する。我々を喜びあるいは悲しみの感情に刺激するのを常とする対象に多少類似しているという理由だけで、我我を喜びあるいは悲しみに刺激するような対象(これについては次の定理で示すであろう)もまたこうしたものの中に入れられる。
この同感および反感という語を最初に採用した著作家たちがそれでもって事物の中に隠れているある性質を表わそうと欲したことは私ももちろん知っている。しかしそれにもかかわらず我々はこれらの語をよく知られたあるいは明白な特質を表わすものと解して差しつかえないと信ずる。
定理一六 ある物が、精神を喜びあるいは悲しみに刺激するのを常とする対象に多少類似すると我々が表象するというだけのことからして、その物がその対象と類似する点がそうした感情の起成原因〔直接原因〕でなくても、我々はその物を愛しあるいは憎むであろう。
証明 その物がその対象に類似する点を我々は対象自身において(仮定により)喜びあるいは悲しみの感情をもって観想した。したがって(この部の定理一四により)精神はこの類似点の表象像によって刺激される場合ただちに喜びあるいは悲しみの感情にも刺激されるであろう。したがってまたこの類似点をもつと我々が知覚する物は、偶然によって喜びあるいは悲しみの原因となるであろう(この部の定理一五により)。そこで(前の系により)その物が対象に類似する点がそうした感情の起成原因〔直接原因〕でなくても、我々はやはりその物を愛しあるいは憎むであろう。Q・E・D・
定理一七 我々を悲しみの感情に刺激するのを常とする物が、等しい大いさの喜びの感情に我々を刺激するのを常とする他の物と多少類似することを我々が表象する場合、我々はその物を憎みかつ同時に愛するであろう。
証明 なぜなら(仮定により)この物はそれ自体によって悲しみの原因である。そして我々が(この部の定理一三の備考により)この物を悲しみの感情をもって表象する限り我々はそれを憎む。さらにまたそれが我々を等しい大いさの喜びの感情に刺激するのを常とする他の物に多少類似することを我々が表象する限り、我々はそれを等しい大いさの喜びの緊張をもって愛するであろう(前定理により)。したがって我々はそれを憎みかつ同時に愛するであろう。Q・E・D・
備考 二つの相反する感情から生ずるこの精神状態は心情の動揺と呼ばれる。したがってその感情に対する関係は、疑惑の表象に対する関係と同様である(第二部定理四四の備考を見よ)。そして心情の動揺と疑惑との相違は、ただその度合の強弱という点にのみ存するのである。しかしここに注意しなければならぬのは〜〜私は前定理においてこの心情の動揺を、それ自身によってある感情の原因であり・偶然によって他の感情の原因であるような原因から導き出したが、それはそうした方がこの動揺をより容易に前の諸定理から導き出しうるからであって、何も心情の動揺が、多くの場合、二つの感情の起成原因〔直接原因〕であるような一対象から生ずることを否定しているわけではないということである。なぜなら、人間身体は(第二部要請一により)本性を異にするきわめて多くの個体から組織されており、したがって(第二部定理一三のあとにある補助定理三のあとの公理一により)人間身体は同一物体からきわめて多くの異なった仕方で刺激されることができる。また逆に、同一事物が多くの仕方で刺激されうるからには、同一事物がまた多くの異なった仕方で人間身体の同一部分を刺激することができるであろう。すなわちこれらのことからして我々は同一対象が多くのかつ相反する感情の原因となりうることを容易に理解することができるのである。
定理一八 人間は過去あるいは未来の物の表象像によって、現在の物の表象像によるのと同様の喜びおよび悲しみの感情に刺激される。
証明 人間はある物の表象像に刺激されている間は、たとえその物が存在していなくとも、それを現在するものとして観想するであろう(第二部定理一七およびその系により)、そしてその物の表象像が過去あるいは未来の時間の表象像と結合する限りにおいてでなくては、それを過去あるいは未来のものとして表象しない(第二部定理四四の備考を見よ)。だから物の表象像は、単にそれ自体において見れば、それが未来ないし過去の時間に関係したものであろうと現在に関係したものであろうと同じである。言いかえれば(第二部定理一六の系二により)身体の状態(コンスティトゥティオ)あるいは感情(アフェクトゥス)は表象像が過去あるいは未来の物に関するものであろうと現在の物に関するものであろうと同じである。したがって喜びおよび悲しみの感情は表象像が過去あるいは未来の物に関するものであろうと現在の物に関するものであろうと同じである。Q・E・D・
備考一 私がここで物を過去のものとか未来のものとか呼ぶのは、我々がその物によって刺激されたかあるいは刺激されるであろう限りにおいてである。例えば我々がある物を見たかあるいは見るであろう、ある物が我々を活気づけたかあるいは活気づけるであろう、ある物が我々を害したかあるいは害するであろう……などなどの限りにおいて、私はその物を過去のものあるいは未来のものと呼ぶのである。なぜなら、物をそのようなふうに表象する限りにおいて、我々はその物の存在を肯定している。言いかえれば身体はその物の存在を排除するいかなる感情にも刺激されない。したがって(第二部定理一七により)身体はその物の表象像によってあたかもその物自身が現在したであろう場合と同じ仕方で刺激される。ではあるがしかし、数々の経験をもつ人々は、物を未来あるいは過去のものとして観想する間は、大抵動揺して、その物の結果について多くは疑惑を有するから(第二部定理四四の備考を見よ)、したがって事物のこの種の表象像から生ずる感情はさほど確乎たるものでなく、人々がその物の結果について確実になるまでは、しばしば他の事物の表象像によって乱されることになる。
備考二 今しがた述べたことどもから、我々は希望、恐怖、安堵、絶望、歓喜および落胆の何たるかを理解する。すなわち希望とは我々がその結果について疑っている未来または過去の物の表象像から生ずる不確かな喜びにほかならない。これに反して恐怖とは同様に疑わしい物の表象像から生ずる不確かな悲しみである。さらにもしこれらの感情から疑惑が除去されれば希望は安堵となり、恐怖は絶望となる。すなわちそれは我々が希望しまたは恐怖していた物の表象像から生ずる喜びまたは悲しみである。次に歓喜とは我々がその結果について疑っていた過去の物の表象像から生ずる喜びである。最後に落胆とは歓喜に対立する悲しみである。
定理一九 自分の愛するものが破壊されることを表象する人は悲しみを感ずるであろう。これに反して自分の愛するものが鮭持されることを表象する人は喜びを感ずるであろう。
証明 精神は身体の活動能力を増大しあるいは促進するものを(この部の定理一二により)、言いかえれば(この部の定理一三の備考により)自分の愛するものを、できるだけ表象しようと努める。ところが表象力は物の存在を定立するものによって促進され、また反対に物の存在を排除するものによって阻害される(第二部定理一七により)。ゆえに愛するものの存在を定立する事物の表象像は、愛するものを表象しようと努める精神の努力を促進する、言いかえれば(この部の定理一一の備考により)精神を喜びに刺激する。これに反して愛するものの存在を排除する事物の表象像は、精神のこの努力を阻害する、言いかえれば(同じ備考により)精神を悲しみに刺激する。
ゆえに自分の愛するものが破壊されることを表象する人は悲しみを感ずるであろう、云々。Q・E・D・
定理二〇 自分の憎むものが破壊されることを表象する人は喜びを感ずるであろう。
証明 精神は(この部の定理一三により)身体の活動能力を減少しあるいは阻害する事物の存在を排除するようなものを表象しようと努める、言いかえれば精神は(同じ定理の備考により)自分の憎むものの存在を排除するようなものを表象しようと努める。したがって精神の憎むものの存在を排除するような物の表象像は精神のこの努力を促進する、言いかえればそれは(この部の定理一一の備考により)精神を喜びに刺激する。ゆえに自分の憎むものが破壊されることを表象する人は喜びを感ずるであろう。Q・E・D・
定理二一 自分の愛するものが喜びあるいは悲しみに刺激されることを表象する人は、同様に喜びあるいは悲しみに刺激されるであろう。しかもこの両感情が愛されている対象においてより大でありあるいはより小であるのに応じて、この両感情は愛する当人においてもより大でありあるいはより小であるであろう。
証明 愛されているものの存在を定立する事物の表象像は(この部の定理一九で証明したように)、愛されているものを表象しようと努める精神の努力を促進する。ところが喜びは、喜ぶものの存在を定立し、しかも喜びの感情がより大なるに従ってそれだけ多く定立する。なぜなら喜びは(この部の定理一一の備考により)より大なる完全性への移行だからである。ゆえに愛する当人における愛されている対象の喜びの表象像は、愛する当人の精神の努力を促進する、言いかえれば(この部の定理一一の備考により)愛する当人を喜びに刺激する、しかも喜びの感情が愛されている対象においてより大であったのに従ってそれだけ大なる喜びに刺激する。これが第一の点であった。次に物は何らかの悲しみに刺激される限り破壊される、しかもより大なる悲しみに刺激されるに従ってそれだけ多く破壊される(同じくこの部の定理一一の備考)。したがって(この部の定理一九により)自分の愛するものが悲しみに刺激されること表象する人は同様に悲しみに刺激されるであろう、しかも悲しみの感情が愛されている対象においてより大であったのに従ってそれだけ大なる悲しみに刺激されるであろう。Q・E・D・
定理二二 ある人が我々の愛するものを喜びに刺激することを我々が表象するなら、我々はその人に対して愛に刺激されるであろう。これに反して、その人が我々の愛するものを悲しみに刺激することを我々が表象するならば、我々は反対にその人に対して憎しみに刺激されるであろう。
証明 我々の愛するものを喜びあるいは悲しみに刺激する人は、我々がそのこと(我々の愛するものがその事びあるいは悲しみに刺激されたこと)を表象する限り、我々を喜びあるいは悲しみに刺激する(前定理により)。ところがこの喜びあるいは悲しみは、仮定によれば、外部の原因の観念を伴って我々の中に在る。ゆえに(この部の定理一三の備考により)もしある人が我々の愛するものを喜びあるいは悲しみに刺激することを我々が表象するなら、我々はその人に対して愛あるいは憎しみに刺激されるであろう。Q・E・D・
備考 定理二一は憐憫の何たるかを我々に説明してくれる。我々はこれを他人の不幸から生ずる悲しみであると定義することができる。しかし他人の幸福から生ずる喜びがいかなる名前で呼ばれるべきかを私は知らない。さらに我々は他人に善をなした人に対する愛を好意と呼び、これに反して他人に悪をなした人に対する憎しみを憤慨と呼ぶであろう。最後に注意すべきことは、我々は我々の愛したものに憐憫を感ずる(定理二ーで示したように)だけでなく、また以前には我我が何の感情もいだいていなかったものに対しても、ただそのものが我々に類似する〔同類である〕と我々が判断すれば我々はこれに憐憫を感ずる(のちに示すだろうように)。したがって我々は自分と同類のものに善をなした人に対しても好意を感じ、また反対に自分と同類のものに不幸を与えた人に対しても憤慨を感ずるであろう。
定理二三 自分の憎むものが悲しみに刺激されることを表象する人は喜びを感ずるであろう。
これに反して自分の憎むものが喜びに刺激されることを表象すれば悲しみを感ずるであろう。そしてこの両感情は、その反対の感情が自分の憎むものにおいてより大でありあるいはより小であるのに応じて、より大であり、あるいはより小であるであろう。
証明 憎まれたものは悲しみに刺激される限りにおいて破壊される、しかもより大なる悲しみに刺激されるに従ってそれだけ多く破壊される(この部の定理一一の備考により)。ゆえに(この部の定理二〇により)自分の憎むものが悲しみに刺激されることを表象する人は反対に喜びに刺激されるであろう、しかも憎まれたものがより大なる悲しみに刺激されたことを表象するに従ってそれだけ大なる喜びに刺激されるであろう。これが第一の点であった。次に喜びは喜ぶものの存在を定立する(同じくこの部の定理一一の備考により)、しかもその喜びがより大であると考えられるに従ってそれだけ多く定立する。もし自分の憎むものが喜びに刺激されることをある人が表象するなら、この表象は(この部の定理一三により)その人良身の努力を阻害するであろう、言いかえれば(この部の定理一一の備考により)憎む人は悲しみに刺激されるであろう、云々。Q・E・D・
備考 この事びはあまり基礎の固いものでなく、また心情の葛藤を伴わないわけにはいかない。
なぜなら(まもなくこの部の定理二七で証明するだろうように)、人は自分と同類のものが悲しみの感情に刺激されることを表象する限り、悲しまざるをえないからである。また反対に自分と同類のものが喜びに刺激されることを表象すれば、喜ばざるをえない。しかしここで我々は、人があるものを憎んでいる場合のみを念頭に置いて言っているのである。
定理二四 ある人が我々の憎むものを喜びに刺激することを我々が表象するなら、我々はその人に対しても憎しみに刺激されるであろう。反対にその人が我々の憎むものを悲しみに刺激することを我々が表象するなら、我々はその人に対して愛に刺激されるであろう。
証明 この定理はこの部の定理二二と同様の仕方で証明される。その個所を見よ。
備考 これらの感情ならびに憎しみから来るこれと類似の諸感情はねたみの中に入れられる。したがってねたみとは人間をして他人の不幸を喜びまた反対に他人の幸福を悲しむようにさせるものと見られる限りにおける憎しみそのものにほかならない。
定理二五 我々は、我々自身あるいは我々の愛するものを喜びに刺激すると表象するすべてのものを、我々自身および我々の愛するものについて肯定しようと努める。また反対に、我々自身あるいは我々の愛するものを悲しみに刺激すると表象するすべてのものを否定しようと努める。
証明 我々の愛するものを喜びあるいは悲しみに刺激すると我々が表象するものは、我々をも喜びあるいは悲しみに刺激する(この部の定理二一により)。ところが精神は(この部の定理一二により)我々を喜びに刺激するものをできるだけ表象しようと努める。言いかえれば(第二部定理一七およびその系により)そうしたものを現在するものとして観想しようと努める。また反対に(この部の定理一三により)我々を悲しみに刺激するものについてはその存在を排除しようと努める。ゆえに我々は、我々自身あるいは我々の愛するものを喜びに刺激すると表象すかすべてのものを、我々自身および我々の愛するものについて肯定しようと努める。また反対の場合は反対のことに努める。Q・E・D・
定理二六 我々は、我々の憎むものを悲しみに刺激すると表象するすべてのものをその憎むものについて肯定しようと努める。また反対に我々の憎むものを喜びに刺激すると表象するすべてのものを否定しようと努める。
証明 前定理がこの部の定理二ーから帰結されたように、この定理は定理二三から帰結される。
備考 これで我々は、人間が自分自身ならびに自分の愛するものについて正当以上に感じ・また反対に自分の憎むものについて正当以下に感ずるということが起こりやすいことを知りうる。
こうした表象は自分について正当以上に感ずる人間自身に関係する時は高慢と呼ばれ、そしてこれは狂気の一種である。なぜならこのような人間は、単に表象においてのみ達成されることをすべてなしうるものと目を開きながら夢み、そのためにそれらのことを実在するかのように観想し、そしてそれらの存在を排除しかつその人間自身の活動能力を限定するものを表象しえない限りにおいて、それらについて誇っているのだからである。ゆえに高慢とは人間が自分自身について正当以上に感ずることから生ずる喜びである。次に人間が他のものについて正当以上に感ずることから生ずる喜びは買いかぶりと呼ばれ、最後に人間が他のものについて正当以下に感ずることから生ずる喜びは見くびりと呼ばれる。
定理二七 我々と同類のものでかつそれにたいして我々が何の感情もいだいていないものがある感情に刺激されるのを我々が表象するなら、我々はそのことだけによって、類似した感情に刺激される。
証明 事物の表象像とは人間身体の変状〔刺激状態〕のことであり、そしてその変状の観念は外部の物体を我々に現在するものとして思い浮かべさせる(第二部定理一七の備考により)。言いかえれば(第二部定理一六により)その変状の観念は我々の身体の本性と同時に外部の物体の現在的本性を含んでいる。ゆえにもし外部の物体の本性が我々の身体の本性に類似するならば、我々が表象する外部の物体の観念は、外部の物体の変状に類似した我々の身体の変状を含むであろう。したがってもし我々に類を同じくするあるものがある感情に刺激されたことを我々が表象するなら、この表象は、この感情に類似した我々の身体の変状を表現するであろう。だから我々と類を同じくするあるものがある感情に刺激されることを表象することによって、我々はそのものと類似の感情に刺激される。しかしもし我々と類を同じくするものを我々が憎んでいるなら、その限りにおいては、我々は(この部の定理二三により)そのものと反対の感情に刺激され、類似の感情には刺激されないであろう。Q・E・D・
備考 感情のこの模倣が悲しみに関する場合には憐憫と呼ばれる(これについてはこの部の定理二二の備考を見よ)。しかしそれが欲望に関する場合は競争心と呼ばれる。ゆえに競争心とは我々と同類の他のものがあることに対する欲望を有すると我々が表象することによって我々の中に生ずる同じ欲望にほかならない。 (備考1)
系一 その人に対して我々が何の感情もいだいていないある人が、我々と同類のものを喜びに刺激することを我々が表象するならば、我々はその人に対して愛に刺激されるであろう。これに反してその人がそうしたものを悲しみに刺激することを我々が表象するならば、我々はその人に対して憎しみに刺激されるであろう。
証明 この系は、この部の定理二二が定理二ーから証明されたのと同じ仕方で前定理から証明される。
系二 我々の憐れむものの不幸が我々を悲しみに刺激するからといって、我々はそのものを憎むことはできない。
証明 なぜなら、もしこのことのために我々がそうしたものを憎むことができるとしたら、我々はそうしたものの悲しみを喜ぶことになるであろう(この部の定理二三により)。しかしこれは仮定に反する。
系三 我々は我々の憐れむものできるだけその不幸から脱せしめようと努めるであろう。
証明 我々の憐れむものを悲しみに刺激するものは我々をも類似の悲しみに刺激する(前定理により)。したがって我々はそうしたものの存在を除去するすべてのことを、あるいはそうしたものを破壊するすべてのことを、想起しようと努めるであろう(この部の定理一三により)。言いかえれば我々は(この部の定理九の備考により)そうしたものを破壊しようとする衝動を感ずるであろう。あるいはそうしたもの破壊するように決定されるであろう。ゆえに我々は我々の憐れむものをその不幸から脱せしめようと努めるであろう。Q・E・D・
備考 あるものを憐れむことから生ずる、そのものに親切をしてやろうとするこの意志ないし衝動は慈悲心と呼ばれる。したがってこれは憐憫から生ずる欲望にほかならない。なお我々と同類であると我々の表象する対象に善あるいは悪をなした人に対する愛あるいは憎しみについては、この部の定理二二の備考を見よ。(系3備考)
定理二八 我々は、喜びをもたらすと我々の表象するすべてのものを実現しようと努める。反対にそれに矛盾しあるいは悲しみをもたらすと我々の表象するすべてのものを遠ざけあるいは破壊しようと努める。
証明 我々は喜びをもたらすと我々の表象するものをできるだけ表象しようと努める(この部の定理一二により)、言いかえれば我々は(第二部定理一七により)そうしたものを、できるだけ現在するものあるいは現実の存在するものとして観想しようと努めるであろう。ところが精神の努力ないしその思惟能力は身体の努力ないしその行動能力と本性上相等しくかつ同時的である(第二部定理七の系および定理一一の系から明瞭に帰結されるように)。ゆえに我々はそうしたものが存在するように絶対的に努める、あるいは我々は(この部の定理九の備考により同じことだが)そうしたことに衝動を感じまたそうしたことへ力を尽す。これが第一の点であった。次にもし悲しみの原因であると我々の信ずるもの、言いかえれば(この部の定理一三の備考により)我々の憎むもの、が破壊されることを我々が表象するならば、我々は喜ぶであろう(この部の定理二〇により)。したがって我々はそうしたものを現在するものとして観想しないようにそれを破壊することに努め(この定理の最初の部分と同じ理由により)、あるいは(この部の定理一三により)それを我々から遠ざけることに努めるであろう。これが第二の点であった。ゆえに喜びをもたらすと我々の表象するすべてのものを云々。Q・E・D・
定理二九 我々は人々(*)が喜びをもって眺めると我々の表象するすべてのことをなそうと努めるであろう。また反対に我々は人々が嫌悪すると我々の表象することをなすのを嫌悪するであろう。
*注意。ここおよび以下において人々というのは、その人々に対して我々が何の感情もいだいていない場合と解してもらいたい。
証明 人々があるものを愛しあるいは憎むと我々が表象することによって、我々はそのものを愛しあるいは憎むであろう(この部の定理二七により)。言いかえれば我々は(この部の定理一三の備考により)そのことのためにそうしたものの現在を喜びあるいは悲しむであろう。したがって我々は(前定理により)人々が愛しあるいは喜びをもって眺めると我々の表象するすべてのことをなそうと努めるであろう、云々。Q・E・D・
備考 ただ人々の気に入ろうとする理由だけであること差したり控えたりするこの努力は名誉欲と呼ばれる。ことに我々が、我々自身あるいは他人の損害になるのも構わずにあること差したり控えたりするほど熱心に民衆の気に入ろうと努める場合にはそう呼ばれる。しかしそれほどまででない場合は鄭重と呼ばれるのが常である。次に我々を喜ばせようとする努力のもとになされた他人の行為を表象する際に我々の感ずる喜びを私は賞讃と呼び、これに反してその人の行為を嫌悪する際に感ずる悲しみを非難と呼ぶ。
定理三〇 もしある人が他の人々を喜びに刺激すると表象するある事をしたならば、その人は喜びに刺激されかつそれとともに自分自身をその喜びの原因として意識するであろう、すなわち自分自身喜びをもって観想するであろう。これに反してもし他の人々を悲しみに刺激すると表象するある事をなしたならば、その人は反対に自分自身を悲しみをもって観想するであろう。
証明 自分が他の人々を喜びあるいは悲しみに刺激すると表象する人は、そのことだけによって(この部の定理二七により)喜びあるいは悲しみに刺激されるであろう。ところが人間は(第二部定理一九および二三により)自らを行動に決定する刺激〔変状〕によって自分自身を意識する。
だから他の人々を喜びに刺激すると自ら表象するようなある事をなした人は、喜びに刺激されかつそれとともに自分自身をその喜びの原因として意識するであろう。すなわち自分自身を喜びをもって観想するであろう。また反対の場合にはこれと反対のことが起こる。Q・E・D・
備考 愛とは(この部の定理一三の備考により)外部の原因の観念を伴った喜びであり、憎しみとは同じく外部の原因の観念を伴った悲しみであるから、ここに述べた喜びおよび悲しみは愛および憎しみの一種である。しかし愛および憎しみは外部の対象に関連するものであるから、我々は今述べた感情を他の名称で表示するであろう。すなわち我々は内部の原因の観念を伴ったこの喜びを名誉と呼び、これと反対する悲しみを恥辱と呼ぶであろう。しかしこれは人間が他から賞讃されあるいは非難されると信ずるために喜びあるいは悲しみを感じる場合のことである。そうでない場合は、内部の原因の親念を伴ったこの喜びを自己満足と呼び、これに反対する悲しみを後悔と呼ぶであろう。
なお、自分は他の人々を喜びに刺激しているとある人の表象するその喜びが、単に表象的なものにすぎないこともありうるし(第二部定理一七の系により)、また(この部の定理二五により)各人は自分を喜びに刺激すると表象するすべてのものを自分について表象しようと努めるのであるから、名誉を好む人間が高慢になり、またみなに嫌われていながらみなに気に入られていると表象する、というようなことが容易に起こりうるのである。
定理三一 もし我々が自分の愛し、欲し、あるいは憎むものをある人が愛し、欲し、あるいは憎むことを表象するならば、まさにそのことによって我々はそのものをいっそう強く愛し、欲し、あるいは憎むであろう。これに反し、もし我々が自分の愛するものをある人が嫌うことを、あるいはその反対を、(すなわち我々の憎むものをある人が愛することを表象するならば、我々は心情の動揺を感ずるであろう。
証明 ある人があるものを愛することを我々が表象するなら、単にそのことだけによって我々はそのものを愛するであろう(この部の定理二七により)。ところが、もともと初めから我々はそのものを愛していることが仮定されている。だからもとの愛に対して、さらにその愛をはぐくむ新しい原因が加わることになる。したがって我々は自分の愛するものを、まさにそのことのために、いっそう強く愛するであろう。次に、ある人があるものを嫌うことを我々が表象することによって我々はそのものを嫌うようになるであろう(同じ定理により)。ところでもし我々が同時にそれを愛していると仮定するならば、我々はその同じものを同時に愛しかつ嫌うであろう。すなわち我々は(この部の定理一七の備考を見よ)心情の動揺を感ずるであろう。Q・E・D・
系 このことおよびこの部の定理二八の帰結として、各人は自分の愛するものを人々も愛するように、また自分の憎むものを人々も憎むようにできるだけ努めるということになる。こんなところから詩人のあの言葉も出ている〜〜
我ら愛する者はかつ望みかつ恐れようよ、
他人の捨てるものを愛するなんて野暮なことだ、 (オヴィディウス)
備考 自分の愛するものや自分の憎むものを人々に是認させようとするこの努力は実は名誉欲である(この部の定理二九の備考を見よ)。このようにして各人は生来他の人々を自分の意向に従って生活するようにしたがるものであるということが分かる。ところで、このことをすべての人が等しく欲するゆえに、すべての人が等しくたがいに障害になり、またすべての人がすべての人から賞讃されよう愛されようと欲するゆえに、すべての人が相互に憎み合うことになるのである。
定理三二 ただ一人だけしか所有しえぬようなものをある人が享受するのを我々が表象するなら、我々はその人にそのものを所有させないように努めるであろう。
証明 ある人があるものを享受することを我々が表象するなら、そのことだけによって我々は(この部の定理二七およびその系一により)そのものを愛するであろうし、また享受しようと欲するであろう。ところが仮定によれば、他の人がその同じものを享受することは自分がこの喜びを達するのに妨げになることを我々は表象する。ゆえに我々は(この部の定理二八により)その人にそれを所有させぬように努めるであろう。Q・E・D・
備考 このようにして、人間の本性は一般に、不幸な者を憐れみ幸福な者をねたむようにできていること、しかも(前定理により)他人の所有していると彼らの表象するものを彼らがより多く愛するに従ってそれだけ大なる憎しみをもってねたむということが分かる。次に人間が同情心を起こすようになるその同じ人間本性の特質からして、また人間がねたみ心をいだき、あるいは名誉欲に支配されるということが起こってくることが分かる。最後に、もし我々がこれを経験に聴こうと欲するならば、経験そのものもすべてこの通り教えることを我々は見いだすであろう。ことに我々が自分の幼少時代に思いを至すならなおさらのことである。というのは、小児はその身体がいわば絶えざる動揺状態にあるがゆえに、他の人々の笑いあるいは泣くのを見ただけで笑いあるいは泣くのを我々は経験している。さらにまた小児は他の人々がなすのを見て何でもすやに模倣したがるし、最後にまた他の人々が楽しんでいると表象するすべてのことを自分に欲求する。これというのも事物の表象像は、すでに述べたとおり、人間身体の変状そのもの、〜〜すなわち外部の原因によって人間身体にもたらされて人間をこのあるいはかの行動に決定する刺激の様式そのもの、にほかならないからである。
定理三三 我々は我々と同類のものを愛する場合、できるだけそのものが我々を愛し返すように努める。
証明 我々は自分の愛するものをできるだけ他のものよりも多く表象しようと努める(この部の定理一二により)。ゆえにもしそのものが我々と同類のものならば、我々はそのものを他のものよりも多く喜びに刺激することに努めるであろう(この部の定理二九により)。つまり我々は、我々の愛するものが我々の観念を伴った喜びに刺激されるように、言いかえれば(この部の定理一三この備考により)そのものが我々を愛し返すようにできるだけ努めるであろう。Q・E・D・
定理三四 我々の愛するものが我々に対してより大なる感情に刺激されていると我々が表象するに従って、我々はそれだけ大なる名誉〔誇り〕を感ずるであろう。
証明 我々は(前定理により)できるだけ、愛するものが我々を愛し返すように努める。言いかえれば我々は(この部の定理一三の備考により)愛するものが我々の観念を伴った喜びに刺激されるように努める。そこで、愛するものが我々のためにより大なる喜びに刺激されていると我々が表象するに従って、この努力はそれだけ多く促進される。言いかえれば(この部の定理一一およびその備考により)、我々はそれだけ大なる喜びに刺激される。ところが我々は我々と同類の他のものを喜びに刺激したことによって喜びを感ずるたびごとに、我々自身を喜びをもって観想する(この部の定理三〇により)。ゆえに愛するものが我々に対してより大なる感情に刺激されていると我々が表象するに従って、我々はそれだけ大なる喜びをもって我々自身を観想するであろう。
すなわち我々は(この部の定理三〇の備考により)それだけ大なる名誉〔誇り〕を感ずるであろう。Q・E・D・
定理三五 人はもし自分の愛するものが自分のこれまで独り占めにしていたと同じの、あるいはより緊密な愛情の絆によって他人と結合することを表象するならば、愛するもの自身に対しては憎しみを感じ、またその他人をねたむであろう。
証明 人は自分の愛するものが自分に対してより大なる愛を感じていると表象するに従ってそれだけ大なる名誉を感ずるであろう(前定理により)。言いかえれば(この部の定理三〇の備考により)それだけ大なる喜びを覚えるであろう。したがってその人は(この部の定理二八により)愛するものが自分と最も緊密に結びついていることを表象するようにできるだけ努めるであろう。そしてこの努力ないし衝動は、他人もその同じものを欲していると表象される場合なお強められるものである(この部の定理三一により)。ところが仮定によれば、この努力ないし衝動は、愛するもの自身の表象像が愛するものの結合している他人の表象像を伴っていることによって阻害されることになっている。ゆえにその人は(この部の定理一一の備考により)そのことによって悲しみに〜〜愛するものをその原因として意識し、同時にかの他人の表象像を伴った悲しみに、刺激されるであろう。言いかえればその人は(この部の定理一三の備考により)愛するものに対して、また同時にその他人に対して(この部の定理一五の系により)、憎しみに刺激されるであろう。したがってまたその他人を〜〜その他人は愛するものを享楽しているのであるから〜〜ねたむであろう(この部の定理二三により)。Q・E・D・
備考 ねたみと結合した、愛するものに対するこの憎しみは、嫉妬と呼ばれる。したがって嫉妬とは、同時的な愛と憎しみから生じかつそれにねたまれる第三者の観念を伴った心情の動揺にほかならない。なおまた愛するものに対するこの憎しみの大いさは、嫉妬する者がそれまで愛するものの愛し返しによって感ずるのを常としていた喜びの度合に比例し、さらにまた愛するものの結合する相手として表象される人に対して彼が前にいだいていた感情の度合に比例するであろう。というのは、もし彼がその第三者を憎んでいるとしたら、すでにそのことだけで彼は愛するものを憎むであろう(この部の定理二四により)。なぜなら彼は愛するものが彼の憎むものを喜びに刺激することを表象するからである。その上また彼は(この部の定理一五の系により)愛するものの表象像を彼の憎むものの表象像と結合せざるをえないということからも愛するものを憎むであろう。この関係は一般に女に対する愛の場合に見られる。すなわち愛する女が他人に身を要せることを表象する人は、自分の衝動が阻害されるゆえに悲しむばかりでなく、また愛するものの表象像を他人の恥部および分泌物と結合せざるをえないがゆえに愛するものを厭(いと)うであろう。これに加えてまた嫉妬する者は、愛するものが与えるのを常としたと同じ顔つきをもって愛するものから迎えられないということになる。そしてこの理由からも愛する当人は悲しみを感ずる。私がやがて示すであろうように。
定理三六 かつて享楽したものを想起する人は、最初にそれを享楽したと同じ事情のもとにそれを所有しようと欲する。
証明 人間が自分を楽しませたものと同時に見たすべてのものは、彼にとって偶然による喜びの原因となるであろう(この部の定理一五により)。したがって(この部の定理二八により)彼は、これらすべてを、自分を楽しませたものと同時に所有しようと欲するであろう。すなわち彼が最初にそれを楽しんだと同一のすべての事情のもとにそれを所有しようと欲するであろう。Q・E・D・
系 それでもし、愛する当人は、これらの事情の一つでも欠けていることに気づけば、悲しむであろう。
証明 なぜなら、何らかの事情が欠けていることに気づく限り、彼はそのものの存在を排除するある物を表象する。ところが彼は、そのものあるいはその事情を(前定理により)愛ゆえに欲しているのであるから、したがって(この部の定理一九により)それが欠けていることを表象する限り、悲しみを感ずるであろう。Q・E・D・
備考 我々の愛する物の不在に関するこの悲しみは思慕と呼ばれる。
定理三七 悲しみや喜び、憎しみや愛から生ずる欲望は、それらの感情がより大であるに従ってそれだけ大である。
証明 悲しみは人間の活動能力を減少しあるいは阻害する(この部の定理一一の備考により)。言いかえれば(この部の定理七により)人間が自己の有に固執しようと努める努力を減少しあるいは阻害する。したがって悲しみは(この部の定理五により)この努力に相反するものである。そして悲しみを感じている人間のすべての努力は悲しみを除去することに向けられる。ところが(悲しみの定義により)悲しみがより大であるに従ってそれは必然的に人間の活動能力のそれだけ大なる部分を阻害する。ゆえに悲しみがより大であるに従って人間は反対にそれだけ大なる活動能力をもって悲しみを除去しようと努めるであろう。言いかえれば(この部の定理九の備考により)それだけ大なる欲望ないし衝動をもって悲しみを除去しようと努めるであろう。次に喜びは(再びこの部の定理一一の備考により)人間の活動能力を増大しあるいは促進するから、喜びを感じている人間が喜びを維持することを何よりも欲すること、しかも喜びがより大なるに経ってそれだけ大なる欲望をもってそれを欲することは同じ方法で容易に証明される。最後に、憎しみや愛は悲しみや喜びの感情そのものであるから、憎しみや愛から生ずる努力・衝動ないし欲望の大いさが憎しみや愛の大いさに比例するだろうことも同じ仕方で導き出される。Q・E・D・ 208
定理三八 ある人がその愛するものを憎み始めてついに愛がまったく消滅するに至る場合、彼は、それを全然愛していなかった場合よりも〜〜もしその憎む原因が両方の場合相等しいとしたら〜〜より大なる憎しみに捉われるであろう。そしてこの憎しみは以前の愛がより大であったに従ってそれだけ大であるであろう。
証明 なぜなら、もしある人がその愛するものを憎み始めるなら、それを愛さなかった場合に比し、彼における衝動はより多く阻害される。というのは、愛は喜びであるから(この部の定理一三の備考により)、人間はこれをできるだけ維持しようと努め(この部の定理二八により)、そのため(同じ備考により)愛するものを現在するものとして観想するようにし、また愛するものを(この部の定理二一により)できるだけ喜びに刺激するようにする。この努力は(前定理により)愛がより大なるに従ってそれだけ大である。そして愛するものに自分自身を愛し返させるようにする努力もまた同様である(この部の定理三三を見よ)。ところがこれらの努力は愛するものに対する憎しみによって阻害される(この部の定理一三の系および定理二三により)。ゆえに愛する当人は(この部の定理一一の備考により)この理由のためにも悲しみに刺激されるであろう。そしてその悲しみは愛がより大であったに従ってそれだけ大であるであろう。言いかえれば、憎しみの原因であった悲しみのほかに、なお他の悲しみが、そのものを愛したことから生ずるのである。したがって彼はそのものを愛さなかった場合に比べ、より大なる悲しみの感情をもって愛するものを観想するであろう。言いかえれば(この部の定理一三の備考により)より大なる憎しみに捉われるであろう。そしてこの憎しみは以前の愛がより大であったに従ってそれだけ大であるであろう。Q・E・D・
定理三九 ある人を憎む者はその人に対して悪〔害悪〕を加えようと努めるであろう。ただしそのために自分自身により大なる悪の生ずることを恐れる場合はこの限りでない。また反対に、ある人を愛する者は同じ条件のもとに、その人に対して善〔親切〕をなそうと努めるであろう。
証明 ある人を憎むとは(この部の定理一三の備考により)ある人を悲しみの原因として表象することである。したがって(この部の定理二八により)ある人を憎む者はその人を遠ざけあるいは破壊しようと努めるであろう。だがもし彼がそのため自分自身により大なる悲しみあるいは(同じことだが)より大なる悪の生ずることを恐れるなら、そして企てた悪を、憎む人に加えないことによってそれを避けうると信ずるなら、彼はその悪を加える企てを断念しようと欲するであろう(再びこの部の定理二八により)、しかも(この部の定理三七により)この努力〔欲求〕は他人に悪を加えるように彼を促した努力〔欲求〕に比べより大であるであろう。したがってこの努力の方が、我々の主張したように、優勢を占めるであろう。この定理の第二の部分の証明も同じ仕方でなされる。ゆえにある人を憎む者は云々。Q・E・D・
備考 私はここで、善をあらゆる種類の喜びならびに喜びをもたらすすべてのもの、また特に願望〜〜それがどんな種類のものであっても〜〜を満足させるもの、と解する。これに反して悪をあらゆる種類の悲しみ、また特に願望の満足を妨げるもの、と解する。なぜなら、前に(この部の定理九の備考において)示したように、我々は物を善と判断するがゆえに欲するのでなく、かえって反対に我々の欲するものを善と呼ぶのだからである。したがってまた我々は我々の嫌悪するものを悪と呼ぶ。ゆえに各人は、何が善で何が悪であるか、何がより善く何がより悪くあるか、最後に何が最も善く何が最も悪くあるかを自己の感情に基づいて判断しあるいは評価する。こうして食欲者は金の集積を最も善いものと判断し、その欠乏を最も悪いものと判断する。しかし名誉欲者は何にもまして名誉を欲し、反対に何にもまして恥辱を恐れる。最後に、ねたみ屋にとっては他人の不幸ほど愉快なものはなく、また他人の幸福ほど不快なものはない。このようにして各人は、自己の感情に基づいて、あるものが善か悪か、有用か無用かを判断するのである。
なおまた、人間をしてその欲するものを欲せずあるいはその欲せざるものを欲するように仕向けるこの感情は臆病と呼ばれる。したがって臆病とは人間をしてその予見する悪をより小なる悪によって避けるように仕向ける限りにおける恐怖にほかならない(この部の定理二八を見よ)。しかしもしその恐れる悪が恥辱である場合にはその臆病は羞恥と呼ばれる。最後にもし予見される悪を避けようとする欲望が他の悪への怯(おび)えによって阻害されていずれを選ぶべきかを知らない場合には〜〜特にその恐れる二つの害悪がきわめて大なる場合には〜〜その恐怖は恐慌と呼ばれる。
定理四〇 自分が他人から憎まれていると表象し、しかも自分は憎まれる何の原因もその人に与えなかったと信ずる者は、その人を憎み返すであろう。
証明 人が憎しみに刺激されていることを表象する者はそのことによって自分も同様に憎しみに刺激されるであろう(この部の定理二七により)。言いかえれば彼は(この部の定理一三の備考
により)外部の原因の観念を伴った悲しみに刺激されるであろう。ところが彼自身は(仮定により)自分を憎んでいる人以外にこの悲しみの何の原因も表象しない。すえに彼は、自分がある人から憎まれていると表象することによって、自分を憎む人の観念を伴った悲しみに刺激されるであろう。すなわち(同じ備考により)その人を憎むであろう。Q・E・D・
備考 もし彼が憎しみに対する正当な原因を与えたことを表象するならば、彼は(この部の定理三〇およびその備考により)恥辱に刺激されるであろう。だがこうしたことは(この部の定理二五により)稀にしか起こらない。
なおこの憎み返しは、憎しみにはその憎む柏手に害悪を加えようとする努力がつきものだということからも生じうる(この部の定理三九により)。すなわち、他人から憎まれることを表象する者は、その人をある害悪または悲しみの原因として表象するであろう。したがって彼は自分を憎む人をその原因として意識した悲しみまたは恐怖に刺激されるであろう。言いかえれば、上述のごとく、その人を憎み返すであろう。Q・E・D・
系一 自分の愛する人が自分に対して憎しみを感じていると表象する者は、同時に憎しみと愛とに捉われるであろう。なぜなら、自分がその人から憎まれると表象する限り彼はその人を憎み返すように決定される(前定理により)。ところが彼は(仮定により)その人をそれにもかかわらず愛している。ゆえに彼は同時に憎しみと愛とに捉われるであろう。
系二 もしある人が、前に自分がいかなる感情もいだいていなかった他人から憎しみのゆえにある害悪を加えられたことを表象するなら、彼はただちに同じ害悪をその他人に報いようと努めるであろう。
証明 他人が自分に対して憎しみを感じていると表象する者はその人を憎み返すであろう(前定理により)。そして(この部の定理二八により)その人を悲しみに刺激しうるあらゆることを案出しようと努め、かつそれをその人に(この部の定理三九により)加えようと励むであろう。ところが(仮定により)この種のことに関して彼の表象に浮かぶ第一のことは、彼自身に加えられた害悪である。ゆえに彼は同じものをただちにその人に加えようと努めるであろう。Q・E・D・
備考 我々の憎む者に対して害悪を加えようとする努力は怒りと呼ばれる。また我々に対して加えられた害悪に報いようとする努力は復讐と称される。
定理四一 もしある人が他人から愛されると表象し、しかも自分は愛される何の原因も与えなかったと信ずる場合は(こうしたことはこの部の定理一五の系および定理一六によって可能である)、彼はその人を愛し返すであろう。
証明 この定理は前定理と同様の仕方で証明される。なお前定理の備考を見よ。
備考 もし自分が愛に対する正当な原因を与えたと信ずるならば彼は名誉を感ずるであろう(この部の定理三〇およびその備考により)。こうしたことは(この部の定理二五により)かなりしばしば起こる。これに対してある人が他人から憎まれることを表象する場合は、前に述べたように、そうしたこと〔正当な原因を与えたと信ずること〕は稀にしか起こらない(前定理の備考を見よ)。なおこの愛し返し、したがってまた(この部の定理三九により)我々を愛し・かつ(同じくこの部の定理二九により)我々に親切をなそうと努める人に対して親切をなそうとする努力、は感謝または謝恩と呼ばれる。これからして、人間は親切に報いるよりもはるかに復讐に傾いているということが明らかになる。
系 自分の憎む者から愛されていることを表象する人は、同時に憎しみと愛とに捉われるであろう。このことは前定理の系一と同じ仕方で証明される。
備考 この場合憎しみの方が優勢を占めるならば、彼は自分を愛してくれる者に害悪を加えようと努めるであろう。この感情は残忍と称される。特に、愛してくれる者が憎しみを受ける何の一般的原因も与えなかったと見られる場合にはそうである。
定理四二 愛に基づいて、あるいは名誉を期待して、ある人に親切をなした人は、その親切が感謝をもって受け取られないことを見るなら悲しみを感ずるであろう。
証明 自分と同類のものを愛する人はできるだけそのものから愛し返されるように努める(この部の定理三三により)。だから、愛に基づいてある人に親切をなした人は、愛し返されるようにとの願望をもって、言いかえれば(この部の定理三四により)名誉すなわち(この部の定理三〇の備考により)喜びを期待して、それをなすのである。したがって彼は(この部の定理一二により)名誉のこの原因を表象することに、あるいはこの原因を現実に存在するものとして観想することに、できるだけ努めるであろう。ところが(仮定により)彼はこの原因の存在を排除する他のあるものを表象する。ゆえに彼は(この部の定理一九により)まさにそのために悲しみを感ずるであろう。Q・E・D・
定理四三 憎しみは憎み返しによって増大され、また反対に愛によって除去されることができる。
証明 自分の憎む者が自分を憎み返していることを表象する人は、そのことによって(この部の定理四〇により)新しい憎しみが生ずる〔のを感ずる〕。しかも最初の憎しみは(仮定により)なお依然として存続しているのである。しかしもし反対に、自分の憎む者が自分に対して愛を感じていることを表象するなら、彼は、そのことを表象する限りにおいて(この部の定理三〇により)自分自身を喜びをもって観想する。またその限りにおいて(この部の定理二九により)その人の気に入ろうと努めるであろう。言いかえれば(この部の定理四一により)彼はその限りにおいてその人を憎まないように、またその人を悲しみに刺激しないように、努める。この努力は(この部の定理三七により)それを生ぜしめる感情の度合に比例してより大でありあるいはより小であるであろう。したがってもしこの努力が、憎しみから生ずるあの努力、自分の憎むものを悲しみに刺激しようと努めるあの努力(この部の定理二六により)よりもより大であるならば、それは優勢を占めて憎しみを心から除去するであろう。Q・E・D・
定理四四 愛にまったく征服された憎しみは愛に変ずる。そしてこの場合、愛は、憎しみが先立たなかった場合よりもより大である。
証明 この定理の証明はこの部の定理三八のそれと同一の仕方でなされる。すなわち自分の憎むものあるいは自分が悲しみをもって観想するのを常としたものを愛し始める人は、愛するということそのことによってすでに喜びを感ずる。そして愛が含むこの喜び(この部の定理一三の備考におけるその定義を見よ)の上に、憎しみが含む悲しみを除去しようとする努力(この部の定理三七で示したように)が完全に促進されることから生ずる喜び〜〜自分の憎んだ者をその原因として意識したような〜〜が加わる。
備考 事情はかくのごとくであるけれども、何びともしかしあとでこのより大なる喜びを享楽しようとしてあるものを憎んだり・悲しみを感じたりするように努めはしないであろう。すなわち何びとも損害賠償の希望に促されて害悪をわが身に受けることを欲したり、全快の希望に促されて病気にかかることを願ったりはしないであろう。なぜなら各人は自己の有を維持し・悲しみをできるだけ遠ざけることに常に努めるだろうからである。これに反して、もし人間はあとでより大なる愛をもってある人に対しようとするためにその人を憎むことを欲しうるということが考えられるものとしたら、彼はその人を常に憎むことを願うであろう。なぜなら、憎しみがより大であったに従って愛はそれだけ大となるのであり、こうして彼は憎しみがますます増大することを常に願うであろうからである。また同じ理由から、人間はあとで健康回復によってより大なる喜びを享楽しようとするためにますます多く病むことに努めるであろう、したがってまた常に病むことに努めるであろう。しかしこのようなことは(この部の定理六により)不条理である。
定理四五 ある人がもし自分と同類の他人が同じく自分と同類である自分の愛するものに対して憎しみを感じていることを表象するなら、彼はその他人を憎むであろう。
証明 なぜなら、自分の愛するものは己(おの)れを憎む人を憎み返す(この部の定理四〇により)。それゆえ愛する当人は、自分の愛するものを他人が憎むことを表象する場合、まさにそのことによって、自分の愛するものが憎しみを、言いかえれば(この部の定理一三の備考により)悲しみを、感じていることを表象する。したがってまた彼自身(この部の定理二一により)悲しみを感ずる、しかも自分の愛するものを憎む人をその原因として意識した悲しみを感ずる。言いかえれば彼は(この部の定理一三の備考により)その人を憎むであろう。Q・E・D・
定理四六 もしある人が自分と異なった階級ないし民族に属するある者から、その階級ないし民族の一般的名称のもとにあるその者を原因として意識した喜びまたは悲しみに刺激されたなら、彼は単にその者だけでなく、さらにその同じ階級ないし民族に属するすべての者を愛しあるいは憎むであろう。
証明 この定理の証明はこの部の定理一六から明白である。
定理四七 我々の憎むものが滅ぼされたりあるいは他の何らかの害悪を受けたりすることを我我が表象することによって生ずる喜びは、同時にある悲しみを伴うものである。
証明 この部の定理二七から明白である。なぜなら、我々は自分と同類のものが悲しみに刺激されることを表象する限り自分も悲しみを感ずるからである。
備考 この定理は第二部定理一七の系からも証明されうる。すなわち我々はある物を想起するごとに、その物がもはや現実に存在しない場合でもやはりそれを現在するもののように観想し、そして身体は〔その物が現実に存在していた時と〕同じ仕方で刺激される。ゆえにその物への記憶が我々に残っている限り、その限りにおいて人間はそれを悲しみをもって観想するように決定される。この決定は、その物の表象像がなお存する間は、その物の存在を排除する事物への想起によって阻害されはするがまったく除去されることはない。したがって人間はこの決定が阻害される限りにおいてのみ喜びを感ずるのである。これで見てもわかるように、我々の憎む物に加えられた害悪から生ずる喜びは、我々がその物を想起するごとに繰り返されるのである。すなわちすでに述べたように、その物の表象像が喚起される場合、この表象像はその物の存在を含むがゆえに、人間はそのものがなお存在していた時にそれを観想するのを常としたと同じ悲しみをもってそれを観想するように決定される。だが彼はこのものの存在を排除する他の表象像をこの物の表象像と結合したがゆえに、悲しみに対するこの決定はただちにさえぎられそして人間は新たに喜びを感ずるのである。しかもこのことが繰り返されるごとに喜びを感ずるのである。
そしてこのことは、なぜ人間がある過去の害悪を想起するごとに喜びを感ずるか、またなぜ自分のまぬがれた危難について物語るのを楽しむかの理由でもある。すなわち、彼らはある危難を表象する場合、それをあたかもなおこれから起こるもののように観想し、かつこれを恐れるように決定される。しかしこの決定は、彼らがこの危難をまぬがれた時にこの危難の観念と結合した救助の観念によって新たにさえぎられる。この救助の観念が彼らに新たに安全感を与え、したがって彼らは新たに喜びを感ずるのである。
定理四八 愛および憎しみ〜〜例えばペテロに対する〜〜は、憎しみが含む悲しみおよび愛が含む喜びが他の原因の観念と結合する場合には消滅する。また両者〔愛および憎しみ〕は、ペテロがそのどちらかの感情〔喜びあるいは悲しみ〕の唯一の原因でなかったことを我々が表象する限りにおいて減少する。
証明 単に愛および憎しみの定義から明白である。この部の定理一三の備考におけるその定義を見よ。というのは、喜びがペテロに対する愛と呼ばれ・悲しみがペテロに対する憎しみと呼ばれるわけは、ただペテロが喜びあるいは悲しみの感情の原因であると見られるからにほかならぬ。だからこの前提が全部あるいは一部除去されれば、ペテロに対する感情もまた全部あるいは一部終熄(そく)する。Q・E・D・
定理四九 自由であると我々の表象する物に対する愛および憎しみは、原因が等しい場合には、必然的な物に対する愛および憎しみより大でなければならぬ。
証明 自由であると我々の表象する物は、他のものなしにそれ自身によって知覚されなければならぬ(第一部定義七により)。ゆえにもし我々がこうした物を喜びあるいは悲しみの原因であると表象するなら、まさにそのことによって我々は(この部の定理一三の備考により)それを愛しあるいは憎むであろう。しかも(前定理により)与えられた感情から生じうる最大の愛あるいは憎しみをもって愛しあるいは憎むであろう。これに反してもしこの感情の原因たる物を必然的なものとして表象するなら、我々はそれが(同じく第一部の定義七により)単独にでなく他の物と合同してこの感情の原因であることを表象するであろう。したがって(前定理により)その物に対する愛および憎しみはより小であろう。Q・E・D・
備考 この帰結として出てくるのは、人間は自らを自由であると思うがゆえに他の物に対してよりも相互に対してより大なる愛あるいは憎しみをいだき合う、ということである。なおこれに感情の模倣ということが加わる。感情の模倣についてはこの部の定理二七、三四、四〇、および四三を見よ。
定理五〇 おのおのの物は偶然によって希望あるいは恐怖の原因であることができる。
証明 この定理はこの部の定理一五と同じ
方法で証明される。同定理をこの部の定理一八の備考二と併(あわ)せ見よ。
備考 偶然によって希望あるいは恐怖の原因たる物は善い前兆あるいは悪い前兆と呼ばれる。ところでこれらの前兆は、希望あるいは恐怖の原因である限りにおいて喜びあるいは悲しみの原因である(希望および恐怖の定義による。この部の定理一八の備考二にあるその定義を見よ)。したがって我々は(この部の定理一五の系により)その限りにおいてそれを愛しあるいは憎み、また(この部の定理二八により)それを我々の希望するものへの手段として近づけあるいはその障害ないし恐怖の原因として遠ざけるように努める。その上この部の定理二五から分かる通り、我々は希望するものを容易に信じ・恐怖するものを容易に信じないようなふうに、また前者については正当以上に・後者については正当以下に感ずるようなふうに生来できあがっている。そしてこれからして、人間がいたるところで捉われているもろもろの迷信が生じたのである。
なおまた希望および恐怖から生ずる心情のさまざまの動揺をここに説明することは無用であると私は信ずる。なぜなら、単にこの両感情の定義だけからして、恐怖なき希望というものはありえずまた希望なき恐怖というものもありえないことが明らかであり(これは適当な場所でいっそう詳しく説明するであろう)、その上また我々は、あるものを希望しあるいは恐怖する限りそのものを愛しあるいは憎み、したがって我々が愛および憎しみについて述べたことを各人は容易に希望および恐怖に適用しうるからである。
定理五一 異なった人間が同一の対象から異なった仕方で刺激されることができるし、また同一の人間が同一の対象から異なった時に異なった仕方で刺激されることができる。
証明 人間身体は(第二部要請三により)外部の物体からきわめて多様の仕方で刺激される。ゆえに同一の時に二人の人間が異なった仕方で刺激されることができ、したがって(第二部定理一三のあとの補助定理三のあとにある公理により)二人の人間は同一の対象から異なった仕方で刺激されることができる。次に(同じ要請により)人間身体はある時はこの仕方で、ある時は他の仕方で刺激されることができる。したがってまた(同じ公理により)同一の対象から異なった時に異なった仕方で刺激されることができる。Q・E・D・
備考 これからして、ある人の愛するものを他の人が憎み、ある人の恐れるものを他の人が恐れないということや、同一の人間が以前に憎んだものを今愛し、以前に恐れたことを今あえてするなどということの起こりうることが分かる。さらに各人は何が善く何が悪く何がより善く何がより悪いかを自己の感情に基づいて判断するから(この部の定理三九の備考を見よ)、人間はその感情において異なるのと同様、その判断においてもたがいに異なりうることになる(*)。またこの結果、我々は人間を相互に比較する場合に、彼らと我々の感情の相違のみによって彼らを区別し、ある者を果敢、ある者を臆病、最後に他の者を他の名称で呼ぶことになる。例えば私が恐怖するのを常とする害悪を軽視する人を私は果敢と呼ぶであろう。その上憎む者に害悪を加え・愛する者に親切をなそうとする彼の欲望が私の躊躇するのを常とする害悪への恐れによって抑制されぬことを眼中に置くなら、私は彼を大胆と呼ぶであろう。次に私の軽視するのを常とする害悪を恐れる者は私には臆病に見えるであろう、その上もし彼の欲望が私のあえて躊躇しない害悪への恐れによって抑制されるということを眼中に置くなら、私は彼を小心と言うであろう。そして何びともこのようにして判断するであろう。
*人間の精神は神の知性の一部であるとはいえ、こうしたことが起こりうることを我々は第二部定理一三の備考で明らかにした。 (or→一七備考)
最後に、人間の本性がこうしたものであること、その判断が不安定なものであること、さらに人間はしばしば自己の感情のみによって物ごとを判断すること、また喜びあるいは悲しみをもたらすものと信じてそのゆえに(この部の定理二八により)それを実現しあるいは排除しようと努める事物が、往々にして単なる想像にすぎないこと(第二部で事物は確実に認識しがたいものであることについて述べたことどもは今は言わないとして)、そうしたことどもを思う時、我々は人間が自らしばしば自己の喜びあるいは悲しみの原因でありうることを、言いかえれば人間は喜びあるいは悲しみに刺激される場合しばしば自己自身をその原因として意識することを、容易に考えうる。こうして我々は後悔とは何か、また自己満足とは何かを容易に理解する。すなわち後悔とは原因としての自己自身の観念を伴った悲しみであり、自己満足とは原因としての自己自身の観念を伴った喜びである。そしてこれらの感情は人間が自らを自由であると信ずるがゆえにきわめて強烈である(この部の定理四九を見よ)。
定理五二 我々が以前に他のものと一緒に見た対象、あるいは多くのものと共通な点しか有しないことを我々が表象する対象、そうした対象を我々は、ある特殊の点を有することを表象する対象に対してほどに長くは観想しつづけないであろう。
証明 我々が他のものと一緒に見た対象を表象するや否や、我々はただちにその、他のものを想起する(第二部定理一八による。なおその備考も見よ)、こうして我々は一つの対象の観想からただちに他のものの観想に移る。多くのものに共通な点しか有しないことを我々が表象する対象についても同じことがあてはまる。なぜなら、まさにそのことによって我々は、以前に他のものと一緒に見なかったような点をその対象の中に発見しないことを仮定しているからである。これに反して我々が以前に決して見なかったような特殊な点をある対象の中に表象することを仮定するなら、それは精神がその対象を観想する間にその対象の観想から気をそらされうるような他のものを何ら自らの中に有しないというのにほかならぬ。したがって精神は単にその対象のみを観想するように決定される。ゆえに我々が以前に云々。Q・E・D・
備考 精神のこうした変状〔刺激状態〕すなわちある個物についてのこうした表象は、それが単独で精神の中に在る限り、驚異と呼ばれる。もしそれが我々の恐怖する対象によって喚起されるなら恐慌と言われる。なぜなら害悪への驚異は人間がその害悪を避けうるための他のことを思惟することができないまでに人間をもっぱらその〔害悪の〕観想の虜にするからである。だがもし我我の驚異するものがある人間の聡明、勤勉その他これに類する事柄であるとしたら、それによって我々はこの人間が我々をはるかに凌駕することを観想しているのだから、その驚異は尊敬と呼ばれる。そうでなくてもし我々が、ある人間の怒り、ねたみなどを驚異するのであれば、それは戦慄と呼ばれる。次に我々が我々の愛する人間の聡明、勤勉などを驚異する場合は、愛はまさにそれによって(この部の定理一二により)いっそう大になるであろう。そして驚異あるいは尊敬と結合したこの愛を我々は帰依と呼ぶ。またこのようにして我々は憎しみ、希望、安堵およびその他の感情を驚異と結合して考えることができる。こうして我々は常用の語彙によって表示するのを常とするよりもっと多くの感情を導き出すことができるであろう。これから明白なのは、感情の名称は、感情に関する正確な認識に基づくというよりも、日常の用途に基づいて作られているということである。
驚異に対立するものは軽蔑である。軽蔑のよって生ずるところはおおむね次のごときものである。すなわちある人がある物を驚異し、愛し、恐怖しなどするのを我々が見ることによって、またある物が一瞥(べつ)して我々の驚異し、愛し、恐怖しなどする物に類似して見えることによって、我我は一応そのものを驚異し、愛し、恐怖しなどするように決定される(この部の定理一五およびその系ならびに定理二七により)。ところが我々がその物自身の現在によって、あるいはその物をもっと正確に観想することによって、驚異、愛、恐怖などの原因となりうる一切の点をその物について否定せざるをえないようになれば、精神は、その物の現在によって、対象の中に存するものよりも対象の中に存しないものについてより多く思惟するように決定されることになるのである。本来ならこれと反対に、精神は、対象の現在によって、もっぱらその対象の中に存するものについて思惟するのが常であるのに。〜〜さらに帰依が我々の愛するものへの驚異から生ずるように、嘲弄は我々の憎みあるいは恐怖するものへの軽蔑から生ずる。また尊敬が聡明への驚異から生ずるように、侮蔑は愚鈍への軽蔑から生ずる。最後に我々は愛、希望、名誉およびその他の感情を軽蔑と結合して考えてそれからさらに他の諸感情を導き出すことができる。しかしこれらの感情を我々は何ら特別な語彙によって他と区別しないのが常である。 (軽蔑)
定理五三 精神は自己自身ならびに自己の活動能力を観想する時に喜びを感ずる。そして自己自身ならびに自己の活動能力をより判然と表象するに従ってそれだけ大なる喜びを感ずる。
証明 人間は自己の身体の変状ならびにその変状の観念を通してのみ自己自身を認識する(第二部定理一九および二三により)。ゆえに精神が自己自身を観想しうるということが起こるならば、まさにそのことによって精神はより大なる完全性に移行するものと想定される。言いかえれば(この部の定理一一の備考により)喜びに刺激されるものと想定される。そしてこの喜びは、精神が自己自身ならびに自己の活動能力をより判然と表象しうるに従ってそれだけ大なのである。Q・E・D・
系 この事びは人間がより多く他人から賞讃されることを表象するに従ってますます強められる。なぜなら彼がより多く他人から賞讃されることを表象するに従って、彼は他人が彼からそれだけ大なる喜びに〜〜しかも彼自身の観念を伴った喜びに〜〜刺激されることを表象する(この部の定理二九の備考により)。したがって(この部の定理二七により)彼自身は彼自身の観念を伴ったそれだけ大なる喜びに刺激される。Q・E・D・
定理五四 精神は自己の活動能力を定立することのみを表象しようと努める。
証明 精神の努力ないし能力は精神の本質そのものである(この部の定理七により)。ところが精神の本質は(それ自体で明らかなように)精神が有るところのもの、できるところのもののみを肯定し、精神が有らぬところのもの、できぬところのものを肯定しはしない。したがって精神は自己の活動能力を肯定ないし定立することのみを表象しようと努める。Q・E・D・
定理五五 精神は自己の無能力を表象する時、まさにそのことによって悲しみを感ずる。
証明 精神の本質は精神が有るところのもの・できるところのもののみを肯定する。あるいは自らの活動能力を定立することのみを表象することは精神の本性に属する(前定理により)。だから「精神が自己自身を観想する際にその無能力を表象する」と我々が言う時それは「精神がその活動能力を定立するある物を表象しようと努める際に精神のそうした努力が阻害される〜〜すなわち(この部の定理一一の備考により)精神が悲しみを感ずる」と言っているのにほかならないのである。Q・E・D・
系 この悲しみは人間が他人から非難されることを表象する場合にますます強められる。このことはこの部の定理五三の系と同様の仕方で証明される。
備考 我々の弱小の観念を伴ったこの悲しみは謙遜〔自劣感〕と呼ばれる。これに反して、我々自身を観想することから生ずる喜びは自己愛または自己満足と称される。そしてこの喜びは人間が自己の徳あるいは自分の活動能力を観想するたびに繰り返されるから、したがってまた各人は、好んで自分の業績を語ったり、自分の身体や精神のカを誇示したりすることになり、また人間は、このため、相互に不快を感じ合うことになる。さらにまたこの結果として、人間は本性上ねたみ深いということ(この部の定理二四の備考および定理三二の備考を見よ)、すなわち自分と同等の者の弱小を喜び、反対に自分と同等の者の徳を悲しむということになる。なぜなら、各人は自分の活動を表象するたびに喜びを感じ(この部の定理五三により)、しかもその活動がより多くの完全性を表現するのを表象するに従って、またその活動をより判然と表象するに従って、言いかえれば(第二部定理四〇の備考一で述べたことにより)、その活動をより多く他から区別して特殊な物として観想しうるに従って、それだけ大なる喜びを感ずる。ゆえに各人は自己自身を観想するにあたって、他人に認めないあることを自己の中に観想する時に最も多く喜ぶであろう。だが自分について認めることを人間あるいは動物の一般的観念に属するものとして見る時にはそれほどには喜ばないであろう。また反対に自分の活動が他人の活動と比較してより弱小であることを表象する時には悲しむであろう。そして彼はこの悲しみを(この部の定理二八により)除去しようと努めるであろう、しかも自分と同等の者の活動を曲げて解釈し、あるいは自分の活動をできるだけ修飾することによってそうしようとするであろう。
こんな次第で、人間は本性上憎しみおよびねたみに傾いていることが明らかである。さらにこの傾向を助長するものに教育がある。なぜなら、親はその子を単に名誉およびねたみの拍車によって徳へ駆るのを常とするからである。
しかしおそらくこうした疑念が残るかもしれない、〜〜我々は人間の徳を驚嘆してその人間を尊敬するということも稀でないではないかと。ゆえにこの疑念を除くため、私は次の系を付加するであろう。
系 何びとも自分と同等でない者をその徳のゆえにねたみはしない。
証明 ねたみは憎しみそのものである(この部の定理二四の備考を見よ)、あるいは(この部の定理一三の備考により)悲しみである。言いかえれば(この部の定理一一の備考により)人間の活動能力あるいは努力を阻害する感情である。ところが人間は(この部の定理九の備考により)与えられた自己の本性から生じうることのみをなそうと努めかつ欲する。ゆえに人間は他人の本性に特有であって自己の本性に無関係なような活動能力、あるいは(同じことだが)徳を自分に与えられることを欲しないであろう。ゆえに自分と同等でない者の中にある徳を観想することによって彼の欲望は阻害されえない。言いかえれば(この部の定理一一の備考により)そのことによって彼自身悲しみを感じえない。したがってまた彼はその者をねたみえないであろう。これに反して自分と同じ本性を有すると認められる同等の者に対してはねたむであろう。Q・E・D・
備考 それでさきにこの部の定理五二の備考において、我々はある人の聡明、強さなどを驚嘆するためにその人を尊敬すると言った場合、そのことは(その定理自身によって明らかなように)それらの徳がその人に特有であって我々の本性に共通したものでないことを我々が表象するゆえに起こるのである。したがって我々はその人をそれらの徳のゆえにねたみはしないであろう。あたかも樹木をその高きがゆえに、また獅子をその強きがゆえにねたまないと同様に。
定理五六 喜び、悲しみ、および欲望には、したがってまたそれらから合成されたすべての感情(例えば心情の動揺のごとき)、あるいはそれらから導き出されたすべての感情(例えば愛、憎しみ、希望、恐怖など)には、我々を刺激する対象の種類だけ多くの種類がある。
証明 喜びと悲しみ、したがってまたこれから合成されあるいはこれから導き出された感情は受動である(この部の定理一一の備考により)。ところで我々は非妥当な観念を有する限りにおいて必然的に働きを受け(この部の定理一により)、またそうした観念を有する限りにおいてのみ働きを受ける(この部の定理三により)。言いかえれば我々は(第二部定理四〇の備考(1or2?)を見よ)表象する限りにおいてのみ、すなわち(第二部定理一七ならびにその備考を見よ)我々の身体の本性および外部の物体の本性を含む刺激を受ける限りにおいてのみ必然的に働きを受ける。ゆえにおのおのの受動の本性は必然的に、我々を刺激する対象の本性を表現するような仕方で説明されなければならぬ。例えばAという対象から生ずる喜びはまさにこのAという対象の本性を含み、またBという対象から生ずる喜びはまさにこのBという対象の本性を含む。こうしてこれら二つの喜びの感情は、異なった本性を有する原因から生ずるゆえに、その本性を異にしている。同様にある対象から生ずる悲しみの感情もまた、他の原因から生ずる悲しみとはその本性を異にしている。このことは愛、憎しみ、希望、恐怖、心情の動揺、などについてもあてはまる。したがって喜び、悲しみ、愛、憎しみなどには、我々を刺激する対象の種類だけ多くの種類が必然的に存する。
さてまた欲望は、各人の本質ないし本性がその与えられたおのおのの状態においてあることをなすように決定されたと考えられる限り、その本質ないし本性そのものである(この部の定理九の備考を見よ)。ゆえに各人が外部の原因によってこのあるいはかの種類の喜び、悲しみ、愛、憎しみなどに刺激されるに応じて、言いかえれば彼の本性がこのあるいはかの状態に置かれるに応じて、彼の欲望もそれぞれ異なったものでなければならぬ。そして一つの欲望の本性は他の欲望の本性と、ちょうどそれぞれの欲望の生ずる源である諸感情が相互に異なっているだけ異ならねばならぬ。だから欲望には喜び、悲しみ、愛などの種類だけ多くの、したがってまた(すでに示したところにより)我々を刺激する対象の種類だけ多くの、種類が存する。Q・E・D・
備考 きわめて多様であるべき感情の種類(前定理により)の中でも特に著しいのは美味欲、飲酒欲、情欲、食欲および名誉欲である。これらは愛もしくは欲望の感情の本性をその関係する対象によって説明する概念にほかならない。なぜなら、我々は美味欲、飲酒欲、情欲、食欲および名誉欲を美食、飲酒、性交、富および名誉への過度の愛もしくは欲望としか解しないからである。なおこれらの感情は、単にその関係する対象のみによって相互に区別される限り、反対感情を有しない。なぜなら、通常我々が美味欲に対立させる節制、飲酒欲に対立させる禁酒、最後に情欲に対立させる貞操は、感情あるいは受動ではなくて、それらの感情を制御する精神の能力を表示するものだからである。
なおまた私は感情のその他の種類を一々ここに説明することはできない(なぜならその種類は対象の種類だけ多くあるから)。またたとえできたとしてもそれは必要でない。というのは我々の目標のためには、すなわち感情の力と感情に対する精神の能力を決定するためには、我々にとって、おのおのの感情に関する一般的定義をもつだけで十分だからである。たしかに、感情を制御し、抑圧する精神の能力がどのような種類のものであり、またどのように大きいものであるかを決定しうるためには、我々にとって、感情および精神の共通の諸特質を理解することで十分である。そこで、例えば子に対する愛と妻に対する愛との間に相違があるように、愛、憎しみ、欲望におけるこのおよびかの感情の間には大きな相違があるけれども、我々にとってはしかし、これらの相違を認識して諸感情の本性と起源をこれ以上深く究めることは必要でないのである。
定理五七 各個人の各感情は他の個人の感情と、ちょうど一方の人間の本質が他方の人間の本質と異なるだけ異なっている。 (ラカン)
証明 この定理は第二部定理一三の備考につづく補助定理三のあとの公理一から明白である。その公理を見よ。しかしそれにもかかわらず我々はこれを三つの根本的感情の定義から証明するであろう。
すべての感情は我々の与えたその定義から分かるように欲望、喜び、もしくは悲しみに関係する。ところで欲望は各人の本性ないし本質そのものである(この部の定理九の備考におけるその定義を見よ)。ゆえに各個人の欲望は他の個人の欲望と、ちょうど一方の人間の本性ないし本質が他方の人間の本質と異なるだけ相違している。
次に喜びと悲しみは各人が自己の有に固執しようとする能力ないし努力が増大しあるいは減少し、促進されあるいは阻害される受動である(この部の定理一一およびその備考により)。ところが我々は、自己の有に固執しようとする努力を、それが精神と身体に同時に関係する限り、衝動ないし欲望と解する(この部の定理九の備考を見よ)。ゆえに喜びおよび悲しみは外部の原因によって増大されあるいは減少され、促進されあるいは阻害される限りにおける欲望ないし衝動そのもの、言いかえれば(同じ備考により)各人の本性そのもの、である。したがって各人の喜びあるいは悲しみは他人の喜びあるいは悲しみと、やはりちょうど一方の人間の本性ないし本質が他方の人間の本質と異なるだけ相違する。 232
ゆえに各個人の各感情は他の個人の感情とちょうど云々。Q・E・D・
備考 この帰結として、いわゆる非理性的動物の感情(というのは我々は精神の起源を識った以上は動物が感覚を有することを決して疑いえない)は人間の感情と、ちょうど動物の本性が人間の本性と異なるだけ異なっているということになる。もちろん馬も人間も生殖への情欲に駆られるけれども、馬は馬らしい情欲に駆られ、人間は人間らしい情欲に駆られる。また同様に昆虫、魚、鳥の情欲および衝動はそれぞれ異なったものでなければならぬ。こうしておのおのの個体は自己の具有する本性に満足して生き、そしてそれを楽しんでいるのであるが、各自が満足しているこの生およびこの楽しみはその個体の観念あるいは精神にほかならない。したがってある個体の楽しみは他の個体の楽しみと、ちょうど一方の本質が他方の本質と異なるだけ本性上相違している。
最後に、前定理からの帰結として、例えば酔漢の捉われている楽しみと、哲学者の享受している楽しみとの間には、同様に少なからぬ相違があることになる。これもここでついでながら注意しておきたい。
働きを受ける限りにおける人間に関係する感情についてはこれだけにする。残るのは、働きをなす限りにおける人間に関係する感情について若干をつけ加えることだけである。
定理五八 受動である喜びおよび欲望のほかに、働きをなす〔能動的である〕限りにおける我々に関係する他の喜びおよび欲望の感情が存する。
証明 精神は自己自身および自己の活動能力を観想する時に喜びを感ずる(この部の定理五三により)。ところで精神は真のあるいは妥当な観念を有する時に必然的に自己自身を観想する(第二部定理四三により)。ところが精神は妥当な観念を有する(第二部定理四〇の備考二により)。ゆえに精神は妥当な観念を有する限りにおいても、言いかえれば(この部の定理一により)働きをなす限りにおいても、喜びを感ずる。
次に精神は明瞭判然たる観念を有する限りにおいても、また混乱した観念を有する限りにおいても、自己の有に固執しようと努める(この部の定理九により)。ところが我々はこの努力を欲望と解する(同じ定理の備考により)。ゆえに欲望は妥当な認識をなす限りにおいての我々、すなわち(この部の定理一により)働きをなす限りにおいての我々、にも関係する。Q・E・D・
定理五九 すべて、働きをなす限りにおいての精神に関係する感情には、喜びあるいは欲望に関する感情があるだけである。
証明 すべての感情は、我々が与えたその定義から分かるように、いずれも欲望、喜びあるいは悲しみに関係している。ところで悲しみとは精神の思惟能力を減少しあるいは阻害するものであると我々は解する(この部の定理一一およびその備考により)。したがって精神が悲しみを感ずる限り、精神の認識能力すなわち(この部の定理一により)その活動能力は減少されあるいは阻害される。したがって働く限りにおける精神にはいかなる悲しみの感情も帰せられえない。帰せられうるのはただ、働く限りにおける精神にも関係する(前定理により)喜びおよび欲望の感情のみである。Q・E・D・
備考 妥当に認識する限りにおける精神に関係する諸感情から生ずるすべての活動を、私は精神の強さに帰する。そしてこの精神の強さを勇気と寛仁とに分かつ。勇気とは各人が単に理性の指図に従って自己の有を維持しようと努める欲望であると私は解する。これに対して寛仁とは各人が単に理性の指図に従って他の人間を援助しかつこれと交わりを結ぼうと努める欲望であると解する。かくのごとく私は、行為者の利益のみを意図する行革を勇気に帰し、他人の利益をも意図する行為を寛仁に帰する。ゆえに節制、禁酒、危難の際の沈着などは勇気の種類であり、これに反して礼譲、温和などは寛仁の種類である。
これでもって私は三つの根本的感情〜〜すなわち欲望、喜び、悲しみ〜〜の合成から生ずる主要な感情および心情の動揺を説明し、これをその第一原因によって示したと信ずる。これからして、我々は外部の諸原因から多くの仕方で動かされること、また我々は旋風に翻弄される海浪のごとく自らの行末や運命を知らずに動揺することが明白になる。しかし私は単に主要な〈感情〉を示したとは言ったが、存在しうる心情の葛藤のすべてを示したとは言わなかった。というのは、我々は上と同じ方法を継続して、愛が後悔、侮蔑、恥辱などと結合することを容易に示しうるからである。のみならずまた、上に述べたことからして、もろもろの感情がこのように種々の仕方で相互に組み合わせられて、それから数えきれないほど多くの変種が生じうることは誰にも明瞭であると信ずる。しかし私の計画にとっては、単に主要な感情のみを数え上げただけで十分である。なぜなら、私が省略したその他の感情は、実用的価値というよりは好奇的価値を有するにすぎぬからである。
だがしかし、愛についてまだ注意することが残っている。それは次のようなことがしばしば起こることである。すなわち、我々が我々の衝動の対象物を享受する間に、身体はこの享受によって新しい状態に達し、この状態が身体を別様に決定し、事物に関する別な表象像が身体の中に喚起され、それと同時に精神は異なったことを表象し、異なったことを欲し始める、ということである。例えば、その味が我々を楽しませるのを常とするある物を我々が表象する時、我々はそれを享受すること、すなわち食うことを欲する。ところがそれ亨1うして享受する間に胃は充実して、身体は別様な状態に置かれる。だからもし身体がすでに別様な状態になっている際、同じ食物がなお現在するためにその表象像がまだ保存されており、したがってそれを食おうとする努力ないし欲望も保存されているとすれば、あの新しい身体の状態はこの欲望ないし努力と矛盾するであろう。したがってさきに我々の衝動の対象であった食物の現存が今は厭わしくなるであろう。これは我々が飽満および厭悪と呼ぶところのものである。
そのほかもろもろの感情において見られる身体の外的諸変状、例えば震え、青ざめ、すすり泣き、笑いなどは割愛した。それらは単に身体のみに関係し、精神とは何の関係も持たぬからである。 236
最後に、もろもろの感情の定義について若干の注意すべきことがある。だから私はここでそれらの定義を秩序だてて繰り返し、おのおのについて注意すべき事柄をその間に挿入していくであろう。
諸感情の定義
付録:感情の諸定義、
一、二、三、四、五、六、七、八、九、一〇、
一一、一二、一三、一四、一五、一六、一七、一八、一九、二〇、
二一、二二、二三、二四、二五、二六、二七、二八、二九、三〇、
三一、三二、三三、三四、三五、三六、三七、三八、三九、四〇、
四一、四二、四三、四四、四五、四六、四七、四八、
感情の総括的定義、第三部TOP、TOP☆
一 欲望とは、人間の本質が、与えられたそのおのおのの変状によってあることをなすように決定されると考えられる限りにおいて、人間の本質そのものである。
説明 我々はさきに、この部の定理九の備考において、欲望とは意識を伴った衝動であり、また衝動とは人間の本質が自己の維持に役立つことをなすように決定される限りにおいて人間の本質そのものであると言った。しかし私はまた同じ備考で、人間の衝動と欲望との間には実際には何の相違も認めないことを注意した。なぜなら、人間が自己の衝動を意識しようとしまいと衝動は同一にとどまるからである。そこで私は同語反復(タウトロギア)を犯すと見られないように、欲望を衝動によって説明することを好まなかった。むしろ欲望を、我々が衝動、意志、欲望または本能という名称をもって表示する人間本性の一切の努力をその中に包括するような仕方で定義しようとつとめた。もちろん私は「欲望とは人間の本質があることをなすように決定されると考えられる限りにおいて人間の本質そのものである」とだけも言いえたであろう。だがこの定義からは(第二部定理二三により)精神が自己の欲望ないし衝動を意識しうるということは出てこないであろう。ゆえにこの意識の原因を含めるために「与えられたそのおのおのの変状によって決定されると考えられる限りにおいて」と付加することが必要であったのである(同じ定理により)。なぜなら人間の本質の変状ということを我々はその本質のおのおのの状態と解するからである。その状態が生得的のものであろうと、〈外部から得られたものであろうと、〉またそれが思惟の属性のみによって考えられようと、延長の属性のみによって考えられようと、最後にまたそれが両属性に同時に関係しようと、変りはないのである。ゆえに私はここでこの欲望という名称を人間のあらゆる努力、あらゆる本能、あらゆる衝動、あらゆる意志作用と解する。こうしたものは同じ人間にあってもその人間の異なった状態に応じて異なり、また時には相反的でさえあり、この結果人間はそうしたものによってあちこちと引きずりまわされて自らどこへ向かうべきかを知らないというようなことにもなるのである。
二 喜びとは人間がより小なる完全性からより大なる完全性へ移行することである。
三 悲しみとは人間がより大なる完全性からより小なる完全性へ移行することである。
説明 私は移行と言う。なぜなら喜びは完全性そのものではないからである。すなわちもし人間がその移行する完全性を生まれながら持っていたとしたら、彼は喜びの感情なしにそれを所有したであろう。このことは喜びの感情と対立する悲しみの感情からいっそう明瞭になる。なぜなら、悲しみがより小なる完全性への移行に存し、より小なる完全性そのものではないことは誰しも否定しえない。人間はある程度の完全性を分有する限りにおいては悲しみを感じえないからである。また悲しみはより大なる完全性の欠乏に存するとも言えない。というのは欠乏は無であるが悲しみの感情は一個の積極的な状態だからである。ゆえに悲しみの感情はより小なる完全性へ移行する状態、言いかえれば人間の活動能力が減少しあるいは阻害される状態(この部の定理一一の備考を見よ)以外のものではありえない。
そのほか快活、快感、憂鬱、および苦痛の定義は省略する。これらは主として身体に関係し、また喜びもしくは悲しみの種類にすぎないからである。
四 驚異とはある事物の表象がきわめて特殊なものであってその他の表象と何の連結も有しないために、精神がその表象に縛られたままでいる状態である。定理五二およびその備考を見よ。
説明 我々は第二部定理一八の備考で、いかなる原因によって精神は一つの物の観想からただちに他の物の思惟に移るかを示した。それはすなわちそれらの物の表象像が相互に結合して一が他に継いで起こるように秩序づけられているからである。こうしたことは物の表象像が新奇なものである場合には考えられない。こういう場合、精神はむしろ他の原因によって他のものを思惟するように決定されるまではその物の観想に引きとどめられているであろう。こうして新奇な物の表象も、それ自体において見れば、その他の諸表象と同じ本性のものである。この理由によって私は驚異を感情の中に数えないし、また数える理由も認めない。なぜなら、精神がこのように他のものから離されて〔その物にだけとどまって〕いるのは、精神を他のものから引き離す積極的な原因から生ずるのではなくて、単に、ある物の観想をやめて他のものを思惟するように精神を決定するような原因が欠けているという事実からのみ生ずるのだからである。
このようにして私は(この部の定理一一の備考で注意したように)単に三つの根本的ないし基本的な感情を、すなわち喜び、悲しみ、欲望の三つの根本的感情を、認めるのみである。そして私が驚異について言及したのは、この三つの根本的感情から導き出されるある種の感情が我々の驚異する対象に関係する場合には別な名称をもって呼ばれるのが習いとなっているためにほかならない。私が軽蔑の定義をもここに付加することにしたのも、また同じ理由からである。
五 軽蔑とは精神が、ある事物の現在によって、その事物自身の中に在るものよりもむしろその事物自身の中にないものを表象するように動かされるほど、それほどわずかしか精神をとらえるところのない事物の表象である。この部の定理五二の備考を見よ。
尊敬および侮蔑の定義はここには割愛する。なぜなら、私の知る限り、いかなる名称の感情もこの二者から導き出されていないからである。
六 愛とは外部の原因の観念を伴った喜びである。
説明 この定義は愛の本質を十分明瞭に説明する。これに反して著作家たちのあの定義、愛とは愛する対象と結合しようとする愛する者の意志であるという定義は、愛の本質ではなくその一特質を表現するにすぎない。そしてこれらの著作家たちは、愛の本質を十分に洞察しなかったから、愛の特質に関しても明瞭な概念を持つことができなかったのであり、その結果として彼らの定義はいたって曖昧なものと人々から批判されている。しかしここに次のことを注意してもらわなければならぬ。意志によって愛する対象と結合しようとするのが愛する者における一特質であると私が言う場合、私は意志ということを精神の同意ないし考慮、あるいは自由決意と解せず(なぜなら第二部定理四八で証明したようにそうしたものは想像の産物にすぎないから)、また愛する対象が不在ならばこれと結合しようとし、それが存在するならばその現在に固執しようとする欲望であるとも解しない。なぜなら愛はこのあるいはかの欲望なしにも考えられうるからである。むしろ私は意志ということを愛する対象の現在のゆえに愛する当人が感ずる満足、それによって愛する当人の喜びが強化されあるいは少なくともはやくまれるその満足と解する。
七 憎しみとは外部の原因の観念を伴った悲しみである。
説明 ここで注意すべきことは前の定義の説明の中で述べたことから容易に看取される。そのほかこの部の定理一三の備考を見よ。
八 好感とは偶然によって喜びの原因となるようなある物の観念を伴った喜びである。
九 反撥とは偶然によって悲しみの原因となるようなある物の観念を伴った悲しみである。
この二つについてはこの部の定理一五の備考を見よ。
一〇 帰依とは我々の驚異する人に対する愛である。
説明 驚異は物の新奇性から生ずることを我々はこの部の定理五二で示した。だからもし我々が驚異するものをしばしば表象するということが起こるなら、我々はそれを驚異することをやめるであろう。したがって我々は帰依の感情が容易に単純な愛に変ることを知る。
一一 嘲弄とは我々の軽蔑するあることが我々の憎む物の中に存することを表象することから生ずる喜びである。
説明 我々が憎む物を軽蔑する限りにおいて我々はその物の存在を否定する(この部の定理五二の備考を見よ)、そしてその限りにおいて我々は(この部の定理二〇により)喜ぶ。しかし人が
その嘲弄するものを憎んでもいるということを我々は仮定しているのであるから、その帰結として、この喜びは基礎の固いものではないということになる。この部の定理四七の備考を見よ。
一二 希望とは我々がその結果について幾分疑っている未来あるいは過去の物の観念から生ずる不確かな喜びである。
一三 恐怖とは我々がその結果について幾分疑っている未来あるいは過去の物の観念から生ずる不確かな悲しみである。
この二つについてはこの部の定理一八の備考二を見よ。
説明 これらの定義からして、恐怖なき希望もないし希望なき恐怖もないということになる。なぜなら、希望に頼ってある物の結果につき疑っている人は、その未来の物の存在を排除するあることを表象し、かくてその限りにおいて悲しみ(この部の定理一九により)、したがって希望に頼っている間はその物が出現しないことを恐れもしている、と認められるからである。これに反して恐怖の中に在る人すなわち憎むある物の結果について疑う人は、同様にその物の存在を排除するあることを表象し、かくて喜び(この部の定理二〇により)、したがってその限りにおいていまだその物の出現しないことを希望してもいるのである。
一四 安堵とは疑いの原因が除去された未来あるいは過去の物の観念から生ずる喜びである。
一五 絶望とは疑いの原因が除去された未来あるいは過去の物の観念から生ずる悲しみである。
説明 こうして物の出現に対する疑いの原因が除去される時に希望から安堵が生じ、恐怖から絶望が生ずる。この原因の除去は、人間が過去あるいは未来の物をあたかもそこにあるかのように表象してこれを現在するものとして観想することによっても起こるし、あるいは人間が彼に疑いを惹き起こさせた事物の存在を排除するような他のことを表象することによっても起こるのである。というのは、たとえ我々は個々の物の結果について決して確実でありえないとしても(第二部定理三一の系により)、しかし我々がそれらの物の結果について疑わないということは起こりうる。我々の示したように、ある物について疑わないということとその物について確実性を有するということは別問題だからである(第二部定理四九の備考を見よ)。したがって我々は過去あるいは未来の物の表象像によってあたかも現在の物の表象像によるのと同じ喜びあるいは悲しみの感情に刺激されることが起こりうる。これはこの部の定理一八で証明したところである。その定理ならびにその二つの備考を見よ。
一六 歓喜とは恐怖に反して起こった過去の物の観念を伴った喜びである。
一七 落胆とは希望に反して起こった過去の物の観念を伴った悲しみである。
一八 憐憫とは我々が自分と同類であると表象する他人の上に起こった害悪の観念を伴った悲しみである。この部の定理二二の備考および定理二七の備考を見よ。
説明 憐憫と同情との間には、おそらく、憐憫は個々の感情を眼中に置いたものであり同情は憐憫の習性を眼中に置いたものであるという以外には何の相違もないように思われる。
一九 好意とは他人に親切をなした人に対する愛である。
二〇 憤慨とは他人に害悪を加えた人に対する憎しみである。
説明 この二つの名称が通常の用法では別の意味を有することを私は知っている。しかし私の意図するところは、言葉の意味を説明することではなくて、事物の本性を説明しかつ事物を一定の言葉で〜〜その通常の意味が私の用いたいと思う意味とひどくはくい違わないような言葉で表示することにある。このことは一度注意しておけば十分であろう。なおこの二つの感情の原因についてはこの部の定理二七の系一および定理二二の備考を見よ。
二ー 買いかぶりとはある人について、愛のゆえに、正当以上に感ずることである。
二二 見くびりとはある人について、憎しみのゆえに、正当以下に感ずることである。
説明 こうして買いかぶりは愛の一結果もしくは一特質であり、見くびりは憎しみの一結果あるいは一特質である。したがって買いかぶりとは愛するものについて正当以上に感ずるように人間を動かす限りにおける愛であると定義し、また反対に、見くびりとは憎むものを正当以下に感ずるように人間を動かす限りにおける憎しみであると定義することもできる。この二つについてはこの部の定理二六の備考を見よ。
二三 ねたみとは他人の幸福を悲しみまた反対に他人の不幸を喜ぶように人間を動かす限りにおける憎しみである。
説明 ねたみには通常同情が対立させられる。したがって同情を言葉のもともとの意味から離れて次のように定義することができる。
二四 同情とは他人の幸福を喜びまた反対に他人の不幸を悲しむように人間を動かす限りにおける愛である。
説明 なお、ねたみについてはこの部の定理二四の備考および定理三二の備考を見よ。 244
以上は外部の原因(それ自身による原因たると偶然による原因たるとを問わない)の観念を伴った喜びおよび悲しみの感情である。これから私は内部の原因の観念を伴った他の喜びおよび悲しみの感情に移る。
二五 自己満足とは人間が自己自身および自己の活動能力を観想することから生ずる喜びである。
二六 謙遜〔自劣感〕とは人間が自己の無能力あるいは弱小を観想することから生ずる悲しみである。
説明 自己満足は、我々が自分の活動能力を観想することから生ずる喜びであると解される限りにおいて謙遜と対置される。しかしそれは、我々が精神の自由な決意によってなしたと信ずるある行為の観念を伴った喜びであると解される限りにおいては、次のように定義される後悔と対置される。
二七 後悔とは我々が精神の自由な決意によってなしたと信ずるある行為の観念を伴った悲しみである。
説明 我々はこの三つの感情の原因をこの部の定理五一の備考および定理五三、五四、五五ならびにその備考において示した。また精神の自由な決意については第二部定理三五の備考を見よ。
しかしなおここに注意すべきことがある。それは習慣上から「悪い」と呼ばれているすべての行為に悲しみが伴い、「正しい」と言われているすべての行為に喜びが伴うのは不思議ではないということである。実際このことは、前に述べた事柄から容易に理解される通り、主として教育に由来しているのである。すなわち親は「悪い」と呼ばれている行為を非難し、子をそのためにしばしば叱責し、また反対に「正しい」と言われている行為を推奨し、賞讃し、これによって悲しみの感情が前者と結合し喜びの感情が後者と結合するようにしたのである。このことはまた経験そのものによっても確かめられる。何となれば習慣および宗教はすべての人において同一ではない。むしろ反対に、ある人にとって神聖なことが他の人にとって涜神的であり、またある人にとって端正なことが他の人にとって非礼だからである。このようにして各人はその教育されたところに従ってある行為を悔いもしまた誇りもする。
二八 高慢とは自己への愛のため自分について正当以上に感ずることである。
説明 だから高慢と買いかぶりとの相違は、後者は外部の対象に関係するが高慢は自己を正当以上に感ずる当人に関係するという点にある。なおまた買いかぶりが愛の一結果あるいは一特質であるように、高慢は自己愛の一結果あるいは一特質である。このゆえに高慢とは自分について正当以上に感ずるように人間を動かす限りにおける自己愛あるいは自己満足であると定義することもできる(この部の定理二六の備考を見よ)。この感情には反対感情が存しない。なぜなら、何びとも自分への憎しみのため自分について正当以下に感ずることはないからである。実に人間は、自分がこのことあるいはかのことができないと表象する限りにおいても自分について正当以下に感じているのではない。というのは、人間が自分にできないと表象する事柄はすべてそう表象せざるをえないのであって、この表象によって彼は自分ができないと表象することを実際になしえないようなある状態に置かれる。すなわち自分はこのことあるいはかのことができないと表象する間は彼はそれをなすように決定されないのであり、したがってまたその間はそれをなすことが彼には不可能でもあるのである。
しかし単に他人の意見のみに関する事柄を眼中に置くなら、我々は、人間が自分自身について正当以下に感ずるということもありうることを考えうるであろう。例えばある人が悲しみをもって自己の弱小を観想し、他の人々が少しも彼を軽蔑しようと思わないのに自分がすべての人から軽蔑されるように表象するということはありうるのである。そのほか人間は不確実な未来に関して現在の瞬間にある事を自分自身について否定する場合に、自分について正当以下に感ずることができる。例えば自分は何も確実なことを考ええないし、また悪いこと賎(いや)しむべきことしか欲しあるいはなすことができないなどという場合のごときである。最後にある人が自分と同等の他の人々のあえてなすようなことも、恥辱に対する過度の恐れからあえてしないのを我々が見る時に、その人が自分自身について正当以下に感じていると我々は言うことができる。そこで我々はこうした感情を高慢と対置させることができる。この感情を私は自卑と名づけるであろう。すなわち自己満足から高慢が生ずるように、謙遜から自卑が生ずるのである。したがって我々はこれを次のように定義する。
二九 自卑とは悲しみのために自分について正当以下に感ずることである。
説明 しかし我々はしばしば高慢に謙遜を対置させるのが慣(なら)いである。けれどもその場合には両感情の本性よりもむしろ結果を眼中に置いているのである。すなわち過度に自らを誇り(この部の定理三〇の備考を見よ)、自分の美点と他人の欠点のみを語り、すべての人の上に立とうと欲し、また最後に、自分よりはるかに地位の高い人々に見るような威儀と服装とをもって立ち現われる人、そうした人を我々は高慢な人と呼ぶのが常である。これと反対に、しばしば赤面し、自分の欠点を告白して他人の美点を語り、すべての人に譲歩し、最後にまた、頭を垂れて歩み、かつ身を飾ることを嫌う人、そうした人を我々は謙遜な人と呼んでいる。
なおこれらの感情、すなわち謙遜と自卑とはきわめて稀である。なぜなら人間本性は、それ自体で見れば、できるだけそうした感情に反抗するからである(この部の定理一三および五四を見よ)。こんなわけできわめて自卑的でありきわめて謙遜であると見られる人々は大抵の場合きわめて名誉欲が強くきわめてねたみ深いものである。
三〇 名誉とは他人から賞讃されると我々の表象する我々のある行為の観念を伴った喜びである。
三一 恥辱とは他人から非難されると我々の表象する我々のある行為の観念を伴った悲しみである。
説明 この二つについてはこの部の定理三〇の備考を見よ。
だが恥辱と羞恥との相違をここに注意しなくてはならぬ。すなわち恥辱とは我々の恥じる行為に伴う悲しみである。これに対して羞恥とは恥辱に対する恐怖ないし臆病であって、醜い行ないを犯さぬように人間を抑制させるものである。羞恥には通常無恥が対置されるが、無恥は、適当な場所で示すだろうように、実は感情ではない。しかし一般に感情の諸名称は(すでに注意したように)その本性を表わすよりもその日常の慣用に関係しているのである。 248
これでもって喜びおよび悲しみの感情に関する予定の説明を終えた。だからこれから欲望に関係する感情へ移る。
三二 思慕とは、その物を想起することによってそれを所有しようとする欲望があおられ、また同時にその物の存在を排除する他の事物を想起することによってその欲望が阻まれる、そうしたある物への欲望ないし衝動である。
説明 我々がある物を想起するなら、すでにしばしば述べたように、我々はそのために、その物が現在した場合と同様の感情をもってその物を観想するように促される。しかしこの傾向ないし努力は、我々の精神がはっきり醒めている間は、大抵、我々の想起する物の存在を排除するような事物の表象像によって阻まれる。だから我々が自分をある種類の喜びに刺激する物を思い出す時、そのために我々は同じ喜びの感情をもってそれを現在するものとして観想するように努める。だがこの努力はその物の存在を排除する事物の想起によってただちに阻まれる。ゆえに思慕は実際は我々の憎む物の不在から生ずるあの喜び(これについてはこの部の定理四七の備考を見よ)に対立するある種の悲しみなのである。しかし思慕なる名称は欲望に関係するように見えるので、そのゆえに私はこの感情を欲望の感情に数える。
三三 競争心とは、他の人がある物に対する欲望を有することを我々が表象することによって我々の中に生ずる同じ物に対する欲望である。
説明 他人が逃げるのを見て逃げ、あるいは他人が恐れるのを見て恐れ、あるいはまたある人がその手を焼いたのを見てそのため自分の手を引っこめて、あたかも自分の手が焼かれたかのような動作をする人、そうした人を目して我々は、他人の感情を模倣するとは言うが他人と競争するとは言わないであろう。これは競争には模倣の場合と異なった原因があることを我々が指摘しうるためではない。ただ端正であり、有益であり、あるいは愉快であると判断される事柄を模倣する人だけを競争すると呼ぶ慣わしになっているためである。
なお競争心の原因についてはこの部の定理二七およびその備考を見よ。だがねたみがなぜ多くの場合この感情と結びつくかについてはこの部の定理三二およびその備考を見よ。
三四 感謝あるいは謝恩とは我々に対して愛の感情から親切をなした人に対して親切を報いようと努める欲望あるいは同様な愛の情熱である。
この部の定理三九および定理四一の備考を見よ。
三五 慈悲心とは我々の憐む人に対して親切をなそうとする欲望である。
この部の定理二七の備考を見よ。(系3備考)
三六 怒りとは我々の憎む人に対して、憎み心から、害悪を加えるように我々を駆る欲望である。この部の定理三九を見よ。
三七 復讐心とは我々に対して、憎しみの感情から害悪を加えた人に対して、同じ憎み返しの心から、害悪を加えるように我々を駆る欲望である。
この部の定理四〇の系二ならびにその備考を見よ。
三八 残忍あるいは苛酷とは我々の愛する者あるいは憐む者に対して、害悪を加えるように我々を駆る欲望である。 250
〔この部の定理四一の系の備考を見よ〕
説明 残忍には温和が対置される。しかし温和は受動ではなく、人間が怒りおよび復讐を抑制するような精神の能力である。
三九 臆病とは我々の恐れるより大なる害悪をより小なる害悪によって避けようとする欲望である。
この部の定理三九の備考を見よ。
四〇 大胆とは同輩が立ち向かうことを恐れるような危険を冒してある事をなすようにある人を駆る欲望である。
四一 小心とは同輩があえて立ち向かうこと辞さないような危険を恐れて、自己の欲望を阻まれる人間について言われる。
説明 そこで小心とは大抵の人が通常恐れないようなある害悪に対する恐怖にほかならない。だから私は小心を欲望の感情に数えない。それにもかかわらず私がここで説明しようとしたのは、欲望を眼中に置く限り、小心は大胆の感情と事実対立するからである。
四二 恐慌とはある害悪を避けようとする欲望がその恐れる害悪に対する驚きのため阻まれる人間について言われる。
説明 そこで恐慌とは小心の一種である。しかし恐慌は二重の恐れから生ずるゆえに、我々はこれをもっと適切に次のように定義することができる。すなわち恐慌とは人間をして迫っている害悪を排除することができないようなふうに驚愕させあるいは動揺させる恐怖であると。「驚愕させる」と私が言うのは、その事惑を排除しようとする彼の欲望が驚きのため阻止されると解される限りにおいてである。また「動揺させる」というのは、この欲望が、同様にその人を悩ましている他の害悪に対する恐れのため阻止され、その結果彼は二つの害悪のいずれを避けるべきかを知らないと考えられる限りにおいてである。
こうしたことについてはこの部の定理三九の備考および定理五二の備考を見よ。なお小心および大胆についてはこの部の定理五一の備考を見よ。
四三 鄭重あるいは礼譲とは人々に気に入ることをなし・人々に気に入らぬことを控えようとする欲望である。
四四 名誉欲とは名誉に対する過度の欲望である。
説明 名誉欲はすべての感情をはぐくみかつ強化する欲望である(この部の定理二七および三一により)。したがってこの感情は、ほとんど征服できないものである。なぜなら、人間は何らかの感情に囚われている間は必ず同時に名誉欲に囚われているからである。キケロは言う、「最もすぐれた人々も特に名誉欲には支配される。哲学者は名誉の軽蔑すべきことを記した書物にすら自己の名を署する云々」。
四五 美味欲とは美味に対する過度の欲望あるいは愛である。
四六 飲酒欲とは飲酒に対する過度の欲望および愛である。
四七 貪欲とは富に対する過度の欲望および愛である。
四八 情欲とは性交に対する欲望および愛である。 252
説明 性交に対するこの欲望は適度であっても適度でなくても情欲と呼ばれるのが常である。
なおこれら五つの感情は(この部の定理五六の備考で注意したように)反対感情を有しない。なぜなら礼譲〔鄭重〕は名誉欲の一種であるし(これについてはこの部の定義二九の備考を見よ)、また節制、禁酒および貞操が精神の能力を示すものであって受動を示すものでないことはこれまたすでに注意したところである。もちろん貪欲な人間、名誉欲の強い人間、あるいは臆病な人間が、食事、飲酒および性交の過度を供しむということは有りうるにしても、それだからといって食欲、名誉欲および臆病が美味欲、飲酒欲、もしくは情欲の反対ではない。なぜなら食欲者は一般に、他人のところでなら飲食をむさぼることを願っている。また名誉欲の強い者〔すなわち人々に賞讃されようとのみしている者〕は露見しないという望みさえあればどんなことにも節制を守らないであろうし、またもし彼が飲酒家たちや好色家たちの間に生活するならば、まさに人の気に入ろうとのみするその性情のゆえに、ますます多くこの同じ悪行に傾くであろう。最後に臆病者は、もともと自らの欲しないことをなすものである。たとえ彼が死を逃れるために自己の財宝を海中に投じようとも、彼の食欲家たることには変りがないし、また好色家〔としての彼〕がその情欲をほしいままにすることができないのを悲しむとしても、彼はそのゆえに好色家たることを失いはしないのである。一般的に言えば、これらの感情は美味、飲酒などに対する個々の行為に関係するよりはそれへの衝動そのもの、それへの愛そのものに関係する。したがってこれらの感情に対置されうるものは、我々がのちに述べるであろう寛仁と勇気のみである。
嫉妬およびその他の心情の動揺の定義はここでは省略する。なぜならそれらの感情は、これまで定義した諸感情の合成から生ずるものであるし、またその多くは特に名称をもっていないからである。このことは、実生活のためにはこれらのものをただ種類として知るだけで十分であることを物語っている。
なおまた我々が説明した諸感情の定義からして、そのすべての感情は欲望、喜びあるいは悲しみから生ずること、あるいはむしろすべての感情はこの三者以外の何ものでもないこと、そしてこれら三者のおのおのはその異なった関係およびその異なった外的特徴に応じて、それぞれ異なった名称で呼ばれる償いになっていることが明らかになる。
今もし我々がこれら三つの根本的感情およびさきに精神の本性について述べた事柄に注意するなら、我々は、もっぱら精神に関係する限りにおける諸感情を次のように定義しうるであろう。
感情の総括的定義
精神の受動状態(アニミ・パテマ)と言われる感情は、ある混乱した観念〜〜精神がそれによって自己の身体あるいはその一部分について、以前より大なるあるいは以前より小なる存在力を肯定するような、また精神自身がそれの現在によってあるものを他のものよりいっそう多く思惟するように決定されるような、ある混乱した観念である。
説明 私はまず感情あるいは精神の受動は「ある混乱した観念」であると言う。なぜなら、すでに我々の示したように、精神は非妥当な観念あるいは混乱した観念を有する限りにおいてのみ働きを受けるからである(この部の定理三を見よ)。 254
次に私は「精神がそれによって自己の身体あるいはその一部分について以前より大なるあるいは以前より小なる存在力を肯定する」という。なぜなら諸物体について我々の有するすべての観念は外部の物体の本性よりも我々の身体の現実的状態をより多く表示するものであるが(第二部定理一六の系二により)、特に感情の形相を構成する観念は、身体あるいはその一部分の活動能力あるいは存在力が増大しあるいは減少し、促進されあるいは阻害されるにつれて、身体あるいはその一部分が呈する状態を表示ないし表現しなければならぬからである。
しかし注意すべきことは、私が「以前より大なるあるいは以前より小なる存在力」と言っているのは、精神が身体の現在の状態を過去の状態と比較するという意味ではなく、むしろ感情の形相を構成する観念が身体について以前より大なるあるいは以前より小なる実在性を実際に含むようなあるものを肯定するという意味だということである。そして精神の本質は精神が自己の身体の現実的存在を肯定する点に存するし(第二部定理一一および一三により)、また我々は完全性ということを物の本質そのものと解するから、したがって精神が自己の身体あるいはその一部分について、以前より大なるあるいは以前より小なる実在性を含むようなあるものを肯定するごとに、精神はより大なるあるいはより小なる完全性に移行することになる。だから私がさきに、精神の思惟能力が増大しあるいは減少するとよく言ったのも、精神が自己の身体あるいはその一部分について、以前に肯定したよりもより大なるあるいはより小なる実在性を表現するような観念を形成する、という意味にほかならなかったのである。なぜなら、観念の価値とその現実的な思惟能力は、対象の価値によって評価されるからである。
最後に私が「精神自身がそれの現在によってあるものを他のものよりいっそう多く思惟するように決定される」と付加したのは、定義の始めの部分に説明されている喜びおよび悲しみの本性のほかに、欲望の本性も表現しようとしたためであった。
第三部 終り
序言、
定義、一、二、三、四、五、六、七、八、公理
定理、
一、二、三、四、五、六、七、八、九、一〇、一一、一二、一三、一四、一五、一六、一七、一八、一九、二〇、
二一、二二、二三、二四、二五、二六、二七、二八、二九、三〇、三一、三二、三三、三四、三五、三六、三七、三八、三九、四〇、
四一、四二、四三、四四、四五、四六、四七、四八、四九、五〇、五一、五二、五三、五四、五五、五六、五七、五八、五九、六〇、
六一、六二、六三、六四、六五、六六、六七、六八、六九、七〇、七一、七二、七三
付録、
一、二、三、四、五、六、七、八、九、一〇、一一、一二、一三、一四、一五、一六、一七、一八、一九、二〇、
二一、二二、二三、二四、二五、二六、二七、二八、二九、三〇、三一、三二、第四部TOP、
TOP☆
人間の隷属あるいは感情の力について
序 言
感情を統御し抑制する上の人間の無能力を、私は隷属と呼ぶ。なぜなら、感情に支配される人間は自己の権利のもとにはなくて運命の権利のもとにあり、自らより善きものを見ながらより悪しきものに従うようにしばしば強制されるほど運命の力に左右されるからである。私はこの部でこの原因を究め、さらに感情がいかなる善あるいは悪を有するかを説明することにした。しかしこれを始める前にあらかじめ完全性と不完全性、および善と悪について少しく語ってみたい。 (善きもの〜、オヴィディウス)
ある物を製作しようと企てそしてそれを完成した人は誰でも、その物が完成された〔完全になった〕と言うであろう。これはその作品の製作者自身ばかりでなく、その製作者の精神ないし意図を正しく知っている者、あるいは知っていると信ずる者はみなそう言うであろう。例えば、ある人がある作品(それがまだ仕上げられていないと仮定する)を見て、その作品の製作者の意図が家を建てることにあると知るならば、その人はその家が完成されていない〔不完全である〕と言うであろうし、これに反して、その作品に製作者の与えようと企てた目的が遂げられたのを見るや否や、それは完成された〔完全になった〕と言うであろう。しかしある人がいまだかつて他に類例を見たことのないようなある作品を見、かつその製作者の精神をも知らない場合には、その人はもちろんその作品が完成されているか完成されていないかを知ることができないであろう。こういうのが完全および不完全という言葉の最初の意味であったように思われる。
しかし人間が一般的観念を形成して家、建築物、塔などの型を案出し、事物について他の型よりもある型を選択することを始めてからというものは、各人はあらかじめ同種の物について形成した一般的観念と一致するように見える物を完全と呼び、これに反してあらかじめ把握した型とあまり一致しないように見えるものを、たとえ製作者の意見によればまったく完成したものであっても、不完全と呼ぶようになった。
もろもろの自然物、すなわち人間の手で製作されたのでないものについても、人々が通常完全とか不完全とか名づけるのはこれと同じ理由からであるように見える。すなわち人間は、自然物についても、人工物についてと同様に一般的観念を形成し、これをいわばそれらの物の型と見なし、しかも彼らの信ずるところでは、これを自然(自然は何ごとも目的なしにはしないと彼らは思っている)が考慮し、型として自己の前に置くというのである。このようにして彼らはあらかじめ同種の物について把握した型とあまり一致しないある物が自然の中に生ずるのを見る時に、自然自身が失敗しあるいはあやまちを犯して、その物を不完全にしておいたと信ずるのである。
これで見ると、人間が自然物を完全だとか不完全だとか呼び慣れているのは、物の真の認識に基づくよりも偏見に基づいていることが分かる。実際、我々は自然が目的のために働くものでないことを第一部の付録で明らかにした。つまり我々が神あるいは自然と呼ぶあの永遠・無限の実有は、それが存在するのと同じ必然性をもって働きをなすのである。事実、神がその存在するのと同じ本性の必然性によって働きをなすことは我々のすでに示したところである(第一部定理一六)。したがって神あるいは自然が何ゆえに働きをなすかの理由ないし原因と、神あるいは自然が何ゆえに存在するかの理由ないし原因とは同一である。ゆえに神は、何ら目的のために存在するのではないように、また何ら目的のために働くものでもない。すなわち、その存在と同様に、その活動もまた何の原理ないし目的も有しないのである。 (神即自然) 9
ところで目的原因と呼ばれている原因は、人間の衝動が何らかの物の原理ないし第一原因と見られる限りにおいて人間の衝動そのものにほかならない。例えば「居住する」ということがこれこれの家屋の目的原因であったと我々が言うなら、たしかにそれは、人間が屋内生活の快適さを表象した結果、家屋を建築しようとする衝動を有した、という意味にほかならない。ゆえにここに目的原因として見られている「居住する」ということは、この特定の衝動にほかならないのであり、そしてこの衝動は実際に起成原因なのである。この原因が同時にまた第一原因と見られるのは、人間というものが一般に自己の衝動の原因を知らないからである。すなわち、すでにしばしば述べたように、人間は自己の行為および衝動を意識しているが、自分をある物に衝動を感ずるように決定する諸原因は知らないからである。
なおまた自然が時に失敗しあるいはあやまちを犯して不完全な物を産出するという世人の主張を、私は、第一部の付録において論じたもろもろの虚構的な考えの一つに数える。 10
このようにして、完全および不完全とは実は単に思惟の様態にすぎない。すなわち我々が同じ種あるいは同じ類に属する個体を相互に比較することによって作り出すのを常とする概念にすぎない。私が先に(第二部定義六)実在性と完全性とを同一のものと解すると言ったのもこのためである。すなわち我々は自然における一切の個体を最も普遍的と呼ばれる一つの類に、言いかえれば自然におけるありとあらゆる個物に帰せられる有という概念に、還元するのを常とする、こうして自然における個体をこの類に還元して相互に比較し、そしてある物が他の物よりも多くの有性あるいは実在性を有することを認める限り、その限りにおいて我々はある物を他の物よりも完全であると言い、またそれらの物に限界、終局、無能力などのような否定を含むあるものを帰する限りその限りにおいて我々はそれらの物を不完全と呼ぶのである。これを不完全と呼ぶのは、それらの物は我々が完全と呼ぶ物と同じようには我々の精神を動かさないからであって、それらの物自身に本来属すべき何かが欠けているとか、自然があやまちを犯したとかいうためではない。なぜなら、物の本性には、その起成原因の本性の必然性から生ずるもの以外のいかなるものも属さないし、また起成原因の本性の必然性から生ずるものはすべて必然的に生ずるからである。
善および悪に関して言えば、それらもまた、事物がそれ自体で見られる限り、事物における何の積極的なものも表示せず、思惟の様態、すなわち我々が事物を相互に比較することによって形成する概念、にほかならない。なぜなら、同一事物が同時に善および悪ならびに善悪いずれにも属さない中間物でもありうるからである。例えば、音楽は憂鬱の人には善く、悲傷の人には悪しく、聾者には善くも悪しくもない。事情はかくのごとくであるけれどもしかし、我々はこれらの言葉を保存しなくてはならぬ。なぜなら、我々は、眺めるべき人間本性の型として、人間の観念を形成することを欲しているので、これらの言葉を前に述べたような意味において保存するのは我々にとって有益であるからである。
そこで私は以下において、善とは我々が我々の形成する人間本性の型にますます近づく手段になることを我々が確知するものであると解するであろう。これに反して、悪とは我々がその型に一致するようになるのに妨げとなることを我々が確知するものであると解するであろう。さらに我々は、人間がこの型により多くあるいはより少なく近づく限りにおいて、その人間をより完全あるいはより不完全と呼ぶであろう。というのは、私が「ある人がより小なる完全性からより大なる完全性へ移る、あるいは反対により大なる完全性からより小なる完全性へ移る」と言う場合、それは「彼が一つの本質ないし形相から他の本質ないし形相に変化する」という意味で言っているのではなく(なぜなら例えば馬が人間に変化するならそれは昆虫に変化した場合と同様に馬でなくなってしまうから)、単に「彼の活動能力〜〜彼の本性を活動能力と解する限りにおいて〜〜が増大しあるいは減少すると考えられる」という意味で言っているのであって、この点は特に注意しなければならぬ。 (完全性)
最後に私は、一般的には、完全性を、すでに述べたように、実在性のことと解するであろう。言いかえれば、おのおのの物がある仕方で存在し作用する限りにおいて、その物の本質のことと解するであろう。そしてこの際その物の持続ということは考慮に入れない。なぜなら、いかなる個物も、それがより長い時間のあいだ存在に固執したゆえをもってより完全だとは言われえないからである。事物の本質には何ら一定の存在時間が含まれていない以上、事物の持続はその本質からは決定されえないのだから。むしろおのおのの事物は、より多く完全であってもより少なく完全であっても、それが存在し始めたのと同一の力をもって常に存在に固執することができるであろう。したがってこの点においてはすべての物が同等なのである。
定 義
一 善とは、それが我々に有益であることを我々が確知するもの、と解する。
二 これに反して、悪とは、我々がある善を所有するのに妨げとなることを我々が確知するもの、と解する。
この二つについては前の序言の終りを見よ。
三 我々が単に個物の本質のみに注意する場合に、その存在を必然的に定立しあるいはその存在を必然的に排除する何ものをも発見しない限り、私はその個物を偶然的と呼ぶ。
四 その個物が産出されなければならぬ原因に我々が注意する場合に、その原因がそれを産出するように決定されているか否かを我々が知らぬ限り、私はその同じ個物を可能的と呼ぶ。
第一部定理三三の備考一においては可能的と偶然的との間に何の差異も設けなかった。これはそこではこの二つを精密に区別する必要がなかったからである。
五 相反する感情ということを、私は以下において、人間を異なった方向へ引きずる感情のことと解するであろう。これは共に愛の種類である美味欲と食欲のごとくたとえ同じ類に属するものであってもかまわない。この場合は本性上相反するのではなく偶然によって相反するのである。
六 未来・現在・および過去の物に対する感情ということを私がどう解するかは第三部定理一八の備考一および二において説明した。そこを見よ。
しかしここになお注意しなければならぬことがある。それは我々は、時間的距離を、空間的距離の場合と同様、ある一定の限界までしか判然と表象しえないことである。すなわち、我々から二百フィート以上も離れているすべての対象、あるいはその距離が我々の判然と表象する距離以上に我々の居る場所から隔たっているすべての対象を、我々は我々から等しい距離で隔たりかつ同一の平面にあるかのように表象するのを常とするが、これと同様に、その出現の時間が我々の通常判然と表象する間隔よりもいっそう長い間隔で現在から隔たっていると表象されるすべての対象を、我々は現在から等しい時間的距離で隔たっているように表象し、これをいわば一時点に帰するのである。
七 我々をしてあることをなさしめる目的なるものを私は衝動と解する。
八 徳と能力とを同一のものと私は解する。言いかえれば(第三部定理七により)、人間について言われる徳とは、人間が自己の本性の法則のみによって理解されるようなあることをなす能力を有する限りにおいて、人間の本質ないし本性そのもののことである。
公 理
自然の中にはそれよりもっと有力でもっと強大な他の物が存在しないようないかなる個物もない。どんな物が与えられても、その与えられた物を破壊しうるもっと有力な他の物が常に存在する。
定理一 誤った観念が有するいかなる積極的なものも、真なるものが真であるというだけでは、真なるものの現在によって除去されはしない。
証明 誤謬〔虚偽〕は単に非妥当な観念が含む認識の欠乏のみに存する(第二部定理三五により)、そしてそれらの観念はそれを誤りといわしめるような積極的なものは何も有しない(第二部定理三三により)。むしろ反対にそれらの観念は神に関する限り真である(第二部定理三二により)。だからもし誤った観念が有する積極的なものが、真なるものが真であるというだけで異なるものの現在によって除去されるとしたら、真なる観念が自分自身によって除去されることになろう。これは(第三部定理四により)不条理である。ゆえに誤った観念が有するいかなる積極的なものも云々。Q・E・D・
備考 この定理は第二部定理一六の系二からいっそう明瞭に理解される。すなわち表象は、外部の物体の本性よりもより多く人間身体の現在的状態を〜〜しかも判然とではなく、混乱して〜〜表示する観念である。精神が誤ると言われるのはこれから起こる。例えば我々が太陽を観る場合、それが我々から約二百フィート隔たっていると表象する。我々は太陽の真の距離を知らない間はこのことについて誤っている。しかし我々がその距離を知ったとすれば、誤謬は除去されるが、表象は、言いかえれば太陽の観念〜〜身体が太陽から刺激される限りにおいてのみ太陽の本性を表示するような〜〜は除去されない。したがって我々は、たとえ太陽の真の距離を知っても、太陽が依然として我々の近くにあるように表象するであろう。なぜなら、第二部定理三五の備考で述べたように、我々が太陽をこれほど近いように表象するのは、太陽の真の距離を知らないからではなく、精神は身体が太陽から刺激される限りにおいて太陽の大きさを考えるからである。同様に、太陽の光線が水面に落ちてそこから我々の目に反射して来る場合、我々は太陽の真の場所を知っていながらも、それがあたかも水中にあるかのように表象する。精神を誤らしめるその他の表象についても同じことが言われるのであって、それらの表象は、身体の自然的状態を表示していようと身体の活動能力の増大ないし減少を表示していようと、真なるものに矛盾せずまた真なるものの現在によって消失しない。なるほど、我々が誤ってある害悪を恐れる場合に、真の報告を聞いて恐怖が消失するということはありうる。しかし反対に、我々が確実に生起する尊意を恐れる場合、誤った報告を聞いて恐怖が同様に消失する、ということも等しく起こりうる。したがって表象は、異なるものが真であるというだけで真なるものの現在によって消失するのではなく、むしろ、第二部定理一七で示したように、我々の表象する事物の現在する存在を排除するより強力な他の表象が現われることによって消失するのである。
定理二 我々は、他の物なしに自分自身だけで考えられることができないような自然の一部分である限りにおいて働きを受ける。
証明 我々がその部分的原因にすぎないようなあることが我々の中に生ずる場合(第三部定義二により)、言いかえれば(第三部定義一により)我々の本性の法則のみからは導き出されえないようなあることが我々の中に生ずる場合、我々は働きを受けると言われる。ゆえに我々は、他の物なしに自分自身だけで考えられることができないような自然の一部である限りにおいて働きを受ける。Q・E・D・
定理三 人間が存在に固執する力は制限されており、外部の原因の力によって無限に凌駕される。
証明 この部の公理から明らかである。なぜなら、ある人間が存在するや否やそれよりもっと有力な他のあるもの、例えばAが存在し、またAが存在するや否やA自身よりもっと有力な他のもの、例えばBが存在する。このようにして無限に進む。したがって、人間の能力は他の物の能力によって規定され、外部の原因の力によって無限に凌駕される。Q・E・D・
定理四 人間が自然の一部分でないということは、不可能であり、また人間が単に自己の本性のみによって理解されうるような変化、自分がその妥当な原因であるような変化だけしか受けないということも不可能である。
証明 個物が、したがってまた人間が、自己の有を維持する能力は神あるいは自然の能力そのものであるが(第一部定理二四の系により)、しかしそれは無限なる限りにおける神あるいは自然の能力そのものではなく、人間の現実的本質によって説明されうる限りにおける神あるいは自然の能力そのものである(第三部定理七により)。ゆえに人間の能力はそれが彼の現実的本質によって説明される限り、神あるいは自然の無限なる能力の、言いかえれば(第一部定理三四により)神あるいは自然の無限なる本質の、一部分である。これが第一の点であった。 (神即自然、人間の能力)
次にもし人間が単に彼自身の本性のみによって理解されうるような変化だけしか受けないということが可能であるとしたら、人間は(第三部定理四および六により)滅びえずして必然的に常に存在することになるであろう。そしてこのことは有限な能力を有する原因からかあるいは無限な能力を有する原因から起こらなければならぬであろう。すなわち単なる人間の能力によるか〜〜この場合は人間は外部の原因から生じうる他の諸変化を退ける力を有することになろう〜〜あるいは自然の無限なる能力によるか〜〜この場合は人間が自己の保存に有効な変化だけしか受けないようなふうに自然が一切の個物を導くことになろう〜〜そのどちらかでなければならぬであろう。ところが始めのことは不条理である(前定理による。その定理の証明は普遍的であってすべての個物に適用されうるから)。ゆえに人間が単に彼自身の本性のみによって理解されうるような変化だけしか受けず・したがってまた(すでに示したように)必然的に常に存在するということが可能だとしたら、それは神の無限なる能力から起こらなければならぬであろう。したがって(第一部定理一六により)ある人間に発現したと見られる限りにおける神の本性の必然性からして、延長および思惟の属性のもとに考えられた全自然の秩序が導き出されなければならぬであろう。
この帰結として(第一部定理二ーにより)人間は無限であることになろう。しかしこれは(この証明の始めの部分により)不条理である。ゆえに自らがその妥当な原因であるような変化だけしか人間が受けないということは不可能なのである。Q・E・D・
系 この帰結として、人間は必然的に常に受動に隷属し、また自然の共通の秩序に従い、これに服従し、かつこれに対して自然が要求するだけ順応する、ということになる。
定理五 おのおのの受動の力および発展、ならびにそれの存在への固執は、我々が存在に固執しようと努める能力によっては規定されずに、我々の能力と比較された外部の原因の力によって規定される。
証明 受動の本質は単に我々の本質のみによって説明されることができぬ(第三部定義一および二により)。言いかえれば(第三部定理七により)受動の力は我々が存在に固執しようと努める能力によっては規定されず、むしろ(第二部定理一六において示したように)必然的に、我々の能力と比較された外部の原因の力によって規定されなければならぬ。Q・E・D・
定理六 ある受動ないし感情の力は人間のその他の働きないし能力を凌駕することができ、かくてそのような感情は執拗に人間につきまとうことになる。
証明 おのおのの受動の力および発展ならびにそれの存在への固執は我々の能力と比較された外部の原因の力によって規定される(前定理により)。したがって(この部の定理三により)その力は人間の能力を凌駕することができ、云々。Q・E・D・
定理七 感情はそれと反対のかつそれよりも強力な感情によってでなくては抑制されることも除去されることもできない。
証明 感情とは、精神に関する限り、ある観念〜〜精神がそれによって自己の身体につき以前より大なるあるいは以前より小なる存在力を肯定するある観念である(第三部の終りにある感情の総括的定義により)。したがって、精神がある感情に捉われる場合、それとともに身体は自己の活動能力を増大しあるいは減少するある変状に移る。なおまた身体のこの変状は(この部の定理五により)自己の有に固執する力をその原因から受ける。ゆえにこの変状は、それと反対の(第三部定理五により)かつそれよりも強力な(この部の公理により)変状を身体に起こさせるある物体的原因(第二部定理六により)によるのでなくては抑制されることも除去されることもできない。
そしてこれにつれて(第二部定理一二により)精神は前のよりも強力なかつ前のと反対のある変状の観念に刺激されるであろう。言いかえれば(感情の総括的定義により)精神は前のよりも強力なかつ前のと反対のある感情に、すなわち前の感情の存在を排除ないし除去する凍る感情に刺激されるであろう。これで見ると感情はそれと反対のかつそれよりも強力なある感情によってでなくては除去されることも抑制されることもできない。Q・E・D・
系 感情は、精神に関する限り、我々に起こっている身体的変状と反対のかつそれよりも強力なある変状の観念によってでなくては抑制されることも除去されることもできない。なぜなら、我々を支配している感情は、それよりも強力でかつそれと反対のある感情によってでなくては抑制されることも除去されることもできないのであるが(前定理により)、それはつまり(感情の総括的定義により)我々に起こっている身体的変状よりも強力でかつそれと反対のある変状の観念によってでなくては抑制されることも除去されることもできないというのと同じことだからである。
定理八 善および悪の認識は、我々に意識された限りにおける喜びあるいは悲しみの感情にほかならない。
証明 我々は我々の存在の維持に役立ちあるいは妨げるものを(この部の定義一および二により)、言いかえれば(第三部定理七により)我々の活動能力を増大しあるいは減少し、促進しあるいは阻害するものを善あるいは悪と呼んでいる。我々はこうしてある物が我々を喜びあるいは悲しみに刺激することを知る限りにおいてそのものを善あるいは悪と呼ぶのである(喜びおよび悲しみの定義による。第三部定理一一の備考におけるその定義を見よ)。したがって善および悪の認識は、喜びあるいは悲しみの感情そのものから必然的に生ずる喜びあるいは悲しみの観念にほかならない(第二部定理二二により)。ところでこの観念は、精神が身体と合一しているのと同じ仕方で感情と合一している(第二部定理二一により)。言いかえれば(同定理の備考で示したように)この観念は感情自身と、すなわち(感情の総括的定義により)身体的変状の観念と、実は単なる概念によって区別されるのみである。ゆえに善および悪の認識は、我々に意識された限りにおける感情そのものにほかならない。Q・E・D・
定理九 感情は、その原因が現在我々の前にあると表象される場合には、それが我々の前にないと表象される場合よりも強力である。
証明 表象とはある観念〜〜精神がそれによって物を現在するとして観想するある観念である(第二部定理一七の備考におけるその定義を見よ)。この観念はしかし外部の物の本性よりもより多く人間身体の状態を表示する(第二部定理一六の系二により)。ゆえに感情は(感情の総括的定義により)身体の状態を表示する限りにおける表象である。ところが表象は(第二部定理一七により)外部の物の現在的存在を排除する何ものも我々が表象しない間はより活撥である。ゆえに感情もまた、その原因が現在我々の前にあると表象される場合には、それが我々の前にないと表象される場合に比べより活撥である。あるいはより強力である、。Q・E・D・
備考 私がさきに、第三部定理一八において、我々は未来あるいは過去の物の表象像によって、あたかも、我々の表象する物が現在している場合と同じ感情に刺激されると言った時に、単にその物の表象像を眼中に置く限りにおいてそのことが真であることを私は特に注意した。表象像は我々がその物を現在するとして表象しようとしまいと、同一本性を有するからである。しかし未来の物の現実的存在を排除する他の物が現在するとして観想される場合には、その表象像がより弱くなることを私は否定したわけではなかった。そのことを私があの時注意することをしなかったのは、感情の力についてはこの部に入ってから論ずることに決めていたからである。 22
系 未来あるいは過去の物の表象像、言いかえれば現在のことは度外視して未来あるいは過去の時に関連させて観想する物の表象像は、その他の事情が等しければ、現在の物の表象像よりも弱い。したがって未来あるいは過去の物に対する感情は、その他の事情が等しければ、現在の物に対する感情よりも弱い。
定理一〇 我々は、速やかに出現するだろうと表象する未来の物に対しては、その出現の時が現在からより遠く隔たっていると表象する場合よりもより強く刺激される。また我々は、まだ遠く過ぎ去らないと表象する物の想起によっては、それがすでに遠く過ぎ去ったと表象する場合よりもより強く刺激される。
証明 なぜなら、物が速やかに出現するであろう、あるいはまだ遠く過ぎ去っていない、と表象する限り、我々はまさにそのことによってその物の未来における出現の時間が現在からより遠く隔たっている、あるいはその物がすでに遠く過ぎ去った、と表象する場合よりも、その物の現在を排除することのより少ないあるものを表象する(それ自体で明らかなように)。したがって(前定理により)我々はその限りにおいてその物に対してより強く刺激されるであろう。Q・E・D・
備考 この部の定義六に対してなした注意からの帰結として、我々は、表象によって決定しえないほど長い時間的間隔で現在から隔たっている対象に対しては、たとえそれらの対象が相互同士長い時間的間隔で隔たっていることを知る場合でも、同程度の弱い感情に刺激される、ということになる。
定理一一 我々が必然的として表象する物に対する感情は、その他の事情が等しければ、可能的あるいは偶然的なもの、すなわち必然的でないものに対する感情よりも強い。
証明 我々はある物を必然的であると表象する限り、その物の存在を肯定し、これに反してある物を必然的でないと表象する限り、その物の存在を否定する(第一部定理三三の備考により)。
それゆえ(この部の定理九により)必然的な物に対する感情は、その他の事情が等しければ、必然的でない物に対する感情よりも強い。Q・E・D・
定理一二 現在に存在しないことが知られているがなお可能的として表象される物に対する感情は、その他の事情が等しければ、偶然的なものに対する感情よりも強い。
証明 我々は、ある物を偶然的として表象する限り、その物の存在を定立する他の物の表象像に刺激されることがない(この部の定義三により)。むしろ反対に(仮定に従い)、その現在的存在を排除するあるものを表象する。ところが我々は物を未来において可能的であると表象する限り、その物の存在を定立するあるものを(この部の定義四により)、言いかえれば(第三部定理一八により)希望あるいは恐怖をあおるあるものを表象する。したがって可能的な物に対する感情の方がより強いのである。Q・E・D・
系 現在に存在しないことが知られているがなお偶然的として表象される物に対する感情は、我々がその物を現在我々の前に在ると表象する場合よりもはるかに弱い。
証明 現在に存在すると我々の表象する物に対する感情は、我々がその物を未来的として表象する場合よりも強いし(この部の定理九の系により)、また我々がその未来の時を現在からはるかに遠く隔たっていると表象する場合よりはさらにいっそう強い(この部の定理一〇により)。このように、その存在する時が現在から遠く隔たっていると我々の表象する物に対する感情は我々がその物を現在的として表象する場合よりもはるかに弱いのであるが、それにもかかわらずその感情は(前定理により)我々がその物を偶然的として表象する場合よりも強い。したがって偶然的な物に対する感情は、我々がその物を現在我々の前に在ると表象する場合よりもはるかに弱いのである。Q・E・D・
定理一三 現在に存在しないことが知られている偶然的な物に対する感情は、その他の事情が等しければ、過去の物に対する感情よりも弱い。
証明 我々はある物を偶然的として表象する限り、その物の存在を定立する他の物の表象像に刺激されることがない(この部の定義三により)。むしろ反対に(仮定に従い)、その物の現在的存在を排除するあるものを表象する。ところが我々がその物を過去の時と関連させて表象する限り、その限りにおいて我々は、その物を想起させるあるもの、すなわちその物の表象像を喚起するあるもの(第二部定理二八ならびにその備考を見よ)、を表象するものと想定される。したがってその限りにおいて我々はその物をあたかも現在的であるかのごとく観想するようにさせられる(第二部定理一七の系により)。ゆえに(この部の定理九により)現在に存在しないことが知られている偶然的な物に対する感情は、その他の事情が等しければ、過去の物に対する感情よりも弱いであろう。Q・E・D・
定理一四 善および悪の真の認識は、それが真であるというだけでは、いかなる感情も抑制しえない。ただそれが感情として見られる限りにおいてのみ感情を抑制しうる。
証明 感情とはある観念〜〜精神がそれによって自己の身体につき以前より大なるあるいは以前より小なる存在力を肯定するある観念である(感情の総括的定義により)。このゆえに(この部の定理一により)感情は真なるものの現在によって除去されうるいかなる積極的なものも有しない。したがって善および悪の真の認識は、それが真であるというだけでは、いかなる感情も抑制しえない。しかしそれが感情である限り(この部の定理八を見よ)、その限りにおいてのみそれは感情を抑制しうるであろう、もしそれが抑制されるべき感情よりも強力であるならば(この部の定理七により)。Q・E・D・
定理一五 善および悪の真の認識から生ずる欲望は、我々の捉われる諸感情から生ずる多くの他の欲望によって圧倒されあるいは抑制されることができる。
証明 善および悪の真の認識が感情である限り(この部の定理八により)それから必然的に欲望が生ずる(感情の定義一により)。この欲望はそれを生ずる感情がより大なるに従ってそれだけ大である(第三部定理三七により)。ところがこの欲望は(仮定により)我々がある事を真に認識することから生ずるのであるから、それは、我々が働きをなす限りにおいて我々の中に起こるものである(第三部定理三により)。ゆえにそれは単に我々の本質のみによって理解されなければならぬ(第三部定義二により)。したがってまた(第三部定理七により)その力および発展は単に人間の能力のみによって規定されなければならぬ。次に我々の捉われる諸感情から生ずる欲望も、同様にそれらの感情がより強烈であるに従ってそれだけ大である。ところでその欲望のカおよび発展は(この部の定理五により)外部の原因のカによって規定されなけ
ればならぬ
。この
外部の原因の力は、我々の能力と比較すれば、我々の能力を無限に凌駕する(この部の定理三により)。ゆえにこぅした感情から生ずる欲望は、善および悪の真の認識から生ずる欲望よりも強烈であることができ、したがって(この部の定理七により)それを抑制しあるいは圧倒しうるであろう。Q・E・D・
定理一六 善および悪の認識が未来に関係する限り、その認識から生ずる欲望は、現在において快を与える物に対する欲望によっていっそう容易に抑制あるいは圧倒されうる。
証明 我々が未来的として表象する物に対する感情は、現在の物に対する感情よりも弱い(この部の定理九の系により)。ところが善および悪の真の認識から生ずる欲望は、たとえその認識が現在善なる物に関する場合でさえも、何らかの激しい欲望によって圧倒あるいは抑制されうる(前定理による。その定理の証明は普遍的なものであるから)。ゆえにこうした認識が未来に関する限り、その認識から生ずる欲望は、現在において快を与える物に対する欲望によっていっそう容易に抑制あるいは圧倒されうるであろう。Q・E・D・
定理一七 善および悪の真の認識が偶然的な物に関係する限り、その認識から生ずる欲望は、現在の物に対する欲望によってさらにいっそう抑制されうる。
証明 この定理は前定理と同じ仕方でこの部の定理一二の系から証明される。
備考 これでもって私は、なぜ人間が真の理性によってよりもむしろ意見(オビニオ)によって動かされるか、またなぜ善および悪の真の認識が心情の動揺を惹き起こしかつしばしばあらゆる種類の官能欲に征服されるかの原因を示したと信ずる。かの詩人の言葉はここから来ている、「我はより善きものを見てこれを可とす、されど我はより悪しきものに従う」。伝道者〔ソロモン〕が「知識を増す者は憂患を増す」と言っているのも同じことを念頭に置いたものと思われる。 (オヴィディウス、ソロモン)
しかし私がこうしたことを言うのは、それから無知が知にまさるとか、感情の制御において愚者と智者の間に差別がないとかいうようなことを結論しようと思ってではない。むしろ、理性が感情の制御において何をなしえ、また何をなしえざるかを決定しうるには、我々の本性の能力とともにその無能力をも知ることが必要だからである。それに私はこの部では単に人間の無能力のみについて論ずることにすると言っておいた。なぜなら、感情に対する理性の能力については、別に論ずる予定なのであるから。
定理一八 喜びから生ずる欲望は、その他の事情が等しければ、悲しみから生ずる欲望よりも強力である。
証明 欲望は人間の本質そのものである(感情の定義一により)。言いかえればそれは(第三部定理七により)人間が自己の有に固執しようと努める努力である。ゆえに喜びから生ずる欲望は喜びの感情自身によって促進されあるいは増大される(喜びの定義による。第三部定理一一の備考におけるその定義を見よ)。しかしこれに反して悲しみから生ずる欲望は悲しみの感情自身によって減少されあるいは阻害される(同じ備考により)。したがって喜びから生ずる欲望の力は人間のカと同時に外部の原因のカによって規定され、これに反して悲しみから生ずる欲望のカは人間の力のみによって規定されなければならぬ。このゆえに前者は後者よりも強力である。Q・E・D・
備考 以上少数の命題をもって私は人間の無能力および無常の原因、ならびに人間が理性の命令に従わないことの原因を説明した。今や残るのは、理性が我々に何を命ずるか、またいかなる感情が人間理性の規則と一致し、いかなる感情がこれと反対するかを示すことである。しかしこれを詳細にわが幾何学的秩序に従って証明し始める前に、私は理性の指図そのものをここにあらかじめ簡単に示しておきたい。私の考えるところをより容易に人々に理解してもらえるように。
理性は自然に反する何ごとをも要求せぬゆえ、したがって理性は、各人が自己自身を愛すること、自己の利益・自己の真の利益を求めること、また人間をより大なる完全性へ真に導くすべてのものを欲求すること〜〜一般的に言えば各人が自己の有をできる限り維持するように努めること、を要求する。これは実に全体がその部分よりも大であるというのと同様に必然的に真である(第三部定理四を見よ)。
次に徳は(この部の定義八により)自己固有の本性の法則に従って行動することにほかならないし、また各人は自己固有の本性の法則に従ってのみ自己の有を維持しようと努めるのであるから(第三部定理七により)、この帰結として
第一に、徳の基礎は自己固有の有を維持しようとする努力そのものであり、また幸福は人間が自己の有を継持しうることに存する、ということになる。 (幸福)
第二に、徳はそれ自身のために求められるべきであって徳よりも価値あるもの、徳よりも我々に有益なもの、それのために徳が追求されなければならぬようなもの、そうしたものは決して存在しない、ということになる。
最後に第三に、自殺する人々は無力な精神の持ち主であって自己の本性と矛盾する外部の諸原因にまったく征服されるものである、ということになる。
さらに第二部要請四から分かるとおり、我々は自己の有を維持するのに我々の外部にある何ものも必要としないというようなわけにはいかぬし、また我々は我々の外部にある物と何の交渉も持たないで生活するというようなわけにもいかない。なおまた我々の精神を顧みると、もし精神が単独で存在し自己自身以外の何ものも認識しないとしたら、我々の知性はたしかにより不完全なものになっていたであろう。これで見ると、我々の外部には、我々に有益なもの、そのゆえに我々の追求に値するものが沢山存するわけである。そのうちで我々の本性とまったく一致するものほど価値あるものは考えられることができない。なぜなら、例えばまったく本性を同じくする二つの個体が相互に結合するなら、単独の個体よりも二倍の能力を有する一個体が構成されるからである。
このゆえに、人間にとっては人間ほど有益なものはない。あえて言うが、人間が自己の有を維持するためには、すべての人間がすべての点において一致すること、すなわちすべての人間の精神と身体が一緒になってあたかも一精神一身体を構成し、すべての人間がともどもにできるだけ自己の有の推持に努め、すべての人間がともどもにすべての人間に共通な利益を求めること、そうしたこと以上に価値ある何ごとも望みえないのである。
この結論として、理性に支配される人間、言いかえれば理性の導きに従って自己の利益を求める人間は、他の人々のためにも欲しないようないかなることも自分のために欲求することがなく、したがって彼らは公平で誠実で端正な人間であるということになる。
以上は私がもっと詳細な秩序で証明し始める前にここに簡単に示そうとした理性の指図である。これを私がここに示した理由は、「各人は自己の利益を求めるべきである」というこの原則が徳および道義の基礎ではなくて不徳義の基礎であると信ずる人々の注意をできるだけ私に引きつけたいためである。今私は事態がこれと反対であることを簡単に示したのだから、ひきつづき私はこれをこれまでやってきたのと同じ方法で証明していくことにする。 (スミス?)
定理一九 各人はその善あるいは悪と判断するものを自己の本性の法則に従って必然的に欲求しあるいは忌避する。
証明 善および悪の認識は(この部の定理八により)我々に意識された限りにおける喜びあるいは悲しみの感情そのものである。したがって(第三部定理二八により)各人はその善と判断するものを必然的に欲求し、反対に悪と判断するものを必然的に忌避する。ところがこの衝動〔欲求〕は人間の本質ないし本性そのものにほかならない(衝動の定義による。それについては第三部定理九の備考ならびに感情の定義一を見よ)。ゆえに各人はその善あるいは悪と判断するものを自己の本性の法則のみに従って必然的に云々。Q・E・D・
定理二〇 各人は自己の利益を追求することに、言いかえれば自己の有を維持することに、より多く努めかつより多くそれをなしうるに従ってそれだけ有徳である。また反対に、各人は自己の利益を、言いかえれば自己の有を維持することを放棄する限りにおいて無力である。
証明 徳とは人間の能力そのものであり、そしてそれは人間の本質にほかならない(この部の定義八により)、言いかえればそれは人間が自己の有に固執しようと努める努力にのみ存する(第三部定理七
により)。ゆえに各人は自己の有を維持することにより多く努めかつより多くこれをなしうるに従ってそれだけ有徳であり、したがってまた(第三部定理四および六により)人は自己の有を維持することを放棄する限りにおいて無力である。Q・E・D・
備考 それゆえに何びとも自己の本性に反する外部の原因に強制されるのでなくては自己の利益の追求を、すなわち自己の有の維持を放棄しはしない。あえて言うが、何びとも自己の本性の必然性によって食を拒否したり自殺したりするものでなく、そうするのは外部の原因に強制されてするのである。この自殺は種々の仕方で起こりうる。例えばある人は、偶然剣を握ったその手を、他人からねじ返されて自分自身の心臓にその剣を向けるように強制されて自殺する。あるいはセネカのように暴君の命令によって自らの血管を切開するように強制されて、すなわち、より大なる害悪をより小なる害悪によって避けようと欲して自殺する。最後にあるいはまた、隠れた外部の原因が彼の表象力を狂わせ彼の身体を変化させてその身体が前とは反対な別種の本性を〜〜それについて精神の中に何の観念も存しえないような(第三部定理一〇により)そうした本性を〜〜帯びるようにさせられることによって自殺する。これに反して人間が自己の本性の必然性によって自分が存在しないように努めたり、他の形相に変ずるように努めたりすることは、無から有が生ずるのと同様に不可能である。これは誰でも少しく考えれば分かることである。 (セネカ、自殺、本性)
定理二一 何びとも、生存し行動しかつ生活すること、言いかえれば現実に存在すること、を欲することなしには幸福に生存し善く行動しかつ善く生活することを欲することができない。
証明 この定理の証明、あるいはむしろこの事実そのものはそれ自体で明白であり、また欲望の定義からも明らかである。なぜなら、幸福にあるいは善く生活し・行動しなどなどの欲望は(感情の定義一により)人間の本質そのもの、言いかえれば(第三部定理七により)各人が自己の有を維持しようと努める努力そのものだからである。ゆえに何びとも生存し行動し云々。Q・E・D・
定理二二 いかなる徳もこれ(すなわち自己保存の努力)よりさきに考えられることができない。
証明 自己保存の努力は物の本質そのものである(第三部定理七により)。そこでもし何らかの徳がこれ、すなわちこの努力よりさきに考えられうるとしたら、その結果(この部の定義八により)、物の本質がその本質自身よりもさきに考えられることになるであろう。このことは(それ自体で明らかなように)不条理である。ゆえにいかなる徳も云々。Q・E・D・
系 自己保存の努力は徳の第一かつ唯一の基礎である。なぜならこの原理よりさきには他のいかなる原理も考えられることができず(前定理により)、またこの原理なしには(この部の定理二一により)いかなる徳も考えられえないからである。
定理二三 人間が非妥当な観念を有することによってある行動をするように決定される限りは、有徳的に働くとは本来言われえない。彼が認識〔妥当な認識〕することによって行動するように決定される限りにおいてのみそう言われる。
証明 人間が非妥当な観念を有することによって行動するように決定される限り、その限り彼は働きを受ける(第三部定理一により)、言いかえれば、その限り彼は自己の本質のみによって知覚されえないある事(第三部定義一および二により)、すなわち(この部の定義八により)自己の徳から起こらないある事をなすのである。これに反して彼が認識〔妥当な認識〕することによって行動するように決定される限りその限り彼は働きをなす(同じく第三部定理二により)、言いかえればその限り彼は(第三部定義二により)自己の本質のみによって知覚されうるある事、すなわち(この部の定義八により)自己の徳から妥当に起こるある事をなすのである。Q・E・D・
定理二四 真に有徳的に働くとは、我々においては、理性の導きに従って行動し、生活し、自己の有を推持する(この三つは同じことを意味する)こと、しかもそれを自己の利益を求める原理に基づいてすること、にほかならない。
証明 真に有徳的に働くとは自己固有の本性の法則に従って働くことにほかならない(この部の定義八により)。ところが我々は認識〔妥当な認識〕する限りにおいてのみ働きをなす(第三部定理三により)。ゆえに有徳的に働くとは、我々においては、理性の導きに従って行動し、生活し、自己の有を推持すること、しかもそれを(この部の定理二二の系により)自己の利益を求める原理に基づいてすること、にほかならない。Q・E・D・
定理二五 何びとも他の物のために自己の有を維持しようと努めはしない。
証明 おのおのの物が自己の有に固執しようと努める努力は単にその物自身の本質によって規定される(第三部定理七により)。この本質が与えられただけでそれから各自が自己の有の維持に努力するということが必然的に起こるのであり(第三部定理六により)、それは他の物の本質に促されて起こるのではない。その上、この定理はこの部の定理二二の系からも明らかである。なぜなら、もし人間が他の物のために自己の有を維持しようと努めるとしたら、その他の物こそ徳の第一の基礎となるであろう(それ自体で明白なように)。このことは(今引用した系により)不条理である。ゆえに何びとも他の物のために云々。Q・E・D・
定理二六 我々が理性に基づいてなすすべての努力は認識することにのみ向けられる。そして精神は、理性を用いる限り、認識に役立つものしか自己に有益であると判断しない。
証明 自己保存の努力は物自身の本質にほかならない(第三部定理七により)。そして物はこのようなものとして存在する限り、存在に固執する力(第三部定理六により)、ならびにその与えられた本性から必然的に生ずることをなす力を有すると考えられる(第三部定理九の備考における衝動の定義を見よ)。ところで理性の本質は明瞭判然と認識する限りにおける我々の精神にほかならない(第二部定理四〇備考二におけるその定義を見よ)。ゆえに(第二部定理四〇により)我々が理性に基づいてなすすべての努力は認識することにのみ向けられる。次に精神のこの努力〜〜理性的に思惟する限りにおける精神が自己の有を維持しようと努めるこの努力は、認識することにのみ向けられるのであるからには(この定理の始めの部分により)、認識しようとするこの努力は(この部の定理二二の系により)徳の第一かつ唯一の基礎である。そして我々は何か他の目的のために物を認識しようと努めはしないであろう(この部の定理二五により)。むしろ反対に、精神は理性的に思惟する限り、認識に役立つものしか自己に善であると考えることができないであろう(この部の定義一により)。Q・E・D・ 36
定理二七 我々は、真に認識に役立つものあるいは我々の認識を妨害しうるもののみが善あるいは悪であることを確知する。
証明 精神は理性的に思惟する限り認識以外のことを追求せずまた認識に役立つものしか自己に有益であると判断しない(前定理により)。ところが精神は妥当な観念を有する限りにおいてのみ、言いかえれば(第二部定理四〇の備考によって同じことだが)理性的に思惟する限りにおいてのみ物について確実でありうる(第二部定理四一および四三による。なお後者の備考も見よ)。ゆえに我々は真に認識に役立つもののみが善であることを確知し、また反対に我々の認識を妨害しうるもののみが悪であることを確知する。Q・E・D・ (確知)
定理二八 精神の最高の善は神の認識であり、また精神の最高の徳は神を認識することである。 (善、認識、徳)
証明 精神が認識しうる最高のものは神、言いかえればそれなしには何ものも在りえずまた考えられえない(第一部定理一五により)絶対に無限なる実有(第一部定義六により)である。したがって(この部の定理二六および二七により)精神の最高の利益すなわち(この部の定義一により)最高の善は神の認識である。次に精神は認識する限りにおいてのみ働きをなし(第三部定理一および三により)、また精神はもともと、その限りにおいてのみ(この部の定理二三により)有徳的に働くと言われうる。したがって精神の本来の徳は認識することである。ところが精神が認識しうる最高のものは神である(我々が今示したように)。ゆえに精神の最高の徳は神を理解することあるいは認識することである。Q・E・D・
定理二九 その本性が我々の本性とまったく異なる個物は我々の活動能力を促進することも阻害することもできない。また一般に、いかなる物も、もしそれが我々とある共通点を有しなければ我々にとって善でも悪でもありえない。
証明 おのおのの個物の能力、したがって(第二部定理一〇の系により)人間が存在し・作用する人間の能力もまた、他の個物によってのみ決定されるのであるが(第一部定理二八により)、しかしその個物の本性は人間の本性が考えられるのと同一の属性によって考えられるものでなければならぬ(第二部定理六により)。ゆえに我々の活動能力は、これをどのように解しても、我々とある共通点を有する他の個物の力によって決定され、したがってまた促進あるいは阻害されうるのであって、その本性が我々の本性とまったく異なるような物の力によっては促進あるいは阻害されることができない。次に我々が善あるいは悪と呼ぶのは喜びあるいは悲しみの原因であるもの(この部の定理八により)、言いかえれば(第三部定理一一の備考により)我々の活動能力を増大あるいは減少し、促進あるいは阻害するもののことであるから、したがってその本性が我々の本性とまったく異なるような物は我々にとって善でも悪でもありえないのである。Q・E・D・
定理三〇 いかなる物も、それが我々の本性と共通に有するものによって悪であることはできない。それが我々にとって悪である限り、その限りにおいてそれは我々と対立的である。 38
証明 我々が悪と呼んでいるのは悲しみの原因であるもの(この部の定理八により)、言いかえれば我々の活動能力を減少ないし阻害するもの(悲しみの定義による。第三部定理一一の備考におけるその定義を見よ)のことである。ゆえにもしある物が、我々と共通に有するものによって我々にとって悪であるとしたら、その物はまさに我々と共通に有するものを減少ないし阻害しうることになろう。これは(第三部定理四により)不条理である。ゆえにいかなる物もそれが我々と共通に有するものによって我々に悪であることはできない。むしろ逆に、それが悪である限り、言いかえれば(いま我々が示したように)それが我々の活動能力を減少ないし阻害しうる限り、その限りにおいてそれは(第三部定理五により)我々と対立的である。Q・E・D・
定理三一 物は我々の本性と一致する限り必然的に善である。
証明 何となれば、物は我々の本性と一致する限り悪でありえない(前定理により)。ゆえにそれは必然的に善であるか、それとも善悪いずれにも属さない中間物であるかであろう。後者すなわち善でも悪でもない場合は、その物の本性から(この部の公理三により ?→第一部公理三)我々の本性の維持に役立つ何ものも、言いかえれば(仮定により)その物自身の本性の維持に役立つ何ものも生じないことになろう。しかしこれは不条理である(第三部定理六により)。ゆえに物は我々の本性と一致する限り必然的に善であるであろう。Q・E・D・
系 この帰結として、物は我々の本性とより多く一致するに従ってそれだけ我々にとって有益あるいは善であり、また逆に物は我々にとってより有益であるに従って我々の本性とそれだけ多く一致する、ということになる。なぜなら、物は我々の本性と一致しない限り必然的に我々の本性と異なり、あるいは我々の本性と対立的であるであろう。もし我々の本性と異なるなら、それは(この部の定理二九により)善でも悪でもありえないであろう。もし対立的であるなら、それは我々の本性と一致するものにも対立的であり、言いかえれば(前定理により)善と対立的であり、すなわち悪であるであろう。ゆえに何ものも我々の本性と一致する限りにおいてでなくては善であることができない。したがって物は我々の本性とより多く一致するに従ってそれだけ有益である。そしてその逆も真である。Q・E・D・
定理三二 人間は受動に従属する限りにおいては本性上一致すると言われえない。
証明 ある物が本性上たがいに一致すると言われる場合、それはそれらの物が能力の点で一致するという意味であって(第三部定理七により)、無能力あるいは否定の点で、したがってまた(第三部定理三の備考を見よ)受動の点で一致するという意味ではない。このゆえに人間は受動に従属する限り本性上一致するとは言われえない。Q・E・D・
備考 このことはそれ自体においても明らかである。なぜなら、白と黒とはその両者とも赤でないという点においてのみ一致すると言う者があれば、それは白と黒とはいかなる点においてもー致しないことを絶対に肯定する者である。同様にまた石と人間とはその両者とも有限で無力である、あるいはその両者とも自己の本性の必然性によって存在するものでない、あるいは最後にその両者とも外部の原因の力によって無限に凌駕される、という点においてのみ一致すると言う者があるとしたら、それは石と人間とはいかなる点においても一致しないことをまったく肯定する者である。なぜなら、単に否定においてのみ、すなわち自らの有せざるものにおいてのみ一致する物は、実はいかなる点においても一致していないのだから。 40
定理三三 人間は受動という感情に捉われる限りにおいて本性上たがいに相違しうるし、またその限りにおいては同一の人間でさえ変りやすくかつ不安定である。
証明 感情の本性ないし本質は単に我々の本質ないし本性のみによっては説明されえない(第三部定義一および二により)。むしろそれは我々の能力と比較された外部の原因の力、言いかえば(第三部定理七により)外部の原因の本性によって規定されなければならぬ。この結果として、すべて感情には我々を刺激する対象の種類だけ多くの種類があるということになるし(第三部定五六を見よ)、また人間が同一の対象から異なった仕方で刺激され(第三部定理五一を見よ)、その限りにおいて本性上たがいに相違する、ということにもなり、最後にまた同一の人間が同じ対象に対して異なった仕方で刺激され(同じく第三部の定理五一により)、その限りにおいて変りすくかつ云々である、ということにもなるのである。Q・E・D・
定理三四 人間は受動という感情に捉われる限り相互に対立的でありうる。
証明 ある人間例えばペテロはパウロが悲しむ原因となりうる。それはペテロがパウロの憎むのと何らかの類似点を有するか(第三部定理一六により)、あるいはパウロ自身も愛するものをペテロが一人で所有しているためか(第三部定理三二およびその備考を見よ)、あるいはその他の諸原因(その主なるものは第三部定理五五の備考について見よ)のためである。こうしてその結果(感情の定義七により)パウロはペテロを憎むことになり、したがってまた容易に(第三部定理四〇およびその備考により)ペテロがパウロを憎み返すことにもなって、ひいては(第二部定理三九により)両者が相互に害悪を加えようと努めることになるであろう。言いかえれば(この部の定理三〇により)両者が相互に対立的であることになるであろう。ところが悲しみの感情は常に受動である(第三部定理五九により)。ゆえに人間は受動という感情に捉われる限り相互に対立的でありうる。Q・E・D・
備考 パウロは自分自身も愛するものをペテロが所有していると表象するためにペテロを憎むと私は言った。このことからして一見、この両者は同じものを愛するがゆえに、したがってまた本性上一致するがゆえに、相互に有害であるということになるように見える。そしてこのことが真なら、この部の定理三〇および三一は虚偽であることになろう。しかし、事態を公平に検討するならば、これらすべてがまったく調和することを我々は見いだすであろう。なぜなら、この両者は本性上一致する限りにおいて、すなわち両者のおのおのが同じものを愛する限りにおいて相互に不快の種になるのではなくて、両者がたがいに相違する限りにおいて不快の種になるのだからである。というのは、両者のおのおのが同じものを愛する限りまさにそのことによって両者おのおのの愛は強められるから(第三部定理三一により)、言いかえれば(感情の定義六により)まさにこのことによって両者のおのおのの喜びは強められるからである。だから両者が同じ物を愛しかつ本性上一致するという限りにおいて相互に不快の種になるというようなことは決してないのである。むしろこのことの原因は、今言ったように、両者が本性上たがいに相違しているということが仮定されているためにほかならない。なぜなら、ペテロは愛するものの現実的所有の観念を有し、これに反してパウロは愛するものの現実的喪失の観念を有していることを我々は仮定しているのだから。この結果としてパウロは悲しみに、またペテロは喜びに刺激されるごとになり、そしてその限りにおいて両者は相互に対立的であることになるのである。この仕方で我々は、憎しみを引き起こす他の諸原因も、人間が本性上たがいに相違するということにのみ由来し、その一致する点に由来しないことを容易に示すことができる。
定理三五 人間は、理性の導きに従って生活する限り、ただその限りにおいて、本性上常に必然的に一致する。
証明 人間は受動という感情に捉われる限り本性上異なりうるし(この部の定理三三により)、またたがいに対立的でありうる(前定理により)。しかし人間は理性の導きに従って生活する限り、ただその限りにおいて働きをなすと言われる(第三部定理三により)。したがって理性によって規定される限りにおける人間本性から生ずる一切は、その最近原因としての人間本性のみによって理解されなければならぬ(第三部定義二により)。ところで各人は自己の本性の法則に従って自分が善と判断するものを欲求し、自分が悪と判断するものを遠ざけようと努めるのであるから(この部の定理一九により)、なおまた我々が理性の指図に従って善あるいは悪と判断するものは必然的に善あるいは悪なのであるから(第二部定理四一により)、この結果として、人間は、理性の導きに従って生活する限り、ただその限り、人間本性にとって必然的に善なることを、したがってまた、おのおのの人間にとって必然的に善なることを、言いかえれば(この部の定理三一の系により)おのおのの人間の本性と一致することを、必然的になすことになる。したがって人間は理性の導きに従って生活する限り相互間においても必然的に常に一致する。Q・E・D・
系一 人間にとっては、理性の導きに従って生活する人間ほど有益ないかなる個物も自然の中に存しない。なぜなら、人間にとっては、自己の本性と最も多く一致するもの(この部の定理三一の系により)、言いかえれば(それ自体で明らかなように)人間、が最も有益である。ところが人間は理性の導きに従って生活する時に真に自己の本性の法則に従って行動し(第三部定義二により)、またその限りにおいてのみ他の人間の本性と必然的に常に一致する(前定理により)。ゆえに人間にとっては、個物の中で、理性の導きに従って生活する人間ほど有益なものはない。Q・E・D・
系二 おのおのの人間が自己に有益なるものを最も多く求める時に、人間は相互に最も有益である。なぜなら、各人が、自己の利益をより多く求め・自己の維持により多く努力するにつれて、彼はそれだけ有徳であり(この部の定理二〇により)、あるいは同じことだが(この部の定義八により)、自己の本性の法則に従って行動する能力、言いかえれば(第三部定理三により)、理性の導きに従って生活する能力がそれだけ大である。ところが人間は理性の導きに従って生活する時に本性上最も多く一致する(前定理により)。ゆえに(前の系により)各人が自己に有益なものを最も多く求める時に、人間は相互に最も有益であるであろう。Q・E・D・
備考 我々が今しがた示した事柄は、経験自身も毎日多数のかつきわめて明白な証拠によって立証しているものであって、その結果、「人間は人間にとって神である」という諺がほとんどすべての人の口にのぼっているほどである。しかし人間が理性の導きに従って生活するということは稀である。むしろ彼らはおおむねねたみ深く、相互に不快の種になっているというのがその実情である。しかしそれにもかかわらず彼らは孤独の生活にほとんど耐えきることができない。こうして「人間は社交的動物である」というあの定義が多くの人々から多大の賛成をかち得たのである。そしてまた実際、人間の共同社会からは損害よりもはるかに多くの利益が生ずるような事情になっている。だから諷刺家は欲するままに人事を嘲笑するがよい。神学者はそれを呪詛するがよい。また憂鬱家は未開な、野蛮な生活をできるだけ謳歌し、人間を軽蔑して野獣を讃美するがよい。しかも彼らは、人間がその必需品を相互扶助によってはるかに容易に調達しうること、また諸方から迫ってくる危険を避けるには結合した力によるほかないことを経験するであろう。人間の行為を考察するのが野獣の行動を考察するよりもはるかに価値ありかつ我々の認識にいっそう多く価することは今は言わないとしても。しかしこれらのことどもについては他のところでもっと詳しく述べるであろう。 (相互扶助)
定理三六 徳に従う人々の最高の善はすべての人に共通であって、すべての人が等しくこれを楽しむことができる。
証明 有徳的に働くとは理性の導きに従って行動することである(この部の定理二四により)。そして理性に従って我々のなすすべての努力は認識ということに向けられる(この部の定理二六により)。それゆえ(この部の定理二八により)徳に従う人々の最高の善は神を認識することである。そしてこれは(第二部定理四七およびその備考により)すべての人々に共通である善、かつすべての人間が本性を同じくする限り等しく所有しうる善である。Q・E・D・
備考 だがあるいは次のように尋ねる人があるかもしれない。徳に従う人々の最高の善がもしすべての人に共通でなかったとしたらどうであろう。その場合にはそれから、前の場合のように(この部の定理三四を見よ)、理性の導きに従って生活する人間、言いかえれば(この部の定理三五により)本性上一致する限りにおける人間が、相互に対立的であるというようなことが起こりはしないだろうかと。こうした人に対しては次のことが答えとなるであろう。人間の最高の善がすべての人に共通であるということは偶然によるのではなくて、理性の本性そのものから生ずるのである。なぜなら、この最高の善は理性によって規定される限りにおける人間の本質そのものから導き出されるからである。そして人間は、この最高の善を楽しむ力を有しないとしたら、存在することも考えられることもできないであろう。神の永遠・無限なる本質について妥当な認識を有することは人間精神の本質に属するのであるから(第二部定理四七により)。
定理三七 徳に従うおのおのの人は自己のために求める善を他の人々のためにも欲するであろう。そして彼の有する神の認識がより大なるに従ってそれだけ多くこれを欲するであろう。 46
証明 人間は理性の導きに従って生活する限り、人間にとって最も有益である(この部の定理三五の系一により)。それゆえ(この部の定理一九により)、我々は理性の導きに従う場合、必然的に、人間をして理性の導きに従って生活させるように努めるであろう。ところが理性の指図に従って生活するおのおのの人、言いかえれば(この部の定理二四により)、徳に従うおのおのの人が自己のために欲求する善とは認識することにほかならない(この部の定理二六により)。ゆえに徳に従うおのおのの人は自己のために欲求する善を他の人々のためにも欲するであろう。次に欲望は、精神に関係する限り、精神の本質そのものである(感情の定義一により)。ところが精神の本質は認識に存する(第二部定理一一により)。そしてこの認識は神の認識を含み(第二部定理四七により)、また神の認識なしには存在することも考えられることもできない(第一部定理一五により)。このゆえに、精神の本質が含む神の認識がより大なるに従って、徳に従う人が自分のために欲求する善を同時に他人のために欲する欲望もまたそれだけ大であるであろう。Q・E・D・
別の証明 人間は自分のために欲求しかつ愛する何らかの善を他人もまた愛するのを見るとしたらいっそう強くそれを愛するであろう(第三部定理三一により)。だから彼は(同定理の系により)他人もそれを愛するように努めるであろう。ところで今問題となっている善は(前定理により)すべての人に共通であり、すべての人が等しくこれを楽しみうるのであるから、したがって彼は(同じ理由により)すべての人がそれを楽しむように努めるであろう。そして(第三部定理三七により)彼がこの善をより多く享楽するに従ってそれだけ多くそのことに努めるであろう。Q・E・D・
備考一 自分の愛するものを他の人々が愛することを、また自分の意向通りに他の人々が生活することを、単に感情に基づいて努める人は、本能的にのみ行動するものであって、そのゆえに人から憎まれる。ことに別の好みを有してそのために同様の努力をなし、やはり自分の意向通りに他の人々を生活させようと等しく本能的に努めるような人々から憎まれる。次に人間が感情によって欲求する最高の善は、しばしば一人だけしか享受しえないような種類のものであるから、この結果、愛する当人はその心中に不安を蔵し、自分の愛するものに対する賞讃を語ることを喜びながらも同時にそれが人から信じられるのを恐れるというようなことになる。
ところが他の人々を理性によって導こうと努める人は本能的に行動するのでなく、友愛的かつ善意的に行動するのであってその心中きわめて確固たるものがある。 (友愛的)
さらに、神の観念を有する限りにおける我々、すなわち神を認識する限りにおける我々から起こるすべての欲望および行動を私は宗教心に帰する。しかし我々が理性の導きに従って生活することから生ずる、善行をなそうとする欲望を私は道義心と呼ぶ。次に理性の導きに従って生活する人間が他の人々と友情を結ぶにあたっての根底となる欲望を私は端正心と呼び、また理性の導きに従って生活する人々が賞讃するようなことを端正と呼び、これに反して友情を結ぶのに妨げとなるようなことを非礼と呼ぶ。このほかに私は国家の基礎の何たるかをも示した。 (国家の基礎)
次に、真の徳と無能力との差別は上に述べたことから容易に知られる。すなわち真の徳とは理性の導きのみに従って生活することにほかならない。したがって無能力とは人間が自己の外部にある事物から受動的に導かれ、かつ外界の一般状態が要求する事柄〜〜それ自身だけで見られた彼の本性そのものが要求する事柄ではなく〜〜をなすように外部の事物から決定されることにのみ存する。 48
さて以上は私がこの部の定理一八の備考において証明を約束した事柄である。これからして動物の屠殺を禁ずるあの掟が健全な理性によりはむしろ虚妄な迷信と女性的同情とに基づいていることが明らかである。我々の利益を求める理性は、人間と結合するようにこそ教えはするが、動物、あるいは人間本性とその本性を異にする物、と結合するようには教えはしない。むしろ理性は、動物が我々に対して有するのと同一の権利を我々が動物に対して有することを教える。否、各自の権利は各自の徳ないし能力によって規定されるのだから、人間は動物が人間に対して有する権利よりはるかに大なる権利を動物に対して有するのである。 (動物)
しかし私は動物が感覚を有することを否定するのではない。ただ、我々がそのため、我々の利益を計ったり、動物を意のままに利用したり、我々に最も都合がいいように彼らを取り扱ったりすることは許されない、ということを私は否定するのである。実に彼らは本性上我々と一致しないし、また彼らの感情は人間の感情と本性上異なるからである(第三部定理五七の備考を見よ)。
なお正義とは何であるか、不正義とは何であるか、罪過とは何であるか、また最後に功績とは何であるかを説明することが残っている。しかしこれについては次の備考を見よ。
備考二 第一部の付録において私は賞讃および非難とは何か、功績および罪過とは何か、正義および不正義とは何かを説明することを約束した。賞讃および非難についてはすでに第三部定理二九の備考において説明した。しかし他の概念について述べるにはここが適当な場所であろう。だがその前に人間の自然状態および国家状態について少しく述べなくてはならぬ。
人はみな最高の自然権によって存在し、したがってまた各人は自己の本性の必然性から生ずることを最高の自然権によってなすのである。それゆえ各人は、最高の自然権によって、何が善であり何が悪であるかを判断し、自己の意のままに自己の利益を計り(この部の定理一九および二〇を見よ)、復讐をなし(第三部定理四〇の系二を見よ)、また自分の愛するものを維持し、自分の憎むものを破壊しようと努める(第三部定理二八を見よ)。
もし人間が理性の導きに従って生活するのだとしたら、各人は他人を何ら害することなしに自己のこの権利を享受しえたであろう(この部の定理三五の系一により)。ところが人間は諸感情に隷属しており(この部の定理四の系により)しかもそれらの感情は人間の能力ないし徳をはるかに凌駕するのであるから(この部の定理六により)、そのゆえに彼らはしばしば異なった方向に引きずられ(この部の定理三三により)、また相互扶助を必要とするにもかかわらず(この部の定理三五の備考により)相互に対立的であることになる(この部の定理三四により)。それゆえ人間が和合的に生活しかつ相互に援助をなしうるためには、彼らが自己の自然権を断念して、他人の害悪となりうるような何ごともなさないであろうという保証をたがいに与えることが必要である。しかしこのこと、すなわち諸感情に必然的に隷属し(この部の定理四の系により)かつ不安定で変りやすい(この部の定理三三により)人間が、相互に保証を与え相互に信頼しうるということがいかにして可能であろうかといえば、それはこの部の定理七および第三部の定理三九から明らかである。そこで述べたところによれば、どんな感情も、それより強力でかつそれと反対の感情によってでなくては抑制されえないものであり、また各人は、他人に善悪を加えたくてももしそれによってより大なる害悪が自分に生ずる恐れがあれば、これを思いとどまるものである。そこでこの法則に従って社会は確立されうるのであるが、それには社会自身が各人の有する復讐する権利および善悪を判断する権利を自らに要求し、これによって社会自身が共通の生活様式の規定や法律の制定に対する実権を握るようにし、しかもその法律を、感情を抑制しえない理性(この部の定理一七の備考により)によってではなく、刑罰の威嚇によって確保するようにしなければならぬ。さて法律および自己保存の力によって確立されたこの社会を国家と呼び、国家の権能によって保護される者を国民と名づけるのである。 (相互援助、国家)
これからして、自然状態においては、すべての人の同意に基づいて善あるいは悪であるようないかなることも存在しないことを我々は容易に知りうる。なぜなら、自然状態における各人はもっばら自己の利益のみを計り、自分の意のままにかつ自分の利益のみを考慮して何が善であり何が悪であるかを決定し、またいかなる法律によっても自分以外の他人に服従するように義務づけられないからである。したがってまた自然状態においては罪過というものは考えられない。しかし一般の同意に基づいて何が善であり何が悪であるかが決定されて各人が国家に服従するように義務づけられる国家状態においてはそれが考えられる。すなわち罪過とは不服従にほかならず、それはこのゆえに国家の権能によってのみ罰せられる。これに反して服従は国民の功績とされる。まさにそのことによって国民は国家の諸便益を享受するのに価すると判断されるからである。
次に、自然状態においては、何びとも一般的同意によってある物の所有主であることはない。また自然の中にはこの人に属してかの人に属さないといわれうるような何ものも存しない。むしろすべての物がすべての人のものである。したがって自然状態においては各人に対し各人の物を認めようとかある人からその所有のものを奪おうとかする意志は考えられえない。言いかえれば自然状態においては正義とか不正義といわれうる何ごとも起こらない。しかし一般の同意に基づいて何がこの人のものであり何がかの人のものであるかが決定される国家状態においてはこのことが起こる。以上のことから正義ならびに不正義、罪過および功績は外面的概念であって、精神の本性を説明する属性でないことが判明する。しかしこれらのことについてはこれで十分である。 (自然状態)
定理三八 人間身体を多くの仕方で刺激されうるような状態にさせるもの、あるいは人間身体をして外部の物体を多くの仕方で刺激するのに適するようにさせるものは、人間にとって有益である。そしてそれは、身体が多くの仕方で刺激されることおよび他の物体を刺激することにより適するようにさせるに従ってそれだけ有益である。これに反して身体のそうした適性を減少させるものは有害である。
証明 身体がそうしたことにより適するようにされるに従って精神は知覚に対してそれだけ適するようになる(第二部定理一四により)。したがって身体をこのような状態にしてそうしたことに適するようにさせるものは必然的に善すなわち有益である(この部の定理二六および二七により)。そしてそれは身体をそうしたことにより適するようにさせうるに従ってそれだけ有益である。また反対に(第二部の同じ定理一四の裏ならびにこの部の定理二六および二七により)身体のそうした適性を減少させるものは有害である。Q・E・D・ 52
定理三九 人間身体の諸部分における運動および静止の相互の割合が維持されるようにさせるものは善である。これに反して人間身体の諸部分が相互に運動および静止の異なった割合をとるようにさせるものは悪である。
証明 人間身体はその維持のためにきわめて多くの他の物体を要する(第二部要請四により)。しかし人間身体の形相を構成するものは、身体の諸部分がその運動をある一定の割合で相互に伝達することに存する(第二部定理一三のあとの補助定理四の前にある定義により)。ゆえに人間身体の諸部分が相互に有する運動および静止の割合が維持されるようにさせるものは人間身体の形相を維持するものであり、したがってまた(第二部要請三および六により)人間身体が多くの仕方で刺激されうるようにさせ、また人間身体が外部の物体を多くの仕方で刺激しうるようにさせるものである。ゆえにそれは(前定理により)善である。次に人間身体の諸部分が運動および静止の異なった割合を取るようにさせるものは人間身体が異なった形相を取るようにさせるものであり(第二部の同じ定義により)、言いかえれば(それ自体で明らかでありまたこの部の序言の終りに注意したように)人間身体が破壊されるようにさせ、したがってまたそれが多くの仕方で刺激されるのに全然適しないようにさせるものである。ゆえにそれは(前定理により)悪である。Q・E・D・
備考 このことが精神にとってどれだけ害になりあるいは益になりうるかは第五部で説明されるであろう。しかしここで注意しなければならぬのは、身体はその諸部分が相互に運動および静止の異なった割合を取るような状態に置かれる場合には死んだものと私は解していることである。つまり、血液の循環その他身体が生きているとされる諸特徴が持続されている場合でも、なお人間身体がその本性とまったく異なる他の本性に変化しうることが不可能でないと私は信ずるのである。なぜなら、人間身体は死骸に変化する場合に限って死んだのだと認めなければならぬいかなる理由も存しないからである。かえって経験そのものは反対のことを教えるように見える。というのは、人間がほとんど同一人であると言えぬほどの大きな変化を受けることがしばしば起こるからである。私はあるスペインの詩人について次のような話を聞いた。彼は病気にかかり、そしてそれは回復したものの、彼は自分の過去の生活をすっかり忘れきって、自分が以前作った物語や悲劇を自分の作と信じなかったというのである。それでもし彼が母国語も忘れたとしたら、彼はたしかに大きな小児と見なされえたであろう。もしこうした話が信じがたいように思えるなら、小児について我々は何と言うべきであろうか。成人となった人間は、他人の例で自分のことを推測するのでなかったならば、自分がかつて小児であったことを信じえないであろうほどに小児の本性が自分の本性と異なることを見ているのである。しかし迷信的な人々に新しい疑問をひき起こすような材料を与えないために、私はむしろこの問題をこのくらいでやめておこうと思う。
定理四〇 人間の共同社会に役立つもの、あるいは人間を和合して生活するようにさせるものは有益である。これに反して国家の中に不和をもたらすものは悪である。 (国家)54
証明 なぜなら、人間を和合して生活するようにさせるものは、同時に人間を理性の導きに従って生活するようにさせるものである(この部の定理三五により)。したがってそれは(この部の定理二六および二七により)善である。これに反して、不和をひき起こすようなものは悪である(同じ理由により)。Q・E・D・
定理四一 喜びは直接的には悪でなくて善である。これに反して悲しみは直接的に悪である。
証明 喜びは(第三部定理一一およびその備考により)身体の活動能力を増大あるいは促進する感情である。これに反して悲しみは身体の活動能力を減少しあるいは阻害する感情である。ゆえに(この部の定理三八により)喜びは直接的には善であり云々。Q・E・D・
定理四二 快活は過度になりえず、常に善である。反対に憂鬱は常に悪である。
証明 快活は(第三部定理一一の備考におけるその定義を見よ)喜びの一種であって、この喜びは身体に関する限り、身体のすべての部分が均等に刺激されることに存する。言いかえれば(第三部定理一一により)身体のすべての部分が相互に運動および静止の同じ割合を維持するような仕方で身体の活動能力が増大しあるいは促進されることに存する。したがって(この部の定理三九により)快活は常に善であって過度になりえない。ところが憂鬱は(同様に第三部定理一一の備考におけるその定義を見よ)悲しみの一種であって、この悲しみは、身体に関する限り、身体の活動能力がすべての点において減少しあるいは阻害されることに存する。ゆえに(この部の定理三八により)憂鬱は常に悪である。Q・E・D・
定理四三 快感は過度になりうるしまた悪でありうる。しかし苦痛は快感あるいは喜びが悪である限りにおいて善でありうる。
証明 快感は喜びの一種であって、この喜びは、身体に関する限り、身体の一部分あるいは若干部分がその他の部分以上に刺激されることに存する(第三部定理一一の備考におけるその定義を見よ)。そうした感情の力は身体のその他の働きを凌駕して身体に執拗につきまとい(この部の定理六により)、こうして身体がきわめて多くの他の仕方で刺激されるのに適しないようにするほど、それほど大なるものでありうる。ゆえに快感は(この部の定理三八により)悪でありうる。次に、これと反対に、悲しみの一種である苦痛は、それ自体で見れば善でありえない(この部の定理四一により)。しかしその力と発展とは我々の能力と比較された外部の原因の力によって規定されるのであるから(この部の定理五により)、そのゆえに我々は、この感情について、無限に多くの強度と様式とを考えることができる(この部の定理三により)。したがって我々は、快感が過度になるのを防ぎうるような、そしてその限りにおいて(この定理の始めの部分により)身体の能力を減少しないようにさせうるような、そうした苦痛も考えることができる。ゆえに苦痛はその限りにおいて善であるであろう。Q・E・D・ 56
定理四四 愛および欲望は過度になりうる。
証明 愛は外部の原因の観念を伴った喜びである(感情の定義六により)。ゆえに(第三部定理一一の備考により)外部の原因の観念を伴った快感も愛の一種である。したがって愛は(前定理により)過度になりうる。次に欲望はそれを生ずる感情がより大なるに従ってそれだけ大である(第三部定理三七により)。ゆえに感情が(この部の定理六により)人間のその他の働きを凌駕しうるのと同様に、その感情から生ずる欲望もまたその他の欲望を凌駕しうるのであり、したがってまたそれは前定理において快感について示したのと同様に過度になりうるであろう。Q・E・D・
備考 善であると私の言った快活については単に観察するよりも概念的に考える方がいっそう容易にわかる。すなわち我々が日々捉われる諸感情は、もっぱら身体の何らかの部分がその他の部分以上に刺激されるのに関係するのであり、したがってそうした感情は一般に過度になり、精神をただ一つの対象の考察に引きとどめて精神が他のことについて思惟しえないようにするのである。人間は数多くの感情に従属するものであって、常に同一の感情に捉われている人間は稀にしか見られないけれども、それにしても同一の感情に執拗にまといつかれている人間もないではない。すなわち人間がただ一つの対象から強く刺激されて、その結果それが現在していない場合にもそれを自分の前にあるように信ずるのを我々はしばしば見かける。もしこうしたことが眠っていない人間に起こるならば、この人間を我々は狂っているとか気違い沙汰だとか言うのである。また恋に焦れて夜も昼もただ恋人あるいは情婦のみを夢みる者も同様に気違い沙汰と思われる。こうした者は通常我々の笑いをさそうからである。ところが食欲者が利得や金銭のほか何ものもえない場合、また名誉欲者が名誉のほか何ものも考えない場合などにはそうした人々は狂っているとは信じられない。それは彼らは通常我々の不快の種であり、憎悪に価すると思われるからである。しかし食欲、名誉欲、情欲などは、一般には〔精神〕病に数えられていないにしても、実際はやはり狂気の一種である。
定理四五 憎しみは決して善ではありえない。
証明 我々は我々の憎む相手を滅ぼそうと努める(第三部定理三九により)。言いかえれば我々はそれによって(この部の定理三七により)悪であるようなあることをしようと努める。ゆえに云云。Q・E・D・
備考 私がここならびに以下において、憎しみを人間に対する憎しみとのみ解することに注意されたい。
系一 ねたみ、嘲弄、軽蔑、怒り、復讐その他憎しみに属しあるいは憎しみから生ずる諸感情は、悪である。このことは第三部定理三九およびこの部の定理三七からも明らかである。
系二 我々が憎しみに刺激される結果として欲求するすべてのことは非礼であり、また国家においては不正義である。このことは第三部定理三九からおよび非礼と不正義との定義からも明らかである。この部の定理三七の備考におけるその定義を見よ。 (国家)
備考 嘲弄(系一で言ったようにそれは悪である)と笑いとの間に私は大きな差異を認める。なぜなら、笑いは諧謔と同様に純然たる喜びであり、したがって過度になりさえしなければそれ自体では善である(この部の定理四一により)。実際、楽しむことを禁ずるものは厭世的で悲しげな迷信のみである。いったい憂鬱を追い払うことが何で飢渇をいやすことよりも不適当であろうか。私の原則は次のごとくであって私はこの信念を固くとる者である。すなわちいかなる神霊も、またねたみ屋以外のいかなる人間も、私の無能力や苦悩を喜びはしないし、また落涙、すすり泣き、恐怖、その他精神の無能力の標識であるこの種の事柄を我々の徳に数えはしない。むしろ反対に、我々はより大なる喜びに刺激されるに従ってそれだけ大なる完全性に移行するのである。言いかえれば我々はそれだけ多くの神の本性を必然的に分有するのである。だからもろもろの物を利用してそれをできる限り楽しむ(と言っても飽きるまでではない、なぜなら飽きることは楽しむことでないから)ことは賢者にふさわしい。たしかに、ほどよくとられた味のよい食物および飲料によって、さらにまた芳香、緑なす植物の快い美、装飾、音楽、運動競技、演劇、そのほか他人を害することなしに各人の利用しうるこの種の事柄によって、自らを爽快にし元気づけることは、賢者にふさわしいのである。なぜなら、人間身体は本性を異にするきわめて多くの部分から組織されており、そしてそれらの部分は、全身がその本性から生じうる一切に対して等しく有能であるために、したがってまた精神が多くのものを同時に認識するのに等しく有能であるために、種種の新しい栄養をたえず必要とするからである。こうしてこの生活法は我々の原則とも、また一般の実行ともきわめてよく一致する。ゆえにもし最上の生活法、すべての点において推奨されるべき生活法なるものがあるとすれば、それはまさにこの生活法である。そしてこれについてはこれ以上明瞭にも詳細にも論ずる必要はない。 (食事、美)
定理四六 理性の導きに従って生活する人は、できるだけ、自分に対する他人の憎しみ、怒り、軽蔑などを逆に愛あるいは寛仁で報いるように努める。
証明 すべて憎しみの感情は悪である(前定理の系一により)。ゆえに理性の導きに従って生活する人は、できるだけ憎しみの感情に捉われぬように努めるであろうし(この部の定理一九により)、したがってまた(この部の定理三七により)他人にもそうした感情に悩ませないように努めるであろう。ところが憎しみは憎み返しによって増大し、反対に愛によって消滅されうるのであり(第三部定理四三により)、こうして憎しみは愛に移行する(第三部定理四四により)。ゆえに理性の導きに従って生活する人は他人の憎しみその他を逆に愛で、言いかえれば寛仁(第三部定理五九の備考におけるその定義を見よ)で報いることに努めるであろう。Q・E・D・
備考 自分の受けた不法を憎み返しによって復讐しようと思う人はたしかに惨めな生活をするものである。これに反して憎しみを愛で克服しようとつとめる人は、実に喜びと確信とをもって戦い、多くの人に対しても一人に対するのと同様にやすやすと対抗し、運命の援助をほとんどまったく要しない。一方、彼に征服された人々は喜んで彼に服従するが、しかもそれは力の欠乏のためではなくて力の増大のためである。これらすべては単に愛および知性の定義のみからきわめて明瞭に帰結されるのであって、これを一々証明することは必要でない。
定理四七 希望および恐怖の感情はそれ自体では善でありえない。
証明 希望および恐怖の感情は悲しみを伴うことなしに存しえない。なぜなら恐怖は(感情の定義一三により)悲しみであるし、また希望は(感情の定義一二および一三の説明を見よ)恐怖を伴うことなしには存しえないからである。したがつて(この部の定理四二により)、これらの感情はそれ自体では善でありえず、ただ喜びの過度になるものを抑制しうる限りにおいてのみ善である(この部の定理四三により)。Q・E・D・
備考 これに加えて、これらの感情は認識の欠乏および精神の無能力を表示するものである。そしてこの理由から安堵、絶望、歓喜および落胆もまた無能な精神の標識である。なぜなら安堵および歓喜は喜びの感情であるとはいえ、それは悲しみ〜〜すなわち希望および恐怖〜〜の先行を前提としているからである。だから我々が理性の導きに従って生活することにより多くつとめるにつれて我々は希望にあまり依存しないように、また恐怖から解放されるように、またできるだけ運命を支配し・我々の行動を理性の確実な指示に従って律するようにそれだけ多く努める。
定理四八 買いかぶりおよび見くびりの感情は常に悪である。
証明 なぜならこれらの感情は(感情の定義二一および二二により)理性に矛盾する。したがって(この部の定理二六および二七により)それは悪である。Q・E・D・
定理四九 買いかぶりは買いかぶられる人間を容易に高慢にする。
証明 もしある人が愛のため我々について正当以上に感ずるのを我々が見るなら、我々は容易に名誉を感ずるであろう(第三部定理四一の備考により)。すなわち喜びに刺激されるであろう(感情の定義三〇により)。そして我々は自分について言われている善を容易に信ずるであろう(第三部定理二五により)。したがって我々は自分に対する愛のため自分について正当以上に感ずるであろう。言いかえれば(感情の定義二八により)我々は容易に高慢になるであろう。Q・E・D・
定理五〇 憐憫は理性の導きに従って生活する人間においてはそれ自体では悪でありかつ無用である。
証明 なぜなら憐憫は(感情の定義一八により)悲しみである。したがって(この部の定理四一により)それ自体では悪である。ところで憐憫から生ずる善、すなわち我々が憐憫を感ずる人間を不幸から救おうと努めること(第三部定理二七の系三により)に関して言えば、我々は単に理性の指図のみによってこれをなそうと欲する(この部の定理三七により)、また我々は善であると我我の確知することを単に理性の指図のみによってなしうる(この部の定理二七により)。ゆえに憐憫は理性の導きに従って生活する人においてはそれ自体では悪でありかつ無用である。Q・E・D・
系 この帰結として、理性の指図に従って生活する人は、できるだけ憐憫に動かされないように努めるということになる。
備考 一切が神の本性の必然性から起こり、自然の永遠なる諸法則、諸規則に従って生ずることを正しく知る人は、たしかに、憎しみ、笑いあるいは軽蔑に価する何ものも見いださないであろうし、また何びとをも憐れむことがないであろう。むしろ彼は人間の徳が及ぶ限り、いわゆる正しく行ないて自ら楽しむことに努めるであろう。これに加えて、容易に憐憫の感情を催し他人の不幸や涙に動かされる者は、のちにいたって自ら悔いるような行ないをしばしばなしているのである。なぜなら我々は、感情に基づいては、善であると我々の確知するような何ごとをもなすものでなく、また我々は偽わりの涙に容易に欺かれるからである。 (「正しく行ないて〜〜」)
しかし私はここで明らかに、理性の導きに従って生活する人について語っているのである。というのは、理性によっても憐憫によっても他人を援助するように動かされない者は非人間と呼ばれてしかるべきである。なぜなら、そうした者は(第三部定理二七により)まったく人間らしいところがない(あるいはあらゆる人間性を欠いている)ように見えるからである。
定理五一 好意は理性と矛盾せず、むしろそれと一致することができ、またそれから生ずることができる。
証明 なぜなら、好意は他人に親切をなした人に対する愛である(感情の定義一九により)。したがってそれは働きをなすと言われる限りにおける精神に関係ずることができる(第三部定理五九により)。言いかえれば(第三部定理三により)認識する限りにおける精神に関係することがでる。ゆえに好意は理性と一致し云々。Q・E・D・
別の証明 理性の導きに従って生活する人は自分のために欲求する善を他人のためにも欲する(この部の定理三七により)。だから親切をなそうとする彼の努力は、ある人が他人に親切をなすのを彼が見ることによって促進される。言いかえれば(第三部定理一一の備考により)彼はそれによって喜ぶであろう。しかも(仮定により)その喜びは他人に親切をなした人の観念を伴ったものである。ゆえに(感情の定義一九により)彼はその人に対して好意を感ずる。Q・E・D・
備考 我々が定義したような憤慨(感情の定義二〇を見よ)は必然的に悪である(この部の定理四五により)。しかし注意しなければならぬのは、最高権力〔国家〕が平和を確保する願望に促されて、他人に不法を加えたある国民を罰する場合、私は最高権力がその国民に対して憤慨するとは言わないということである。なぜなら、最高権力は憎しみに駆られてその国民を害するために罰するのでなく、道義の念によって罰するのだからである。 (国家)
定理五二 自己満足は理性から生ずることができる。そして理性から生ずるこの満足のみが、存在しうる最高の満足である。
証明 自己満足は人間が自己自身および自己の活動能力を観想することから生ずる喜びである(感情の定義二五により)。ところが人間の真の活動能力ないし徳は理性〔妥当な観念〕そのものであり(第三部定理三により)、そして人間はこの理性〔妥当な観念〕を明瞭判然と観想しうる(第二部定理四〇および四三により)。ゆえに自己満足は理性から生じうる。次に人間は自己自身を観想するにあたり、自己の活動能力から生ずることのみを明瞭判然と、すなわち妥当に、知覚する(第三部定義二により)。言いかえれば(第三部定理三により)自己の認識能力から生ずることのみを妥当に知覚する。それゆえにこうした観想のみから、存在しうる最高の満足が生ずるのである。Q・E・D・
備考 まことに自己満足は我々の望みうる最高のものである。なぜなら(この部の定理二五において我々が示したように)何びとも自己の有を何らかの他の目的のために維持しようとは努めないからである。そしてこの満足は賞讃によってますます養われ強められ(第三部定理五三の系
により)、また反対に(第三部定理五五の系により)非難によってますますかき乱されるから、このゆえに我々は、名誉に最も多く支配され、そして恥辱の生活はほとんど耐えることができないのである。
定理五三 謙遜〔自劣感〕は徳ではない。すなわち理性からは生じない。
証明 謙遜は人間が自己の無能力を観想することから生ずる悲しみである(感情の定義二六により)。しかし人間が自己自身を真の理性によって認識する限り、彼は自己の本質を、言いかえれば(第三部定理七により)自己の能力を認識するものと想定される。だからもし人間が自己自身を観想するにあたり自己のある無能力を知覚するとしたら、それは彼が自己を真に認識することから来るのではなくて、むしろ(第三部定理五五において示したように)彼の活動能力が阻害されることから来るのである。しかしもし、人間が自分より有力なある物を認識しその認識から自己の活動能力を正しく限定しこれによって自己の無能力を考えるという場合を我々が仮定するとしたら、それは人間が自己自身を明瞭に認識する場合、すなわち(この部の定理二六により)彼の活動能力が促進される場合を考えているのにほかならない。このゆえに謙遜すなわち人間が自己の無能力を観想することから生ずる悲しみは、真の観想あるいは理性からは生じない。それは徳ではなくて受動である。Q・E・D・
定理五四 後悔は徳ではない。すなわち理性からは生じない。むしろある行為を後悔する者は二重に不幸あるいは無能力である。
証明 この定理の始めの部分は前定理と同様にして証明される。あとの部分は単にこの感情の定義(感情の定義二七を見よ)のみから明らかである。なぜなら、後悔する人間は最初に悪しき欲望によって、次には悲しみによって、征服される者だからである。
備考 人間は理性の指図に従って生活することが稀であるから、この二感情すなわち謙遜と後悔、なおそのほかに希望と恐怖もまた、害悪よりもむしろ利益をもたらす。したがってもしいつかあやまちを犯さなければならないとすればこの方面であやまちを犯すがよい。なぜなら、もし精神の無能な人間がみな一様に高慢で、何ごとにも恥じず、また何ごとをも恐れなかったとすれば、いかにして彼らは社会的紐帯によって結合され統一されえようか。民衆は恐れを知らない時に恐るべきものである。ゆえに少数者の利益ではなく社会全体の利益を考慮した予言者たちが謙遜、後悔および恭順をいたく推奨したのは怪しむに足りない。また実際に、これらの感情に支配される人々は他の人々よりもはるかに容易に、ついには理性の導きに従って生活するように、言いかえれば自由になって幸福な生活を享受するように導かれることができるのである。 (民衆、恐るべきもの、タキトゥス) 66
定理五五 最大の高慢あるいは最大の自卑は自己に関する最大の無知である。
証明 感情の定義二八および二九から明らかである。
定理五六 最大の高慢あるいは最大の自卑は精神の最大の無能力を表示する。
証明 徳の第一の基礎は、自己の有を維持すること(この部の定理二二の系により)、しかもそれを理性の導きに従ってなすこと(この部の定理二四により)、である。だから自分自身を知らない者は一切の徳の基礎を知らない者であり、したがってまた一切の徳を知らない者である。次に有徳的に働くとは理性の導きによって行動することにほかならず(この部の定理二四により)、そして理性の導きに従って行動する者は自分が理性の導きに従って行動していることを必ず知っていなければならぬ(第二部定理四三により)。これで見れば自分自身を、したがってまた(今しがた示したように)一切の徳を知ることの最も少ない者は有徳的に働くことの最も少ない者、言いかえれば(この部の定義八から明らかなように)精神的に最も無能力な者である。それゆえに(前定理により)最大の高慢あるいは最大の自卑は精神の最大の無能力を表示する。Q・E・D・
系 これからきわめて明瞭に帰結されるのは、高慢な人間および自卑的な人間はもろもろの感情に最も多く従属するということである。
備考 しかし自卑は高慢よりも容易に矯正されうる。なぜなら、高慢は喜びの感情で自卑は悲しみの感情であり、したがって(この部の定理一八により)高慢は自卑よりも強力だからである。
定理五七 高慢な人間は追従の徒あるいは阿訣(あゆ)の徒の現在することを愛し、反対に寛仁の人の現在することを憎む。
証明 高慢は人間が自己について正当以上に感ずることから生ずる喜びである(感情の定義二八および六により)。この謬見を高慢な人間はできるだけはやくむことに努めるであろう(第三部定理一三の備考を見よ)。したがって彼らは追従の徒あるいは阿訣の徒(これらについての定義は略した、それはきわめて明白だから)の現在することを愛するであろう。そして彼らをその正当の価値において判断する寛仁の人の現在することを忌避するであろう。Q・E・D・
備考 ここで高慢の弊害のすべてを列挙するとしたらあまりに長くなるであろう。なぜなら高慢な人間はあらゆる感情に支配され、ただ愛および同情の感情から最も縁遠いだけだからである。
しかしここに言わずにいられないのは、他人について正当以下に感ずる者もまた高慢と呼ばれるということである。したがってこの意味において高慢は、人間が自己を他の人々よりすぐれていると思う謬見から生ずる喜びであると定義される。そしてこの高慢の反対である自卑は、人間が自己を他の人々よりも劣ると信ずる謬見から生ずる悲しみとして定義されるであろう。このことが明らかにされた上は、高慢な人間が必然的にねたみ深いこと(第三部定理五五の備考を見よ)、そして彼は、徳について最も多く賞讃されるような人々を最も多く憎み、これらの人々に対する彼の憎しみは愛や親切によって容易に征服されないこと(第三部定理四一の備考を見よ)、また彼の無能な精神に迎合して彼を愚者から狂者たらしめるような人々の現在することのみを彼は喜ぶこと、そうしたことを我々は容易に了解しうるのである。
自卑は高慢の反対であるけれども、自卑的な人間は高慢な人間にもっとも近い。実際彼の悲しみは自己の無能力を他の人々の能力ないし徳に照して判断することから生ずるのであるから、彼の表象力が他人の欠点の観想に専心する時に彼の悲しみは軽減するであろう。言いかえれば彼は喜びを感ずるであろう。「不幸な者にとっては不幸な仲間を持ったことが慰安である」というあの諺はここから来ている。反対に彼は自分が他の人々に劣ると信ずれば信ずるだけますます多く悲しみを感ずるであろう。この結果として、自卑者ほど多くねたみに傾く者はないこと、彼らは是正してやるためによりも、とがめだてをするために熱心に人々の行為を観察することに努めること、最後にまた彼らは自卑のみを賞讃し、己れの目卑を誇り、しかも自卑の外観を失わないようにしてそれをやるということになる。こうしたことどもはこの感情から必然的に起こるのであって、それはあたかも三角形の本性からその三角の和が二直角に等しいということが起こるのと同様である。
私がこれらの感情ならびにこれと類似の諸感情を悪と呼ぶのは、ただ人間の利益を念頭に置く限りにおいてであるということはすでに述べたところである。これに反して自然の諸法則は、人間がその一部分にすぎない自然の共通の秩序に関係している。このことを私はここでついでに注意したいと思う。なぜなら、私はここで人間の欠点や不条理な行為を語ることを欲して、諸物の本性およびその諸特質を証明しようとは欲していなかったなどと人に誤解されないようにである。事実私は、第三部の序言で述べたように、人間の諸感情およびその諸特質をその他の自然物と同様に考察する者である。そしてたしかに人間の諸感情は、人間の能力を表示するものでないにしても、少なくとも自然の能力および技巧を表示するものであって、その点は、我々が驚嘆しかつその観想を楽しむ他の多くのものと何ら異なるところがないのである。
しかし私はひきつづき、諸感情について、いかなる点が人間に利益をもたらし、いかなる点が人間に害悪を与えるかを注意することにする。
定理五八 名誉は理性に矛盾せず、理性から生ずることができる。
証明 感情の定義三〇および端正の定義から明らかである。端正の定義についてはこの部の定理三七の備考一を見よ。
備考 いわゆる虚名〔虚しき名誉〕とは単に民衆の意見によってはぐくまれる自己満足であって、この意見が終熄すれば満足そのもの、言いかえれば(この部の定理五二の備考により)各人の愛する最高の善も終熄する。それで、民衆の意見の裡に名誉を求める者は、名声を維持するために日日心配と不安の中に努力し、行動し、企てることになる。実に民衆は移り気で無定見であって、名声はうまく維持しなければたちまち消失するからである。のみならずすべての人間が民衆の喝采を博そうと欲するがゆえに、各人は好んで他人の名声を阻止する。そこで、最高と評価される善を得ようと争うのであるから、あらゆる方法で仲間を圧倒しようとする激しい情熱が生ずる。そして最後に勝利者となる者は、自己を益したことによりも他人を害したことにより多く名誉を見いだす。このようにしてこの名誉ないし満足は何の満足でもないのだから、実は空虚なものなのである。 (民衆、名誉) 70
恥辱について注意すべきことは同情および後悔について述べたことから容易に推知される。ただここに付け加えたいのは、恥辱もまた、憐情と同様に、徳ではないけれども、それは、恥辱を感ずる人間には端正な生活を営もうとする欲望が存している証拠である限りにおいて善であるということである。あたかも苦痛が身体の損傷部分のまだ腐敗しない証拠である限りにおいて善と言われるのと同様に。ゆえにある行為を恥じる人間は実際は悲しみを感ずるけれども、端正な生活を営もうとする欲望を有しない無恥の人よりも完全なのである。
以上が喜びおよび悲しみの感情について私の注意しようと思ったことである。ところで欲望に関して言えば、それはたしかに善き感情あるいは悪しき感情から生ずるに従って善きものあるいは悪しきものである。しかし欲望は受動という感情から我々の中に生ずる限り実はすべて盲目的である(この部の定理四四の備考で述べたことから容易に推知されるように)。そしてもし人間が単に理性の指図のみに従って生活するようにたやすく導かれうるとしたら、そうした欲望はまったく無用なものであろう。私が次に簡単に示すだろうように。
定理五九 我々は受動という感情によって決定されるすべての活動へ、その感情なしにも理性によって決定されることができる。
証明 理性に従って働くとは(第三部定理三および定義二により)、我々の本性、単にそれ自体で観られた我々の本性、の必然性に由来する活動をなすことにほかならない。
ところでまず悲しみはこの活動能力を減少しあるいは阻害する限りにおいて悪なのである(この部の定理四一により)。ゆえに我々は悲しみの感情からは、理性によって導かれる場合になしえないようないかなる活動へも決定されることができない。
次に喜びは人間の活動能力を妨げる限りにおいて悪である(この部の定理四一および四三により)。したがって我々はそうした喜びからもまた、理性によって導かれる場合になしえないようないかなる活動へも決定されることができない。
最後に、善である限りにおける喜びは理性と一致する(なぜならそれは人間の活動能力が増大されあるいは促進される点に存するのだから)。そしてこういう喜びは人間が自己および自己の活動を妥当に認識するに足るまでに人間の活動能力を増大しえない限りにおいてのみ受動なのである(第三部定理三およびその備考により)。ゆえにもし喜びを感じている人間が自己および自己の活動を妥当に認識するほどの完全性にまで達しえたとしたら、彼は、いま受動という感情によって決定されるのと同一の活動をなすことができるであろう。否いっそう多くできるであろう。
ところがすべての感情は喜び、悲しみあるいは欲望に還元されるのであり(感情の定義四の説明を見よ)、そして欲望は(感情の定義一により)活動をなそうとする努力そのものにほかならない。このゆえに我々は、受動という感情によって決定されるすべての活動へ、その感情なしにも単に理性のみによって導かれることができる。Q・E・D・
別の証明 おのおのの活動は、我々が憎しみその他の悪しき感情に刺激されたという事実から発する限りにおいて悪と言われる(この部の定理四五の系一を見よ)。しかしそれ自体だけで観ればいかなる活動も善でも悪でもない(この部の序言で示したように)。むしろ同表動が時には善であり時には悪である。ゆえに現充着であるような活動、すなわちある悪しき感情から生じている活動、その同じ活動へ我々は理性によって導かれることができる(この部の定理一九により)。Q・E・D・
備考 このことは例を挙げることによっていっそう明瞭に説明される。すなわち殴打という行動は、我々がこれを物理的に見て、人間が腕を上げ、拳を固め、力をこめて全腕を振り下すということのみを眼中に置く限り、人間身体の機構から考えられる一個の徳である。そこでもしある人間が怒りもしくは憎しみから挙を固め、あるいは腕を振り下すように決定されるとしたら、そうしたことは、我々が第二部で示したように、同一の行動がありとあらゆる物の表象像と結合されうるがゆえに起こるのである。したがって我々は混乱して認識する物の表象像によっても、また明瞭判然と認識する物の表象像によっても、同一の行動へ決定されうるのである。だからもし人間が理性によって導かれうるとしたら、受動という感情から生ずるすべての欲望はまったく無用であることは明白である。今や我々は受動という感情から生ずる欲望がなぜ我々によって盲目的と呼ばれるかの理由を見ることにしよう。
定理六〇 身体のすべての部分にでなくその一部分あるいは若干部分にのみ関係する喜びあるいは悲しみから生ずる欲望は人間全体の利益を顧慮しない。
証明 例えば身体のAという部分がある外部の原因の力によって強められて他の諸部分より優勢になると仮定すると(この部の定理六により)、この部分は、それだからといって、身体のその他の部分にその機能を果させるために自分の力を失おうと努めるようなことはしないであろう。なぜなら、そうしたことをするには、その部分は自己の力を失う力ないし能力を持たなければならぬであろうが、そうしたことは(第三部定理六により)不条理だからである。ゆえにその部分、したがって(第三部定理七および一二により)精神もまた、その状態を維持することに努めるであろう。このゆえに、そうした喜びの感情から生ずる欲望は全体を顧慮しない。また反対に、Aという部分の働きが阻害されて他の部分がそれより優勢になる場合を仮定すれば、こういう悲しみから生ずる欲望もまた全体を顧慮しないということが同じ仕方で証明される。Q・E・D・
備考 ところで喜びは大抵身体の一部分のみに関係するのだから(この部の定理四四の備考により)、このゆえに、我々は多くの場合、我々の有の推持を欲しながら全身の健康を顧慮していないことになる。これに加えて我々を最も強く拘束する諸欲望は(この部の定理九の系により)現在のみを顧慮して未来を考慮しないのである。
定理六一 理性から生ずる欲望は過度になることができない。
証明 欲望は、一般的に見れば、人間の本質が何らかの仕方であることをなすように決定されると考えられる限りにおいて、人間の本質そのものである(感情の定義一により)。ゆえに理性から生ずる欲望、言いかえれば(第三部定理三により)働きをなす限りにおいて我々の中に生ずる欲望は、人間の本質が単に人間の本質のみから妥当に考えられる事柄をなすように決定されると考えられる限りにおいて人間の本質ないし本性そのものである(第三部定義二により)。だからもしこういう欲望が過度になりうるとしたら、それ自体で見られた人間本性が自己自身を超脱しうることになるであろう。すなわち人間本性がその能力にあることよりももっと多くのことをなしうることになるであろう。これは明白な矛盾である。したがってこういう欲望は過度になることができない。Q・E・D・
定理六二 精神は、理性の指図に従って物を考える限り、観念が未来あるいは過去の物に関しようとも現在の物に関しようとも同様の刺激を受ける。
証明 精神は理性の導きのもとに考えるすべてのものを同じく永遠ないし必然の相のもとに考え(第二部定理四四の系二により)、かつそれについて同じ確実性を有する(第二部定理四三およびその備考により)。ゆえに観念が未来あるいは過去の物に閲しようとも現在の物に関しようとも、精神は同じく必然的なものとしてその物を考えかつそれについて同じ確実性を有する。そしてその観念は、未来あるいは過去の物に関しようとも現在の物に関しようともそのいずれの場合でも同等に真であろう(第二部定理四一により)。言いかえればその観念は(第二部定義四により)そのいずれの場合でも常に妥当な観念の持つ同一の特質を有するであろう。したがって精神は、理性の指図に従って物を考える限り、観念が未来あるいは過去の物に関しようとも現在の物に関しようとも、同様の刺激を受ける。Q・E・D・
備考 もし我々が物の持続について妥当な認識を有し、物の存在の時を理性によって決定しうるとしたら、我々は未来の物を現在の物と同一の感情で観想したであろう。そして精神は未来のものとして考える善を現在の善と同様に欲求したであろう。したがってまた精神はより小なる現在の善をより大なる未来の善のために必ずや断念し、また現在において善であるが未来の悪の原因となるような物を決して欲求しなかったであろう。我々が間もなく証明するであろうように。ところが我々は物の持続についてきわめて非妥当な認識しか持つことができぬし( 第二部定理三一 により)、また物の存在の時を単に表象力のみによって決定する( 第二部定理四四の備考により)。そしてこの表象力なるものは現在の物の表象像と未来の物の表象像とからでは同様な刺激は受けない。この結果として、我々の有する善および悪の真の認識は抽象的ないし一般的なものにすぎず、また現在我々にとって、何が善であり悪であるかを決定しうるために物の秩序および原因の連結について我々の下す判断は、実際に合致したものであるよりもむしろ表象的なものにすぎぬということになる。ゆえに、善および悪の認識が未来に関する限り、その認識から生ずる欲望が、現在において快を与える物への欲望によって容易に抑制されうることも怪しむに足りない。これについてはこの部の定理一六を見よ。
定理六三 恐怖に導かれて、悪を避けるために善をなす者は、理性に導かれていない。
証明 働きをなす限りにおいての精神に関係する感情、言いかえれば(第三部定理三により)理性に関係する感情は、すべて喜びの感情と欲望の感情だけである(第三部定理五九により)。したがって(感情の定義一三により)恐怖に導かれて悪に対する危惧(きぐ)から善をなす者は理性に導かれていないわけである。Q・E・D・
備考 徳を教えるよりも欠点を非難することを心得、また人々を理性によって導く代りに恐怖によって抑えつけて徳を愛するよりも悪を逃れるように仕向ける迷信家たちは、他の人々を自分たちと同様に不幸にしようとしているのにほかならない。それで彼らが多くの場合人々の不快の種となり、人々に憎まれるというのも怪しむに足りないのである。
系 理性から生ずる欲望によって我々は直接に善に就き、間接に悪を逃れる。
証明 なぜなら、理性から生ずる欲望は受動でない喜びの感情のみから生じうる(第三部定理五九により)。言いかえれば過度になりえない喜びから生じうる(この部の定理六一により)。そして悲しみからは生じない。ゆえにこの欲望は(この部の定理八により)善の認識から生じ、悪の認識からは生じない。それゆえ我々は理性の導きに従って直接に善を欲求しまたその限りにおいてのみ悪を逃れる。Q・E・D・
備考 この系は病人と健康者の例によって説明される。病人は自分の嫌いなものを死に対する恐れのゆえに食べる。これに反して健康者は食物を楽しみ、そして死を恐れて死を直接に避けようと欲する場合よりもいっそうよく生を享受する。同様に、憎しみや怒りなどからでなく単に公共の安寧を愛するために罪人に死を宣告する裁判官は、理性のみによって導かれる者である。
定理六四 悪の認識は非妥当な認識である。
証明 悪の認識は(この部の定理八により)我々に意識された限りにおける悲しみそのものである。ところが悲しみはより小なる完全性への移行であり(感情の定義三により)、したがって悲しみは人間の本質自身によっては理解されえない(第三部定理六および七により)。ゆえに悲しみは(第三部定義二により)受動であって非妥当な観念に依存するものである(第三部定理三により)。したがって(第二部定理二九により)悲しみの認識、ひいては悪の認識は非妥当な認識である。Q・E・D・
系 この帰結として、人間の精神は、もし妥当な観念しか有しないとしたら、悪に関するいかなる概念も形成しないであろうということになる。
定理六五 理性の導きに従って我々は、二つの善のうちより大なるものに、また二つの悪のうちより小なるものに就くであろう。
証明 我々がより大なる善を享受することを妨げるような善は、実は悪である。なぜなら(この部の序言で示したように)物は我々がそれを相互に比較する限りにおいてのみ悪あるいは善と言われるからである。また(同じ理由により)より小なる悪は実は善である。ゆえに理性の導きに従って我々は(この部の定理六三の系により)より大なる善およびより小なる悪のみを欲求するであろう、あるいはそれのみに就くであろう。Q・E・D・
系 理性の導きに従って我々は、より大なる善のためにより小なる悪に就き、またより大なる悪の原因たるより小なる善を断念するであろう。なぜなら、ここでより小と言われる悪は実は善であり、これに反してより小と言われる善は実は悪である。ゆえに我々は(この部の定理六三の系により)前者を欲求し後者を断念するであろう。Q・E・D・ 78
定理六六 理性の導きに従って我々は、より小なる現在の善よりはより大なる未来の善を、またより大なる未来の悪よりはより小なる現在の悪を欲求するであろう。
証明 もし精神が未来の物に関して妥当な認識を有しうるとしたら、精神は未来の物に対しても現在の物に対するのと同じ感情に刺激されるであろう(この部の定理六二により)。ゆえに我々が理性そのものを念頭に置く限り〜〜この定理で我々はそうした場合を仮定しているのである〜〜より大なる善ないし悪が未来のものと仮定されようと現在のものと仮定されようとそれは同じことである。このゆえに(この部の定理六五により)我々はより小なる現在の善よりはより大なる未来の善を、またより大なる未来の悪よりは云々。Q・E・D・
系 理性の導きに従って我々は、より大なる未来の善の原因たるより小なる現在の悪を欲求し、またより大なる未来の悪の原因たるより小なる現在の善を断念するであろう。この系は前定理に対して、定理六五の系が定理六五に対するのと同一の関係にある。
備考 そこでもしこれらのことをこの部の定理一八までに感情の力について述べたことどもと比較するなら、感情ないし意見のみに導かれる人間と理性に導かれる人間との間にどんな相違があるかを我々は容易に見うるであろう。すなわち前者は、欲しようと欲しまいと自己のなすところをまったく無知でやっているのであり、これに反して後者は、自己以外の何びとにも従わず、また人生において最も重大であると認識する事柄、そしてそのため自己の最も欲する事柄、のみをなすのである。このゆえに私は前者を奴隷、後者を自由人と名づける。なお自由人の心境および生活法について以下に若干の注意をしてみたい。
定理六七 自由の人は何についてよりも死について思惟することが最も少ない。そして彼の知恵は死についての省察ではなくて、生についての省察である。
証明 自由の人すなわち理性の指図のみに従って生活する人は、死に対する恐怖に支配されない(この部の定理六三により)。むしろ彼は直接に善を欲する(同定理の系により)。言いかえれば彼は(この部の定理二四により)自己自身の利益を求める原則に基づいて、行動し、生活し、自己の有を維持しようと欲する。したがって彼は何についてよりも死について思惟することが最も少なく、彼の知恵は生についての省察である。Q・E・D・
定理六八 もし人々が自由なものとして生まれたとしたら、彼らは自由である間は善悪の概念を形成しなかったであろう。
証明 私は理性のみに導かれる人を自由であると言った。そこで自由なものとして生まれかつ自由なものにとどまる人は妥当な観念しか有しない。またそのゆえに何ら悪の概念を有しない(この部の定理六四の系により)。したがってまた善の概念をも有しない(善と悪とは相関的概念であるから)。Q・E・D・
備考 この定理の仮定が誤りであること、そしてそれは人間本性だけを眼中に置く限りにおいてのみ、あるいはむしろ、無限なものとしての神ではなく、単に人間の存在の原因にすぎない神を眼中に置く限りにおいてのみ、考えられるのだということは、この部の定理四から明らかである。
このことや我々のすでに証明したその他のことどもは、モーゼが最初の人間に関するあの物語の中で暗示しているように見える。すなわちその物語の中では、人間を創造したあの能力、言いかえれば人間の利益のみを考慮したあの能力、以外のいかなる神の能力も考えられていない。そしてこの考え方にそって次のことが物語られている。すなわち神は自由な人間に対して善悪の認識の木の実を食うことを禁じた、そして人間はそれを食うや否や生を欲するよりもむしろ死を恐れた、それから人間は自己の本性とまったく一致する女性を発見した時、自然の中に自分にとって彼女より有益な何ものも存しえないことを認めた、しかし彼は動物が自分と同類であると思ってからはただちに動物の感情を模倣(第三部定理二七を見よ)して自分の自由を失い始めた。この失われた自由を、族長たちが、そのあとでキリストの精神、すなわち神の観念〜〜神の観念は人間が自由になるための、また前に証明したように(この部の定理三七により)人間が自分に欲する善を他の人々のためにも欲するようになるための、唯一の基礎である〜〜に導かれて再び回復したのであった。 (モーゼ)
定理六九 自由の人の徳は危難を回避するにあたっても危難を克服するにあたってと同様にその偉大さが示される。
証明 感情はそれと反対のかつそれよりも強力な感情によってでなくては抑制されることも除去されることもできない(この部の定理七により)。ところが盲目的大胆と〔盲目的〕恐怖とは等しい大いさのものと考えられうる感情である(この部の定理五および三により)。ゆえに大胆を抑制するには恐怖を抑制するのと等しい大いさの精神の徳すなわち精神の強さ(その定義は第三部定理五九の備考について見よ)を必要とする。言いかえれば(感情の定義四〇および四一により)自由の人は危難を克服しようと試みる時と同じ精神の徳をもって危難を回避する。Q・E・D・
系 このゆえに、自由の人にあっては、適時における逃避は戦闘と同様に大なる勇気の証明である。すなわち自由の人は戦闘を選ぶ時と同じ勇気ないし沈着をもって逃避を選ぶ。
備考 勇気とは何か、あるいは勇気ということを私がいかに解するかは第三部定理五九の備考において説明した。これに対して危難とは何らかの害悪すなわち悲しみ、憎しみ、不和などなどの原因となりうる一切のものと私は解する。
定理七〇 無知の人々の間に生活する自由の人はできるだけ彼らの親切を避けようとつとめる。
証明 各人は自己の意向に従って何が善であるかを判断する(第三部定理三九の備考を見よ)。ゆえに誰かに親切をなした無知の人はそれを自己の意向に従って評価するであろう。そして彼はそれを受けた人からそれがより小さく評価されるのを見るとしたら悲しみを感ずるであろう(第三部定理四二により)。ところが自由の人は他の人々と交友を結ぶことにはつとめるが(この部の定理三七により)、しかし彼らに対して彼らの感情から判断して同等とされるような親切を報いることにはつとめないでむしろ自己ならびに他の人々を自由な理性の判断によって導こうとし、彼自身が最も重要として認識する事柄のみをなそうとつとめる。ゆえに自由の人は、無知の人々から憎しみを受けぬために、そしてまた彼らの衝動にでなく単に理性のみに従うために、彼らの親切をできるだけ避けようと努めるであろう。Q・E・D・
備考 私は「できるだけ」という。なぜなら彼らは無知な人間であってもやはり人間であって危急な場合には、何より貴重な人間的援助をなしうる。このゆえに彼らから親切を受け、したがってまた彼らに対し彼らの意向に従って感謝を示すことの必要な場合がしばしば起こるのである。これに加えて、親切を避けるにあたっても、我々が彼らを軽蔑するかに見えぬように、あるいは我々が貧欲のゆえに報酬を恐れるかに見えぬように、慎重にしなくてはならぬ。すなわち彼らの憎しみを逃れようとしてかえって彼らを憤らせるようなことがあってはならぬ。ゆえに親切を避けるにあたっては、何が利益であるか何が端正であるかを考慮しなければならぬ。
定理七一 自由の人々のみが相互に最も多く感謝しあう。
証明 自由の人々のみが相互に最も有益であり、かつ最も固い友情の絆をもって相互に結合する(この部の定理三五およびその系一により)。そして同様な愛の欲求をもって相互に親切をなそうと努める(この部の定理三七により)。したがって(感情の定義三四により)自由の人々のみが相互に最も多く感謝しあう。Q・E・D・
備考 盲目的な欲望に支配される人々が相互に示すような感謝は、多くは感謝というよりもむしろ取引あるいは計略(アウクビウム)である。
次に忘恩は感情でない。しかし忘恩は非礼なことである。なぜなら、それは多くは人間が過度の憎しみ、怒り、高慢、食欲などに据われていることを示すものだからである。というのは愚かであるために贈与に報いることを知らない者は忘恩的と言われない。ましてや情婦の贈物によって彼女の情欲(または色情)に奉仕するように動かされない人、あるいは盗賊の贈物によって盗賊の盗品を隠匿(いんとく)するように動かされない人、その他この種の人間の贈物によって動かされない人はなおさら忘恩的とは言われない。いかなる贈物によっても自己あるいは社会の破滅になるような行ないへ誘惑されない人は、確固たる精神の所有者であることを示しているからである。
定理七二 自由の人は決して詐(いつわ)りの行動をせず常に信義をもって行動する。
証明 もし自由の人が自由である限りにおいて何らかの詐りの行動をするとしたら、彼はそれを理性の指図に従ってなしたであろう(なぜなら理性の指図に従って行動する限りにおいてのみ人は自由であると呼ばれるのだから)。ゆえに詐りの行動をなすことが徳であることになろう(この部の定理二四により)。したがってまた(同定理により)各人にとって、自己の有を維持するためには詐りの行動をすることがより得策であることになろう。言いかえれば(それ自体で明らかなように)人々にとっては単に言葉においてのみ一致して事実においては相互に対立的であることがより得策であることになろう。これは(この部の定理三一の系により)不条理である。ゆえに自由の人は云々。Q・E・D・
備考 ここに次のような問いがなされるかもしれぬ。もし人間が背信によって現在の死の危難から救われうるとしたらどうであろう。その場合、自己の有の維持をたてまえとする理性は無条件で人間に背信的であるように教えるのではないかと。これに対しては上にならって次のような答えがなされるであろう。もし理性がそうしたことを教えるとしたら理性はそれをすべての人々に教えることになる。したがって理性は一般に人々に、相互の協力および共通の法律の遵守への約束を、常に詐(いつわ)って結ぶように教えることになる。言いかえれば結局共通の法律を有しないように教えることになる。しかしこれは不条理である。
定理七三 理性に導かれる人間は、自己自身にのみ服従する孤独においてよりも、共同の決定に従って生活する国家においていっそう自由である。 (国家)
証明 理性に導かれる人間は恐怖によって服従に導かれることがない(この部の定理六三により)。むしろ彼は、理性の指図に従って自己の有を維持しようと努める限りにおいて、言いかえれば(この部の定理六六の備考により)自由に生活しようと努める限りにおいて、共同の生活および共同の利益を考慮し(この部の定理三七により)、したがってまた(この部の定理三七の備考二で示したように)国家の共同の決定に従って生活することを欲するのである。ゆえに理性に導かれる人間は、より自由に生活するために、国家の共通の法律を守ることを欲する。Q・E・D・
備考 このことおよび我々が人間の真の自由について示したこれと類似のことどもは精神の強さに、言いかえれば(第三部定理五九の備考により)勇気と寛仁とに帰せられる。しかし私は精神の強さのすべての特質をここで一々証明することを必要とは思わない。ましてや毅然とした精神の人間が何びとをも憎まず、何びとをも怒らず、ねたまず、憤慨せず、何びとをも軽蔑せずまた決して高慢でないことを証明するのはなおさら必要であるまい。なぜならこのことおよび真の生活や宗教に関するすべてのことは、この部の定理三七および四六から容易に理解されうるからである。すなわち憎しみは愛によって征服されなければならぬということ、および理性に導かれる各人は自分のために欲求する善を他の人々のためにも欲するということから容易に理解されるのである。これに加えて、我々がこの部の定理五〇の備考およびその他の諸個所で注意したことがある。それによれば、毅然とした精神の人間は、一切が神の本性の必然性から生ずることを特に念頭に置き、したがってすべて不快に、邪悪に思われるもの、さらにすべて不敬に、嫌悪的に、不正に、非礼に見えるものは、事物をまったく顛倒し、毀損し、混乱して考えることから起こることを知っている。そこで彼は事物をそのあるがままに把握しようとし、また真の認識の障害になるもの〜〜例えば憎しみ、怒り、ねたみ、嘲笑、高慢その他我々が前に注意したこの種のことども〜〜を除去することに最も努める。それゆえまた彼は、すでに述べたように、できるだけ「正しく行ないて自ら楽しむ」ことに努めるのである。
しかしこれを達成するにあたって人間の徳はどの程度まで及び、そしてまた何をなしうるかは次の部で証明するであろう。
付 録 86
この部で正しい生活法について述べたことは一覧して見通せるようなふうには配列されていない。私は、一を他からより容易に導き出しえたところに従って分散的にこれを証明しているのである。だから私はここでそれを総括して主要項目に還元してみることにした。
第一項 我々のすべての努力ないし欲望は我々の本性の必然性から生ずるのであるが、それは、その最近原因としての我々の本性のみによって理解されるような仕方で生ずるか、それとも我々が他の個体なしに自身だけでは妥当に考えられないような自然の一部分である限りにおいて生ずるか、そのどちらかである。
第二項 我々の本性のみによって理解されるような仕方で我々の本性から生ずる欲望は、妥当な観念から成ると考えられる限りにおける精神に帰せられる欲望である。これに反してその他の欲望は、物を非妥当に考える限りにおける精神にのみ帰せられる。そして後者のような欲望の力および発展は、人間の能力によってではなく、我々の外部にある諸物の力によって規定されなければならぬ。ゆえに前者のごとき欲望は能動と呼ばれ、後者のごとき欲望は受動と呼ばれるべきである。なぜなら、前者は常に我々の能力を表示し、反対に後者は我々の無能力および毀損した認識を表示するからである。
第三項 我々の能動〜〜言いかえれば人間の能力ないし理性によって規定されるような欲望〜〜は、常に善であり、これに反してその他の欲望は、善でも悪でもありうる。
第四項 だから人生において何よりも有益なのは知性ないし理性をできるだけ完成することであり、そしてこの点にのみ人間の最高の幸福すなわち至福は存する。なぜなら、至福とは神の直観的認識から生ずる精神の満足そのものにほかならないのであり、他方、知性を完成するとはこれまた神、神の諸属性、および神の本性の必然性から生ずる諸活動を認識することにほかならないからである。ゆえに理性に導かれる人間の究極目的、言いかえれば、彼が他のすべての欲望を統御するにあたって規準となる最高欲望は、彼自身ならびに彼の認識の対象となりうる一切の物を妥当に理解するように彼を駆る欲望である。 (至福、知性,欲望)
第五項 だから妥当な認識なしには理性的な生活というものはありえない。そして物は、妥当な認識作用を本領とする精神生活を享受することにおいて人間を促進する限り、その限りにおいてのみ善である。これに反して人間が理性を完成して理性的な生活を享受するのに妨げとなるもの、そうしたもののみを我々は悪と呼ぶのである。
第六項 しかし人間自身を起成原因として生ずるすべてのものは必然的に善なのであるから、したがって悪は人間にとってただ外部の原因からのみ起こりうる。すなわち人間が全自然の一部分であってその諸法則に人間本性は服従するように迫られ、ほとんど無限に多くの仕方で人間本性は全自然に順応するように強いられる、ということからのみ悪は人間に起こりうるのである。
第七項 しかも人間が自然の一部分でないということ、また人間が自然の共通の秩序に従わないということは不可能である。だがもし人間が自己自身の本性と一致するような個体の間に生活するなら、まさにそのことによって人間の活動能力は促され、養われるであろう。これに反してもし自己の本性と全然一致しないような個体の間に在るなら、彼は自己自身を大いに変化させることなしには彼らに順応することがほとんど不可能であろう。
第八項 自然の中に存在するもので我々がそれを悪である、あるいは我々の存在ならびに理性的な生活の享受に妨害となりうる、と判断するもの、そうしたすべてのものを我々は最も確実と思える方法で我々から遠ざけてよい。これに反してそれは善である、あるいは我々の有の維持ならびに理性的な生活の享受に有益である、と我々の判断するものが存するなら、我々はそうしたすべてのものを我々の用に供し、あらゆる仕方でこれを利用してよい。一般的に言えば、各人は自己の利益に寄与すると判断する事柄を最高の自然権によって遂行することが許されるのである。
第九項 ある物の本性と最もよく一致しうるものはそれと同じ種類に属する個体である。したがって(第七項により)人間にとってその有の維持ならびに理性的な生活の享受のためには、理性に導かれる人間ほど有益なものはありえない。ところで、個物の中で理性に導かれる人間ほど価値あるものを我々が知らないのであるからには、すべて我々は人々を教育してついに人々を各自の理性の指図に従って生活するようにさせてやることによって、最もよく自分の技倆と才能を証明することができる。
第一〇項 人間は相互に対してねたみあるいは何らかの憎しみの感情に駆られる限りその限りにおいて相互に対立的である。したがってまた、人間は自然の他の個体よりいっそう有能であるだけにそれだけ相互にいっそう恐るべき敵なのである。 (人間、恐るべき敵)
第一一項 しかし人間の心は武器によってでなく愛と寛仁とによって征服される。
第一二項 人間にとっては、たがいに交わりを結び、そして自分たちすべてを一体となすのに最も適するような紐帯によって相互に結束すること、一般的に言えば、友情の強化に役立つような事柄を行なうこと、これが何より有益である。
第一三項 しかしこれをなすには技倆と注意が必要である。なぜなら、人間というものは種々多様であり(理性の指図に従って生活する者は稀であるから)、しかも一般にねたみ深く、同情によりも復讐に傾いている。ゆえに彼らすべての意向に順応し、それでいて彼らの感情の模倣に陥らないように自制するには、特別な精神の能力を要する。一方、人間を非難し、徳を教えるよりは欠点をとがめ、人間の心を強固にするよりはこれを打ち砕くことしか知らない人は、自分でも不快であり他人にも不快を与える。このような次第で多くの人は、過度の性急さと誤った宗教熱とのゆえに、人間の間に生活するよりも野獣の間に生活することを欲した。これは親の叱責を平気で堪えることができない少年もしくは青年が家を捨てて軍隊に走り、家庭の安楽と父の訓戒との代りに戦争の労苦と暴君の命令とを選び、ただ親に復讐しようとするためにありとあらゆる負担を身に引受けるのにも似ている。 (軍隊)
第一四項 このように人間は大抵自己の欲望に従って一切を処理するものであるけれども、人間の共同社会からは損害よりも便利がはるかに多く生ずる。ゆえに彼らの不法を平気で堪え、和合および友情をもたらすのに役立つことに力を至すのがより得策である。
第一五項 この和合を生むものは正義、公平、端正心に属する事柄である。なぜなら人間は不正義なこと、不公平なことばかりでなく非礼と思われること、すなわち国家で認められている風習が何びとかに犯されるようなことも堪えがたく感ずるからである。さらに進んで愛を得るには宗教心および道義心に属することが最も必要である。これらのことについては第四部の定理三七の備考一と二、定理四六の備考および定理七三の備考を見よ。
第一六項 そのほかに和合はしばしば恐怖から生まれるのが常である。しかしこれは信義の裏づけのない和合である。これに加えて、恐怖は精神の無能力から生ずるものであり、したがって理性にとっては無用である。あたかも憐憫が道義心の外観を帯びているにもかかわらず理性にとって無用であるのと同様に。
第一七項 なおまた人間は施与によっても征服される。特に生活を支える必需品を調達するすべを持たない人々はそうである。しかしすべての困窮者に援助を与えることは一私人の力と利害をはるかに凌駕する。一私人の富はこれをなすのに到底及ばないからである。それにまたただ一人の人間の能力はすべての人と友情を結びうるにはあまりに制限されている。ゆえに貧者に対する配慮は社会全体の義務であり、もっぱら公共の福祉の問題である。 (福祉)
第一八項 親切を受け容れまた感謝を表わすにあたってはこれとまったく異なった配慮がなされなくてはならぬ。これについては第四部定理七〇の備考および定理七一の備考を見よ。
第一九項 なおまた肉的愛、言いかえれば外的美から生ずる生殖欲、また一般的には精神の自由以外の他の原因を持つすべての愛は容易に憎しみに移行する(ただしその愛が狂気の一種にまでなっている〜〜これはもっとしまつの悪い場合であるが〜〜ならこの限りでない)。こうした場合には和合よりも不和がいっそう多くはぐくまれる。第三部定理三一の備考を見よ。
第二〇項 結婚に関して一言えば、もし性交への欲望が外的美からのみでなく、子を生んで賢明に教育しようとする愛からも生ずるとしたら、その上もし両者〜〜男と女〜〜の愛が外的美のみでなく特に精神の自由にも基づくとしたら、それは理性と一致することが確実である。 (結婚)
第二一項 阿訣(あゆ)もまた和合を生ずるがそれは醜悪な屈従もしくは背信によってである。だが阿訣に最も多く捉えられるのは、第一人者たらんと欲してそうではない高慢な人間である。
第二二項 自卑には道義心および宗教心という虚偽の外観がつきまとっている。そして、自卑は高慢の反対であるけれども、自卑的な人間は高慢な人間に最も近い。第四部定理五七の備考を見よ。
第二三項 恥辱もまた和合に寄与するところがある。しかしこれは匿(かく)すことのできぬ事柄についてだけである。それに、恥辱そのものは悲しみの一種だから理性にとっては無用である。
第二四項 他人に対して向けられたその他の悲しみの感情は正義、公平、端正心、道義心および宗教心の正反対である。憤慨のごときは公平の外観を帯びているけれども、もし他人の行為について審判して自己もしくは他人の権利を擁護することが各人に許されるとしたら、人間は無法律で生活することになる。
第二五項 礼譲、言いかえれば人々の気に入ろうとする欲望は、それが理性によって決定される場合は道義心に属し(第四部定理三七の備考一で述べたように)、これに反してそれが感情から生ずる場合は名誉欲、すなわち人間が道義心の仮面のもとにしばしば不和と争闘をひき起こす欲望となる。なぜなら〔理性によって決定される人すなわち〕、他の人々が自分とともに最高の善を享受するように助言ないし実践をもって彼らを助けようと欲する人は、特に彼らの愛をかち得ようとつとめはするであろうが、彼らに驚嘆されて自分の教えが自分の名前によって呼ばれるようにしようとは努めないであろうし、また一般に、ねたみを招くようないかなる機縁をも作らないようにするであろう。また普通の会話においても人の短所を挙げることを慎み、人の無能力についてはわずかしか語らないように注意し、これと反対に、人間の徳ないし能力について、またそれを完成する方法については大いに語るようにするであろう。このようにして彼は、人々が恐怖や嫌悪からでなく、ただ喜びの感情のみに動かされてできるだけ理性の指図による生活をしようと努めるようにさせるであろう。
第二六項 自然の中で我々は人間のほかに、その物の精神を我々が楽しみうるような、また、我々がその物と友情あるいはその他の種類の交際を結びうるような、そうしたいかなる個物も知らない。ゆえに我々の利益というものを顧慮すれば、人間以外に自然に存するものをすべて保存するようなことは必要でない。むしろそれらをその種々多様な用途に従って保存したり、破壊したり、あるいはあらゆる方法でこれを我々の用に順応させたりするように我々の利益への顧慮は要求するのである。
第二七項 我々が我々以外の物から引き出す利益は、まず我々がそれらの物を観察したり、それらの物の形相をさまざまに変化させたりすることによって得られる経験と認識とであるが、そのほかには何といっても身体の維持ということである。この点から見れば、身体のすべての部分がその機能を正しく果しうるようなふうに身体を養いはぐくみうるものが何より有益である。なぜなら、身体が多くの仕方で刺激されうることに、また多くの仕方で外部の物体を刺激しうることにより適するのに従って、精神は思惟することにそれだけ適するからである(第四部定理三八および三九を見よ)。しかしそうした種類のものは自然の中にきわめてわずかしかないように見える。ゆえに身体を必要なだけ養うためには、本性を異にする多様の養分を取らなければならぬ。実際、人間身体は本性を異にするきわめて多くの部分から組織されていて、これらの部分は、全身がその本性上なしうるすべてのことに対して等しく適するためには、したがってまた精神が多くの事柄を把握することに等しく適するためには、たえず種々の養分を必要とするからである。
第二八項 しかしこれを調達するには、人間が相互に助け合わない限り、個々人の力だけではほとんど十分でないであろう。ところですべての物が簡単に貨幣で代表されるようになった。この結果として通常貨幣の表象像が大衆の精神を最も多く占めるようになっている。人々は、金銭がその原因と見られないような喜びの種類をほとんど表象することができないからである。
第二九項 しかしこうしたことは、欠乏や生活の必要から金銭を求める人々についてではなく、貨殖の術を学んでこれを誇りとするがゆえに金銭を求めるような人々についてのみ非難されるべきである。もともとこうした人々は習慣上身体を養ってはいるが身体の維持についやすものを財産の損失と信ずるがゆえに出し吝(お)しみしながら身体を養っている。これに反して金銭の真の用途を知り富の程度を必要によってのみ量る人々は、わずかなもので満足して生活する。
第三〇項 このように、身体の諸部分をその機能の遂行に関して促進するものが善であり、また喜びは人間の精神的および身体的能力が促進され増大されることに存するのだから、このゆえに、すべて喜びをもたらすものは善である。しかし一方、物は我々を喜びに刺激する目的ではたらいているのでなく、また物の活動能力は我々の利益に従って調整されるものでなく、最後にまた喜びは大抵の場合主として身体の一部分にのみ関係するのであるから、このゆえにおおむね喜びの感情は(もし理性と用心とを欠くならば)過度になり、したがってそれから生ずる欲望もまた過度になる。これに加えて、我々は現在において快適なものを感情に基づいて最も重要なものと思い、そして未来のものを精神の等しい感情をもって評価することができない。第四部定理四四の備考および定理六〇の備考を見よ。
第三一項 迷信はこれと反対に悲しみをもたらすものを善、喜びをもたらすものを悪と認めているように見える。だが、すでに述べたように(第四部定理四五の備考を見よ)、ねたみ屋以外のいかなる人間も私の無能力や苦悩を喜びはしない。なぜなら、我々はより大なる喜びに刺激されるに従ってそれだけ大なる完全性に移行し、したがってまたそれだけ多く神の本性を分有するからである。その上喜びは、我々の利益への正当な顧慮によって統御される限り、決して悪でありえない。これに反して、恐怖に導かれて悪を避けるために善をなす者は、理性に導かれていないのである。 (四定理45系2備考)
第三二項 しかし人間の能力はきわめて制限されていて、外部の原因の力によって無限に凌駕される。したがって我々は、我々の外に在る物を我々の使用に適合させる絶対的な力を持っていない。だがたとえ我々の利益への考慮の要求するものと反するようなできごとに遇っても、我々は自分の義務を果したこと、我々の有する能力はそれを避けうるところまで至りえなかったこと、我々は単に全自然の一部分であってその秩序に従わなければならぬこと、そうしたことを意識する限り、平気でそれに耐えるであろう。もし我々がこのことを明瞭判然と認識するなら、妥当な認識作用を本領とする我々自身のかの部分、すなわち我々自身のよりよき部分はそれにまったく満足し、かつその満足を固執することに努めるであろう。なぜなら、我々は妥当に認識する限りにおいて、必然的なもの以外の何ものも欲求しえず、また一般に、真なるもの以外の何ものにも満足しえないからである。それゆえに、我々がこのことを正しく認識する限り、その限りにおいて、我々自身のよりよき部分の努力〔欲望〕は全自然の秩序と一致する。
第四部 終り
序言、
公理、一、二、
定理、
一、二、三、四、五、六、七、八、九、一〇、一一、一二、一三、一四、一五、一六、一七、一八、一九、二〇、
二一、二二、二三、二四、二五、二六、二七、二八、二九、三〇、三一、三二、三三、三四、三五、三六、三七、三八、三九、四〇、
四一、四二、第四部TOP、第五部TOP、TOP☆
知性の能力あるいは人間の自由について
序 言
最後に私は自由に達する方法ないし道程に関する倫理学(エチカ)の他の部分に移る。私はこの部で理性の能力について論ずるであろう。すなわち理性そのものが感情に対して何をなしうるかを示し、次に精神の自由ないし至福とは何であるかを示すであろう。これによって我々は賢者が無知者よりどれだけ有能であるかを見るであろう。しかし知性はいかなる方法、いかなる道程で完成されなければならぬか、さらにまた身体はその機能を正しく果しうるためにはいかなる技術で養護されなければならぬかはここには関係しない。なぜなら後者は医学に属し、前者は論理学(ロギカ)に属するからである。ゆえにここでは、今も言ったように、精神ないし理性の能力だけについて論ずるであろう。特に、それが感情を抑制し統御するために、感情に対してどれだけ大きなまたどのような種類の権力を有するかを示すであろう。なぜなら、我々が感情に対して絶対的権力を有しないことはすでに前に証明したからである。
ストア学派では感情が絶対に我々の意志に依存して我々は感情を絶対に支配しうると信じていた。けれども彼らは、経験の抗議により、彼ら自身の原理に反して、「感情を抑制し統御するには少なからぬ訓練と労力を要する」ということを容認せざるをえなくなった。ある人はこれを(私の記憶に誤りがなければ)二匹の犬、一は家犬、他は猟犬、の例によって示そうと試みた。すなわちその人は訓練によってついに、家犬が猟をするように、また反対に猟犬が野兎を追うことを止めるように、慣らすことができたというのである。 98
デカルトも少なからずこの意見に傾いている。なぜなら彼は、魂つまり精神は松果腺と呼ばれる脳の一定部分と特別に結合していること、この腺を介して精神は身体内に起こるすべての運動ならびに外部の対象を感覚すること、そして精神は単に意志するだけでこの腺を種々さまざまに動かしうること、そうしたことを主張しているからである。
彼の主張によれば、この腺は脳の中央に懸(かか)っていて動物精気のごく微細な運動によっても動かされうるようになっている。なお、動物精気が多くの異なった仕方でこの腺を衝くのに応じてこの腺は脳の中央においてそれだけ多くの異なった状態を呈すること、さらにまた動物精気をこの腺に向かって推進せしめる外部の対象が種々異なるのに応じてそれだけ多くの異なった痕跡がこの腺に刻印されることを彼は主張している。したがって、もし松果腺があとで、これを多種多様に動かしうる精神の意志によって、かつてさまざまに刺激された精気の活動のもとに呈したことのあるこのあるいはかの状態を呈すると、今度はこの腺自身が、以前にこれと類似の腺状態において動物精気を体内に押し戻したのと同じ仕方で、精気を推進せしめかつ指導するようになる。
なおまた彼は精神のそれぞれの意志が自然的に一定の腺運動と結合していると主張する。例えばある人が遠方の対象を見ようとする意志を持つなら、この意志は瞳孔の拡大をひき起こすであろう。しかし単に瞳孔を拡大しようと思う場合、その意志を持っても瞳孔は拡大しないであろうなぜなら自然は、瞳孔の拡大ないし縮小をきたすように精気を視神経へ推進せしめる役目をなす腺運動を、瞳孔を拡大ないし縮小しようとする意志とは連結しないで、遠くのあるいは近くの対象を見ようとする意志にのみ連結したからである。
最後に彼は、この腺のそれぞれの運動は我々が生まれた時以来自然的に我々のそれぞれの思想と連絡されているように見えるけれども、それにもかかわらずこの運動を習慣によって他の思想と連結することもできると主張し、これを彼は『感情論』第一部第五〇節で証明しようと試みている。 (デカルト『感情論』)
これによって彼は、いかなる精神も、適当に指導されるならば、自己の感情〔受動感情〕に対して絶対権を得られないほど薄弱なものではないと結論する。なぜなら、感情は彼の定義に従えば「知覚あるいは感覚あるいは精神の動きであって、これらはもっばら精神の領域に属し、そしてこれらは(ここに注意!)精気のある運動によって産出され、維持され、強化される」のである(『感情論』第一部第二七節を見よ)。ところが我々は松果腺の各運動を、したがってまた動物精気の各運動を、任意の意志と結合することができるのであり、また意志の決定は我々の力にのみ依存するのであるから、このゆえにもし我々が自分の生活活動の規準としている一定の確実な判断によって自分の意志を決定し、そして自分の持とうと欲する感情の動きをこれらの判断と結合するならば、我々は自分の感情に対して絶対的権力をかち得ることになるであろう。
これがかの有名な人の見解である(私が彼の言葉から推知する限り)。もしこの見解がこれほど尖鋭なものでなかったとしたら、私はそれがこのように偉大な人から出たとはほとんど信じなかったであろう。それ自体で明白な諸原理からでなくては何ごとも導出せぬことを、また明瞭判然と知覚したことがら以外の何ごとも肯定しないことを断乎と主張し、スコラ学派が不明瞭な物を隠れた性質によって説明しようと欲したことをあれほどしばしば非難した哲学者その人が、あらゆる隠れた性質よりもいっそう隠微な仮説を立てるとは実に不思議にたえないのである。 100
いったい彼は、精神と身体との結合をいかに解しているのか。またいったい彼は、延長のある小部分〔松果腺〕と最も密接に結合した思惟についていかなる明瞭判然たる概念を有しているのか。
実に私は彼がこの結合をその最近原因によって説明して欲しかったのである。ところが彼は精神を身体から截然(せつぜん)と区別して考えていたので、この結合についても、また精神自身についても、何ら特別な原因を示すことができないで、全宇宙の原因へ、すなわち神へ、避難所を求めざるをえなかったのである。それから私は、精神がいかなる程度の動きをかの松果腺に与えうるのか、またどれだけの力で精神は松果腺をある状態に保ちうるのかを知りたい。なぜならこの腺は、精神によって動かされる場合、動物精気によって動かされる場合よりもより遅く動くのかそれともより速く動くのか、また我々が確実な判断と密接に結合させた感情の動きが物体的原因によって再びこれらの判断から分離するということがありえないかどうか、そうしたことについて私は何も聞いていないからである。もしそういうことがありうるとしたら、たとえ精神が断乎と危難に赴こうと企て、この決意に大胆という心の動きを結合するとしても、危難を目撃するや否や松果腺がある状態を呈してそのため精神が逃亡しか思惟しないというようなことにもなるであろう。しかし実際のところは、意志と運動との間には何の関係もないのだから、精神の能力ないし力と身体の能力ないし力との間には何の比較もありえないのである。したがってまた身体の力は決して精神の力によって決定されえないのである。その上に、この腺が脳の中央に懸っていて、そのように容易にまたそのように多くの仕方で動かされうるということはないのであり、またすべての神経がみな脳窩(のうか)にまで続いているわけではないのである。
最後に彼が意志およびその自由について主張したすべての事柄はこれを省略する。なぜなら、それらが誤りであることは私の十二分に明らかにしたところであるから。
ところで、精神の能力は、さきに私の示したように、もっぱら妥当な認識作用にのみあるのであるから、感情に対する療法〜〜私の信ずるところではそうしたものを誰でもみな経験して知っているのであって、ただそれを正確に観察したり判然と識別したりしていないだけなのである〜〜を我々はただ精神の認識によって決定し、精神の至福に関するすべてのことをこの認識から導き出すであろう。
公 理
一 もし同じ主体の中に二つの相反する活動が喚起されるならば、両者が相反することを止めるまでは、両者の中にか両者の一方の中にか必ずある変化が起こらざるをえないであろう。
二 結果の本質がその原因の本質によって説明され・規定される限り、結果の力はその原因の力によって規定される。
この公理は第三部定理七から明らかである。 102
定理一 思想および物の観念が精神の中で秩序づけられ・連結されるのにまったく相応して、身体の変状あるいは物の表象像は身体の中で秩序づけられ・連結される。
証明 観念の秩序および連結は物の秩序および連結と同一であり(第二部定理七により)、また逆に物の秩序および連結は観念の秩序および連結と同一である(第二部定理六および七の系により)。ゆえに観念の秩序および連結が精神の中で身体の変状の秩序および連結に相応して行なわれるように(第二部定理一八により)、逆に(第三部定理二により)身体の変状の秩序および連結は思想および物の観念が精神の中で秩序づけられ・連結されるのに相応して行なわれる。Q・E・D・
定理二 もし我々が精神の動きあるいは感情を外部の原因の思想から分離して他の思想と結合するならば、外部の原因に対する愛あるいは憎しみ、ならびにそうした感情から生ずる精神の動揺は破壊されるであろう。
証明 なぜなら、愛あるいは憎しみの形相を構成するものは外部の原因の観念を伴った喜びあるいは悲しみである(感情の定義六および七により)。ゆえにこの観念が除去されれば愛あるいは憎しみの形相も同時に除去される。したがってそうした感情ならびにそれから生ずる諸感情は破壊される。Q・E・D・
定理三 受動という感情は、我々がそれについて明瞭判然たる観念を形成するや否や、受動であることを止める。
証明 受動という感情は混乱した観念である(感情の総括的定義により)。ゆえにもし我々がその感情について明瞭判然たる観念を形成するならば、この観念と、精神のみに関係する限りにおいての感情そのものとの間には、ただ見方の相違以外のいかなる柑違もないであろう(第二部定理二一およびその備考により)。したがって(第三部定理三により)感情は受動であることを止めるであろう。Q・E・D・
系 ゆえに我々が感情をよりよく認識するに従って感情はそれだけ多く我々の力の中に在り、また精神は感情から働きを受けることがそれだけ少なくなる。
定理四 我々が何らかの明瞭判然たる概念を形成しえないようないかなる身体的変状も存しない。
証明 すべての物に共通したものは妥当にしか考えられ〔概念され〕えない(第二部定理三八により)。したがって(第二部定理一二、および定理一三の備考のあとにある補助定理二により)我々が何らかの明瞭判然たる概念を形成しえないようないかなる身体的変状も存しない。Q・E・D・
系 この帰結として、我々が何らかの明瞭判然たる概念を形成しえないようないかなる感情も存しないことになる。なぜなら、感情は身体の変状の観念であり(感情の総括的定義により)、したがって(前定理により)その中には何らかの明瞭判然たる概念が含まれていなければならぬからである。
備考 存在するすべてのものは必ず何らかの結果を生ずるのであり(第一部定理三六により)、また我々は我々の中における妥当な観念から生ずるすべてのものを明瞭判然と認識するのであるから(第二部定理四〇により)、この帰結として、各人は自己ならびに自己の諸感情を、たとえ絶対的にでないまでも、少なくとも部分的には、明瞭判然と認識する力を、したがってまたそれらの感情から働きを受けることをより少なくする力を有するということになる。ゆえに我々が特につとめなければならぬのは、おのおのの感情をできるだけ明瞭判然と認識し、このようにして精神が、感情から離れて、自らの明瞭判然と知覚するもの・そして自らのまったく満足するものに思惟を向けるようにすることである。つまり感情そのものを外部の原因の思想から分離して真の思想と結合させるようにすることである。
これによってただ愛・憎しみなどが破壊されるばかりでなく(この部の定理二により)、さらにまたそうした感情から生ずるのを常とする衝動ないし欲望も過度になりえないことになろう(第四部定理六一により)。というのは、人間が働きをなす〔能動する〕と言われるのも働きを受ける〔受動する〕と言われるのも同一の衝動によるのであることを我々は何よりも注意しなくてはならない。例えば、前に示したように、人間はその本性上他の人々が己れの意向通りに生活することを欲求〔衝動〕するものであるが(第三部定理三一の備考を見よ)、この衝動は、理性によって導かれない人間にあっては受動であって、この受動は名誉欲と呼ばれ、高慢とあまり違わないのであり、これに反して理性の指図によって生活する人間にあってはそれは能動ないし徳であって、これは道義心と呼ばれる(第四部定理三七の備考一およびその定理の第二の証明を見よ)。このようにしてすべての衝動ないし欲望は非妥当な観念から生ずる限りにおいてのみ受動であり、その同じ衝動ないし欲望が妥当な観念によって喚起されあるいは生じさせられる時には徳に数えられるのである。なぜなら、我々をある行動に決定するすべての欲望は、妥当な観念からも非妥当な観念からも生じうるからである(第四部定理五九を見よ)。
さて(再び出発点に立ちもどって)感情に対しては、感情を真に認識することに存するこの療法を措(お)いては我々の力の中に存するこれよりいっそうすぐれた他の療法は考えられえないのである。実に精神の能力と言っても、上に示したように(第三部定理三により)、思惟しかつ妥当な観念を形成する以外のいかなる能力も存しないのであるから。
定理五 我々が単純に表象するのみで必然的とも可能的とも偶然的とも表象しない物に対する感情は、その他の事情が等しければ、すべての感情のうちで最大のものである。
証明 我々が自由なものとして表象する物に対する感情は、必然的な物に対する感情よりも大であり(第三部定理四九により)、したがって我々が可能的あるいは偶然的と表象する物に対する感情よりもさらにいっそう大である(第四部定理一一により 二一→×)。ところが何らかの物を自由なものとして表象するとは、その物が行動に決定された原因を我々が知らないで、その物をただ単純に表象するということにほかならない(第二部定理三五の備考において示したところにより)。ゆえに我々が単純にのみ表象する物に対する感情は、その他の事情が等しければ、必然的・可能的あるいは偶然的な物に対する感情よりも大であり、したがってまたそれは最大のものである。Q・E・D・
定理六 精神はすべての物を必然的として認識する限り、感情に対してより大なる能力を有しあるいは感情から働きを受けることがより少い。
証明 精神はすべてのものが必然的であること(第一部定理二九により)、また原因の無限な連結によって存在および作用へ決定されること(第一部定理二八により)を認識する。したがって(前定理により)そのことによって精神は、そうした物から生ずる感情から働きを受けることがより少ないように、また(第三部定理四八により)そうした物に対して刺激を感ずることがより少ないようにすることができる。Q・E・D・
備考 物が必然的であるというこの認識が、我々のより判然とまたより生き生きと表象する個物の上により多く及ぶに従って、感情に対する精神のこの能力はそれだけ大である。このことは経験によっても実証される。なぜなら、失われた善に対する悲しみは、その善を失った人間がいかなる仕方でもその善を保持することができなかったと考える場合、ただちに軽減されるのを我々は知っているからである。同様にまた、幼児が話すことも散歩することも推理することもできず、その上に幾年間も自己意識を欠いたような生活をするからといって、誰も幼児を憐まないことを我々は知っている。しかしもし多くの人が成人として生まれ、一、二の者が幼児として生まれるのだとしたら、誰しも幼児を憐むであろう。なぜならこの場合は、人は幼児の状態を自然的あるいは必然的なものとは見ないで、自然の欠陥あるいは過失として見るからである。こうしたことについて我々は、なお他に多くの例を挙げることができる。
定理七 理性から生じあるいは理性によって喚起される感情は、時間〔持続〕という点から見れば、不在として観想される個物に関する感情よりも強力である。
証明 我々が物を不在として観想するのはその物自身から受ける刺激によってではなく、その物の存在を排除する他の刺激を身体が受けることによるのである(第二部定理一七により)。ゆえに我々が不在として観想する物に関する感情は、その本性上人間のその他の活動や能力を凌駕するようなものではなく(これについては第四部定理六を見よ)、むしろ反対にその外部の原因の存在を排除する諸刺激によって多かれ少なかれ阻害されうるようなものである(第四部定理九により)。ところが理性から生ずる感情は必然的に物の共通の諸特質に関係し(第二部定理四〇の備考二における理性の定義を見よ)、この共通の諸特質を我々は常に現在するものとして観想し(なぜならそうしたものの現在的存在を排除する何ものも存しえないから)、そして我々はこれを常に同じ仕方で表象する(第二部定理三八により)。ゆえにこうした感情は常に同一にとどまる。したがってまた(この部の公理一により)そうした感情に相反するしかも外部の原因から支えられない感情は、しだいしだいにそうした感情に順応して、ついにはそれと相反しなくなるところまで来ざるをえないであろう。こうした限りにおいて、理性から生ずる感情の方がより強力である。Q・E・D・
108
定理八 感情は共にはたらくより多くの原因から同時に喚起されるに従ってそれだけ大である。
証明 同時に存在する多くの原因は少数の原因よりも多くの能力を有する(第三部定理七により)。したがって(第四部定理五により)感情はより多くの原因から喚起されるに従ってそれだけ強力である。Q・E・D・
備考 この定理はこの部の公理二からも明らかである。
定理九 精神が同時に観想する多くの異なった原因に関係する感情は、ただ一つの原因あるいは少数の原因に関係する等しい大いさの他の感情の場合に比し、害がより少なく、我々はそれから働きを受けることがより少なく、また我々はその原因のおのおのに対して刺激を感ずることがより少ない。
証明 感情は精神の思惟する能力を妨げる限りにおいてのみ悪あるいは有害である(第四部定理二六および二七により)。したがって精神を同時に多くの対象を観想するように決定する感情は、精神をただ一つだけのあるいは少数の対象のみの観想に拘束しておいて他のことを思惟しえないようにさせる等しい大いさの他の感情よりも害がより少ない。これが第一の点であった。次に精神の本質すなわち(第三部定理七により)精神の能力はただ思惟にのみ存するのであるから(第二部定理一一により)、このゆえに精神は、多くの物を同時に観想するように自分を決定する感情からは、ただ一つあるいは少数の対象のみの観想に自分を拘束しておく等しい大いさの他の感情からよりも働きを受けることがより少ない。これが第二の点であった。最後にこうした感情は(第三部定理四八により)、外部の多数の原因に関係する限り、その原因のおのおのに対してもより小さい。Q・E・D・
定理一〇 我々は、我々の本性と相反する感情に捉えられない間は、知性と一致した秩序に従って身体の変状〔刺激状態〕を秩序づけ・連結する力を有する。
証明 我々の本性と相反する感情、言いかえれば(第四部定理三〇により)悪しき感情は、精神の認識する働きを妨げる限りにおいて悪なのである(第四部定理二七により)。したがって我々が我々の本性と相反する感情に捉えられない間は、物を認識しようと努める精神の能力(第四部定理二六により)は妨げられないのである。ゆえにその間は、精神は明瞭かつ判然たる観念を形成し・一の観念を他の観念から導出する力を有する(第二部定理四〇の備考二および定理四七の備考を見よ)。したがってまた(この部の定理一により)その間は、我々は知性に一致した秩序に従って身体の変状を秩序づけ・連結する力を有するのである。Q・E・D・
備考 身体の変状を正しく秩序づけ・連結するこの力によって我々は、容易に悪しき感情に刺激されないようにすることができる。なぜなら(この部の定理七により)知性と一致した秩序に従って秩序づけられ・連結された感情を阻止するには、不確実で漠然たる感情を阻止するよりもいっそう大なる力を要するからである。ゆえに、我々の感情について完全な認識を有しない間に我我のなしうる最善のことは、正しい生活法あるいは一定の生活律を立て、これを我々の記憶に留め、人生においてしばしば起こる個々の場合にたえずそれを適用することである。このようにして我々の表象力はそうした生活律から広汎な影響を受け、その生活律は常に我々の眼前にあることになるであろう。 110
例えば我々は憎しみを愛もしくは寛仁によって征服すべきであって憎み返しによって報いてはならぬことを生活律の中にとり入れた(第四部定理四六およびその備考を見よ)。しかし理性のこの指図が必要ある場合に常に我々の眼前にあるためには、人間が通常加えるもろもろの不法を思い浮かべ、これを再三熟慮し、かつ寛仁によってそれが最もよく除去されうる方法と経路とを考えておかなくてはならぬ。このようにすれば我々は不法の表象像をこの生活律の表象と結合することになり、そして(第二部定理一八により)我々に不法が加えられた場合に、この生活律は常に我々の眼前にあることになるであろう。その上我々が我々の真の利益について、また相互の友情と共同社会から生ずる善について、たえず考慮するならば、そしてさらに、正しい生活法から精神の最高の満足が生ずること(第四部定理五二により)、また人間は存在する他のすべてのものと同様に自然の必然性によってしか行動しえないものであることをたえず念頭に置くならば、不法あるいは不法から生ずるのを常とする憎しみは、単に我々の表象力の極小部分のみを占め、容易に征服されるであろう。たとえきわめて大なる不法から生ずるのを常とする怒りはそう容易には征服されないとしても、それはしかし〜〜たとえ心情の動揺を経てではあっても〜〜こうしたことをあらかじめ熟慮しなかった場合よりもはるかに短期間に征服されるであろう。これはこの部の定理六、七および八から明らかである。
同様に我々は、恐怖を脱するためには勇気について思惟しなくてはならぬ。すなわち人生において普通に起こるもろもろの危難を数え上げ、再三これを表象し、そして沈着と精神の強さとによってそれを最もよく回避し・征服しうる方法を考えておかなくてはならぬ。
しかしここに注意しなければならぬのは、我々の思想および表象像を秩序づけるにあたっては、常におのおのの物における善い点を眼中に置くようにし、こうして我々がいつも喜びの感情から行動へ決定されるようにしなければならぬことである(第四部定理六三の系および第三部定理五九により)。例えばある人が、自分はあまりに名誉に熱中しすぎることに気づいたなら、彼は名誉の正しい利用について思惟し、なぜ人は名誉を求めなければならぬかまたいかなる手段で人はそれを獲得しうるかを思惟しなければならぬ。だが名誉の悪用〔弊害〕とか、その虚妄とか、人間の無定見とか、その他そうした種類のことは思わないほうがよい。そうしたことは病的な精神からでなくては何びとも思惟しない事柄である。というのは、最も多く名誉欲に囚われた者は、自分の求める名誉を獲得することについて絶望する時に、そうした思想をもって最も多く自らを苦しめるものである。そして彼は、怒りを吐き出しつつもなお自分が賢明であるように見られようと欲するのである。これで見ても名誉の悪用やこの世の虚妄について最も多く呼号する者は、最も多く名誉に飢えているのであることが確かである。
しかしこれは名誉欲に囚われている者にだけ特有なことでなく、すべて恵まれぬ運命をにないかつ無力な精神を有する者に共通な現象である。なぜなら、貧乏でしかも食欲な者もまた金銭の悪用や富者の罪悪を口にすることを止めないが、これによって彼は自分自身を苦しめ、かつ自分の真のみならず他人の富もが彼の忿懣(ふんまん)の種であることを人に示す結果にしかなっていない。これと同様に、愛する女からひどく取り扱われた者もまた、女の移り気や、その不実な心や、その他歌の文句にある女の欠点などのことしか考えない。しかも愛する女から再び迎えられると、これらすべてのことをただちに忘れてしまうのである。
ゆえに自己の感情および衝動を自由に対する愛のみによって統御しようとする者は、できるだけ徳および徳の原因を認識し、徳の真の認識から生ずる歓喜をもって心を充たすように努力するであろう。だが彼は人間の欠点を観想して人間を罵倒したり偽わりの自由の外観を喜んだりするようなことは決してしないであろう。そしてこれらのことを注意深く観察し(なぜならそれは困難なことではないから)かつそれについて修練を積む者は、たしかに短期間のうちに自己の活動を大部分理性の命令に従って導くことができるようになるであろう。
定理一一 表象像はより多くの物に関係するに従ってそれだけ頻繁である。言いかえればそれだけ繁く現われる。そしてそれだけ多く精神を占有する。
証明 なぜなら表象像あるいは感情がより多くの物に関係するに従ってそれを喚起し養いうる原因がそれだけ多くなり、この原因のすべてを精神は(仮定により)その感情と同時に観想する。したがってその感情はそれだけ頻繁である。言いかえればそれだけ繁く現われる。そして(この部の定理八により)それだけ多く精神を占有する。Q・E・D・
定理一二 物の表象像は、他の表象像とよりも、我々が明瞭判然と認識する物に関する表象像と、より容易に結合する。
証明 我々が明瞭判然と認識する物は、物の共通の特質であるか、それとも、共通の特質から導き出されたものである(第二部定理四〇の備考二における理性の定義を見よ)。したがってそれはよりしばしば(前定理により)我々の中に喚起される。このゆえに、我々が物を表象する時、それと同時に今言ったような物を観想することの方が他の物を観想することよりもより容易に起こりうる。したがってまた(第二部定理一八により)物の表象像は、他の表象像とよりも、今言ったような物の表象像と、より容易に結合することになる。Q・E・D・
定理一三 表象像はより多くの他の表象像と結合するに従ってそれだけ繁く現われる。
証明 なぜなら、表象像がより多くの他の表象像と結合するに従って、それを喚起する原因がそれだけ多くなるからである(第二部定理一八により)。Q・E・D・
定理一四 精神は身体のすべての変状あるいは物の表象像を神の観念に関係させることができる。
証明 精神が何らかの明瞭判然たる概念を形成しえないようないかなる身体的変状も存しない(この部の定理四により)。したがって精神はすべての身体的変状を神の観念に関係させることができる(第一部定理一五により)。Q・E・D・ 114
定理一五 自己ならびに自己の感情を明瞭判然と認識する者は神を愛する。そして彼は自己ならぴに自己の感情を認識することがより多いに従ってそれだけ多く神を愛する。
証明 自己ならびに自己の感情を明瞭判然と認識する者は喜びを感ずる(第三部定理五三により)。しかもその喜びは神の観念を伴っている(前定理により)。したがって彼は(感情の定義六により)神を愛する。そして(同じ理由により)彼は自己ならびに自己の感情を認識することがより多いに従ってそれだけ多く神を愛する。Q・E・D・
定理一六 神に対するこの愛は精神を最も多く占有しなければならぬ。
証明 なぜなら、この愛は身体のすべての変状と結合している(この部の定理一四により)。そしてそれらすべてによって養われる(この部の定理一五により)。したがってこの愛は(この部の定理一一により)精神を最も多く占有しなければならぬ。Q・E・D・
定理一七 神はいかなる受動にもあずからず、またいかなる喜びあるいは悲しみの感情にも動かされない。
証明 すべての観念は神に関係する限り真である(第二部定理三二により)。言いかえれば(第二部定義四により)妥当である。ゆえに(感情の総括的定義により)神はいかなる受動にもあずからない。次に神はより大なる完全性へ移行することも、またより小なる完全性へ移行することもありえない(第一部定理二〇の系二により)。したがって神は(感情の定義二および三により)いかなる喜びあるいは悲しみの感情にも動かされない。Q・E・D・
系 神は本来的な意味では何びとをも愛さずまた何びとをも憎まない。なぜなら、神は(前定理により)いかなる喜びあるいは悲しみの感情にも動かされず、したがって神は(感情の定義六および七により)何びとをも愛さずまた何びとをも憎まないのである。
定理一八 何びとも神を憎むことができない。
証明 我々の中における神の観念は妥当かつ完全である(第二部定理四六および四七により)。
ゆえに我々は神を観想する限り、その限りにおいて働きをなすものである(第三部定理三により)。
したがってまた(第三部定理五九により)神の観念を伴ったいかなる悲しみもありえない。言いかえれば(感情の定義七により)何びとも神を憎むことができない。Q・E・D・
系 神に対する愛は憎しみに変ずることができない。
備考 しかし次のような駁論がなされるかもしれぬ。我々は神をすべての物の原因として認識するのだから、まさにそのことによって我々はまた神を悲しみの原因と見るものである、と。だがこれに対して私は次のごとく答える、我々が悲しみの原因を認識する限り、その限りにおいて悲しみは受動であることをやめる(この部の定理三により)。言いかえればその限りにおいてそれは悲しみであることをやめる(第三部定理五九により)。したがって我々が神を悲しみの原因として認識する限り、我々は喜びを感ずるのである、と。
定理一九 神を愛する者は、神が自分を愛し返すように努めることができない。 (ゲーテ)
証明 もし人間がこのことに努めるとしたら、彼は(この部の定理一七の系により)自分の愛する神が神でないことを欲することになるであろう。したがってまた彼は(第三部定理一九により)悲しみを感ずることを欲することになるであろう。これは(第三部定理二八により)不条理である。ゆえに神を愛する者は云々。Q・E・D・
定理二〇 神に対するこの愛はねたみや嫉妬の感情に汚されることができない。むしろより多くの人間が同じ愛の紐帯によって神と結合することを我々が表象するに従って、この愛はそれだけ多くはぐくまれる。
証明 神に対するこの愛は我々が理性の指図に従って徴求しうる最高の善である(第四部定理二八により)、そしてこの最高の善はすべての人に共通であって(第四部定理三六により)、我々はすべての人がそれを楽しむことを欲する(第四部定理三七により)。したがってこの愛はねたみの感情に汚されることができないし(感情の定義二三により)、また嫉妬の感情に汚されることもできない(この部の定理一八および嫉妬の定義による。嫉妬の定義は第三部定理三五の備考について見よ)。むしろ反対にこの愛は(第三部定理三一により)より多くの人間がこれを楽しむことを我々が表象するに従って、それだけ多くはぐくまれざるをえない。Q・E・D・
備考 この愛に直接的に相反していてこの愛を破壊させうるようないかなる感情も存しないことは同様の仕方で明らかにすることができる。したがって我々は神に対するこの愛がすべての感情のうちで最も恒久的なものであること、またこの愛が身体と結合する限りにおいては身体自身とともにでなくては破壊されえないことを結論することができる。しかしそれが単に精神のみと結合する限りにおいていかなる本性を有するかはあとで見るであろう。
これをもって私は感情に対するすべての療法を、あるいはそれ自体のみで見られた精神が感情に対してなしうる一切のことを、総括した。これからして感情に対する精神の能力は次の点に存することが明白である。 (プルードン)
一 感情の認識そのものに(この部の定理四の備考を見よ)。
二 我々が混乱して表象する外部の原因の思想から感情を分離することに(この部の定理二ならびに今引用した定理四の備考を見よ)。
三 我々が妥当に認識する物に関係する感情は我々が混乱し毀損して把握する物に関係する感情よりも時間〔持続〕という点でまさっているその時間〔持続〕という点に(この部の定理七を見よ)。
四 物の共通の特質ないし神に関係する感情はこれを養う原因が多数であるということに(この部の定理九および一一を見よ)。
五 最後に、精神が自己の感情を秩序づけ・相互に連結しうるその秩序に(この部の定理一〇の備考を、さらにまた定理一二、一三および一四を見よ)。 118
しかしながら感情に対する精神のこの能力をいっそう明瞭に理解するためにはまず第一に次のことを注意しなくてはならぬ。我々が一人の人間の感情を他の人間の感情と比較して同じ感情に一人が他の人よりも多く捉われるのを見る時、あるいは我々が同一の人間の諸感情を相互に比較してその人間が他の感情によりもある一つの感情に多く刺激され、動かされるのを知る時、我々はその感情を大と呼ぶ。なぜなら(第四部定理五により)おのおのの感情の力は、我々の能力と比較された外部の原因の力によって規定されるからである。ところが精神の能力は認識のみによって規定され、これに反して精神の無能力ないし受動は単に認識の欠乏によって、言いかえれば非妥当な観念を非妥当と呼ばしめるものによって、測られる。この帰結として、その最大部分が非妥当な観念から成っている精神、すなわちその能動性においてよりもその受動性においていっそう多く識別される精神は、最も受動的な精神であることになり、これに反してその最大部分が妥当な観念から成っている精神、すなわちたとえ他の精神と同様に多くの非妥当な観念を含んでいてもなおかつ人間の無能力を表わす非妥当な観念によってよりも人間の徳に属する妥当な観念によっていっそう多く識別される精神は、最も能動的な精神であるということになるのである。
第二に次のことを注意しなければならぬ。心の病気や不幸は、主として、多くの変転に従属する物、我々の決して確実に所有しえない物に対する過度の愛から起こるのである。なぜなら、何びとも自分の愛さない物のためには不安や心配に悩まされることがないし、また、もろもろの不法・疑惑・敵意などは何びとも真に確実に所有しえない物に対する愛からのみ生ずるからである。我々は以上から、明瞭判然たる認識、特に、神の認識そのものを基礎とするあの第三種の認識(これについては第二部定理四七の備考を見よ)が感情に対して何をなしうるかを容易に理解する。すなわちこの認識は、受動である限りにおいての諸感情を絶対的には除去しないまでも(この部の定理三と定理四の備考とを見よ)、少なくともそれらの感情が精神の極小部分を構成するようにさせうる(この部の定理一四を見よ)。次にこの認識は、不変にして永遠なる物(この部の定理一五を見よ)、我々が真に確実に所有しうる物(第二部定理四五を見よ)に対する愛を生ずる。そのゆえにこの愛は通常の愛に潜(ひそ)むもろもろの欠点に汚されえずして、かえって常にますます大となることができ(この部の定理一五により)、そして精神の最大部分を占有して(この部の定理一六により)、広汎な影響を精神に与えうるのである。
これで私はこの現在の生活に関する一切の事柄を終了した。なぜなら、私がこの備考の冒頭に述べたように、これら若干の定理の中に感情に対するすべての療法が総括されていることは、この備考の内容に、同時にまた、精神およびその諸感情の定義に、そして最後に第三部定理一および三に、注意する者には誰にも容易に分かるであろう。
ゆえに今や身体に対する関係を離れた精神の持続に関する問題に移る時である。
定理二一 精神は身体の持続する間だけしか物を表象したり・過去の事柄を想起したりすることができない。
証明 精神は身体の持続する間だけしかその身体の現実的存在を表現しないし、またその間だけしか身体の変状を現実的なものとして把握しない(第二部定理八の系により)。したがって精神は(第二部定理二六により)その身体の持続する間だけしかいかなる物体をも現実に存在するものとして把握することがない。このゆえに精神は身体の持続する間だけしか物を表象したり(第二部定理一七の備考における表象の定義を見よ)、過去の事柄を想起したり(第二部定理一八の備考における記憶〔想起〕の定義を見よ)することができない。Q・E・D・ (表象)
定理二二 しかし神の中にはこのまたはかの人間身体の本質を永遠の相のもとに表現する観念が必然的に存する。
証明 神はこのまたはかの人間身体の存在の原因であるばかりでなく、またその本質でもある(第一部定理二五により)。ゆえにその本質は必然的に神の本質そのものを通して考えられなければならぬ(第一部公理四により)。しかもある永遠なる必然性によって考えられなければならぬ(第一部定理一六により)。こうしてその概念は必然的に神の中に存しなければならぬ(第二部定理三により)。Q・E・D・
定理二三 人間精神は身体とともに完全には破壊されえずに、その中の永遠なるあるものが残存する。
証明 神の中には人間身体の本質を表現する概念ないし観念が必然的に存する(前定理により)。この概念ないし観念は、それゆえ必然的に、人間精神の本質に属するあるものである(第二部定理一三により)。ところが我々は人間精神に対して、人間精神が身体の現実的存在(それは持続によって説明され、時間によって規定されうるものである)を表現する限りにおいてしか持続〜〜時間によって規定されうるような〜〜を賦与しない。言いかえれば我々は人間精神に対して(第二部定理八の系により)身体の持続する間だけしか持続を賦与しない。しかしそれにもかかわらず今言ったあるものは神の本質そのものを通してある永遠なる必然性によって考えられるものなのであるから(前定理により)、精神の本質に属するこのあるものは必然的に永遠であるであろう。Q・E・D・
備考 身体の本質を永遠の相のもとに表現するこの観念は、今言ったように、精神の本質に属する必然的に永遠なる一定の思惟様態である。しかし我々は、我々が身体以前にすでに存在していたことを想起することはできない。というのは身体の中にそれについての痕跡は何も存しえないし、また永遠性は時間によって規定されえず、時間とは何の関係も有しえないからである。しかしそれにもかかわらず我々は我々の永遠であることを感じかつ経験する。なぜなら精神は、知性によって理解する事柄を、想起する事柄と同等に感ずるからである。つまり物を視、かつ観察する精神の眼がとりもなおさず〔我々が永遠であることの〕証明なのである。 (精神の眼)
このように、我々が身体以前に存在したということを我々は想起しないけれども、しかし我々の精神が身体の本質を永遠の相のもとに含む限りにおいてそれ〔我々の精神〕は永遠であるということ、そして精神のこの存在は時間によって規定されえず持続によって説明されえないということ、そうしたことを我々は感ずる。ゆえに我々の精神は、身体の現実的存在を含む限りにおいてのみ持続すると言われうるし、またその限りにおいてのみ我々の精神の存在は一定の時間によって規定されうるのである。そしてその限りにおいてのみ我々の精神は物の存在を時間によって決定する能力、物を持続のもとに把握する能力を有するのである。 122
定理二四 我々は個物をより多く認識するに従ってそれだけ多く神を認識する(あるいはそれだけ多くの理解を神について有する)。
証明 第一部定理二五の系から明白である。
定理二五 精神の最高の努力および最高の徳は、物を第三種の認識において認識することにある。
証明 第三種の認識は神のいくつかの属性の妥当な観念から物の本質の妥当な認識へ進む(第二部定理四〇の備考二におけるその定義を見よ)。そして我々はこの仕方で物をより多く認識するに従ってそれだけ多く(前定理により)神を認識する。このゆえに(第四部定理二八により)精神の最高の徳、言いかえれば(第四部定義八により)精神の能力ないし本性、すなわち(第三部定理七により)精神の最高の努力は、物を第三種の認識において認識することにある。Q・E・D・
定理二六 精神は、物を第三種の認識において認識することにより多く適するに従って、まさにこの種の認識において物を認識することをそれだけ多く欲する。
証明 明白である。なぜなら我々は、精神をこの種の認識において物を認識するのに適すると考える限り、その精神をまさにこの種の認識において物を認識するように決定されていると考えているのである。したがって(感情の定義一により)精神はこのことにより多く適するに従ってそれだけ多くこのことを欲する。Q・E・D・
定理二七 この第三種の認識から、存在しうる限りの最高の精神の満足が生ずる。
証明 精神の最高の徳は神を認識することにある(第四部定理二八により)。すなわち物を第三種の認識において認識することにある(この部の定理二五により)。そしてこの徳は精神が物をこの種の認識においてより多く認識するに従ってそれだけ大である(この部の定理二四により)。ゆえに物をこの種の認識において認識する者は人間の最高の完全性に達し、したがってまた(感情の定義二により)最高の喜びに刺激される。しかもこの喜びは(第二部定理四三により)自己および自己の徳の観念を伴ったものである。したがって(感情の定義二五により)この種の認識から、存在しうる限りの最高の満足が生ずる。Q・E・D・
定理二八 物を第三種の認識において認識しようとする努力ないし欲望は、第一種の認識から生ずることはできないが、第二種の認識からは生ずることができる。
証明 この定理はそれ自体で明らかである。なぜなら、明瞭判然と我々が認識するすべてのものを、我々はそれ自体によって認識するか、それともそれ自体で明らかな他の物によって認識するかである。言いかえれば、我々の中に在る明瞭判然たる観念、あるいは第三種の認識に属する観念(第二部定理四〇の備考二を見よ)は、第一種の認識に属する毀損し混乱した観念(同じ備考により)から生じえずに、妥当な観念から、すなわち(同じ備考により)第二種および第三種の認識からのみ生じうる。したがって(感情の定義一により)物を第三種の認識において認識しようとする欲望は、第一種の認識からは生じえないが、第二種の認識からは生ずることができる。Q・E・D・ 124
定理二九 精神は永遠の相のもとに認識するすべてのものを、身体の現在の現実的存在を考えることによって認識するのではなくて、身体の本質を、永遠の相のもとに考えることによって認識する。
証明 精神は、その身体の現在的存在を考える限り、時間によって決定されうる持続を考え、またその限りにおいてのみ物を時間と関係して考える能力を有する(この部の定理二一および第二部定理二六により)。ところが永遠性は持続によって説明されることができない(第一部定義八およびその説明により)。ゆえに精神はその限りにおいては物を永遠の相のもとに考える力を有しない。しかし物を永遠の相のもとに考えることが理性の本性に属し(第二部定理四四の系二により)、また身体の本質を永遠の相のもとに考えることも精神の本性に属するから(この部の定理二三により)、そして以上二様の〔身体の考え方の〕ほかには何ものも精神の本質に属さないのであるから(第二部定理一三により)、このゆえに物を永遠の相のもとに考えるこの能力は、精神が身体の本質を永遠の相のもとに考える限りにおいてのみ精神に属する。Q・E・D・ (持続、ベルグソン?)
備考 物は我々によって二様の仕方で現実として考えられる。すなわち我々は物を一定の時間および場所に関係して存在するとして考えるか、それとも物を神の中に含まれ、神の本性の必然性から生ずるとして考えるかそのどちらかである。ところでこの第二の仕方で真あるいは実在として考えられるすべての物を我々は永遠の相のもとに考えているのであり、そしてそうした物の観念の中には、第二部定理四五で示したように(なおその備考も見よ)、神の永遠・無限なる本質が含まれているのである。
定理三〇 我々の精神はそれ自らおよび身体を永遠の相のもとに認識する限り、必然的に神の認識を有し、また自らが神の中に在り神によって考えられることを知る。
証明 永遠性とは神の本質が必然的存在を含む限り神の本質そのものである(第一部定義八により)。ゆえに物を永遠の相のもとに考えるとは、物を神の本質を通して実在的有として考えること、すなわち物をその存在が神の本質の中に含まれているとして考えることである。したがって我々の精神はそれ自らおよび身体を永遠の相のもとに考える限り必然的に神の認識を有し、また自らが神の中に在り云々。Q・E・D・
定理三一 第三種の認識は、永遠である限りにおいての精神をその形相的原因とする。
証明 精神はその身体の本質を永遠の相のもとに考える限りにおいてのみ物を永遠の相のもとに老える(この部の定理二九により)。言いかえれば精神は(この部の定理二一および二三により)永遠である限りにおいてのみ物を永遠の相のもとに考える。したがって精神は(前定理により)永遠である限り神の認識を有する。そしてこの認識は必然的に妥当である(第二部定理四六により)。ゆえに精神は永遠である限り、与えられた神のこの認識から生じうる一切のことを認識することができる(第二部定理四〇により)。言いかえれば物を第三種の認識において認識することができる(第二部定理四〇の備考二におけるその定義を見よ)。したがって精神は永遠である限りこの種の認識の妥当な原因(第三部定義一により)、すなわち形相的原因である。Q・E・D・
備考 このようにして各人はこの種の認識においてよりすぐれているに従ってそれだけ良く自己および神を意識する。言いかえればその人はそれだけ完全でありそれだけ幸福である。このことは以下のことからさらにいっそう明瞭になるであろう。しかしここで注意しなければならぬことがある。それは〜〜精神が物を永遠の相のもとに考える限り永遠であることは我々のすでに確知しているところであるけれども、しかし我々の叙述したい事柄がいっそう容易に説明され、いっそうよく理解されるために、我々はこれまでしてきた通り、精神をあたかも今存在し始めたかのように、またあたかも今物を永遠の相のもとに認識し始めたかのように考察するであろう、ということである。我々は何ごともきわめて明白な諸前提からでなくては結論しないように用心しさえすれば、このことを何ら誤謬の危険なしにやっていける。
定理三二 我々は第三種の認識において認識するすべてのことを楽しみ、しかもこの楽しみはその原因としての神の観念を伴っている。
証明 この種の認識から、存在しうる限りの最高の精神の満足が生ずる(この部の定理二七により)。言いかえれば(感情の定義二五により)最高の喜び、〜〜しかもその原因としての精神自身の観念を伴った最高の喜びが生ずる。したがってこの喜びは(この部の定理三〇により)その原因としての神の観念をも伴っている。Q・E・D・
系 第三種の認識から必然的に神に対する知的愛が生ずる。なぜならこの認識からは(前定理により)原因としての神の観念を伴った喜び、言いかえれば(感情の定義六により)神に対する愛が生ずる。しかも現在するものとして表象される限りにおける神に対する愛ではなくて(この部の定理二九により)、永遠であると認識される限りにおける神に対する愛である。そして、これこそ私が神に対する知的愛と呼ぶところのものである。 (神への知的愛)
定理三三 第三種の認識から生ずる神に対する知的愛は永遠である。
証明 なぜなら、第三種の認識は永遠である(この部の定理三一および第一部公理三により)。したがって(第一部の同じ公理により)それから生ずる愛もまた必然的に永遠である。Q・E・D・
備考 神に対するこの愛は始まりを有しないけれども(前定理により)、しかしそれは、あたかもそれが生じた場合〜〜我々が前定理の系で仮定したように〜〜とまったく同様に、愛のあらゆる完全性を有している。ただ一つの相違点は、精神は、今はじめて獲得すると我々の仮定したその完全性を永遠この方所有しており、しかもそれは永遠なる原因としての神の観念を伴っている、ということだけである。そしてもし喜びがより大なる完全性への移行に存するとしたら、至福は実に精神が完全性そのものを所有することに存しなければならぬ。 128
定理三四 精神は身体が持続する間だけしか受動に属する感情に従属しない。
証明 表象はある観念〜〜精神がそれによって物を現在するとして観想するある観念である(第二部定理一七の備考におけるその定義を見よ)。しかしこの観念は外部の物の本性よりも人間身体の現在的状態をより多く表示する(第二部定理一六の系二により)。ゆえに感情は(感情の総括的定義により)身体の現在的状態を表示する限りにおいての表象である。したがって(この部の定理二一により)精神は身体が持続する間だけしか受動に属する感情に従属しない。Q・E・D・
系 この帰結として、知的愛以外のいかなる愛も永遠でないということになる。
備考 もし我々が人々の共通の意見に注意するなら、彼らは自己の精神の永遠性を意識してはいるが永遠性を持続と混同し、表象ないし記憶に永遠性を賦与し、表象ないし記憶が死後も存続すると信じているのを我々は見いだすであろう。
定理三五 神は無限の知的愛をもって自己自身を愛する。 (知的愛)
証明 神は絶対に無限である(第一部定義六により)。言いかえれば(第二部定義六により)神の本性は無限の完全性を楽しんでいる。しかもそれは(第二部定理三により)自己自身の観念を伴っている、言いかえれば(第一部定理一一および定義一により)原因としての自己自身の観念を伴っている。そしてこれが、この部の定理三二の系において知的愛であると我々が述べたものである。
定理三六 神に対する精神の知的愛は、神が無限である限りにおいてではなく、神が永遠の相のもとに見られた人間精神の本質によって説明されうる限りにおいて、神が自己自身を愛する神の愛そのものである。言いかえれば、神に対する精神の知的愛は、神が自己自身を愛する無限の愛の一部分である。
証明 精神のこの愛は精神の働きに数えられなければならぬ(この部の定理三二の系および第三部定理三により)。つまりこの愛は精神が原因としての神の観念を伴いながら自己自身を観想する働きである(この部の定理三二およびその系により)。言いかえればこの愛は(第一部定理二五の系および第二部定理一一の系により)人間精神によって説明されうる限りにおける神が〔原因としての〕自己の観念を伴いながら自己自身を観想する働きである。ゆえに(前定理により)精神のこの愛は神が自己自身を愛する無限の愛の一部分である。Q・E・D・
系 この帰結として、神は自分自身を愛する限りにおいて人間を愛し、したがってまた人間に対する神の愛と神に対する精神の知的愛とは同一である、ということになる。
備考 以上によって我々の幸福あるいは至福または自由が何に存するかを我々は明瞭に理解する。すなわちそれは神に対する恒常・永遠の愛に、あるいは人間に対する神の愛に存するのである。この愛ないし至福は聖書においては名誉(グロリア)と呼ばれているがそれは不当ではない。なぜなら、この愛は、神に関すると人間に関するとを問わず、まさしく心の満足(アニミ・アクイエスケンティア)と呼ばれうるのであり、そして心の満足は実際には(感情の定義二五および三〇により)名誉と異ならないからである。なぜ心の満足と呼ばれうるかと言えば、この愛は、神に関する限り、神自身の親念を伴った喜び〜〜神について今なお喜びという言葉を用いることが許されるならば〜〜であって(この部の定理三五により)、その点この愛が精神に関する場合(この部の定理二七により)と同じだからである。次に我々の精神の本質は認識のみに存し、そして神はこの認識の始源であり基礎であるから(第一部定理二五および第二部定理四七の備考により)、前に述べたことから、我々の精神は本質ならびに存在に関していかなる仕方、いかなる様式で神の本性から起こり、そしてたえず神に依存するかが我々にきわめて明瞭になる。このことを私はここで注意した方がよいと思った。これによって私は直観的認識あるいは第三種の認識と名づけた個物の認識(第二部定理四〇の備考二を見よ)がいかに多くのことをなしうるかまたそれが第二種の認識と名づけた普遍的認識よりどれだけ有力であるかを明らかにしようとしたのである。というのは私は、第一部において、一切が(したがって人間精神もまた)本質ならびに存在に関して神に依存することを一般的に示したけれども、その証明は、たとえ正当であって何ら疑惑の余地がないとはいえ、神に依存すると我々が言った個物各自の本質そのものからこのことが結論される場合のようには我々の精神を感銘させないからである。
定理三七 自然の中にはこの知的愛に対立的であったりあるいはこれを消滅させたりしうるようないかなる物も存しない。
証明 この知的愛は、精神が神の本性を通して永遠の真理として見られる限りにおいて、精神の本性から必然的に生ずる(この部の定理三三および二九により)。ゆえにもしこの愛に対立するある物が存するとしたら、それは真なるものに対立することになるであろう。したがってまたこの愛を消滅させうるものは真なるものを偽なるものとならしめることになるであろう。これは(それ自体で明らかなように)不条理である。ゆえに自然の中には云々。Q・E・D・
備考 第四部の公理は、一定の時間と場所に関係して考察される限りにおける個物を念頭に置いたものであって、そのことは誰にも明瞭なことと信ずる。
定理三八 精神はより多くの物を第二種および第三種の認識において認識するに従ってそれだけ悪しき感情から働きを受けることが少なく、またそれだけ死を恐れることが少ない。
証明 精神の本質は認識に存する(第二部定理一一により)。ゆえに精神がより多くの物を第二種および第三種の認識において認識するにつれて精神のそれだけ大なる部分が残存し(この部の定理二三および二九により)、したがってまた(前定理により)精神のそれだけ大なる部分が我々の本性と相反する感情から、言いかえれば(第四部定理三〇により)悪しき感情から冒(おか)されなくなる。ゆえに精神がより多くの物を第二種および第三種の認識において認識するにつれて精神のそれだけ大なる部分が害されずに残り、したがって精神はそれだけ感情から働きを受けることが少ない、云々。Q・E・D・
備考 このことから、第四部定理三九の備考において触れ、この部において説明すると約束した事柄が明らかになる。それはすなわち、精神のもつ明瞭判然たる認識が大になればなるほど、したがってまた精神が神を愛することの多ければ多いほど、それだけ死が有害でなくなるということである。さらに、第三種の認識からおよそ存在しうる最高の満足が生ずるのだから(この部の定理二七により)、この帰結として〜〜人間精神は、その中で身体とともに滅びることを我々が示した部分が(この部の定理二一を見よ)その残存する部分と比べてまるで取るに足りぬといったような本性を有しうるものである〜〜ということになる。しかしこれについては今にもっと詳しく述べる。 132
定理三九 きわめて多くのことに有能な身体を有する者は、その最大部分が永遠であるような精神を有する。
証明 きわめて多くのことをなすのに適する身体を有する者は、悪しき感情に捉われることがきわめて少ない(第四部定理三八により)。言いかえれば(第四部定理三〇により)我々の本性と相反する感情に捉われることがきわめて少ない。ゆえに彼は(この部の定理二〇により)身体の諸変状を知性に相応した秩序において秩序づけ・連結する力を、したがってまた(この部の定理二四により)身体のすべての変状を神の観念に関係させる力を有する。この結果として彼は(この部の定理一五により)神に対して愛に刺激される。そしてこの愛は(この部の定理一六により)精神の最大部分を占有ないし構成しなければならぬ。このゆえに彼は(この部の定理三三により)、その最大部分が永遠であるような精神を有する。Q・E・D・
備考 人間身体はきわめて多くのことに有能である。だから人間身体は、きわめてすぐれた精神に関係するような〜〜自己および神について大なる認識を有し、その最大部分あるいは主要部分が永遠であり、したがって死をほとんど恐れないそうした精神に関係するような本性を有しうるものであることは疑いない。
しかしこれをいっそう明瞭に理解するためにここで注意しなければならぬのは、我々はたえざる変化の中に生きており、そして我々はより善きものあるいはより悪しきものに変化するに従って幸福あるいは不幸と言われるということである。例えば、幼児あるいは少年のままで死骸に化する者は不幸と言われ、これに反して健全な身体に健全な精神を宿して全生涯を過しうるのは幸福とされる。実際また、幼児や少年のように、きわめてわずかなことにしか有能でない身体、外部の原因に最も多く依存する身体、を有する者は、その精神もまた、それ自身だけで見られる限り、自己・神および物についてほとんど意識しない。これに反してきわめて多くのことに有能な身体を有する者は、その精神もまた、それ自身だけで見て、自己・神および物について多くを意識している。ゆえにこの人生において、我々は特に、幼児期の身体を、その本性の許す限りまたその本性に役立つ限り、他の身体に変化させるように努める。すなわちきわめて多くのことに有能な身体、そして自己・神および物について最も多くを意識するような精神に関係する身体、に変化させるように努める。そのように変化すれば、私がすでに前定理の備考において言ったように、精神における記憶ないし表象力に属する一切は、知性に比べてほとんど取るに足りぬものになるであろう。
定理四〇 おのおのの物はより多くの完全性を有するに従って働きをなすことがそれだけ多く、働きを受けることがそれだけ少ない。反対におのおのの物は働きをなすことがより多いに従ってそれだけ完全である。
証明 おのおのの物はより多く完全であるに従ってそれだけ多くの実在性を有し(第二部定義六により)、したがって(第三部定理三ならびにその備考により)働きをなすことがそれだけ多く、働きを受けることがそれだけ少ない。この証明は順序を逆にしてやってもあてはまるのであり、その結果として逆に、物は働きをなすことがより多いに従ってそれだけ完全であることになる。Q・E・D・
系 この帰結として、精神の残存する部分は、それがどの程度の大いさのものであるにしても、その他の部分よりも完全であることになる。なぜなら、精神の永遠の部分は知性であり(この部の定理二三および二九により)、そして我々が働きをなすと言われるのはもっばらこの知性によるのである(第三部定理三により)。これに反してその消滅することを我々が示した部分は表象力そのものであり(この部の定理二一により)、そして我々が働きを受けると言われるのはもっばらこの表象力によるのである(第三部定理三および感情の総括的定義により)。したがって(前定理により)前者はそれがどの程度の大いさのものであっても後者よりも完全である。Q・E・D・
備考 以上は身体の存在に対する関係を離れて考察される限りにおける精神について、私の示そうと企てた事柄である。このことから、また同時に第一部定理二一およびその他の諸定理から、我々の精神は物を知性的に認識する限り思惟の永遠なる様態であり、これは思惟の他の永遠なる様態によって決定され、後者はさらに他のものによって決定され、こうして無限に進み、このようにしてこれらすべての様態は合して神の永遠・無限なる知性を構成するということが分かるのである。
定理四一 たとえ我々が我々の精神の永遠であることを知らないとしても、我々はやはり道義心および宗教心を、一般的に言えば我々が第四部において勇気および寛仁に属するものとして示したすべての事柄を、何より重要なものと見なすであろう。
証明 徳の、あるいは正しい生活法の、第一にして唯一の基礎は自己の利益を求めることである(第四部定理二二の系および定理二四により)。しかし理性が何を有益として命ずるかを決定するのに我々は精神の永遠性ということには何の考慮も払わなかった。精神の永遠性ということを、我々はこの第五部においてはじめて識ったのである。このようにして、あの当時はまだ精神の永遠であることを知らなかったけれども、我々はそれでも、勇気と寛仁に属するものとして示した事柄を何よりも重要なものと見なした。だからたとえ我々が今なおそのことを知らないとしても、我々はやはり、理性のそうした命令を重要なものと見なすであろう。Q・E・D・
備考 民衆の一般の信念はこれと異なるように見える。なぜなら大抵の人々は快楽に耽りうる限りにおいて自由であると思い、神の法則の命令に従って生活するように拘束される限りにおいて自己の権利を放棄するものと信じているように見えるからである。そこで彼らは道義心と宗教心を、一般的に言えば精神の強さに帰せられるすべての事柄を、負担であると信じ、死後にはこの負担から逃れて、彼らの隷属〜〜つまり彼らの道義心と宗教心〜〜に対して報酬を受けることを希望している。だがこの希望によるばかりでなく、特にまた死後に恐るべき責苦をもって罰せられるという恐怖によって、彼らは、その微力とその無能な精神との許す限り、神の法則の命令に従って生活するように導かれている。もしこの希望と恐怖とが人間にそなわらなかったら、そして反対に、精神は身体とともに消滅し、道義心の負担のもとに仆(たお)れた不幸な人々にとって未来の生活が存しないと信ぜられるのであったら、彼らはその本来の考え方に立ちもどってすべてを官能欲によって律し、自分自身によりもむしろ運命に服従しようと欲するであろう。こうしたことは、人が良い食料によっても身体を永遠に保ちうるとは信じないがゆえに、むしろ毒や致命的な食物を飽食しようと欲したり、精神を永遠ないし不死でないと見るがゆえに、むしろ正気を失い理性なしに生活しようと欲したりする(これらのことはほとんど検討に価しないほど不条理なことである)のにも劣らない不条理なことであると私には思われる。
定理四二 至福は徳の報酬ではなくて徳それ自身である。そして我々は快楽を抑制するがゆえに至福を享受するのではなくて、反対に、至福を享受するがゆえに快楽を抑制しうるのである。
証明 至福は神に対する愛に存する(この部の定理三六およびその備考により)。そしてこの愛は第三種の認識から生ずる(この部の定理三二の系により)。したがってこの愛は(第三部定理五九および三により)働きをなす限りにおける精神に帰せられなければならぬ。ゆえにそれは(第四部定義八により)徳それ自身である。これが第一の点であった。次に精神はこの神の愛すなわち至福をより多く享受するに従ってそれだけ多く認識する(この部の定理三二により)。言いかえれば(この部の定理三の系により)感情に対してそれだけ大なる能力を有しまた(この部の定理三八により)悪しき感情から働きを受けることがそれだけ少なくなる。ゆえに精神はこの神の愛すなわち至福を享受することによって快楽を抑制する力を有するのである。そして感情を抑制する人間の能力は知性にのみ存するのであるから、したがって何びとも感情を抑制したがゆえに至福を享受するのでなく、かえって反対に、快楽を抑制する力は至福それ自身から生ずるのである。Q・E・D・
備考 以上をもって私は、感情に対する精神の能力について、ならびに精神の自由について示そうと欲したすべてのことを終えた。これによって、賢者はいかに多くをなしうるか、また賢者は快楽にのみ駆られる無知者よりもいかに優れているかが明らかになる。すなわち無知者は、外部の諸原因からさまざまな仕方で揺り動かされて決して精神の真の満足を享有しないばかりでなく、その上自己・神および物をほとんど意識せずに生活し、そして彼は働きを受けることをやめるや否や同時にまた存在することをもやめる。これに反して賢者は、賢者として見られる限り、ほとんど心を乱されることがなく、自己・神および物をある永遠の必然性によって意識し、決して存在することをやめず、常に精神の真の満足を享有している。
さてこれに到達するものとして私の示した道はきわめて峻険であるように見えるけれども、なお発見されることはできる。また実際、このように稀にしか見つからないものは困難なものであるに違いない。なぜなら、もし幸福がすぐ手近かにあって大した労苦なしに見つかるとしたら、それがほとんどすべての人から閑却されているということがどうしてありえよう。
たしかに、すべて高貴なものは稀であるとともに困難である。
終 り

〈 〉印のカッコはその中の言葉が一六七七年のオランダ語訳遺稿集から補われたものであることを示す。
また〔 〕印のカッコの中の言葉は訳者による補足語ないし語註である。
E T H I C A
ORDINE GEOMETRICO DEMONSTRATA
1677
Benedictus de Spinoza
☆
リンク→:諸感情の定義、TOP☆
ラテン語原文→
http://users.telenet.be/rwmeijer/spinoza/works.htm、
英語、日本語対訳
索引、目次→一、二、三、 四、五、TOP☆
[ア][イ][ウ][エ][オ][カ][キ][ク][ケ][コ][サ][シ][ス] [セ][ソ][タ][チ][ツ][テ][ト]
[ナ][ニ][ヌ][ネ][ノ] [ハ][ヒ][フ][へ][ホ][マ][ミ][ム][メ][モ][ヤ][ユ][ヨ]
[ラ][リ][ル][レ][ロ][ワ] 、TOP☆
[ア] ☆
愛 amor, 三定理13備考,三感情定義6./ 〜は憎しみを征服する 三定理43.ある物への〜は他の原因の観念と結合する時消滅する 三定理48.自由な物への〜は必然的な物への〜より大である 三定理49.// その他 三定理38,44,四定理44,46,同備考./// 神に対する愛,神に対する知的愛についてはおのおのその項を見よ.
悪(害悪) malum, 三定理39備考,四序言(下10f.),四定義2. / 〜の認識は我々に意識された限りにおいての悲しみの感情にほかならぬ 四定理8.〜の真の認識は真であるというだけでは感情を抑制しえぬ 四定理14.我々は〜と判断するものを必然的に忌避する 四定理19. 〜の認識は非妥当な認識である 四定理64.// その他 四定理39,40,付録3,5,6,8./// 諸感情の悪については四定理41,42,43,45系1,48,50,51備考.//// 善悪の概念 四定理68.
アプリオリ a priori, 一定理11備考.
アポステリオリ a posteriori, 一定理11備考.
誤った観念 idea falsa〔偽なる観念の項もあわせ見よ〕,一定理8備考2(上44),四定理1.
阿訣(あゆ, =へつらい) adulatio, 四付録21.
阿訣の徒 adulator, 四定理57.
安堵 securitas, 三定理18備考(2),三感情定義14./ その他 四定理47備考.
[イ] ☆
怒り ira, 三定理40系2備考,三感情定義36./ その他 四定理45系1,46,五定理10備考(下110f.).
意見 opinio, 二定理40備考2(〜=表象=第一種の認識)./ その他 一定理33備考2(上81),二定理35備考,三感情定義28説明,四定理17備考,66備考.// sensus ,「頭数だけの意見」テレンティウス, "quot capita, tot sensus" Terentius 一付録(上91).
意志 voluntas, 三定理9備考./ 自由〜は存しない 一定理32,二定理48.〜は思惟のある様態 一定理32証明.〜=肯定し否定する能力 二定理48備考.〜=知性 二定理49系.〜は一般的概念 二定理48備考,49備考(上160f.) // その他 一定理32系1および2,三定理27系3備考,三感情定義1説明,6説明./// 〜によって身体の運動が生ずるとする考え方への反駁は二定理35備考,三定理2以下,五序言(下98f.).我々が一般に神に帰している知性や〜 一定理17備考(上62).
意志作用(意志活動, 意欲) volitio, 〜=このあるいはかの肯定ないし否定 二定理49証明.すべての〜は観念そのものである 二定理49証明./ その他 一定理32証明,付録(上84),二定理48備考,三感情定義1説明.
異端者 haereticus, 一付録(上88).
一般的 universalis.
一般的概念 notiones universales, universalia, 〜の生ずる原因 二定理40備考1(上141f.).なお二定理48備考参照.
詐り(悪しき欺瞞) dolus malus, 四定理72,同証明,同備考.
犬 canis,星座の〜と吠える動物の〜との間の一致 一定理17備考(上63).
飲酒欲 ebrietas,三定理56備考,三感情定義46.
[ウ] ☆
運動および静止 motusetquies,〜から無限に多くのものが生ずる 一定理32系2./ 運動および静止一般については二補助定理1以下.
運動競技 lndus exercitatorins,四定理45備考(系2備考).
運命 fatum, fortuna,一定理33備考2(上81),二定理49備考(上163),四定理47備考.
[エ] ☆
永遠, 永遠性 aeternum, aeternitas,一定義8./ 永遠性=必然性 一定理10備考,23証明,四定理62証明.// 永遠の中にはいつ・以前・以後ということがない 一定理33備考2(上79). /// その他 一定理19,五定理23,30証明,39.
永遠の相のもとに sub specie aeternitatis,二定理44系2,四定理62証明,五定理22,23備考,29,同証明,同備考,30,同証明,31証明,同備考,36.
永遠無限なる本質 essentia aeterna et infinita,一定義6,一定理10備考./ 神の〜 二定理45,46,47.
演劇 theatrum,四定理45備考.
延長(エクステンシオ) extensio,〜は神の属性である 二定理2,7備考.
延長した実体(延長的実体)(=延長の属性) substantia extensa,一定理15備考(上54,56),二定理7備考.
延長した物 res extensa,〜は神の属性かその変状である 一定理14系2./ その他 二定理2,7備考.
[オ] ☆
オヴィディウス, Ovidius, 善きものを 三定理2備考(上173),四序言(上7). 四定理17備考. 三定理31系(詩人, 恋愛詩). (引用文のみ、本文中に名前なし).
臆病, 臆病な timor, timidus,三定理39備考,定理51備考,三感情定義39./ その他 三感情定義48説明.
音楽 musica,四序言(下10). 定理45備考(系2備考).
温和 clementia,〜は寛仁の一種 三定理59備考.〜は残忍と対立する精神力 三感情定義38説明.
[カ] ☆
快活 hilaritas,三定理11備考,三感情定義3説明./ その他 四定理42.
買いかぶり existimatio,三定理26備考,三感情定義21./ 四定理48,49.
快感(官能的快感) titillatio,三定理11備考,三感情定義3説明./ その他 四定理43.
懐疑論 scepticismus,一付録(上91).
概念 conceptus, notio, 〜と知覚との区別 二定義3説明.公理あるいは〜 二定理40備考1(上140).〜=観念 二定義3,定理38系,49証明,同備考(上156)./ 共通概念,第二次概念についてはそれぞれその項を見よ.
概念する(考える) concipere.
快楽(官能的快楽,官能欲) libido〔情欲の項もあわせ見よ〕, 四定理17備考,五定理41備考,42.
果敢(な) intrepidum,三定理51備考.
確実性 certitudo,真の観念は〜を含む 二定理43備考.〜はある積極的なもので疑惑の欠乏ではない 二定理49備考(上156).
客体(前に横たわったもの, 対象) objectum. 二定理43備考.
活動(行動, 行為, 働き) actio,能動的行動にも受動的行動にも用いる.しかし actio が明らかに受動的行動に対立した意味で用いられている場合は特に能動の語をあてた.能動の項も見よ.
悲しみ tristitia,三定理11備考,三感情定義3./ 〜は基本感情の一 三定理11備考,三感情定義4説明.〜は原則的には悪 四定理41.// その他 三定理15,四定理18.
可能的 possibilis,一定理33備考1(偶然的と区別せずに),四定義4(偶然的と区別して).
神(デウス) Deus,一定義6./ 〜=自己原因 一定理25備考.〜=実体 一定義6. 〜=自然 四序言(下9),定理4証明.〜の必然的存在 一定理11. 〜のほかいかなる実体もない 一定理14.すべては〜の中に在る 一定理15 .〜は万物の起成原因 一定理16系1.〜の存在と本質は同一 一定理20.〜は意志の自由によって働かぬ 一定理32系1. 〜の能力=〜の本質 一定理34 .〜の諸特質 一付録(上82f.).思惟と延長は〜の属性 二定理1および2.〜はいかなる受動にもあずからぬ 五定理17.〜は自己自身を愛する 五定理35.またその限りにおいて人間を愛する 五定理36系.// その他 一定理17から25にいたる諸定理,二の初めの諸定理参照.
神に対する愛 amor erga Deum,〜は最も多く精神を占有する 五定理16. 憎しみに変ずることができぬ 五定理18系.ねたみや嫉妬に汚されぬ 五定理20.すべての感情のうち最も恒久的 五定理20備考(下117)./ 神を愛する者は 五定理19.
神に対する知的愛 amor Dei intellectualis,五定理32系./ 〜は第三種の認識から必然的に生ずる 五定理32系.〜は永遠 五定理33.神が自らを愛する無限愛の一部 五定理36.人間に対する神の愛と同一 五定理36系.〜を消滅せしめる何ものも存しない 五定理37.〜の中に我々の至福ないし自由は存する 五定理36備考.
考える(概念する) concipere.
感覚(感官), 感覚する sensus, sentire,一付録(上89ff.),二公理4および5,定理40備考2./ 感覚ないし知覚する 二公理5,定理49備考(上159).動物は感覚を有する 四定理37備考1..
歓喜 gaudium,三定理18備考2,三感情定義16./ その他 四定理47備考. // 楽しみ 五感情定義32.
観察する observare.
感謝(謝恩) gratia (gratitudo),三定理41備考,三感情定義34. / その他 四定理71,同備考.
感情 affectus,三定義3,三感情の総括的定義./ 受動〜と能動〜 三感情定義3.基本的〜は喜び・悲しみ・欲望 三定理11備考,三感情定義4説明.〜の種類は無数 三定理56.〜を伴わぬ観念はあるが観念を伴わぬ〜はない 二公理3.〜は表象の一種 四定理9証明,五定理34証明.表象像あるいは〜 五定理11証明.〜ないし意見 四定理66備考.〜はより強大な反対〜によってのみ抑制されうる 四定理7.人間は受動〜に捉われる限り相互に異なり,あるいは対立的でありうる 四定理33および34.受動〜は明瞭判然と認識されれば受動たることをやめる 五定理3.いかなる〜についても明瞭に認識しうる 五定理4系,同備考.// 感情の模倣については三定理27,同備考,三感情定義33説明,四定理68備考,付録13参照.感情に対する療法については五定理20備考(下111).諸感情の善または悪についてはそれぞれ善または悪の項を見よ.
寛仁 (=寛容) generositas,三定理59備考./ 〜は精神の強さの一部 三定理59備考.〜の種類 三定理59備考.〜は人心を征服する 四付録11.// その他 四定理46,五定理41,同証明.
完全性 perfectio,〜=実在性 二定義6,四序言(下11).〜あるいは実在性 一定理11備考,二定理1備考, 43備考, 49備考(上158) 〜=本質 四序言(下11).〜は物の存在を定立する 一定理11備考./ その他 一付録(〜の最高程度から最低程度)あるいは四序言全部,五定理40.
観想, 観想する contemplatio, contemplari.
観念 idea,二定義3./ 〜=概念 二定義3,定理38系,49証明,同備考(上156f.).〜=認識 二定理19証明,20,同証明,22証明,23証明,24証明,25証明.〜の秩序および連結は物の秩序および連結と同一 二定理7.感情を伴わぬ〜は存するが〜を伴わぬ感情はない 二公理3.すべての〜は神に関する限り真 二定理32.〜は無言の絵ではない 二定理43備考,49備考(上156f.).〜は肯定あるいは否定を含む 二定理49備考(上157),三定理2備考(上175).個々の〜=個々の意志作用 二定理49系証明.身体の変状の秩序に相応して生ずる一の連結,知性の秩序に相応して生ずる〜の連結 二定理18備考.存在しない様態の〜 二定理8.〜と表象像と言葉の区別 二定理49備考(上156).// 観念の観念,妥当な観念,非妥当な観念,真の観念,偽の観念についてはそれぞれその項を見よ.
観念の観念 idea ideae,〜は観念の形相(本質)二定理21備考./ なお定理43および同備考参照.
[キ] ☆
帰依 devotio (=献身),三定理52備考,三感情定義10.
記憶(想起) memoria,二定理18備考./ 〜あるいは表象 三定理2備考(上175)五定理34備考.
幾何学的方法, 幾何学的秩序 mos geometricus, ordo geometricus,三序言(上166),四定理18備考(下28).
キケロ Cicero , 三感情定義44説明.
規則 regula, 自然の〜 三序言(上166).理性の〜 四定理18備考(下28).
規定する definire .
偽なる(偽の, 虚偽の)観念 idea falsa 〔誤った観念の項もあわせ見よ〕,〜は確実性を含まぬ 二定理49備考(上155).
希望 spes, 三定理18備考2,三感情定義12 ./ 恐怖なき〜なし 三定理50備考,三感情定義13説明.// その他 三定理50,同備考,四定理47,同備考,54備考.
客体/〔かくたい〕.
Q・E・D・(Quod Erat Demonstrandum), 数学, 哲学などにおけるQ. E. D. はラテン語の Quod Erat Demonstrandum(かく示された)が略されてできた頭字語. 証明や論証の末尾におかれ, 議論が終わったことを示す.
驚異 admiratio , 三定理52備考, 三感情定義4. / 〜は感情でない 三感情定義4説明.
教育, 教育する educatio, educare, 人を教育するのは自己の天分を試みる最良の方法 四付録9./ その他 三定理55系(1)備考,三感情定義27説明,四付録20.
恐慌 consternatio, 三定理39備考,52備考,三感情定義42, 同説明.
競争心 aemulatio, 三定理27備考,三感情定義33.
共通概念(普遍概念) notiones communes,〜の起源 二定理38系,39,40,同備考1(上140). 〜=公理 一定理8備考2(上48).〜=妥当な観念=理性=第二種認識 二定理40備考2. 〜は永遠の相のもとに考えられる 二定理44系2.
共通的 communis.
共同社会 societas communis 〔社会の項もあわせ見よ〕,人間の〜からは損害よりも便利が多く生ずる 四定理35備考,付録14./ その他 四定理40, 五定理10備考(下110).// 一精神一身体 四定理18備考.
恐怖 metus, 三定理18備考2, 三感情定義13. / 希望なき〜なし 三定理50備考,三感情定義13説明./ その他 三定理50,同備考,四定理47, 同備考,54備考,63.
虚偽 falsitas 〔誤謬の項もあわせ見よ〕,〜は非妥当な観念が含む認識の欠乏に存する 二定理35, 49備考(上155), 四定理1証明.〜とは確実性の欠乏 二定理49備考(上156). 〜=誤謬 二定理33証明.〜の唯一の原因は第一種認識 二定理41.
虚名 gloria vana, 四定理58備考.
キリストの精神 Spiritus Christi, 〜=神の観念 四定理68備考.
疑惑 dubitatio , 〜の欠乏は確実性を意味せず 二定理49備考(上156).〜と心情の動揺との異同 三定理17備考.
禁酒 sobrietas, 〜は精神の能力を表示する 三定理56備考./ その他 三定理59備考,三感情定義48説明.
金銭 nummus, 四付録28,29.
[ク] ☆
空虚 vacuum , 〜の存在の否定 一定理15備考(上57).
偶然的 contingens, 一定理33備考1(可能的と区別せずに), 四定義3(可能的と区別して),二定理31系(可滅的と同じ意味で)./ 自然中には〜なものが存しない 一定理29 .理性は物を〜と観ない 二定理44 .
苦痛 dolor, 三定理11備考, 三感情定義3説明./ その他 四定理43.
[ケ] ☆
系 collorarium.
経験 experientia,経験の信憑性について 二定理17備考.漠然たる経験 二定理40備考2./ 経験に基づく立論 二定理49備考(上157f.), 三定理2備考(上172ff.),32備考,三感情定義27説明, 四定理35備考, 39備考, 五定理6備考.
形而上学者 Metaphysici,一付録(上87).
形而上学的有 entia metaphysica , 〜 =一般的概念 二定理48備考.
形相 forma, 時には単に形状, 形態の意味に用いられるが多くは本性, 本質の意味に用いられる 二定理10,同備考,補助定理4,5,6 ,7備考,定理21備考,24証明,33証明,35証明,三序言(上166),三感情の総括的定義説明,四序言(下11), 定理39証明,五定理2証明.
形相的原因 causa formalis,〜=妥当な原因 五定理31証明.
形相的に formaliter,二定理7系.
形相的本質 essentia formalis,一定理17系2備考(備考)(上63), 二定理8, 40備考2.
形相的有 esse formale, 二定理6系./ 観念の〜 二定理5, 同証明, 7備考.
軽蔑 contemptus,三定理52備考,三感情定義5./その他 三感情定義4説明, 四定理45系1, 50備考.
決意 decretum,(神の〜)一定理33備考2(上79), 三定理2備考(上172ff.)./ 〜と決定との区別 三定理2備考(上174).
結果 effectus, 〜の認識は原因の認識を含む 一公理4.すべての物からある〜が生ずる 一定理36./ その他 一公理3, 三定理1証明, 三感情定義28説明, 29説明.
結合する necessitude, 「人間と結合する」(necessitudinem cum hominibus jungere) 四定理37備考1.
結婚 matrimonium, 四付録20.
決定 determinatio, 三定理2備考(上174),47備考.
決定する determinare.
欠乏 privatio, 認識の〜は虚偽ないし誤謬 二定理35, 同備考, 49備考(上155), 四定理1証明.
結論する concludere, 結論ないし知覚する 一定理23証明.
原因(カウサ) causa, 与えられた〜から必然的にある結果が生ずる 一公理3.おのおのの物は存在するための一定の〜を有する 一定理8備考2(上45).おのおのの物は〜の無限連鎖によって存在および作用に決定される 一定理28.〜=理由 一定理11第1別証,四序言(下9). / 起成原因 c. effciens 一定理16系1, 三定理16, 四付録6.それ自身による原因 c. per se 一定理16系2, 32,三定理17備考, 三感情定義24説明.偶然による原因 c. per accidens 一定理16系2,三定理15, 17備考.第一原因 c. prima (primaria) 一定理8備考2(上43), 二定理8備考, 三序言(上166), 定理59備考, 四序言(下9). 自由原因 c. libera 一定理17系2 , 付録(上82f.).必然的原因 c. necessaria 一定理32 . 内在的原因 c. immanens 一定理18 . 超越的原因 c. transiens 一定理18. 最近原因 c. proxima 一定理28備考, 三定理3証明, 四定理35証明, 付録1. 遠隔原因 c. remota 一定理28備考. 外的(外部)原因 c. externa 一定理8備考2(上45f.),11備考.内的(内部)原因 c. interna 三定理30備考, 三感情定義24説明.中間原因 c. intermedia 一付録(上87).永遠の原因 c. aeterna 五定理33備考.有ることの原因 c. essendi 一定理24系.有に関しての原因 c. secundum esse 二定理10系備考.生成に関しての原因 c. secundum fieri 二定理10系備考.自己原因, 妥当な原因, 非妥当な原因, 形相的原因, 目的原因についてはおのおのその項を見よ.
権, 権能, 権利 jus, 神の権能 二定理3備考.各自の権利 四定理37備考1.人の自然権 四定理37備考2(下49).
謙遜(自劣感) humilitas, 三定理55備考, 三感情定義26./ 〜は徳でない 四定理53.〜は害よりも益がある 四定理54備考.// その他 三感情定義26説明, 28説明, 29説明./// 〜の対外的あらわれについては三感情定義29説明参照.また理性認識から生ずる〜については四定理53証明後半参照.
限定する terminare, determinare.
[コ] ☆
硬 dura, 二補助定理3のあとの公理3.
好意 favor,三定理22備考,三感情定義19.
後悔 poenitentia,三定理30備考,51備考,三感情定義27. / 〜は徳でない 四定理54. 〜は害よりは益がある 四定理54備考.
好感 propensio,三感情定義8./ 同感の項,三定理15備考参照.
考察する considerare.
功績 meritum,四定理37備考2(下50).
肯定, 肯定する affirmatio, affirmare. 肯定する能力=意志 二定理48備考.
幸福 felicitas,〜=自己の有を維持しうること 四定理18備考(下29). 最高の〜(=至福)=神への認識=知性の完成 二定理49備考(上163),四付録4./ その他 三定理39備考,三感情定義23,五定理39備考.
高慢 superbia,三定理26備考,三感情定義28,同説明,四定理57備考./ その他 四定理49,55,56,同備考,73備考.
高慢な人間 superbus, 三感情定義29説明,四定理56系,57,同備考, 付録21.
公理 axioma, 〜=共通概念 一定理8備考2(上43).〜=要請 三要請1.〜=概念 二定理40備考1(上140).
国民(人民, 市民) civis,四定理37備考2(下50)./ その他 二定理49備考(上164).
固執する perseverare,存在に〜 一定理24系.自己の有に〜 三定理6,7,8.
個体 individuum,一般的には〜=個物 二定義7./ すべての〜は精神を有する 二定理13備考.全自然は一つの〜 二補助定理7備考.// その他 一定理8備考2(上44f.),二補助定理3のあとの公理3,補助定理4,5,6,7(第二の種類の〜から組織された第三の種類の〜).
国家 civitas,国家の基礎 四定理37備考1. 四定理37備考2(下50) / その他 四定理73.// 国家社会(共同社会) communem societatem 二定理49備考注4(上164).
国家状態(国家的状態) status civilis, 四定理37備考2(下49ff.).
国家の中の国家 imperium in imperio,三序言(上165).
孤独 solitudo,四定理73.
孤独の生活 vita solitaria,四定理35備考.
誤謬 error,〜についての注意 二定理17備考.〜=虚偽 二定理33証明.〜は認識の欠乏に存する 二定理35備考./ その他 二定理47備考,四定理1備考.
個物(レス・シングラリス) res singularis, res particularis,二定義7./ 〜=神の属性の変状=様態 一定理25系.すべての〜は偶然的かつ可滅的 二定理31系.我々は〜を認識すればするほど神を認識する 五定理24.// その他 一定理28,四公理.
[サ] ☆
罪過(罪) peccatum,四定理37備考2(下50)
三角形 triangulum,〜の本性からその三つの角の和が二直角に等しいことが生ずる(明瞭な認識の例として用いられる)一定理17備考(上61f.),二定理49備考(上163),四定理57備考.
産出する producere.
残忍(苛酷) crudelitas (saevitia). 三定理41系備考,三感情定義38.
[シ] ☆
死 mors, 〜は身体の各部が異なった運動と静止の割合をとるに至ること 四定理39備考. 自由人は〜を思わぬ 四定理67.精神が神を愛すれば愛するほど〜は有害でなくなる 五定理38備考. / その他 四定理39備考,63系備考,五定理38,39備考.
思惟(コギタティオ) cogitatio, 〜は神の属性 一定理21証明,二定理1, 7備考,20証明,21備考…….
自意識〔観念の観念もあわせ見よ〕,自意識については二定理20,21,22 ,23,29 ,同系,43,同備考,五定理42備考を参照せよ.
思惟する cogitare ,人間は〜 二公理2.
思惟する実体(思惟的実体)〔=思惟の属性〕substantia cogitans,二定理7備考.
思惟する物 res cogitans,〜は神の属性かその変状である 一定理14系2. 精神は〜である 二定義3.
時間 tempus, 〜の表象については二定理44系1備考. 〜は持続を決定する 三定理8証明. 永遠性は〜によって規定されえぬ 五定理23備考./ その他 一定義8説明, 四定義6 ,定理10備考.
刺激状態〔変状の項を見よ〕.
刺激する, 刺激される affiicere, affici,三要請1.
自己愛 philautia, amor sui,〜=自己満足 三定理55備考./ その他 三感情定義28説明.
自己原因(カウサ・スイ) causa sui, 一定義1. /神は〜 一定理25備考.//その他 一定理7証明, 12証明, 24証明,五定理35証明.
自己保存の努力〔努力の項を見よ〕.
自己満足(精神の満足) acquiescentia in se ipso (acquiescentia mentis),三定理30備考,51備考,55 備考,三感情定義25./ 〜=自己愛 三定理55(系1)備考.// 理性から生ずる〜が最高の〜 四定理52. 第三種の認識から最高の精神の満足が生ずる 五定理27./// その他 四定理52備考,心の満足 五定理36備考.
自殺する se interficere, 四定理18備考(下29),20備考.
自然(ナトゥラ) Natura,神=〜 四序言(下9),定理4証明. 〜は目的を持たぬ 一付録(上86f.). 〜は常に同一 三序言(上7). 全〜は一つの個体 二補助定理7 備考./ その他 一付録,三序言,四序言などの各個所参照.// 能産的自然 N. Naturans および所産的自然 N. Naturata については一定理29備考,31.
自然状態(自然的状態) status naturalis,四定理37備考二(下49ff.).
思想 cogitatio , 一定義2 ,二定理1証明,18備考,三感情定義4説明.
持続 duratio , 二定義5./ 〜 =抽象的に考えられた存在 二定理45備考. 〜は時間によって決定ないし規定される 三定理8証明,五定理23証明.物の〜はその本質からは決定されぬ 四序言(下72).// その他 一定義8説明,二定理30,31, 三定理9 ,五定理21,23備考.
実在性 realitas,〜=完全性 二定義6, 四序言(下11). 〜あるいは有(有性) 四定理9,四序言(下11). 〜あるいは完全性 一定理11備考,二定理1備考,43備考,49備考(上158).
実在的有 entia realia , 二定理49備考(上162),五定理30証明.
実体(スブスタンティア) substantia,一定義3. / 〜=神 一定義6. 神のほかにいかなる〜もない 一定理14. 物体的〜(=延長した〜)は神にふさわしくないとする説への駁論 一定理15備考全体.思惟する〜と延長した〜とは同一の〜 二定理7備考. // その他 一定理1,2,4 ,5 ,6,7 ,8 ,10,12. 13,二定理10 ./// 思惟する〜,延長した〜,物体的〜についてはそれぞれその項も見よ.
実体の有 esse substantiae,二定理10.
嫉妬 zelotypia,三定理35備考./ その他 三感情定義48説明,五定理20.
実有(有, 実在物) ens,絶対に無限な実有=神 一定義6,定理11第1別証および第2 別証,同備考.有限な実有 一定理11第2別証.思惟する実有 二定理1備考.超絶的名辞としての「有」 二定理40備考1(上140)./ 実体の有, 実在的有, 理性の有, 表象の有, 形相的有,想念的有についてはそれぞれその項を見よ.
自卑 abjectio ,三感情定義29 ,四定理57備考./ 謙遜から〜が生ずる 三感情定義28説明. 〜には道義心と宗教心の外観がつきまとう 四付録22. // その他 三感情定義29説明,四定理55 ,56, 同備考.
慈悲心 (=親切) benevolentia,三定理27系3 備考. 三感情定義35.
自卑する人間(自卑的な人間) abjectus,三感情定義29説明,四定理56系,57備考,四付録22.
至福 beatitudo,四付録4. / 精神の自由ないし〜 五序言(下97),定理36備考, 〜=神に対する人間の愛=人間に対する神の愛 五定理36備考.〜=徳 五定理42.// その他 二定理49備考(上163),五定理33備考.
思慕 desiderium, 三定理36備考,三感情定義32.
自明性 evidentia.
社会 societas〔共同社会の項もあわせ見よ〕. 〜の確立について 四定理37備考2(下50).
醜 deformia,一付録(上90).
自由 libertas,〜=神への奉仕 二定理49備考(上163).〜=至福=神への愛 五定理36備考./ 国家においていっそう〜 四定理73.// 〜なものとして表象する 五定理5証明.
自由^意志〔意志の項を見よ〕.
自由^原因〔原因の項を見よ〕.
自由^人 bomoliber,四定理66備考./ 〜の心境の一端については 四定理67から72まで参照.
自由^的(自由である) liber,一定義7./ 人間は自分を〜と謬想する 一付録(上84),二定理35備考,三定理2備考(上174).
宗教, 宗教心 religio, 四定理37備考1./その他 三感情定義27説明,四定理73備考,付録15,五定理41,同備考.
羞恥 verecundia,三定理39備考./ 〜と恥辱との相違 三感情定義31説明.
主体 subjectum, 三定理5,同証明,五公理1.
受動 passio,三定義3,四付録2./ 精神の〜は非妥当な観念からのみ生ずる 三定理3.すべて〜は物が自然の一部であることから生ずる 三定理3備考,四定理2.//その他 四定理4系,5,6,五定理3,17.
受動する(働きを受ける) pati,三定義2./ その他 三定理1,同系,四定理2,五定理40.
松果腺 glandulae pineali,デカルトの〜説およびそれへの駁論 四序言全体.
賞讃 laus,三定理29備考.
小心,小心な pusillanimitas,pusillanimis, 三定理51備考,三感情定義41./ その他 三感情定義41説明.
衝動 appetitus,三定理9備考./ 〜と欲望との相違 三定理9備考.しかし時に〜は欲望・努力・意志と等置される 三感情定義1説明,三定理27系3備考,35証明,37証明.
小児, 幼児 puer, infans,非理性的存在者の例としてしばしば用いられる 二定理44備考,49備考(上160,162),三定理32備考,四定理39備考.五定理6備考.五定理39備考.
証明 demonstratio.
情欲 libido〔快楽の項もあわせ見よ〕,三定理56備考,三感情定義48./ その他 三定理57備考.
女性(=妻) uxore, 自己の本性とまったく一致する〜 四定理68備考.
女性的同情 muliebri misericordia, 二定理49備考, 四定理37備考1.
神学者 Theologi,一付録(上87),四定理35備考.
心情(心) animus,主として精神の感情的方面を示すのに用いられる.
心情の葛藤 animi conaictns,三定理23備考,59備考.
心情の動揺 animi fluctuatio,三定理17備考./ その他 三定理31,同証明,35備考,50備考,56,五定理10備考(下110).
身体(人間身体, 人体)(コルプス) corpus (humanum corpus)〔物体の項もあわせ見よ〕,〜は精神の対象 二定理13.〜は精神と合一する 二定理13備考.〜は精神を思惟に決定しえない 三定理2./ その他 二要請1から6,三要請1,2,四定理38,39,同備考.// 身体の変状については変状の項を見よ./// 一精神一〜 四定理18備考. 〔協同 二定義7〕.
身体の観念(イデア・コルポリス) idea corporis, 三定理3証明, 二定理21備考 他.
真の観念 idea vera,〜はその対象と一致する 一公理6.〜=明瞭判然たる観念 一定理8備考2(上44).〜の自明性 二定理43,同備考.
真理 veritas,〜は〜自身の規範 二定理43備考.永遠の〜 一定義8説明,定理8備考2(上44). 17備考(上63).
[ス] ☆
図〔本文中図像挿入箇所〕. / 一定理15備考, 二定理8備考, 二補助定理3のあとの公理2.
数学 mathesis, 〜は目的には関係せず図形の本質にのみ関係する 一付録(上86).〜はすべての人を同じ確信に導く 一付録(上91).
スコラ学派 Scbolastici,一定理24系,五序言(下100).
ストア学派 Stoici, 五序言(下97).
[セ] ☆
正, 正義 justum, justitia,四定理37備考2(下51)./ その他 四付録15,24.
精気〔動物精気の項を見よ〕.
聖書からの引用 二定理44備考(一般名詞として,ペテロ他)四定理17備考(伝道の書一ノ一八).四定理68備考(創世記,モーゼ).五定理36備考(イザヤ書六ノ三).
精神(人間精神)(メンス) mens(mensbumana),〜は身体の観念 二定理11.神の知性の一部 二定理11系,43備考,五定理40備考.〜は身体と合一している…すべての個体は…〜を 二定理13備考.さらに〜の観念(=観念の観念)は〜自身と合一している 二定理21.〜は身体を運動に決定しえぬ 三定理2,同備考全体.〜は妥当な観念および非妥当な観念から成る(=時に能動し時に受動する) 三定理3,9証明.そのいずれの場合も〜は自己の有に固執しようと努力する 三定理9.〜の永遠性については五定理23以下参照.〜の最高の徳=物を第三種の認識において認識すること 五定理25./ その他 二定理12,13,15,19,20,22,23,24,26,47,48,三定理12,13,14,16など参照.
精神の強さ fortitudo,三定理59備考.〜は勇気と寛仁に分けられる 三定理59備考./ その他 四定理69証明,73備考,五定理41備考.
節制 temperantia,〜は精神の能力 三定理56備考,三感情定義48説明.〜は勇気の一種 三定理59備考.
絶望 desperatio,三定理18備考2,三感情定義15./ その他 四定理47備考.
説明 explicatio.
セネカ Seneca,四定理20備考.
善 bonum,三定理39備考,四序言(下10f.),四定義1./ 我々は我々の欲する物を〜と名づける 三定理9備考,39備考.〜の認識は我々に意識された限りにおける喜びの感情にほかならぬ 四定理8.〜の真の認識は真であるというだけでは感情を抑制しえぬ 四定理14.我我は〜と判断するものを必然的に欲求する 四定理19.最高の〜=神への認識=神への愛 四定理28,五定理20証明.// その他 四定理27,29,31,同系,36,39,40証明,65,同系,66,同系,付録3,5,6,8./// 諸感情の善については四定理41,42,43, 45, 47. //// 善悪の概念 四定理68.
前兆 omen,三定理50備考.
戦慄 horror,三定理52備考.
[ソ] ☆
想起〔記憶の項を見よ〕.
創造する creare.
想念的に objective,一定理17備考(上63),30証明,二定理7系.
想念的有 esse objectum,〜=観念 二定理8系,48備考.
属性(アトリブータ) attributum,一定義4./ 〜の客観的実在性を物語る個所の例 一定理4証明,16証明,19証明.二つの〜が実在的に異なって考えられるからといって二つの異なる実体を構成しはしない 一定理10備考.// その他 一定理9,10,12,19,21,22,23,二定理1,2./// この語の一般的意味での用例(=内的性質) 一付録(上90),四定理37備考2(下51).
族長たち Patriarchae,四定理68備考(モーゼ).
尊敬 veneratio,三定理52備考.
存在 existentia,物の〜の二様式 五定理29備考.定まった〜=一種の量として考えられる限りにおいての〜=時間および場所に限定された〜 一定理21証明,二定理45備考,五定理29備考.物が神ないし神の属性の中に含まれている限りにおいての〜=神の本性の必然性から生ずると考えられる限りにおいての〜 二定理8の系,45備考,五定理29備考./ 神の〜については 一定理11.
[タ] ☆
第一原因〔原因の項を見よ〕.
第一種の認識 cognitio primi generis,〜=意見=表象 二定理40備考2.〜は誤謬の唯一の原因 二定理41.
第二種の認識 cognitio secundi generis,〜=理性=普遍的認識 二定理40備考2,五定理36備考.〜は必然的に真 二定理41.〜から第三種の認識が生ずる 二定理47備考,五定理28.
第三種の認識 cognitio tertii generis,〜=直観知 二定理40備考2.〜は精神の最高の徳 五定理25.〜から精神の最高の満足=神への愛が生ずる 五定理27,32系.〜から生ずる神に対する知的愛 五定理33. 精神が物を第二種および第三種の認識で認識するにつれて死は恐るべきものでなくなる 五定理38./ なお第三種の認識については五定理25以下の諸定理参照.
対象(1)(観念されたもの) ideatum,真の観念はその〜と一致する 一公理6.
対象(2)(前に横たわっているもの, 客体)(イデアトゥム) objectum.
大胆な,大胆 audax,audacia,三定理51備考,三感情定義40./ その他 四定理69証明.
第二次概念 notiones secundae,二定理40備考1(上140).
太陽 sol,〜に関する我々の表象について 二定理35備考,四定理1備考.
正しく行ないて自ら楽しむ bene agere et laetari, 当時人々によく知られたいた慣用句 四定理50, 四定理73備考.
妥当な(十全な)観念 idea adaequata,二定義4./ 〜=明瞭判然たる観念 二定理36.〜からは〜が生ずる 二定理40.〜から精神の能動が生ずる 三定理3,四付録2,五定理20備考(下118)
妥当な(十全な)原因 causa adaequata,三定義1.
楽しみ, →歓喜.
魂の在りか animae sedes,二定理35備考.
端正(な) honestum,四定理37備考1./ その他 (=優雅な)三感情定義27説明,(=気品がある)33説明,四定理18備考(下30). 58備考,70備考.
端正心(=品位) bonestas,四定理37備考1./ その他 四付録15,24.
[チ] ☆
知覚 perceptio,概念との相違 二定義3説明.
知覚する percipere,広義の認識するの意味に用いられ妥当な認識にも非妥当な認識にも適用される./ 〜=結論する 一定理23証明.〜力〔能力の項を見よ〕.
恥辱 pudor,三定理30備考,三感情定義31./ 蓋恥との差 三感情定義31説明.// その他 三定理40備考,四定理58備考,付録23.
知性 intellectus,〜は神の属性とその変状を知覚する 一定義4,定理30.〜と表象の相違 一定理15備考(上58). 〜は思惟のある様態 一定理31証明.〜=意志 二定理49系.理性ないし〜 四付録4./ 無限の〜については一定理16,30,31,二定理4証明,7備考,11系,五定理40備考その他参照.現実的〜および可能的〜については一定理31備考,33備考2(上80)の参照.
知性作用, 知力 intellectio.
秩序 ordo,観念の〜は物(原因)の〜と同一 二定理7,9証明,19証明,20証明,五定理1証明.自然の共通の秩序 二定理29系,四定理4系,57備考.知性による〜 二定理40備考2,五定理10備考(下70). 表象の有としての〜 一付録(上89f.).
抽象的, 抽象的に abstractus,abstracte, 〜あるいは皮相的に 一定理15備考(上58). 〜ないし一般的に 四定理62備考./ その他 二定理45備考,49備考(上161f.).
超絶的名辞 termini transcendentales,その起源 二定理40備考1(上140).
嘲弄(嘲笑) irrisio,三定理52備考,三感情定義11./ 〜と笑いとの差 四定理45備考.
直観知, 直観的認識(スキエンティア・イントゥイティヴァ) scientia intuitiva,cognitio intuitiva,〜=第三種の認識.その項を見よ.なお二定理40備考2,五定理36備考参照.
[ツ] ☆
罪〔罪過の項を見よ〕.
強さ〔精神の強さの項を見よ〕.
[テ] ☆
定義 definitio,物の真の〜はその物の本性を表現する 一定理8備考2(上44).本性ないし〜 一定理8備考2(上45). ある物の〜からその物の諸特質が結論される 一定理16証明.〜すなわち本質 一定理16証明.本質ないし〜 一定理33備考1.
貞節(貞操) castitas,〜は精神の能力を示す.三定理56備考,感情定義48説明.
鄭重 humanitas =人情あるいは従順(礼譲),三定理29備考,三感情定義43.
定理 propositio.
デカルト Cartesius,一定理19備考,三序言(上166),五序言(下98).
[ト] ☆
同感 sympathia,三定理15備考./ 好感の項,三感情定義8参照.
道義心(=正義心) pietas, 四定理37備考1./ その他 二定理49備考(上163),四定理18備考(下30),51備考,付録15,五定理4備考,41,同備考.//(=忠誠心)四付録25.
同情 misericordia,三感情定義24./ 憐憫との相違 三感情定義18説明.
動物 animalia, bruta,〜は感覚を有する 三定理57備考,四定理37備考1.〜と人間と相互間の権利 四定理37備考1.〜の感情は人間の感情と異なる 四定理37備考1.
動物精気 spiritus animales,五序言(下).
徳 virtus, 四定義8./ 〜=能力 三定理55のあとの系証明,四定義8.〜=人間の本質 四定義8.〜の基礎=自己の有を維持しないし自己の利益を求めること 四定理18備考(下29).真の〜=理性の導きに従って生活すること 四定理24,36証明,37備考1. 最高の〜=神の認識 四定理28.至福=〜 五定理42.// その他 二定理49備考(上),四定理22,23,36,59備考.
特質(特性) proprietas,本性ないし本質との対立語として用いられる 一付録(上82f.),二定理49備考(上164). 三感情定義6説明. ある物の〜はその物の定義(=本質)から結論される 一定理16証明. / その他 二定義4,三感情定義28説明.// 神の諸〜 一付録(上82). 実体の諸〜 二定理10備考.
努力(=自存力) conatus,自己保存の〜(=自己の有に固執しようとする〜)=物の本質=徳の第一・唯一の基礎 三定理7,四定理22, 同証明,同系. 〜ないし欲望 三定理37証明,58証明,四付録1. 〜ないし衝動 三定理35証明,37証明.能力ないし〜 三定理7証明. / その他 三定理8,9,同備考,感情定義1説明,32説明.
奴隷 servus,四定理66備考.
食欲 avaritia,三定理56備考,三感情定義47.
食欲者 avarus,三定理39備考,三感情定義48説明,五定理10備考(下112).
[ナ] ☆
軟 mollia,二補助定理3のあとの公理3.
[ニ] ☆
憎しみ Odium,三定理13備考. 三感情定義7. / 〜は愛によって征服される 三定理43.ある物への〜は他の原因の観念と結合する時消滅する 三定理48.自由なものへの〜は必然的なものへの〜より大である 三定理49.// その他 三定理38,44,45,45,四定理45,同系1. 同系2,定理46,同備考,五定理18.
憎み返し odii reciprocatio, reciprocum odium, 三定理40備考, 43.
人間 homo,〜の本質は必然的存在を含まぬ 二公理1. 〜は思惟する 二公理2.精神と身体から成る 二定理13系. 〜が存在に固執する力は外部の原因の力によって無限に凌駕される 四定理3. 〜は自然の一部 四定理4,付録7.〜は感情に捉われる限り対立的であり理性に導かれる限り一致的である 四定理34,35. 〜にとっては理性に導かれる〜ほど有益なものはない 四定理35系1,付録9./ その他 二定理10,同系,四定理18証明, 同備考(下30),32 ,33,68備考,付録4.// 「〜」の表象像(羽のない二足動物:プラトン、理性的動物:アリストテレス) 二定理40備考1.
認識 cognitio , 〜と観念との等置については観念の項を見よ. 善および悪の〜は我々に意識された限りにおける喜びあるいは悲しみの感情にほかならぬ 四定理8 .善および悪の真の〜は真であるというだけでは感情を抑制しえぬ 四定理14 ./ 第一種の〜,第二種の〜,第三種の〜, 直観的〜についてはそれぞれその項を見よ.
認識する(1) cognoscere, 広く一般に認識作用を示すのに用いられる.
認識する(2)(理解する) intelligere, 広義にも用いられるが特にしばしば知性的認識,妥当な認識について用いられる.
[ネ] ☆
ねたみ invidia , 三定理24備考, 三感情定義23. / その他 三定理32備考, 感情定義33説明,四定理73備考,五定理20.
[ノ] ☆
能動 actio 〔活動の項もあわせ見よ〕,三定義3,四付録2 ./ 精神の〜は妥当な観念からのみ生ずる 三定理3 .// その他 四付録3.
能動する(働きをなす) agere, 三定義2 ./ その他 三定理1,同系,五定理40 .
能力(力, 力量) potentia ,vis,potestas, まれにvirtus, 〜ないし努力 三定理7証明,57証明. 〜=本質 三定理7証明. 〜=徳 四定義8. 人間の〜は制限されている 四定理3. おのおのの受動の〜は外部の原因の〜によって規定される 四定理5.精神の〜=正しい認識=妥当な観念の形成 五序言(下101),定理4備考,三定理3. / 神の〜については一定理17備考(上61f.),34 ,35,二定理3証明,同備考. 自然の〜については 三序言(上165f.),四定理57備考. 感情に対する精神の〜については五全体, ことに五定理20備考全体.
能力(機能, 適性) facultas, 意志したり意志しなかったりする〜 二定理48証明.認識し・欲求し・愛しなどする〜,否定し・肯定する 二定理48備考.思惟する〜,感覚する〜,意志する〜 二定理49備考(上159).
[ハ] ☆
働き〔活動および能動の項を見よ〕.
働きを受ける〔受動するの項を見よ).
働きをなす〔能動するの項を見よ).
反感 antipathia ,三定理15備考. / 反撥の項,三感情定義9参照.
反対的(対立的, 相反的, 反対である) contrarius.
反撥(=離反) aversio , 三感情定義9. / 反感の項,三定理15備考参照.
[ヒ] ☆
美 pulchra, 一付録(上90)/〔美なるもの〕.
備考 scbolium . 非妥当な(非十全な)観念 idea inadaequata ,〜=毀損・混乱した観念 二定理35. 〜は妥当な観念と同一の必然性をもって起こる 二定理36. 〜から受動が生ずる 三定理3. 〜は人間の無能力を表わす 五定理20備考(下118).
非妥当な(非十全な)原因 causa in adaequata , 三定義1. / 〜=部分的原因 三定義1.
必然性 necessitas,〜 =永遠性 一定理10備考,23証明,四定理62証明.神の本性の〜 一定理16,29備考,付録(上92). 自然の〜 三序言(上166), 五定理10備考(下110).人間の本性の〜 四定理37備考2(下49).ある永遠の〜 一付録(上86), 五定理22証明,23証明,42備考.
必然的 necessarius,一定義7,定理33備考1./ 理性は物を〜として観る 二定理44.
否定, 否定する negatio, negare .
非難 vituperium ,三定理29備考.
美, 美なるもの pulchra,一付録(上90). 四定理45備考(系2備考). 外的〜 四付録20.
美味欲 luxuria ,三定理56備考, 三感情定義45.
表象(表象知)(イマギナティオ) imaginatio ,四定理1備考,五定理34証明./ 〜=第一種の認識=誤謬の唯一の原因 二定理40備考2 ,41.しかし〜はそれ自身には誤謬を含まぬ 二定理17備考,35備考,49備考(上161).〜においてあるものと知性においてあるもの 一定理15備考(上58).感情は一種の〜 四定理9証明,五定理34証明. 〜ないし記憶 五定理34備考,39備考.
表象作用,表象力 imaginatio. 物を偶然的として観るのは〜による 二定理44系1,〜は身体とともに滅ぶ 五定理40系./ その他 一付録(上89ff.).
表象する imaginari,二定理17備考. / も っぱら感覚的認識作用を表わす 一付録(上89ff.),二定理35備考.〜場合は物を抽象的皮相的に認識する 一定理15備考(上58). 精神は身体が続く間だけ〜ことができる 五定理21.時には広義の認識作用を示すのにも用いる 五定理7証明./ その他 一定理8備考2(上43),三定理11備考,12,13,16,四定理9備考.
表象像 imago ,二定理17備考,三定理27証明,32備考. // 観念との区別 二定理48備考,49備考(上156). 身体の変状あるいは物の〜 五定理14. 〜あるいは感情 五定理11証明.〜の現われる頻度 五定理11,12 ,13 ,14./// その他 二定理18備考(ポームム, くだもの),40備考1(上140f.),三要請2 ,定理18備考1,備考2 ,四定理9備考,59備考.
表象の有 entia imaginationis,一付録(上91).
非礼(な) turpe, 四定理37備考1./ その他 三感情定義27説明, 四定理71備考,73備考,付録15.
[フ] ☆
不可能的 impossibilis, 一定理33備考1.
不完全性 imperfectio ,〜は物の存在を排除する 一定理11備考. なお四序言全体を参照.
復讐(心) vindicta ,三定理40系2備考,三感情定義37. / その他 三定理41備考,四定理45系1.
不条理 absurdum .
不正, 不正義 injustum , 四定理37備考2(下51)./ その他 四付録15 .
物質 materia , 一定理15備考(上58).
物体 corpus, 二定義1,一定理15備考(上54)./ 〜は〜によって限定される 一定義2 .// 物体の本性については二定理13のあとにある公理1以後参照.
物体的自然 corporea Natura,一定理11第1別証.
物体的実体 corporea substantia,〜=延長した実体.実体ならびに延長した実体の項を見よ.
部分的原因 causa partialis,〜=非妥当な原因.三定義1ならびに四定理2証明参照.
侮蔑 dedignatio,三定理52備考./ その他 三定理59備考,三感情定義5.
普遍的 universalis.
不法 injuria, 四定理46備考,付録14,五定理10備考(下110),20備考(下118).
ブリダンの驢馬 asina Buridani,二定理49備考(上158).
憤慨 indignatio,三定理22備考,三感情定義20./ その他 四定理51備考,73備考,付録24.
[ヘ] ☆
ヘブライ人たち(二, 三の〜) quiddam Hebraeorum,二定理7備考.(マイモニデス)
変状(刺激状態, 触発状態,発現)(アフェクティオ) affectio,刺激ないし触発によって呈する一定の状態を意味する.実体の〜=様態(=個物)一定義5.神の属性の〜=個物(=様態)一定理25系.身体の〜主物の表象像 二定理17備考,三定理32備考.身体のある種の〜およびその観念=感情 三定義3.身体の〜の観念は非妥当である 二定理28.身体の〜の観念の観念も非妥当である 二定理29.しかし我々は身体の〜についてある明瞭な概念を形成しうる 五定理4./ なお身体の変状についてはこの他に二定理19,22,23,25,26,27,四定理7証明,同系,五定理4系,10, 同備考(下70),14,39証明参照.
変状する(発現する, 刺激される, 触発される) affici,神または神の属性があるものに〜 一定理28証明,二定理9,同証明,同系証明,12証明,19証明,24証明,25証明,28証明,39証明,40証明,三定理1証明,2証明.
[ホ] ☆
忘恩 ingratitudo, 四定理71備考.
法則 lex,神の本性の諸〜 一定理17,同証明.自然の〜 三序言(上165f.),定理2備考(上171f.).社会を建てる〜 四定理37備考2 (下50)
法律 jus, lex,四定理37備考2(下50),72備考,73証明,付録24.
補助定理 lemma.
本質 essentia,二定義2,定理10系備考./ この語は本性と等置され(三定理56証明,57証明,四定義8),特質と対立させられる(三感情定義6説明).また時に定義と等置され(一定理16証明, 33備考1),形相と等量され〔四序言(下77)〕,永遠の真理と等置され〔一定義8説明,定理17備考(上63)〕,また他面においては自己保存の努力と等直され(三定理7),衝動と等置され(三定理9備考),欲望と等直される(三定理56証明,(57証明).// 絶対に永遠無限なるものの〜 一定義6説明.神の〜 一定理34,二定理3備考.精神の〜 三定理3証明,10証明.人間の〜 二定理10,同系,三定理56証明,57証明,四定義8.形相的〜についてはその項を見よ.
本性 natura,〜=定義 一定理8備考2(上44).物の〜はその物の真の定義によって表現される 一定理8備考2(上44).〜=本質 三定理56証明,57証明,四定義8.特質と対立的に用いられる 一付録(上82),二定理49備考(上164).しかし広義に一般的性質を表わす意味にもしばしば用いられる.
[マ] ☆
満足 acquiescentia. 心の〜 五定理36備考.〔自己満足の項を見よ〕.
[ミ] ☆
見くびり despectns,三定理26備考,三感情定義22./ その他 四定理48.
民衆 vulgus,二定理3備考,三定理29備考,四定理54備考(恐るべきもの、タキトゥス),58備考,五定理41備考.
[ム] ☆
無限(な) infinitum, 一定理8備考1. /その他 一定義6,同説明,定理15備考全体参照, 二定理8, 同系, 同備考.
無限定(な) indefinitum, 二定義5説明,三定理8,9./『デカルトの哲学原理』第二部定義四には「無限定とはその限界(その限界があるとすれば)が人間の知性によって探究されえないもの」としており,『エチカ』での用法もこれと同じと見てよいであろう.
無恥 impudentia, 三感情定義31説明.
無知の避難所 ignorantiae asylum, 一付録(上88)
無能力, 無力, 無能 impotentia, 四定理37備考1./ その他 一定理11第2別証,三感情定義26,四定理18備考(下29),20,32証明,45系2備考,五定理20備考(下118).
夢遊病者 somnambnlus, 三定理2備考(上171f.).
[メ] ☆
迷信 superstitio, 一付録(上85),三定理50備考,四定理37備考1,45系2備考,付録31.
名誉(誇り,=栄光) gloria, 三定理30備考,三感情定義30./ その他 三定理34,39備考,41備考,42,四定理58,同備考,五定理10備考(下111),36備考(イザヤ書六ノ三).
名誉欲(野心,=追従) ambitio, 三定理29備考,56備考,三感情定義44./ その他 三定理31備考,32備考,三感情定義48説明,四定理44備考.付録25,五定理4備考.
名誉欲者(名誉欲の強い者, 名誉に飢える者) ambitiosus,三定理39備考,三感情定義48説明,四定理44備考,五定理10備考(下111).
[モ] ☆
モーゼ Moses,四定理68備考.
目的(フィニス) finis,自然は何ら〜を有しない 一付録(上86ff.),四序言(下9). 〜=衝動 四定義7. 理性に導かれる人間の究極目的=一切の物の妥当認識 四付録4./ 神学者たちのいわゆる同化の〜と需要の〜 一付録(上87).
目的原因 causa finalis,〜=人間の想像物 一付録(上86).〜=衝動 =起成原因 四序言(下9).
[ヤ] ☆
野心〔名誉欲の項を見よ〕.
[ユ] ☆
有(1) esse,〜=本質(この等置は,二定理11と三定理3証明および10証明を比較参照せよ).神は万物の〜に関する原因 一定理24系,二定理10(系)備考. おのおのの物は自己の〜に固執する 三定理6,7,8,9. 時に〜=実在性 一定理9,10備考./ 実体の〜,実在的〜,理性の〜 表象の〜,形相的〜,想念的〜についてはおのおのその項を見よ.
有(2)(実有,実在物)ens〔実有の項を見よ〕.
憂鬱 melancholia,三定理11備考./ その他 三感情定義3説明,四定理42,45系2備考.
有益 utile,〜=善 四定義1,定理31系.おのおのの物は我々の本性に一致すればするだけ〜である 四定理31系.人間にとっては理性に導かれる人間が最も〜である 四定理35系1,付録9.
勇気 animositas,三定理59備考./ 〜は精神の強さの一部 三定理59備考.〜の種類 三定理59備考.// その他 三感情定義48説明,四定理69系,同備考,五定理10備考(下111),41,同証明.
ユークリッド Euclides,二定理40備考2.
有限(な) finitum,一定理8備考1./ その他 一定義2,定理28,二定義7.
友情 amicitia,四定理37備考1,付録12,14,17,26,五定理10備考(下110)
夢 somnium,二定理49備考. / →夢遊病者
[ヨ] ☆
要請 postulatum,〜あるいは公理 三要請1.
様態(モードス) modus,一定義5./ 〜=個物=神の属性の変状 一定理25系,27証明.実体と〜のほか何ものもない 一定理28証明.すべての〜は合して所産的自然を形成する 一定理29備考.延長の〜とこの〜の観念は同一物 二定理7備考.無限の〜については 一定理21,22,23.永遠なる〜 五定理40備考.// その他 一定理15証明, 29証明,二公理3,5,定理6,8.
様態的変状 modificatio,一定理8備考2(上43)./ 〜=様態 一定理8備考2(上43)および 28証明内容を参照.人間の本質は神の属性のある〜から成る 二定理10系.無限の〜 一定理22,23.
抑制 coerce,三定理2備考,四定理序言,四定理7,14,五定理42.他.
欲望 cupiditas,三定理9備考,感情定義1./ 〜は基本的感情の一つ 三定理11備考,感情定義4説明.〜=努力 三定理37証明,58証明,感情定義1説明,四付録1.時に衝動と区別され時に等置される 三定理9備考,37証明,感情定義1説明.〜=人間の本質 三定理56証明,57証明,感情定義1.時に意志と区別され時にやや混同される 二定理48備考,三定理9備考,感情定義1説明.受動感情なる〜のほかに能動感情なる〜が存する 三定理58,四付録2.前者は過度になりうるが後者は過度になりえぬ 四定理44,61. // その他 三定理15. 四定理18,60,同備考.
予言者たち Prophetae,四定理54備考.
喜び laetitia,三定理11備考,三感情定義2. / 〜は基本感情の一 三定理11備考,感情定義4説明.〜は原則的には善 四定理41. 受動感情なる〜のほかに能動感情なる〜が存する 三定理58. // その他 三定理15,四定理18,付録30.
[ラ] ☆
落胆 conscientiae morsus,三定理18備考2,三感情定義17. / その他 四定理47備考.
[リ] ☆
理解する〔認識する(2)の項を見よ〕
理性(理性知)(ラティオ) ratio,〜=第二種の認識 二定理40備考2. 〜は物を必然的として観る 二定理44.〜は物を永遠の相のもとに知覚する 二定理44系2,五定理29証明.〜の基礎は概念 二定理44系2証明. 〜は自己の真の利益を求めるように教える 四定理18備考(下28). 〜の努力は認識することにのみ向けられる 四定理26.〜の導きに従って生活する人間は相互に必然的に一致する 四定理35.〜ないし知性 四付録4./ その他 四定理24,35系1,36備考,59,同証明,付録5,9.
理性の有 entia rationis,一付録(上91),二定理49備考(上162).
理由 ratio,〜ないし原因 一定理11第1別証,四序言(下9).
流動的 fluidum,二補助定理3のあとの公理3.
倫理学 Ethica.
[レ] ☆
礼譲(=従順) modestia,受動・能動両用の意味に用いられ前者の場合は〜=鄭重(=人情) 三感情定義43.また〜=名誉欲の一種 三感情定義48説明,四付録25.能動の場合は〜=寛仁の一種 三定理59備考. また〜=道義心(=忠誠心) 四付録25.
隷属 servitus,四序言(下7).
連結(結合) connexio,観念の〜は物(原因)の〜と同一 二定理7,9証明, 19証明,20証明,五定理1証明.
連結(連鎖) concatenatio,観念のある〜=記憶 二定理18備考.
憐憫 commiseratio,三定理22備考,三感情定義18. 同情との区別 三感情定義18説明.〜は原則的には悪で無用 四定理50. // その他 三定理27備考,四定理50系,同備考,付録16.
[ロ] ☆
論争 controversiae,一付録(上91),二定理40備考1(上142),47備考.
論理学 Logica,五序言(下97).
[ワ] ☆
和合 concordia,〜および友情 四付録14. 〜を生むもの 四付録15,16,21,23.
和合的に, 和合して concorditer,人間が〜生活しうる道 四定理37備考2(下49). 人間が〜生活するに役立つものは有益で善 四定理40,同証明.
笑い risus,〜は身体にのみ関係する 三定理59備考.嘲弄(嘲笑)との差 四定理45系2備考.TOP☆